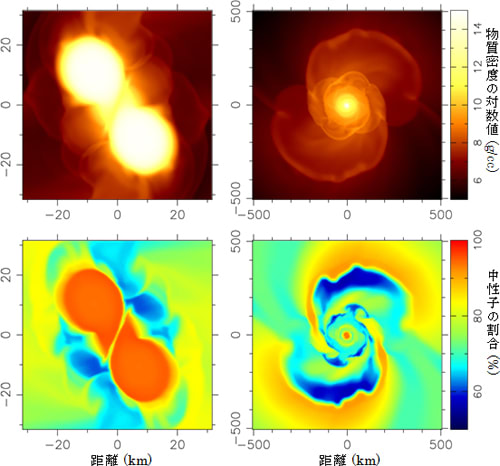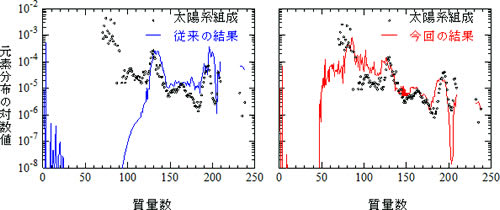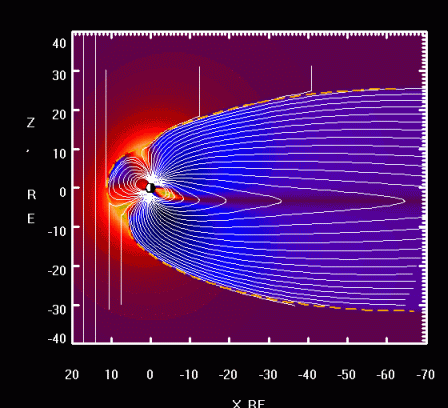地球観測衛星“SMAP”は、
地球全体の土壌に含まれる水分を観測を目的とする衛星です。
この“SMAP”を搭載したデルタIIロケットの打ち上が成功したんですねー
これにより“SMAP”は、天気予報の精度改善や、災害の防止などに役立てられるようです。

デルタIIロケットは、
カリフォルニア州にあるヴァンデンバーグ空軍基地から離昇し、ブースターや第1段ロケットを分離しながら順調に飛行。
約56分後に“SMAP”を予定通りの軌道に投入します。
“SMAP”はNASAのジェット推進研究所が運用する地球観測衛星で、地球全体の土壌に含まれる水分と、
凍結している個所の融解具合を見ることを目的としています。
得られたデータは、
天気予報や気候変動の予測の改善、洪水や干ばつといった災害の予防、
農業の生産性の向上といったことに役立てられることになります。

“SMAP”は、直径6メートルの傘のようなアンテナを持ち、ユニークな姿をしているんですねー
このアンテナは、
合成開口レーダーと放射計、2種類の装置の目と耳として機能します。
合成開口レーダーとは、
電磁波を地上に向けて放射し、反射して衛星に返ってきた信号を分析する観測装置で、
放射計は地表から出る電磁波の放射を計測する装置になります。
“SMAP”は、もともとNASAで開発されていた“ESSPハイドロス”という衛星が基になっています。
っというのも“ESSPハイドロス”が2005年に、NASAの予算削減が原因で中止されたからで、
その遺産を活用したのが“SMAP”になります。
打ち上げ時の質量は944キロ。
高度685キロ×685キロ、軌道傾斜角98.1度の太陽同期軌道で運用され、
8日ごとに同じ地点の上空を通過するそうです。
設計寿命は3年が予定されているようです。
“SMAP”の打ち上げに使われたデルタIIロケットは、ボーイング社が開発したロケットで、
ユナイテッド・ローンチ・アライアンス社によって運用されています。
デルタIIの1号機が打ち上げられたのが1989年2月のこと。
それ以来、153機が打ち上げられているのですが、なんと失敗は2度だけ。
最後の失敗からは98機連続で成功を続けているんですねー
でも、後継機のデルタIVが登場したので生産は終了、在庫は残り2機になっています。
今後、2016年に地球観測衛星“JPSS-1”を、
2017年には地球観測衛星“アイスサット2”を打ち上げて運用を終了するそうですよ。
地球全体の土壌に含まれる水分を観測を目的とする衛星です。
この“SMAP”を搭載したデルタIIロケットの打ち上が成功したんですねー
これにより“SMAP”は、天気予報の精度改善や、災害の防止などに役立てられるようです。

デルタIIロケットは、
カリフォルニア州にあるヴァンデンバーグ空軍基地から離昇し、ブースターや第1段ロケットを分離しながら順調に飛行。
約56分後に“SMAP”を予定通りの軌道に投入します。
“SMAP”はNASAのジェット推進研究所が運用する地球観測衛星で、地球全体の土壌に含まれる水分と、
凍結している個所の融解具合を見ることを目的としています。
得られたデータは、
天気予報や気候変動の予測の改善、洪水や干ばつといった災害の予防、
農業の生産性の向上といったことに役立てられることになります。

“SMAP”は、直径6メートルの傘のようなアンテナを持ち、ユニークな姿をしているんですねー
このアンテナは、
合成開口レーダーと放射計、2種類の装置の目と耳として機能します。
合成開口レーダーとは、
電磁波を地上に向けて放射し、反射して衛星に返ってきた信号を分析する観測装置で、
放射計は地表から出る電磁波の放射を計測する装置になります。
“SMAP”は、もともとNASAで開発されていた“ESSPハイドロス”という衛星が基になっています。
っというのも“ESSPハイドロス”が2005年に、NASAの予算削減が原因で中止されたからで、
その遺産を活用したのが“SMAP”になります。
打ち上げ時の質量は944キロ。
高度685キロ×685キロ、軌道傾斜角98.1度の太陽同期軌道で運用され、
8日ごとに同じ地点の上空を通過するそうです。
設計寿命は3年が予定されているようです。
“SMAP”の打ち上げに使われたデルタIIロケットは、ボーイング社が開発したロケットで、
ユナイテッド・ローンチ・アライアンス社によって運用されています。
デルタIIの1号機が打ち上げられたのが1989年2月のこと。
それ以来、153機が打ち上げられているのですが、なんと失敗は2度だけ。
最後の失敗からは98機連続で成功を続けているんですねー
でも、後継機のデルタIVが登場したので生産は終了、在庫は残り2機になっています。
今後、2016年に地球観測衛星“JPSS-1”を、
2017年には地球観測衛星“アイスサット2”を打ち上げて運用を終了するそうですよ。