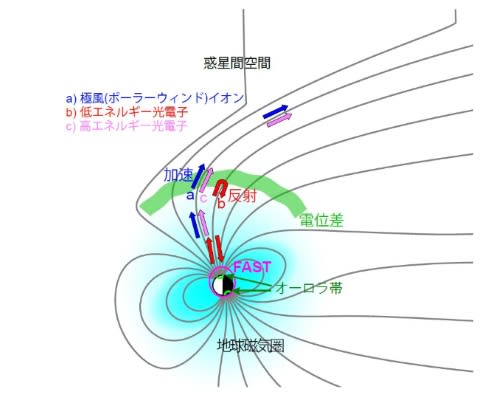“SMAP”はNASAのジェット推進研究所が運用する地球観測衛星で、
地球全体の土壌に含まれる水分と、
凍結している個所の融解具合を見ることを目的としています。
ただ、7月7日に発生したレーダー機器の不具合が未だ解決せず…
“SMAP”に搭載されている観測機器のひとつ、
合成開口レーダーに何らかの問題が発生し、動かせない状態になっているんですねー
復旧は少し先に
これまでの分析から分かったことは、
レーダーの大電力増幅器“HPA”の低電圧電源に問題があるらしいこと。
“HPA”はレーダーのパルスの出力を強くするための装置。
これまでに得られた衛星の状態を示す信号が示している状態から、
問題は、この低電圧電源内で起きていて、
原因としていくつかの候補が考えられています。
でも発表されたのは、
これまでに行われた復旧の試みが、すべて失敗していること…
ただ、その過程で貴重なデータが得られ、
問題の状況や原因を理解するのに役立っているんですねー
今後も引き続き、分析と地上での試験を続け、
早ければ8月下旬にも、再び復旧を試みるそうです。
“SMAP”ミッション
もうひとつの観測機器の放射計は問題なく動いていて、
現在もデータを集め続けています。
“SMAP”はNASAのジェット推進研究所が運用する地球観測衛星で、
地球全体の土壌に含まれる水分と、
凍結している箇所の融解具合を、見ることを目的にしています。
得られたデータは、
天気予報や気候変動の予測の改善、洪水や干ばつといった災害の予防、
農業の生産性の向上といったことに役立てられることになります。
衛星は直径6メートルの傘のようなアンテナを持つ、
大変ユニークな姿をしています。
このアンテナは合成開口レーダーと放射計の、2種類の装置の目と耳として機能。
合成開口レーダーとは、電磁波を地上に向けて照射し、
反射して衛星に返ってきた信号を分析することによって観測する装置で、
放射計は地表から出る電磁波の放射を計測する装置です。
土に含まれる水分を能動的、受動的に観測“Soil Moisture Active Passive”の、
頭文字から取られた“SMAP”です。
“SMAP”ミッションは、
もともとNASAで開発されていた“ESSPハイドロス”という衛星が、
基になっています。
っというのも“ESSPハイドロス”が2005年に、NASAの予算削減が原因で中止されたからで、
その遺産を活用したのが“SMAP”になります。
打ち上げ時の質量は944キロ。
高度685キロ×685キロ、軌道傾斜角98.1度の太陽同期軌道で運用され、
8日ごとに同じ地点の上空を通過するそうです。
設計寿命は3年が予定されているようです。
こちらの記事もどうぞ ⇒ 地球観測衛星“SMAP”打ち上げに成功!
地球全体の土壌に含まれる水分と、
凍結している個所の融解具合を見ることを目的としています。
ただ、7月7日に発生したレーダー機器の不具合が未だ解決せず…
“SMAP”に搭載されている観測機器のひとつ、
合成開口レーダーに何らかの問題が発生し、動かせない状態になっているんですねー
復旧は少し先に
これまでの分析から分かったことは、
レーダーの大電力増幅器“HPA”の低電圧電源に問題があるらしいこと。
“HPA”はレーダーのパルスの出力を強くするための装置。
これまでに得られた衛星の状態を示す信号が示している状態から、
問題は、この低電圧電源内で起きていて、
原因としていくつかの候補が考えられています。
でも発表されたのは、
これまでに行われた復旧の試みが、すべて失敗していること…
ただ、その過程で貴重なデータが得られ、
問題の状況や原因を理解するのに役立っているんですねー
今後も引き続き、分析と地上での試験を続け、
早ければ8月下旬にも、再び復旧を試みるそうです。
“SMAP”ミッション
もうひとつの観測機器の放射計は問題なく動いていて、
現在もデータを集め続けています。
“SMAP”はNASAのジェット推進研究所が運用する地球観測衛星で、
地球全体の土壌に含まれる水分と、
凍結している箇所の融解具合を、見ることを目的にしています。
得られたデータは、
天気予報や気候変動の予測の改善、洪水や干ばつといった災害の予防、
農業の生産性の向上といったことに役立てられることになります。
衛星は直径6メートルの傘のようなアンテナを持つ、
大変ユニークな姿をしています。
このアンテナは合成開口レーダーと放射計の、2種類の装置の目と耳として機能。
合成開口レーダーとは、電磁波を地上に向けて照射し、
反射して衛星に返ってきた信号を分析することによって観測する装置で、
放射計は地表から出る電磁波の放射を計測する装置です。
土に含まれる水分を能動的、受動的に観測“Soil Moisture Active Passive”の、
頭文字から取られた“SMAP”です。
“SMAP”ミッションは、
もともとNASAで開発されていた“ESSPハイドロス”という衛星が、
基になっています。
っというのも“ESSPハイドロス”が2005年に、NASAの予算削減が原因で中止されたからで、
その遺産を活用したのが“SMAP”になります。
打ち上げ時の質量は944キロ。
高度685キロ×685キロ、軌道傾斜角98.1度の太陽同期軌道で運用され、
8日ごとに同じ地点の上空を通過するそうです。
設計寿命は3年が予定されているようです。
こちらの記事もどうぞ ⇒ 地球観測衛星“SMAP”打ち上げに成功!