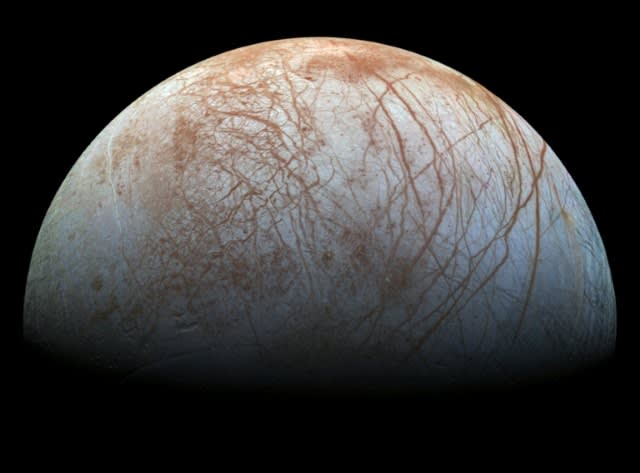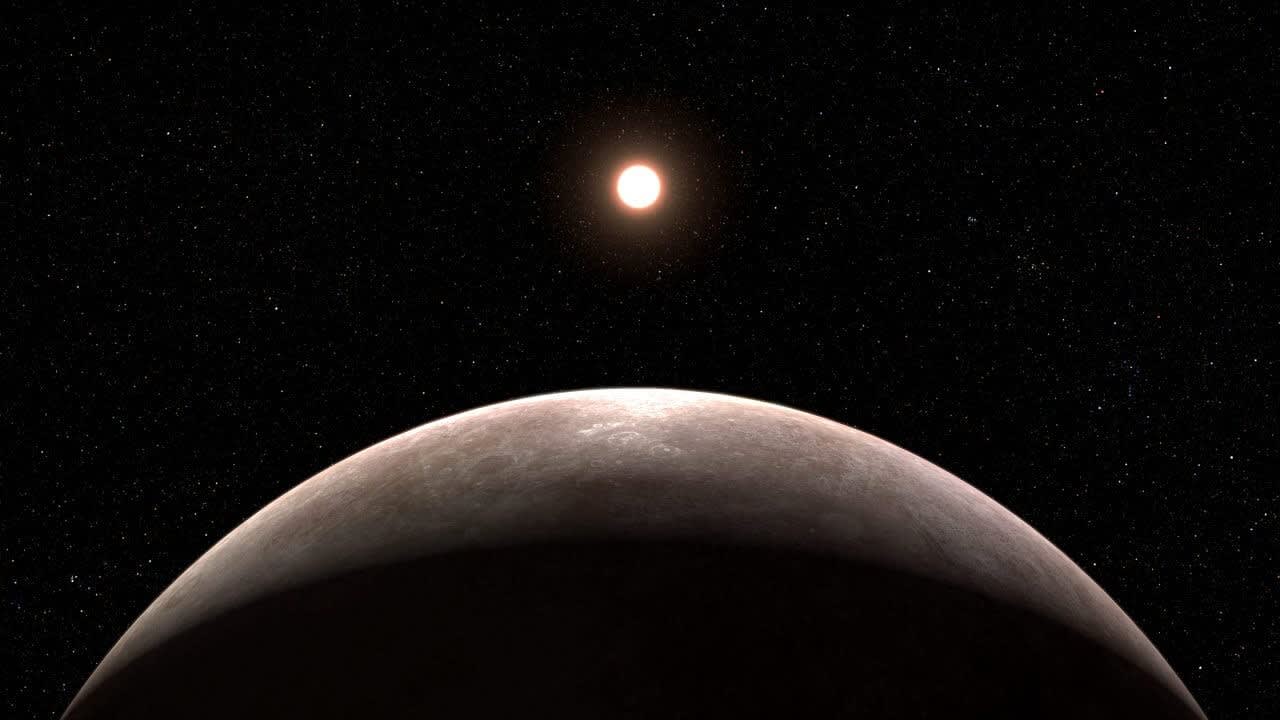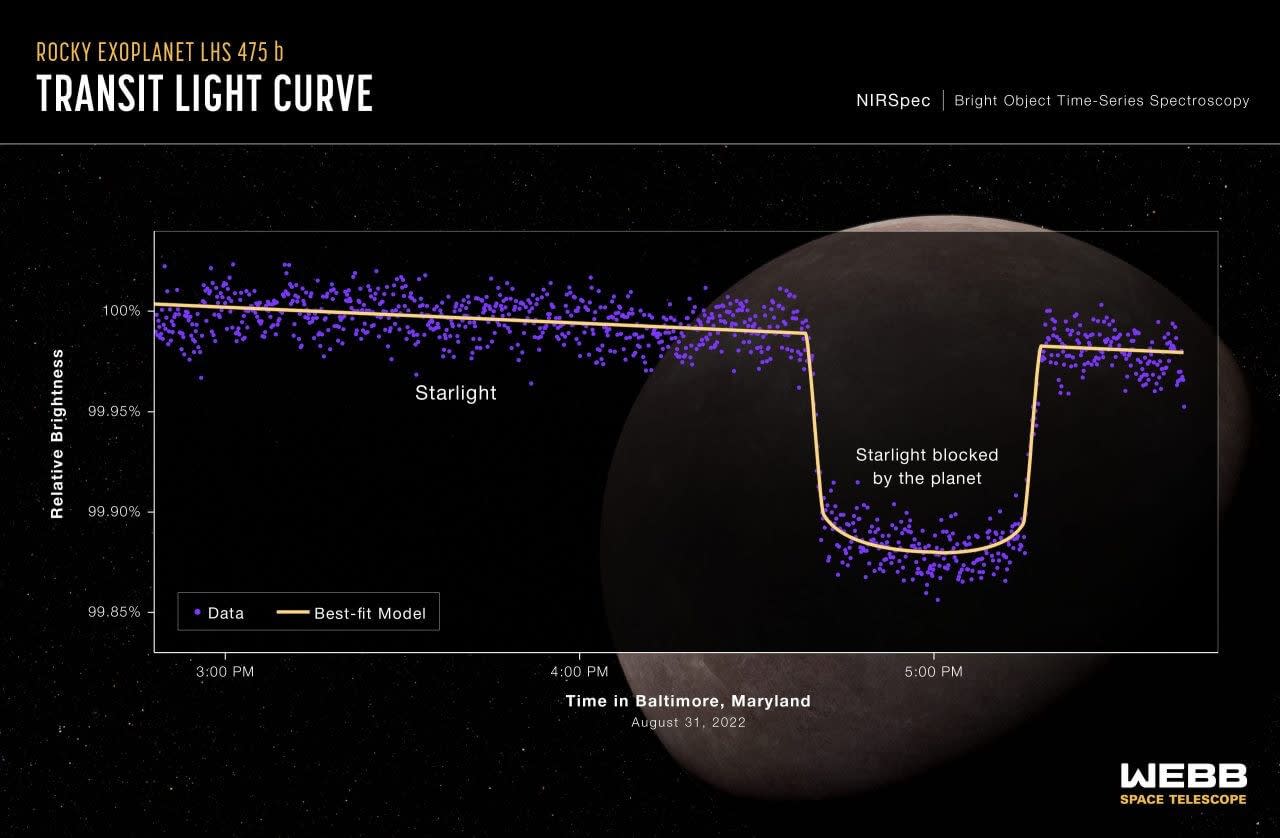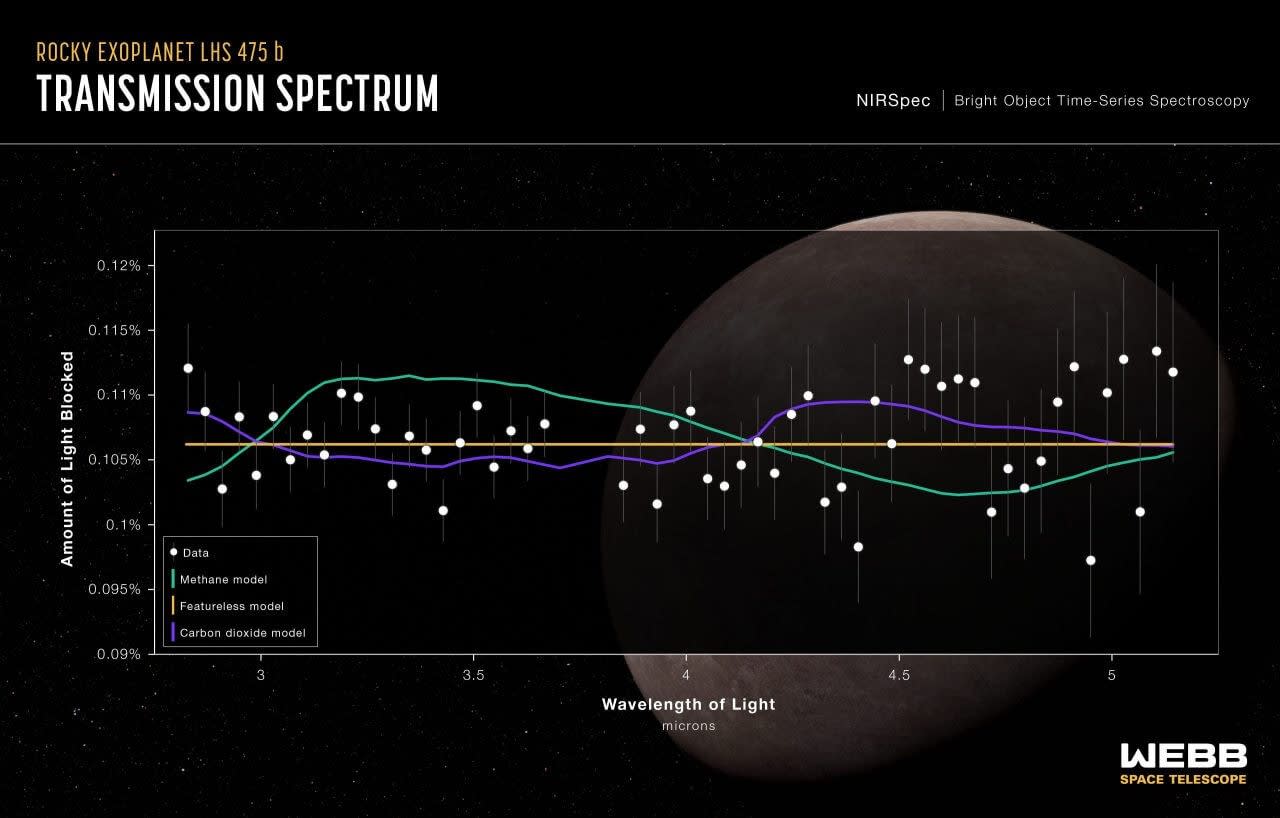夏が近づいてくると、紫外線による日焼けを気にする人が多くなりますよね。
それは、紫外線が生命にとって有害であり、日焼けは紫外線が皮膚の細胞にダメージを与えたことの現れと言えるからです。
さらに、紫外線は細胞の奥深くへと達してDNAを損傷する可能性もあります。
太陽からの紫外線の多くは大気中のオゾン層に遮られているので、地球上の生命はオゾン層に守られていると言われています。
このため、地球のような岩石惑星を対象とした系外惑星探査では、大気中に存在するオゾンの含有量が、複雑な生命の居住可能性を判断するうえで重要な条件になっているんですねー
この疑問を解くため、今回の研究では系外惑星大気中のオゾン含有量に焦点を当てた数値シミュレーションを実施、その成果を発表しています。
その電磁波の一部である紫外線は、可視光線の中でも波長が短い“紫”よりも外側の波長域(波長の短い領域)に位置していることから、そう呼ばれています。
紫外線は可視光線よりも波長が短いので、人間の目では感知することはできません。
UV-Cは、上空のオゾンと酸素分子によってすべて吸収されるので、地表には到達しません。
地表に到達するUV-AとUV-Bのうち、特にUV-Bが生物に大きな影響を与えることになります。
オゾンは酸素原子3個からなる分子で、太陽から放射された紫外線は地球大気中のオゾンの生成と破壊の両方に関わっているんですねー
紫外線のうちUV-Cは、中層大気中でオゾンを生成する役割を担っています。
でも、UV-Bは個々の酸素原子や酸素分子との反応プロセスを通してオゾンを破壊していきます。
このことから、系外惑星の大気でも地球と同じように紫外線が複雑な反応を起こし、影響を与えていると考えることができます。
このグループに注目して研究は進められることになります。
研究チームでは、最初に恒星が放射する紫外線の波長を正確に計算。
この計算では、恒星の金属量に左右される影響も初めて考慮されていました。
この特性は、恒星に含まれる水素と重元素の比率を表していて、研究では鉄の含有量が多い星と少ない星についても検討されています。
例えば、太陽の場合だと鉄原子1個に対して水素原子は3万1000個存在しています。
これには、オゾンや酸素などの気体と紫外線の相互作用をシミュレーションする化学気候モデルを用いて分析しています。
地球大気の歴史には、系外惑星の生命進化に関する手掛かりが隠されているかもしれないからです。
さらに、オゾンを生成するUV-Cとオゾンを破壊するUV-Bの比率は、星の金属量に大きく依存することも示されることになります。
UV-BとUV-Cの比率は非常に大きな意味を持ちます。
金属に乏しい星ではUV-Cの比率が大きいので、惑星の大気では厚いオゾン層が形成されます。
一方、金属に富む星ではUV-Bの比率が大きいので、惑星の大気で形成されるオゾン層ははるかに希薄になってしまいます。
結果的に、金属に富む星は金属に乏しい星よりも紫外線放射が大幅に少ないにもかかわらず、その周りを公転する惑星ではオゾン層が希薄になるので、惑星表面はより強い紫外線にさらされることになります。
研究チームの予測に反して、「金属に乏しい星は生命の誕生にとってより有利な条件を提供する」という研究成果が示されたわけです。
そのため、新しい世代の星は、その前の世代の星が作り出した金属を含む材料から形成されることに…
つまり、星に含まれる金属の量は、星が世代を重ねるごとに増えていくことになります。
そう、宇宙全体で見れば金属に富む星ばかりが増えていき、恒星系で生命が誕生する確率は宇宙が年老いるにしたがって低下していく可能性を、今回の研究は示しているんですねー
とはいえ、今回の成果は必ずしも地球外生命探査にとって絶望的な報せというわけでもないようです。
系外惑星が公転する主星の多くは太陽と同じような年齢の恒星であり、そのような恒星を公転する惑星のうち少なくとも1つは複雑で興味深い生命体を宿しています。
そう、私たちも良く知っている地球の存在があるからです。
こちらの記事もどうぞ
それは、紫外線が生命にとって有害であり、日焼けは紫外線が皮膚の細胞にダメージを与えたことの現れと言えるからです。
さらに、紫外線は細胞の奥深くへと達してDNAを損傷する可能性もあります。
太陽からの紫外線の多くは大気中のオゾン層に遮られているので、地球上の生命はオゾン層に守られていると言われています。
このため、地球のような岩石惑星を対象とした系外惑星探査では、大気中に存在するオゾンの含有量が、複雑な生命の居住可能性を判断するうえで重要な条件になっているんですねー
紫外線は地球大気中のオゾンの「生成と破壊」の両方に関わっている
惑星がオゾン層を形成するために、主星である恒星はどのような性質(化学組成)を持つ必要があるのでしょうか?この疑問を解くため、今回の研究では系外惑星大気中のオゾン含有量に焦点を当てた数値シミュレーションを実施、その成果を発表しています。
研究を進めたのは、マックス・プランク太陽系研究所の科学者Anna Shapiro(アンナ・シャピロ)さんの率いる研究チームです。
太陽などの恒星は様々な電磁波を放射しています。その電磁波の一部である紫外線は、可視光線の中でも波長が短い“紫”よりも外側の波長域(波長の短い領域)に位置していることから、そう呼ばれています。
紫外線は可視光線よりも波長が短いので、人間の目では感知することはできません。
モンシロチョウなど一部の生物は、紫外線を感知できると考えられている。
さらに、紫外線はその波長によりUV-A(315~400nm)、UV-B(280~315nm)、UV-C(100~280nm)の3種類に分類されています。UV-Cは、上空のオゾンと酸素分子によってすべて吸収されるので、地表には到達しません。
地表に到達するUV-AとUV-Bのうち、特にUV-Bが生物に大きな影響を与えることになります。
オゾンは酸素原子3個からなる分子で、太陽から放射された紫外線は地球大気中のオゾンの生成と破壊の両方に関わっているんですねー
紫外線のうちUV-Cは、中層大気中でオゾンを生成する役割を担っています。
でも、UV-Bは個々の酸素原子や酸素分子との反応プロセスを通してオゾンを破壊していきます。
このことから、系外惑星の大気でも地球と同じように紫外線が複雑な反応を起こし、影響を与えていると考えることができます。
表面温度が約5000℃から6000℃の範囲にある恒星
惑星が確認されている恒星のうち約半数の表面温度は約5000℃から6000℃の範囲にあり、太陽もその一つに数えられています。このグループに注目して研究は進められることになります。
研究チームでは、最初に恒星が放射する紫外線の波長を正確に計算。
この計算では、恒星の金属量に左右される影響も初めて考慮されていました。
この特性は、恒星に含まれる水素と重元素の比率を表していて、研究では鉄の含有量が多い星と少ない星についても検討されています。
例えば、太陽の場合だと鉄原子1個に対して水素原子は3万1000個存在しています。
天文学では、水素とヘリウムよりも重い元素のことを“重元素”と呼び、水素に対する重元素の割合は重元素量と呼ぶ。重元素は恒星内部の核融合反応により合成され、恒星の死に伴い星間空間へと放出される。なので、星の生と死のサイクルが十分に繰り返されていない初期の宇宙では、現在の宇宙に比べて重元素量が低かったと考えられている。
次に研究チームが考えたのは、恒星から放射される紫外線がハビタブルゾーン内に位置する惑星の大気にどのような影響を与え、どのように変化させていくのかということ。これには、オゾンや酸素などの気体と紫外線の相互作用をシミュレーションする化学気候モデルを用いて分析しています。
“ハビタブルゾーン”とは、主星(恒星)からの距離が程良く、惑星の表面に液体の水が安定的に存在できる領域。この領域にある惑星では生命が居住可能だと考えられている。太陽系の場合は地球から火星軌道が“ハビタブルゾーン”にあたる。
このモデルを用いることで、研究チームは系外惑星の様々な状況と地球大気の過去5億年にわたる歴史を比較。地球大気の歴史には、系外惑星の生命進化に関する手掛かりが隠されているかもしれないからです。
金属に乏しい星は紫外線を多く放射する
シミュレーションの結果示されたのは、全体として金属に乏しい星は金属に富む星よりも紫外線を多く放射すること。さらに、オゾンを生成するUV-Cとオゾンを破壊するUV-Bの比率は、星の金属量に大きく依存することも示されることになります。
UV-BとUV-Cの比率は非常に大きな意味を持ちます。
金属に乏しい星ではUV-Cの比率が大きいので、惑星の大気では厚いオゾン層が形成されます。
一方、金属に富む星ではUV-Bの比率が大きいので、惑星の大気で形成されるオゾン層ははるかに希薄になってしまいます。
結果的に、金属に富む星は金属に乏しい星よりも紫外線放射が大幅に少ないにもかかわらず、その周りを公転する惑星ではオゾン層が希薄になるので、惑星表面はより強い紫外線にさらされることになります。
研究チームの予測に反して、「金属に乏しい星は生命の誕生にとってより有利な条件を提供する」という研究成果が示されたわけです。
宇宙が年老いるにしたがって生命が誕生する確率は低下していく?
金属(重元素)は、恒星内部の核融合反応によって数十億年かけて合成された後、恒星から流れ出る恒星風や超新星爆発を通して宇宙空間に放出されていき、次の世代の恒星や惑星の材料になります。そのため、新しい世代の星は、その前の世代の星が作り出した金属を含む材料から形成されることに…
つまり、星に含まれる金属の量は、星が世代を重ねるごとに増えていくことになります。
そう、宇宙全体で見れば金属に富む星ばかりが増えていき、恒星系で生命が誕生する確率は宇宙が年老いるにしたがって低下していく可能性を、今回の研究は示しているんですねー
とはいえ、今回の成果は必ずしも地球外生命探査にとって絶望的な報せというわけでもないようです。
系外惑星が公転する主星の多くは太陽と同じような年齢の恒星であり、そのような恒星を公転する惑星のうち少なくとも1つは複雑で興味深い生命体を宿しています。
そう、私たちも良く知っている地球の存在があるからです。
こちらの記事もどうぞ