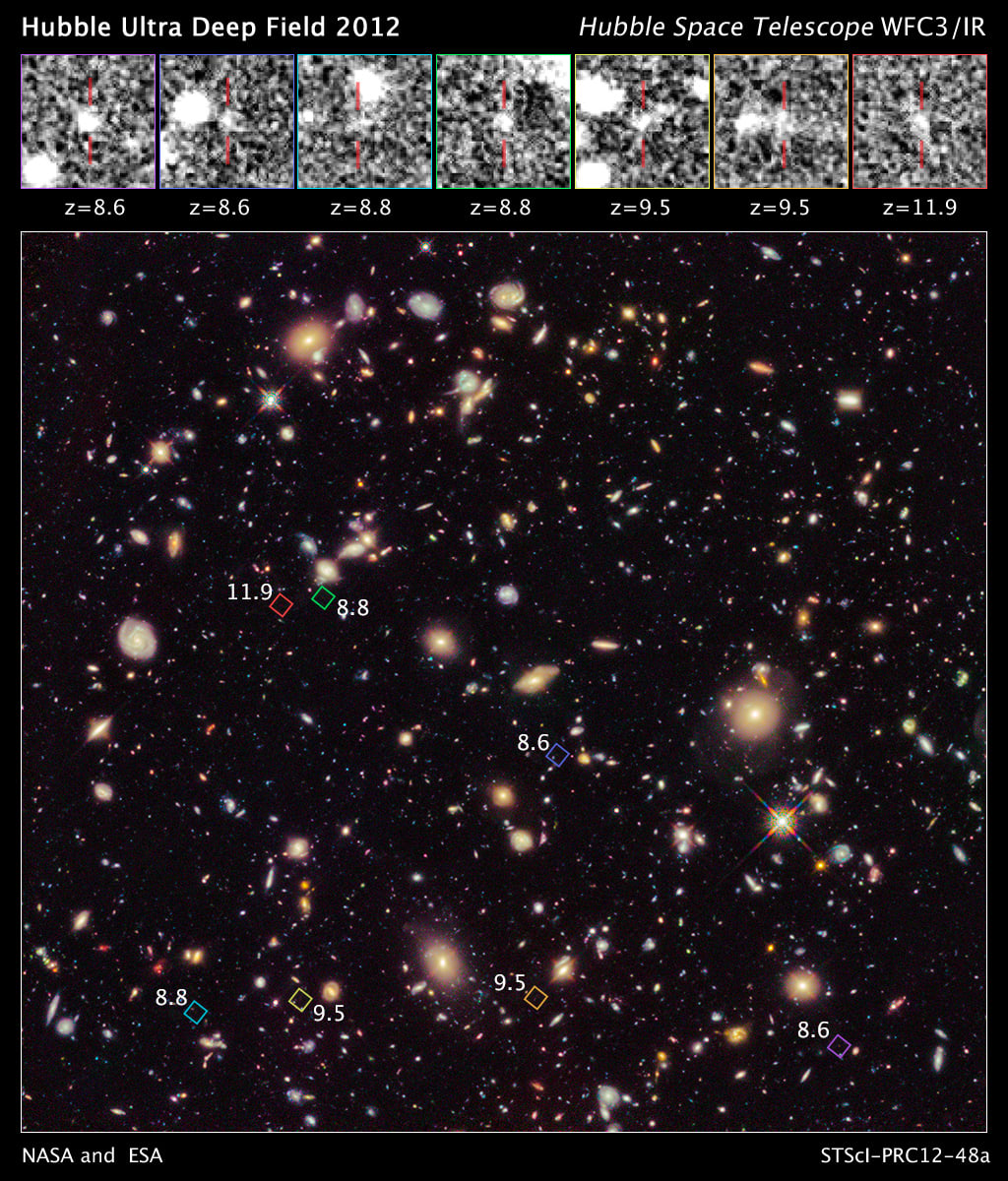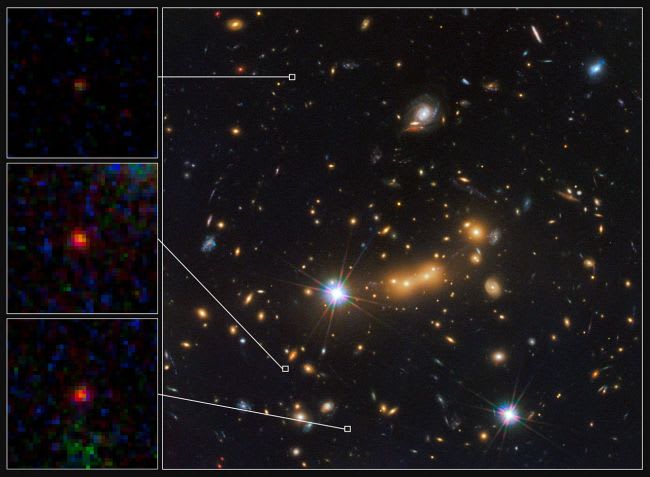欧州の天文衛星“プランク”の観測による、
初の“宇宙マイクロ波背景放射”の全天マップ発表されました。
宇宙誕生時の名残りを伝える微弱なマイクロ波が“宇宙マイクロ波背景放射”です。
この“宇宙マイクロ波背景放射”は、宇宙全体に満ちていて、
これにより、宇宙の年齢や構成割合など、宇宙の歴史に関わる新しい数値が求められました。
“宇宙マイクロ波背景放射”は、宇宙誕生からわずか38万年後に放たれた光の波長が伸びて、
現在マイクロ波として観測されるものです。
なので、“宇宙マイクロ波背景放射”には誕生直後の宇宙に存在した、
わずかな密度のムラが反映されています。
こうしたムラは宇宙誕生直後に起こった、宇宙空間の急激な膨張(インフレーション)で大規模に広がり、
その後、恒星や銀河などの構造が生れる種になっていると考えられています。
NASAの宇宙マイクロ波背景放射観測衛星“COBE”や“WMAP”の後と継ぐために、
2009年に打ち上げられたのが欧州の“プランク”です。
“プランク”は、従来以上の高い解像度と感度で、宇宙マイクロ波背景放射の全容をとらえています。
1年あまりの観測から得られた今回の観測結果は、大枠では宇宙論の標準モデルを踏襲しています。
でも、モデルでは予測されていなかった、エネルギー分布の非対称性や模様も見られたんですねー
なので今後は、この観測結果に一致するようなモデルの構築を目指すことになります。
また、高精度な観測による宇宙全体に関する様々な値も新しく求められ、
宇宙の年齢は、これまでより1億年古い138億歳になりました。
そして、宇宙膨張の加速を示すハッブル定数は、67.15±1.2キロ/秒/Mpcになっています。
これは、距離が1メガパーセクト(約326万光年)離れるごとに、膨張速度が秒速67.15キロ大きくなり、
従来の値より遅くなっています。
宇宙の構成に占める物質やエネルギーの割合についても、
宇宙の加速膨張の元となるダークエネルギーが減り、
逆に重力の元となるダークマターの割合が増加しています。
“プランク”による観測成果の完全版は2014年に発表される見込みです。
まだまだ、新しい発見があるかもしれませんね。
初の“宇宙マイクロ波背景放射”の全天マップ発表されました。
宇宙誕生時の名残りを伝える微弱なマイクロ波が“宇宙マイクロ波背景放射”です。
この“宇宙マイクロ波背景放射”は、宇宙全体に満ちていて、
これにより、宇宙の年齢や構成割合など、宇宙の歴史に関わる新しい数値が求められました。
“宇宙マイクロ波背景放射”は、宇宙誕生からわずか38万年後に放たれた光の波長が伸びて、
現在マイクロ波として観測されるものです。
なので、“宇宙マイクロ波背景放射”には誕生直後の宇宙に存在した、
わずかな密度のムラが反映されています。
こうしたムラは宇宙誕生直後に起こった、宇宙空間の急激な膨張(インフレーション)で大規模に広がり、
その後、恒星や銀河などの構造が生れる種になっていると考えられています。
NASAの宇宙マイクロ波背景放射観測衛星“COBE”や“WMAP”の後と継ぐために、
2009年に打ち上げられたのが欧州の“プランク”です。
“プランク”は、従来以上の高い解像度と感度で、宇宙マイクロ波背景放射の全容をとらえています。
1年あまりの観測から得られた今回の観測結果は、大枠では宇宙論の標準モデルを踏襲しています。
でも、モデルでは予測されていなかった、エネルギー分布の非対称性や模様も見られたんですねー
 |
| プランクによる宇宙マイクロ波背景放射の全天マップ |
なので今後は、この観測結果に一致するようなモデルの構築を目指すことになります。
また、高精度な観測による宇宙全体に関する様々な値も新しく求められ、
宇宙の年齢は、これまでより1億年古い138億歳になりました。
そして、宇宙膨張の加速を示すハッブル定数は、67.15±1.2キロ/秒/Mpcになっています。
これは、距離が1メガパーセクト(約326万光年)離れるごとに、膨張速度が秒速67.15キロ大きくなり、
従来の値より遅くなっています。
宇宙の構成に占める物質やエネルギーの割合についても、
宇宙の加速膨張の元となるダークエネルギーが減り、
逆に重力の元となるダークマターの割合が増加しています。
 |
| 今回の観測研究から宇宙の構成の割合が新しく求められた。 |
“プランク”による観測成果の完全版は2014年に発表される見込みです。
まだまだ、新しい発見があるかもしれませんね。