『beatmania』が大ヒットしていたころは、
筐体に列や人だかりができるのは
当たり前の現象でした。
そんな時代だからこそ享受することができた
楽しみ方も多くあるわけで。
『beatmania』のもともとの料金設定は
200円です。今でもごくまれに
1プレイ200円の筐体を見かけるかも知れません。
そして、ゲームそのものの難易度は高く、
最後までプレイできてもせいぜい
10分程度しか遊べません。
だからこそ、『beatmania』で遊ぶときには
(金銭的に余裕のある人を除けば)みんなどこか慎重でした。
列ができていることを利用して、
前の人がプレイしている最中に
多くを学ぼうとやっきになっていたものです。
幸いこのころの収録曲には
非常に特徴的な譜面が多く、
それを目に焼き付けておいて
イメージトレーニングをしていた人も多いと思います。
オイラの場合は特にこの傾向が強く、
プレイは1日に1回と決めていたので
かなり必死でした。
(それでも計算上
一か月で4、5,000円以上は飛ぶんですぜ?)
2曲目とかで退場させられた時は
その日ずっと気分が重かったですね。
でもおかげさまで、
「20,Nobember(ハウス)」、「Ska a go go(スカ)」という
当時最も話題になっていた難曲は
ものの数回でクリアすることができました。
「OVERDOSER(ミニマルテクノ)」は
一番イメージトレーニングが容易だったので
一発目にできましたね。
逆に、誰もやらないようなマイナー曲には
てこずりまくりましたが・・・
「U gotta groove(ヒップホップストリート)」とか
「LOVE SO GROOVY(ハウススピリチュアル)」とか・・・
また何より、普段ゲームをやらなそうな人も
ギャラリーとしてそばから見物していたり、
ゲームに興味を持って並んでいたりしたのも
このころならではの特徴だと思います。
幅広い層のみんなが
一つになって遊んでいる感じが
とにかく楽しかったですね。
そんな人たちの前でたまたま
「20,Nobember」をほぼ完璧な状態でクリアできた時、
「カッコイイーーー!!」なんて歓声が
聞こえてきたことがあります。
これに気を良くしたオイラは(若かったなあ)、
だったらもっと凄いのを見せてやるよ、と
最難関曲「Ska a go go」を最後にセレクト。
ところどころミスはありつつも
クリア自体は難なく達成できました。
ところが・・・そのギャラリーたちの反応は芳しくない。
恥ずかしいのではっきりした様子は見てないのですが、
想像できる原因はいくつかあります。
1つめは、動作や譜面にヒいていたということ。
この曲のラストは譜面を見る限りでも
かなり大袈裟でしたし、
それに相反するかのように、
演奏には妙にこちょこちょした動作が求められるわけです。
2つめは、クリアしたはいいけどミスも多かったこと。
それも画面上のミスではなく、演奏上のミス。
ゲーム内容を知らないギャラリーにとっちゃ
いくらGREAT繋げようが聴こえが悪けりゃミスなわけで。
3つめは、楽曲にピンと来なかったこと。
ハウスは4つ打ちのわかりやすいダンスミュージックでしたけど、
スカは当時、世間的にはマイナーなジャンルでしたからね。
そうじゃなくても、
ハウスが現在でも名曲として名をとどめているのに比べ、
スカはどうでしょうか?
オイラは結局、ゲーム的な印象しか
残っていなかったりします。
上記のような状況は
現在じゃ解決されるどころか加速しきってしまい、
プレイヤーとギャラリーの間の越えられない壁として
完全に居座ってしまったように思います。
2ndMIXの時代からこの萌芽があったということには
色々と考えさせられてしまうのですが・・・
詳しい考察はまた、こんど。
筐体に列や人だかりができるのは
当たり前の現象でした。
そんな時代だからこそ享受することができた
楽しみ方も多くあるわけで。
『beatmania』のもともとの料金設定は
200円です。今でもごくまれに
1プレイ200円の筐体を見かけるかも知れません。
そして、ゲームそのものの難易度は高く、
最後までプレイできてもせいぜい
10分程度しか遊べません。
だからこそ、『beatmania』で遊ぶときには
(金銭的に余裕のある人を除けば)みんなどこか慎重でした。
列ができていることを利用して、
前の人がプレイしている最中に
多くを学ぼうとやっきになっていたものです。
幸いこのころの収録曲には
非常に特徴的な譜面が多く、
それを目に焼き付けておいて
イメージトレーニングをしていた人も多いと思います。
オイラの場合は特にこの傾向が強く、
プレイは1日に1回と決めていたので
かなり必死でした。
(それでも計算上
一か月で4、5,000円以上は飛ぶんですぜ?)
2曲目とかで退場させられた時は
その日ずっと気分が重かったですね。
でもおかげさまで、
「20,Nobember(ハウス)」、「Ska a go go(スカ)」という
当時最も話題になっていた難曲は
ものの数回でクリアすることができました。
「OVERDOSER(ミニマルテクノ)」は
一番イメージトレーニングが容易だったので
一発目にできましたね。
逆に、誰もやらないようなマイナー曲には
てこずりまくりましたが・・・
「U gotta groove(ヒップホップストリート)」とか
「LOVE SO GROOVY(ハウススピリチュアル)」とか・・・
また何より、普段ゲームをやらなそうな人も
ギャラリーとしてそばから見物していたり、
ゲームに興味を持って並んでいたりしたのも
このころならではの特徴だと思います。
幅広い層のみんなが
一つになって遊んでいる感じが
とにかく楽しかったですね。
そんな人たちの前でたまたま
「20,Nobember」をほぼ完璧な状態でクリアできた時、
「カッコイイーーー!!」なんて歓声が
聞こえてきたことがあります。
これに気を良くしたオイラは(若かったなあ)、
だったらもっと凄いのを見せてやるよ、と
最難関曲「Ska a go go」を最後にセレクト。
ところどころミスはありつつも
クリア自体は難なく達成できました。
ところが・・・そのギャラリーたちの反応は芳しくない。
恥ずかしいのではっきりした様子は見てないのですが、
想像できる原因はいくつかあります。
1つめは、動作や譜面にヒいていたということ。
この曲のラストは譜面を見る限りでも
かなり大袈裟でしたし、
それに相反するかのように、
演奏には妙にこちょこちょした動作が求められるわけです。
2つめは、クリアしたはいいけどミスも多かったこと。
それも画面上のミスではなく、演奏上のミス。
ゲーム内容を知らないギャラリーにとっちゃ
いくらGREAT繋げようが聴こえが悪けりゃミスなわけで。
3つめは、楽曲にピンと来なかったこと。
ハウスは4つ打ちのわかりやすいダンスミュージックでしたけど、
スカは当時、世間的にはマイナーなジャンルでしたからね。
そうじゃなくても、
ハウスが現在でも名曲として名をとどめているのに比べ、
スカはどうでしょうか?
オイラは結局、ゲーム的な印象しか
残っていなかったりします。
上記のような状況は
現在じゃ解決されるどころか加速しきってしまい、
プレイヤーとギャラリーの間の越えられない壁として
完全に居座ってしまったように思います。
2ndMIXの時代からこの萌芽があったということには
色々と考えさせられてしまうのですが・・・
詳しい考察はまた、こんど。













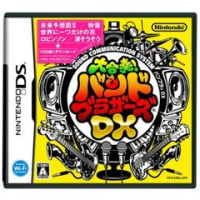
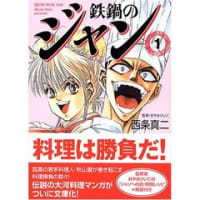
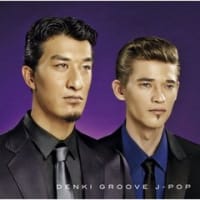
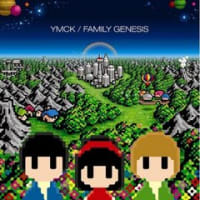

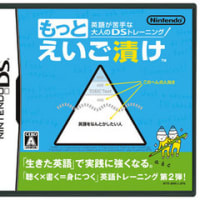

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます