
見てきました
国立西洋美術館
会期は2014年7月8日から2014年9月15日。
今回は指輪。
指輪を中心とする宝飾品約870点からなる"橋本コレクション"が国立西洋美術館に寄贈されたことを記念する企画。
2012年にこのコレクションを収蔵して以来、初のお披露目です。
橋本貫志氏(1924-)が収集した760点あまりの指輪は、年代や素材に偏りがなく、極めて広範な内容を持っているのだそう。
この展示では約300点の指輪を一挙に公開。
橋本コレクションの個性豊かな顔ぶれが見れちゃうということで楽しみに行ってきました。
今回、かなりの量なので2回に分けて書いていきます。
今日は「その1」です。
《1.指輪の4000年》
1「スカラベ」
紀元前1991-1650年頃・エジプト
薄い紫色のキレイな石のついた指輪。
なんとこの石、フンコロガシがモチーフなんだそう。。。
何でもフンを転がすのが太陽の動きに見立てられたとか。
また古代エジプト人にとって復活・再生のモチーフでもあり、フンコロガシは重要な虫なんだとか。。。
なんか複雑。
これは装飾用ではなくお守りとして用いられたんだそう。
2「スカラベ」
紀元前1539-1069年頃・エジプト
こちらは青色がとってもキレイ。
ヒエログリフで"天空の神アメン・ラー"と書かれているのだそう。
4「あぶみ形の指輪」
紀元前1295-525年頃・エジプト
儀式で使われた飾り舟が施されているリング。
ツタンカーメンの墓で見つかった指輪にも似た図柄があったのだそう。
6「ロゼット紋の指輪」
紀元前664-525年頃・エルトリア
金でできたバラの花を模した指輪。
このモチーフは古代人お気に入りだったとか。
エルトリア人は優れた金の加工技術を持っていたそうです。
この指輪、バラというよりはガーベラなどに見えますが花びら一枚一枚まで繊細に作られています。
9「女神ニケ」
紀元前4世紀後期・古典期ギリシャ
ニケはギリシャ神話の勝利の女神。
青いガラスの上に金箔で描かれ、小さなロゼット文に囲まれています。
14「金製指輪」
2-3世紀・古代ローマ
2粒のガーネットがついている指輪。
これが橋本コレクションのはじまりなのだそう
25「パパル・リング」
15世紀・イタリア
いきなり時代が進んで中世。
パパル・リングとは教皇のリング。
水晶のような色の石がついています。
なんとなく、強そう。
34「六弁花のベゼルを持つ金製指輪」
16世紀後期
緑や赤などのさまざまな色の石が使われ華やか。
ベゼルが花のようです。
36「クラスター・リング」
17世紀
大ぶりのひとつの石(ソリティア)が入手困難となり、その代わりに小ぶりの石を寄せ集めたもの。
それでもとても華やか。
38「哀悼の指輪」
1756年・イギリス
白いリボンのような装飾を施された指輪。
その名のとおり、哀悼の指輪。
内側には"AMBホッジ 1756年5月9日40才で永眠"との言葉が。
お守りとして、権力の象徴として、装飾品として、愛のかたちとして。
さまざまに使われてきた指輪はこのようなことにも使われたんですね。
40「花かご」
41「花束」
18世紀後期
これらはガラスの中に螺鈿や真珠でその模様が施されているのです。
ガラスの透明度が高く、その模様がはっきり見えとても素敵。
さわやかで美しい指輪です。
45「星が浦」
18世紀
青いガラスに金や銀で星を施し"切り取った天空"として人気のデザインだったのだそう。
周りはパールで囲まれとても素敵です。
この展示は橋本氏が寄贈したコレクションを紹介しているものですが、これだけは橋本氏の所蔵。
橋本氏が夫人を偲んでつけたその名前。
かつて夫人が暮らしていた大連の星が浦のイメージだそう。
星が浦(現在の星海公園)は、夜になると海面いっぱいに天空の星たちが映り、それはそれはきれいな大宇宙のよう、との思い出話によるそうです。
なんてロマンティックで素敵な話なんだろう。
56「若いヴィクトリア女王の肖像」
ヴィクトリア女王は自らの肖像を収めた指輪、ブレスレット、タイピンなどを婚礼や戴冠式などの歳に配っていたのだそう。
これもそのうちのひとつ。
若く気品ある女性がいました。
64「マーキーズ形の指輪」
1900年頃・アメリカ
ボートのような形をしているものをマーキーズ形というそう。
これはダイヤに囲まれたサファイアという豪華なもの。
色の組み合わせもさわやかで素敵です。
67ジョン・ポール・クーパー「アーツ・アンド・クラフツのリング」
1900年頃・イギリス
アーツ・アンド・クラフツはジュエリーの分野にまで。
この分野は建築家のヘンリー・ウィルソンがひっぱっていましたが、この作者は同僚。
こういった芸術活動も影響を与えているんですね。
73ルネ・ラリック「葉のプリカジュール」
1900年頃・フランス
今度はアール・ヌーヴォー。
葉に真珠のついたデザイン。
このあたりにはラリックによるデザイン画も展示されていました。
79「ミルグレイン・リング」
1920年頃
今度はアール・デコ。
幾何学的で中央に3つの石が縦に配置されています。
おしゃれでかっこいい。
91「カルティエ製スプートニク・リング」
1957年頃・フランス
今度はデザイナーたちがデザインしたブランドのリング。
これは1957年のソ連の人工衛星スプートニクに着想を得た指輪。
さまざまな色の石が輝き、不思議な印象です。
92「ヴァン クーリフ&アーペル製リング」
1936年頃・フランス
カーブした地金に留め具が見えないように石留めをするインビジブル・セッティング。
ヴァン クーリフ&アーペル社のオリジナル技法ですが、この作品にすでに使われています。
そんな昔からこれをやっているんですね。。
《2.飾らない指輪》
109「ヒキガエル石の指輪」
14世紀・イギリス
ちょっと装飾品にするには…な色の石。
蛙は頭に宝石を持っていると信じられ、このヒキガエル石も蛙の頭からとれたとされたもの。
実際は化石化した魚類の歯だそう。
制毒の働きがあると信じられ、毒に近づくと、その石は汗をかき色が変わると言われていました。
お守りですね。
117「フルール・ド・リスが彫刻されたダイヤの指輪」
18世紀後期・フランス
束ねられた3枚の百合の花びらからなるフランス王家の紋章の一つがダイヤに彫り込まれています。
これは難しい技術のため、あまり作例がないそう。
細部までしっかり表現されていて、とてもきれいで輝いていました。
《3.語る指輪》
128「ネメアの獅子と闘うヘラクレス」
紀元前2-1世紀・ヘレニズム文化圏
ヘラクレスのネメアの谷の獅子との戦いをモチーフとしたもの。
こんなに小さいところによくできるなぁ、と感心。
130「ヘラクレスとステュムパリデスの鳥」
紀元前4世紀頃・エルトリア
こちらもヘラクレスで鳥退治。
弓を引く場面です。
このあたりには西洋美術館所蔵の版画も展示されていて、とても分かりやすい。
140「犠牲式を表すカメオ」
紀元前1世紀、マウントは現在・古代ローマ
生贄をささげる儀式をわずか1cmほどの大きさに表現しています。
右の男性が子羊を捧げ、左ではサテュロスが笛を吹いています。
なんてすごい技術。
141「レダと白鳥」
16世紀
絵画でおなじみのテーマも指輪になります。
ここにはサルバドール・ダリ「『神話篇』:レダ」が展示されていて、そちらの方に目がいってしまいました。。。
144「聖ゲオルギウスと龍」
15世紀・スカンジナビア
聖ゲオルギウスは小アジア・カッパドキア生まれ。
3世紀末に殉教しています。
よく見るイメージは馬にのり龍と戦う場面ですが、ここでは槍を手にし龍に乗りかかって戦っています。
これって、装飾用、、、ではないよね。
イメージ的にはお守りかと思うのですが。
146「聖カタリナ」
15世紀・イギリス
聖カタリナといえば車輪。
ここでも車輪が一緒に描かれています。
こんなに細かいのに……
149「受胎告知」
16世紀、マウントは後期
おそらくヴェネツィア
このあたりは西洋絵画でもおなじみのモチーフ。
155デューリック・バウツ(派)「悲しみの聖母」「荊冠のキリスト」
こちらは絵画。
目を真っ赤にし泣き腫らす聖母とキリスト。
キリストは荊の冠のため、おでこから血が流れています。
キリストの手が小さく描かれていてちょっと違和感……
152アドリアーン・イーゼンブラント(に帰属)「玉座の聖母子」
こちらも絵画。
建物の中の椅子に座る聖母子。
かなり立派な建物です。
衣服の布の感じも丁寧に表現されています。
165エル・グレコ「十字架のキリスト」
こちらも絵画。
磔刑のキリストです。
空には暗い雲。
十字架の足元には人骨が転がっています。
マニエリスムで伸ばされた体が、異様な雰囲気を増しているように思います。
159「祈祷のための指輪」
17世紀・ヨーロッパ(ローマ・カトリック)
160「イエスの名が刻まれた指輪」
16-17世紀
どちらも"IHS"と施されています。
ラテン語でIesus Hominum Salvator(救いの人 イエス)の略称です。
このような小さな指輪にも信仰心は託されているのですね。
161「ゴルゴダの丘の十字架」
丘に十字架のみが立っています。
シンプルですが、逆に信仰心が伝わってくる作品。
163「十字架のキリストと聖母マリア、聖ヨハネ」
17世紀
小さい中に3人がいる作品。
このような作品ばかり見ていると、世界は手先の器用な人ばかりなんだ、と別の方向で感心。
164「十字架のキリスト」
19世紀前期・イタリア
指輪のカーブに沿って磔となったキリストが施されています。
すごい発想。
実際にこのポーズやったら背中バキバキ言うでしょう。笑
《4.技術と模倣》
172「スカラベと粒金細工」
19世紀後期・イタリア
エルトリアの金細工の技術が使われた作品は垂涎の的でした。
しかし、簡単に手に入るものではない。
今では技術も分からない。
そこで粒金細工の技術を使って模造し手に入るようになりました。
こうやって技術が生まれていくのですね。
205ナサニエル・マーチャント「ユピテル・セラピスのインタリオ」
1779年・イギリス
描かれている人物はデューラーにちょっと似ています。
カメオですが、古代ローマ風に作りたくて模造したものだそう。
以上が「その1」になります。
まだまだ作品はたっぷり。
「その2」も長文の予定です。
ブログランキングよかったらお願いします


国立西洋美術館

会期は2014年7月8日から2014年9月15日。
今回は指輪。
指輪を中心とする宝飾品約870点からなる"橋本コレクション"が国立西洋美術館に寄贈されたことを記念する企画。
2012年にこのコレクションを収蔵して以来、初のお披露目です。
橋本貫志氏(1924-)が収集した760点あまりの指輪は、年代や素材に偏りがなく、極めて広範な内容を持っているのだそう。
この展示では約300点の指輪を一挙に公開。
橋本コレクションの個性豊かな顔ぶれが見れちゃうということで楽しみに行ってきました。
今回、かなりの量なので2回に分けて書いていきます。
今日は「その1」です。
《1.指輪の4000年》
1「スカラベ」
紀元前1991-1650年頃・エジプト
薄い紫色のキレイな石のついた指輪。
なんとこの石、フンコロガシがモチーフなんだそう。。。
何でもフンを転がすのが太陽の動きに見立てられたとか。
また古代エジプト人にとって復活・再生のモチーフでもあり、フンコロガシは重要な虫なんだとか。。。
なんか複雑。
これは装飾用ではなくお守りとして用いられたんだそう。
2「スカラベ」
紀元前1539-1069年頃・エジプト
こちらは青色がとってもキレイ。
ヒエログリフで"天空の神アメン・ラー"と書かれているのだそう。
4「あぶみ形の指輪」
紀元前1295-525年頃・エジプト
儀式で使われた飾り舟が施されているリング。
ツタンカーメンの墓で見つかった指輪にも似た図柄があったのだそう。
6「ロゼット紋の指輪」
紀元前664-525年頃・エルトリア
金でできたバラの花を模した指輪。
このモチーフは古代人お気に入りだったとか。
エルトリア人は優れた金の加工技術を持っていたそうです。
この指輪、バラというよりはガーベラなどに見えますが花びら一枚一枚まで繊細に作られています。
9「女神ニケ」
紀元前4世紀後期・古典期ギリシャ
ニケはギリシャ神話の勝利の女神。
青いガラスの上に金箔で描かれ、小さなロゼット文に囲まれています。
14「金製指輪」
2-3世紀・古代ローマ
2粒のガーネットがついている指輪。
これが橋本コレクションのはじまりなのだそう
25「パパル・リング」
15世紀・イタリア
いきなり時代が進んで中世。
パパル・リングとは教皇のリング。
水晶のような色の石がついています。
なんとなく、強そう。
34「六弁花のベゼルを持つ金製指輪」
16世紀後期
緑や赤などのさまざまな色の石が使われ華やか。
ベゼルが花のようです。
36「クラスター・リング」
17世紀
大ぶりのひとつの石(ソリティア)が入手困難となり、その代わりに小ぶりの石を寄せ集めたもの。
それでもとても華やか。
38「哀悼の指輪」
1756年・イギリス
白いリボンのような装飾を施された指輪。
その名のとおり、哀悼の指輪。
内側には"AMBホッジ 1756年5月9日40才で永眠"との言葉が。
お守りとして、権力の象徴として、装飾品として、愛のかたちとして。
さまざまに使われてきた指輪はこのようなことにも使われたんですね。
40「花かご」
41「花束」
18世紀後期
これらはガラスの中に螺鈿や真珠でその模様が施されているのです。
ガラスの透明度が高く、その模様がはっきり見えとても素敵。
さわやかで美しい指輪です。
45「星が浦」
18世紀
青いガラスに金や銀で星を施し"切り取った天空"として人気のデザインだったのだそう。
周りはパールで囲まれとても素敵です。
この展示は橋本氏が寄贈したコレクションを紹介しているものですが、これだけは橋本氏の所蔵。
橋本氏が夫人を偲んでつけたその名前。
かつて夫人が暮らしていた大連の星が浦のイメージだそう。
星が浦(現在の星海公園)は、夜になると海面いっぱいに天空の星たちが映り、それはそれはきれいな大宇宙のよう、との思い出話によるそうです。
なんてロマンティックで素敵な話なんだろう。
56「若いヴィクトリア女王の肖像」
ヴィクトリア女王は自らの肖像を収めた指輪、ブレスレット、タイピンなどを婚礼や戴冠式などの歳に配っていたのだそう。
これもそのうちのひとつ。
若く気品ある女性がいました。
64「マーキーズ形の指輪」
1900年頃・アメリカ
ボートのような形をしているものをマーキーズ形というそう。
これはダイヤに囲まれたサファイアという豪華なもの。
色の組み合わせもさわやかで素敵です。
67ジョン・ポール・クーパー「アーツ・アンド・クラフツのリング」
1900年頃・イギリス
アーツ・アンド・クラフツはジュエリーの分野にまで。
この分野は建築家のヘンリー・ウィルソンがひっぱっていましたが、この作者は同僚。
こういった芸術活動も影響を与えているんですね。
73ルネ・ラリック「葉のプリカジュール」
1900年頃・フランス
今度はアール・ヌーヴォー。
葉に真珠のついたデザイン。
このあたりにはラリックによるデザイン画も展示されていました。
79「ミルグレイン・リング」
1920年頃
今度はアール・デコ。
幾何学的で中央に3つの石が縦に配置されています。
おしゃれでかっこいい。
91「カルティエ製スプートニク・リング」
1957年頃・フランス
今度はデザイナーたちがデザインしたブランドのリング。
これは1957年のソ連の人工衛星スプートニクに着想を得た指輪。
さまざまな色の石が輝き、不思議な印象です。
92「ヴァン クーリフ&アーペル製リング」
1936年頃・フランス
カーブした地金に留め具が見えないように石留めをするインビジブル・セッティング。
ヴァン クーリフ&アーペル社のオリジナル技法ですが、この作品にすでに使われています。
そんな昔からこれをやっているんですね。。
《2.飾らない指輪》
109「ヒキガエル石の指輪」
14世紀・イギリス
ちょっと装飾品にするには…な色の石。
蛙は頭に宝石を持っていると信じられ、このヒキガエル石も蛙の頭からとれたとされたもの。
実際は化石化した魚類の歯だそう。
制毒の働きがあると信じられ、毒に近づくと、その石は汗をかき色が変わると言われていました。
お守りですね。
117「フルール・ド・リスが彫刻されたダイヤの指輪」
18世紀後期・フランス
束ねられた3枚の百合の花びらからなるフランス王家の紋章の一つがダイヤに彫り込まれています。
これは難しい技術のため、あまり作例がないそう。
細部までしっかり表現されていて、とてもきれいで輝いていました。
《3.語る指輪》
128「ネメアの獅子と闘うヘラクレス」
紀元前2-1世紀・ヘレニズム文化圏
ヘラクレスのネメアの谷の獅子との戦いをモチーフとしたもの。
こんなに小さいところによくできるなぁ、と感心。
130「ヘラクレスとステュムパリデスの鳥」
紀元前4世紀頃・エルトリア
こちらもヘラクレスで鳥退治。
弓を引く場面です。
このあたりには西洋美術館所蔵の版画も展示されていて、とても分かりやすい。
140「犠牲式を表すカメオ」
紀元前1世紀、マウントは現在・古代ローマ
生贄をささげる儀式をわずか1cmほどの大きさに表現しています。
右の男性が子羊を捧げ、左ではサテュロスが笛を吹いています。
なんてすごい技術。
141「レダと白鳥」
16世紀
絵画でおなじみのテーマも指輪になります。
ここにはサルバドール・ダリ「『神話篇』:レダ」が展示されていて、そちらの方に目がいってしまいました。。。
144「聖ゲオルギウスと龍」
15世紀・スカンジナビア
聖ゲオルギウスは小アジア・カッパドキア生まれ。
3世紀末に殉教しています。
よく見るイメージは馬にのり龍と戦う場面ですが、ここでは槍を手にし龍に乗りかかって戦っています。
これって、装飾用、、、ではないよね。
イメージ的にはお守りかと思うのですが。
146「聖カタリナ」
15世紀・イギリス
聖カタリナといえば車輪。
ここでも車輪が一緒に描かれています。
こんなに細かいのに……
149「受胎告知」
16世紀、マウントは後期
おそらくヴェネツィア
このあたりは西洋絵画でもおなじみのモチーフ。
155デューリック・バウツ(派)「悲しみの聖母」「荊冠のキリスト」
こちらは絵画。
目を真っ赤にし泣き腫らす聖母とキリスト。
キリストは荊の冠のため、おでこから血が流れています。
キリストの手が小さく描かれていてちょっと違和感……
152アドリアーン・イーゼンブラント(に帰属)「玉座の聖母子」
こちらも絵画。
建物の中の椅子に座る聖母子。
かなり立派な建物です。
衣服の布の感じも丁寧に表現されています。
165エル・グレコ「十字架のキリスト」
こちらも絵画。
磔刑のキリストです。
空には暗い雲。
十字架の足元には人骨が転がっています。
マニエリスムで伸ばされた体が、異様な雰囲気を増しているように思います。
159「祈祷のための指輪」
17世紀・ヨーロッパ(ローマ・カトリック)
160「イエスの名が刻まれた指輪」
16-17世紀
どちらも"IHS"と施されています。
ラテン語でIesus Hominum Salvator(救いの人 イエス)の略称です。
このような小さな指輪にも信仰心は託されているのですね。
161「ゴルゴダの丘の十字架」
丘に十字架のみが立っています。
シンプルですが、逆に信仰心が伝わってくる作品。
163「十字架のキリストと聖母マリア、聖ヨハネ」
17世紀
小さい中に3人がいる作品。
このような作品ばかり見ていると、世界は手先の器用な人ばかりなんだ、と別の方向で感心。
164「十字架のキリスト」
19世紀前期・イタリア
指輪のカーブに沿って磔となったキリストが施されています。
すごい発想。
実際にこのポーズやったら背中バキバキ言うでしょう。笑
《4.技術と模倣》
172「スカラベと粒金細工」
19世紀後期・イタリア
エルトリアの金細工の技術が使われた作品は垂涎の的でした。
しかし、簡単に手に入るものではない。
今では技術も分からない。
そこで粒金細工の技術を使って模造し手に入るようになりました。
こうやって技術が生まれていくのですね。
205ナサニエル・マーチャント「ユピテル・セラピスのインタリオ」
1779年・イギリス
描かれている人物はデューラーにちょっと似ています。
カメオですが、古代ローマ風に作りたくて模造したものだそう。
以上が「その1」になります。
まだまだ作品はたっぷり。
「その2」も長文の予定です。
ブログランキングよかったらお願いします


















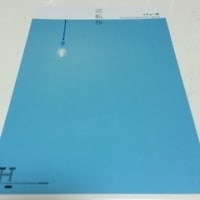
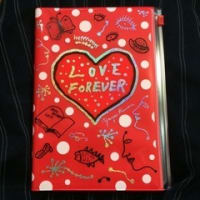


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます