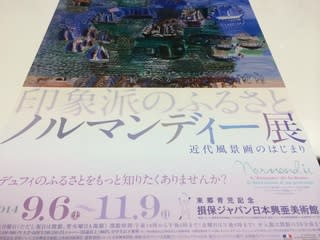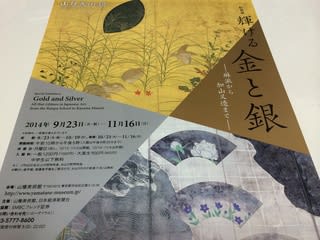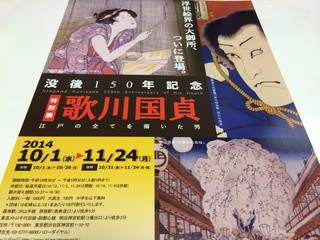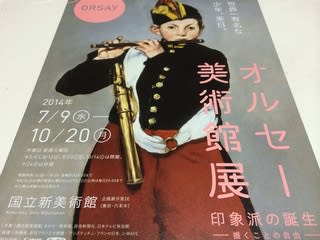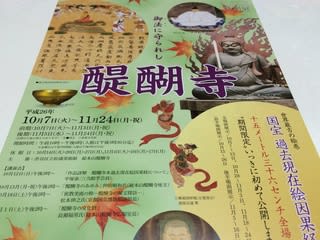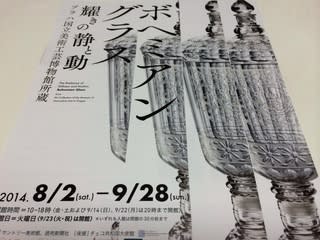毎年恒例、大晦日に書いていたものですが、今回は年明けとなってしまいました。
後半、かなりペースが落ちてしまいましたが、今年もそこそこの量の展示を見てきたと思います。
今、見返すとどの展示も思い入れがあります。
それらを順位づけるのはかなり難しいのですが……
早速、10位から書いていきます。
第10位
「泥象 鈴木治の世界 「使う陶」から「観る陶」、そして「詠む陶」へ」(東京ステーションギャラリー)
鈴木治(1926-2001)の没後初めての大規模個展。
初期から晩年までの未発表作品を含む約140点の展示となっていました。
こんな陶器もあるのかと、驚かされた展示でした。
簡潔ですが温かみのある造形。
詩情を感じさせるタイトル。
すごく素敵な空間だったことを思い出します。
第9位
「ザ・ビューティフル 英国の唯美主義1860-1900」(三菱一号館美術館)
記事はこちら→「その1」「その2」
第8位
「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」(森アーツミュージアム)
記事はこちら→「その1」「その2」
8位と9位を一緒に書いてしまいます。
このころの記事の長さにびっくりしました。笑
9位は日本初の唯美主義展です。
ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館所蔵作品を中心に、油彩画、家具工芸品をはじめとする約140点の展示。
唯美主義とは19世紀半ばのイギリスで発生したもの。
若手芸術家のあいたでは古い慣習や堅苦しい約束事から離れて「新たな美」を見出したいという欲求が沸き起こります。
それまでの物語的な要素を重視せず、視覚的な美しさを追求したものです。
この活動はラファエル前派ともつながりがあり、ラファエル前派展とお得なのチケットも発売されました。
モリスにロセッティ、エドワード・バーン=ジョーンズなどのお馴染みの面々の作品がずらり。
その美しさを追求する姿勢にうっとり。
空間の美しさにもうっとりな展示でした。
そして、8位のラファエル前派展。
1848年、ロンドン、ロイヤル・アカデミーで学ぶ
ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ
ウィリアム・ホルマン・ハント
ジョン・エヴァレット・ミレイ
上記3人が中心となり、
ジェームズ・コリンソン
フレデリック・ジョージ・スティーヴンス
トーマス・ウールナー
ウィリアム・マイケル・ロセッティ
の4人が加わって結成された集団。
正式名称は《Pre-Raphaelite Brotherhood》
アカデミーの慣行からはかけ離れた絵画だったため、批判を受けますが、それらの作品は新興富裕層の心を捉えます。
ジョン・エヴァレット・ミレイの「オフィーリア」が来日したことでも大きな話題となった展示。
オフィーリアを見るのは2回目でしたが、その美しさは健在。
絵画の中で悲しく美しく横たわっていました。
どの作品も見ごたえがあり、とても素敵な展示でした。
第7位
「星を賣る店 クラフト・エヴィング商會のおかしな展覧会」(世田谷文学館)
吉田浩美氏と吉田篤弘氏による、著作およびデザイン・ワーク、アートワークのユニット「クラフト・エヴィング商會」
いいなと思ったり、欲しいと望んでいるものを世に届けているクラフト・エヴィング商會。
初の棚卸し的展覧会でした。
その想像の世界の豊かさに見ていて心躍る展示でした。
星とは夢なのかな。
夢の詰まった、まるで物語のような展示でした。
第6位
「たよりない現実、この世界の在りか」(SHISEIDO GALLERY)
なんとも不思議なタイトルの展示。
若手アーティスト荒神明香さんと、参加者とともにアート作品のアイデアを実現する活動を行うwah document(南川憲二、増井宏文)によって組織された現代芸術活動チーム 目【め】の東京での初めての個展。
SHISEIDO GALLERYがいつもとホテルTGとなっていました。
不思議な不思議なホテルです。
ぞわぞわする展示でした。
ちょっとした迷宮のようで、今思い出しても強烈に頭の中に残っています。
第5位
「菱田春草展」(東京国立近代美術館)
菱田春草(1874-1911)
近代日本画家。
草創期の東京美術学校を卒業後、天心の日本美術院創立に参加。
「朦朧体」の試みや装飾的画風などで、それまでの日本画を色彩溢れるものへと変貌させました。
近年は、岡倉天心没後100年(2013)、下村観山生誕140年(2013)、日本美術院再興100年(2014)と、日本美術院に関連するメモリアルが続いています。
今回は春草生誕140年記念の回顧展。
横山大観展、下村観山展につづき、まさに待望の菱田春草展でした。
代表作「黒き猫」も展示され、作品の前は黒山の人だかり。
36歳という若さで亡くなった春草の画業はおよそ15年と短いのですが、そんなことを感じさせないくらい素晴らしい作品ばかりでした。
どれも見ごたえたっぷり。
春草、大好き。
第4位
「開館10周年記念 レアンドロ・エルリッヒ -ありきたりの?」(金沢21世紀美術館)
今年嬉しかったことの一つ、金沢21世紀美術館へ行けたこと。
そしてレアンドロ・エルリッヒの展示が見れたこと。
金沢21世紀美術館は開館10周年。
ブエノスアイレス生まれのレアンドロ・エルリッヒ(1973-)の日本初個展でした。
レアンドロ・エルリッヒは、金沢21世紀美術館にとって特別なアーティストの一人。
21世紀美術館の所蔵品の中で最も有名なものの一つ。
「スイミング・プール」
これは「レアンドロのプール」として親しまれています。
今回は最新作を含む全17点の展示。
日常の当たり前と思っている光景を、当たりまえに見ようとすると驚きます。
この展示はレアンドロらしさがいっぱいで、とても楽しく見れました。
都内でもまたやってほしいな~。
第3位
「バルテュス展」(東京都美術館)
記事はこちら→「その1」「その2」
"賞賛と誤解だらけの20世紀最後の巨匠"
こんなフレーズが描かれたチラシ。
少女が下着を見せるような挑発的なポーズ。
ただ、私はこれで一気に惹かれてしまったのです。
それが何かはうまく言えないのですが。
こんなふうに書いている過去の私。
ただとにかく衝撃的でした。
バルテュス(1908-2001)
本名バルタザール・クロソフスキー・ド・ローラ。
美術学校に通うことなく、独自に技術を身に付け、作品を世に送り出します。
ピカソをして
"20世紀最後の巨匠"
と言わしめたバルテュス。
その生涯を辿る形での展示。
生涯にわたり少女たちを描き続けたバルテュス。
注目を浴びるための苦肉の策の少女。
そして"この上なく完璧な美の象徴"
それらは美術館の展示室で輝き、不思議な美しさを放っていました。
その妖艶さは今思い出してもため息ものです。
第2位
「こども展 名画にみるこどもと画家の絆」(森アーツセンターギャラリー)
記事はこちら→「その1」「その2」「その3」
「こども」がテーマをした展示。
作品は19世紀初めから20世紀末までの約200年。
モネ、ルノワール、ルソー、マティス、ピカソなど錚々たる画家48人が描いた作品です。
作家自身のこどもを描いたものが多く、温かい家庭が見えてくるものでした。
オランジェリー、オルセーほかルーヴルなどはもちろん、画家の遺族が保管していたプライベートコレクションなどからの出品で約3分の2は日本初公開。
それぞれの画家の思い思いのこどもが描かれていて、とても楽しく鑑賞できました。
また世相を反映したものもあり、その時代のこどもの置かれいてる環境なども見れました。
ボリュームたっぷりで見ごたえありました。
第1位
「ヴァロットン -冷たい炎の画家」(三菱一号館美術館)
この記事、きちんと書いていないことが残念です。
記事を見ると、「あぁ、あのときあの作品のこんなところに共感したんだな」とか思い出すのですが……
この展示、とても面白くて私は3度見に行きました。
フェリックス・ヴァロットン(1865-1925)
画家で木版画家。
スイスに生まれ、パリで活躍。
没後は忘れられていた作家。
その画業を総覧する回顧展がパリ・オランダを巡回し、日本へやってきました。
ヨーロッパでも回顧展は数えるほどしか開催されておらず、日本では今回が初めて。
その描写力の高さ、どこか人を惹き付ける冷たさ。
絵に対する不思議な情熱。
奇妙な景色に奇妙な人物。
心に引っ掛かるところが多く、不思議な魅力にあふれていました。
2014年はキトラ古墳壁画が東京へやってきたり、台湾國立故宮博物院の至宝がやってきたり。
個人的には道後オンセナートを見に道後温泉まで行きました。
2015年もたくさんの展示を見て、書くこといっぱいあるといいな。
今年もよろしくお願いいたします。
ブログランキングよかったらお願いします

後半、かなりペースが落ちてしまいましたが、今年もそこそこの量の展示を見てきたと思います。
今、見返すとどの展示も思い入れがあります。
それらを順位づけるのはかなり難しいのですが……
早速、10位から書いていきます。
第10位
「泥象 鈴木治の世界 「使う陶」から「観る陶」、そして「詠む陶」へ」(東京ステーションギャラリー)
鈴木治(1926-2001)の没後初めての大規模個展。
初期から晩年までの未発表作品を含む約140点の展示となっていました。
こんな陶器もあるのかと、驚かされた展示でした。
簡潔ですが温かみのある造形。
詩情を感じさせるタイトル。
すごく素敵な空間だったことを思い出します。
第9位
「ザ・ビューティフル 英国の唯美主義1860-1900」(三菱一号館美術館)
記事はこちら→「その1」「その2」
第8位
「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」(森アーツミュージアム)
記事はこちら→「その1」「その2」
8位と9位を一緒に書いてしまいます。
このころの記事の長さにびっくりしました。笑
9位は日本初の唯美主義展です。
ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館所蔵作品を中心に、油彩画、家具工芸品をはじめとする約140点の展示。
唯美主義とは19世紀半ばのイギリスで発生したもの。
若手芸術家のあいたでは古い慣習や堅苦しい約束事から離れて「新たな美」を見出したいという欲求が沸き起こります。
それまでの物語的な要素を重視せず、視覚的な美しさを追求したものです。
この活動はラファエル前派ともつながりがあり、ラファエル前派展とお得なのチケットも発売されました。
モリスにロセッティ、エドワード・バーン=ジョーンズなどのお馴染みの面々の作品がずらり。
その美しさを追求する姿勢にうっとり。
空間の美しさにもうっとりな展示でした。
そして、8位のラファエル前派展。
1848年、ロンドン、ロイヤル・アカデミーで学ぶ
ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ
ウィリアム・ホルマン・ハント
ジョン・エヴァレット・ミレイ
上記3人が中心となり、
ジェームズ・コリンソン
フレデリック・ジョージ・スティーヴンス
トーマス・ウールナー
ウィリアム・マイケル・ロセッティ
の4人が加わって結成された集団。
正式名称は《Pre-Raphaelite Brotherhood》
アカデミーの慣行からはかけ離れた絵画だったため、批判を受けますが、それらの作品は新興富裕層の心を捉えます。
ジョン・エヴァレット・ミレイの「オフィーリア」が来日したことでも大きな話題となった展示。
オフィーリアを見るのは2回目でしたが、その美しさは健在。
絵画の中で悲しく美しく横たわっていました。
どの作品も見ごたえがあり、とても素敵な展示でした。
第7位
「星を賣る店 クラフト・エヴィング商會のおかしな展覧会」(世田谷文学館)
吉田浩美氏と吉田篤弘氏による、著作およびデザイン・ワーク、アートワークのユニット「クラフト・エヴィング商會」
いいなと思ったり、欲しいと望んでいるものを世に届けているクラフト・エヴィング商會。
初の棚卸し的展覧会でした。
その想像の世界の豊かさに見ていて心躍る展示でした。
星とは夢なのかな。
夢の詰まった、まるで物語のような展示でした。
第6位
「たよりない現実、この世界の在りか」(SHISEIDO GALLERY)
なんとも不思議なタイトルの展示。
若手アーティスト荒神明香さんと、参加者とともにアート作品のアイデアを実現する活動を行うwah document(南川憲二、増井宏文)によって組織された現代芸術活動チーム 目【め】の東京での初めての個展。
SHISEIDO GALLERYがいつもとホテルTGとなっていました。
不思議な不思議なホテルです。
ぞわぞわする展示でした。
ちょっとした迷宮のようで、今思い出しても強烈に頭の中に残っています。
第5位
「菱田春草展」(東京国立近代美術館)
菱田春草(1874-1911)
近代日本画家。
草創期の東京美術学校を卒業後、天心の日本美術院創立に参加。
「朦朧体」の試みや装飾的画風などで、それまでの日本画を色彩溢れるものへと変貌させました。
近年は、岡倉天心没後100年(2013)、下村観山生誕140年(2013)、日本美術院再興100年(2014)と、日本美術院に関連するメモリアルが続いています。
今回は春草生誕140年記念の回顧展。
横山大観展、下村観山展につづき、まさに待望の菱田春草展でした。
代表作「黒き猫」も展示され、作品の前は黒山の人だかり。
36歳という若さで亡くなった春草の画業はおよそ15年と短いのですが、そんなことを感じさせないくらい素晴らしい作品ばかりでした。
どれも見ごたえたっぷり。
春草、大好き。
第4位
「開館10周年記念 レアンドロ・エルリッヒ -ありきたりの?」(金沢21世紀美術館)
今年嬉しかったことの一つ、金沢21世紀美術館へ行けたこと。
そしてレアンドロ・エルリッヒの展示が見れたこと。
金沢21世紀美術館は開館10周年。
ブエノスアイレス生まれのレアンドロ・エルリッヒ(1973-)の日本初個展でした。
レアンドロ・エルリッヒは、金沢21世紀美術館にとって特別なアーティストの一人。
21世紀美術館の所蔵品の中で最も有名なものの一つ。
「スイミング・プール」
これは「レアンドロのプール」として親しまれています。
今回は最新作を含む全17点の展示。
日常の当たり前と思っている光景を、当たりまえに見ようとすると驚きます。
この展示はレアンドロらしさがいっぱいで、とても楽しく見れました。
都内でもまたやってほしいな~。
第3位
「バルテュス展」(東京都美術館)
記事はこちら→「その1」「その2」
"賞賛と誤解だらけの20世紀最後の巨匠"
こんなフレーズが描かれたチラシ。
少女が下着を見せるような挑発的なポーズ。
ただ、私はこれで一気に惹かれてしまったのです。
それが何かはうまく言えないのですが。
こんなふうに書いている過去の私。
ただとにかく衝撃的でした。
バルテュス(1908-2001)
本名バルタザール・クロソフスキー・ド・ローラ。
美術学校に通うことなく、独自に技術を身に付け、作品を世に送り出します。
ピカソをして
"20世紀最後の巨匠"
と言わしめたバルテュス。
その生涯を辿る形での展示。
生涯にわたり少女たちを描き続けたバルテュス。
注目を浴びるための苦肉の策の少女。
そして"この上なく完璧な美の象徴"
それらは美術館の展示室で輝き、不思議な美しさを放っていました。
その妖艶さは今思い出してもため息ものです。
第2位
「こども展 名画にみるこどもと画家の絆」(森アーツセンターギャラリー)
記事はこちら→「その1」「その2」「その3」
「こども」がテーマをした展示。
作品は19世紀初めから20世紀末までの約200年。
モネ、ルノワール、ルソー、マティス、ピカソなど錚々たる画家48人が描いた作品です。
作家自身のこどもを描いたものが多く、温かい家庭が見えてくるものでした。
オランジェリー、オルセーほかルーヴルなどはもちろん、画家の遺族が保管していたプライベートコレクションなどからの出品で約3分の2は日本初公開。
それぞれの画家の思い思いのこどもが描かれていて、とても楽しく鑑賞できました。
また世相を反映したものもあり、その時代のこどもの置かれいてる環境なども見れました。
ボリュームたっぷりで見ごたえありました。
第1位
「ヴァロットン -冷たい炎の画家」(三菱一号館美術館)
この記事、きちんと書いていないことが残念です。
記事を見ると、「あぁ、あのときあの作品のこんなところに共感したんだな」とか思い出すのですが……
この展示、とても面白くて私は3度見に行きました。
フェリックス・ヴァロットン(1865-1925)
画家で木版画家。
スイスに生まれ、パリで活躍。
没後は忘れられていた作家。
その画業を総覧する回顧展がパリ・オランダを巡回し、日本へやってきました。
ヨーロッパでも回顧展は数えるほどしか開催されておらず、日本では今回が初めて。
その描写力の高さ、どこか人を惹き付ける冷たさ。
絵に対する不思議な情熱。
奇妙な景色に奇妙な人物。
心に引っ掛かるところが多く、不思議な魅力にあふれていました。
2014年はキトラ古墳壁画が東京へやってきたり、台湾國立故宮博物院の至宝がやってきたり。
個人的には道後オンセナートを見に道後温泉まで行きました。
2015年もたくさんの展示を見て、書くこといっぱいあるといいな。
今年もよろしくお願いいたします。
ブログランキングよかったらお願いします