
宮沢賢治の「注文の多い料理店」は傑作だなあと思いました。面白いし、笑えるし、怖いし、示唆に富んでいる。きっといろいろな比喩としても読むことが可能な、オーバーだけども普遍的なレベルにまで達している作品じゃないかと。何よりもタイトルがオシャレな感じだし、レストランの名前が山猫軒というのも絶妙なネーミングでイカシテいます。宮沢賢治のセンスはピカ一です。ハイカラ、モダンという飾り言葉も似合っている。
私はこの傑作短編「注文の多い料理店」をこれまでの賢治作品と同様複数のアプローチで親しもうと試みました。それはまず、宮沢賢治の原作を読む、そしてNHKで過去に放送されたものなのか?朗読とイラストレーション、音楽を組合せた映像作品を見て、そして「セロ弾きのゴーシュ」で絶品の朗読を聞かせてくれた長岡輝子の朗読CDを聞くという試みです。


まずは朗読とイラストレーション、そして音楽による映像作品です。(朗読:千葉裕子、絵:フクハラヒロカズ、作曲:田ノ岡三郎)朗読と音楽によってある程度のイメージは作られるのですがそこにイラストレーションが加わるとさらに鮮烈になっていきます。しかし、アニメと違いあくまでテキストは原作に忠実に進めますから、原作の世界がより立体的に構築されていきます(逆にイラストレーションのイメージに引っ張られるということもあるのですが)。そして長岡輝子の朗読は、「セロ弾きのゴーシュ」で聞かせてくれたように絶品の語り口でした。独特のイントネーションが、オリジナルな世界観を感じさせてくれます。
冒頭に書いたようにこの「注文の多い料理店」はいろいろな読み方ができる作品だと思います。私が気づくままにランダムに書いてみても、
・動物狩りにきた紳士2人が、いつのまにか逆に狩られる立場になっていることによる、遊びで殺生する生き物である人間に対するある種の警告でもあり文明批判にもなっているようだ。
・人間は山猫の仕掛けを仕掛けと気づかず、自分達の都合のいいように解釈してドアを開けていく。それはまさしく人間そのものの行為をあらわしているのではないか。そして時にその都合のいい解釈は笑えるものなのだということ。
・われわれはこの地球という星に、君臨する王様ではない。動物と一緒に同じ地平に生きているという事実。われわれ人間だけが命というレベルにおいて特別な価値があるのではない(もちろん同じ種として憐れむ気持ちは他の種と比べてあるのは当然だが)。命という基準からすれば実は等価なのではないか?という投げかけがあるようだ。
・山猫軒は実はもう魑魅魍魎?としての山猫の口であり食道であり、お腹の中に入っているということか。食べることから食べられることへの逆転の可能性は、自然界の食物連鎖を暗示している?
・最後の詰めでドジってしまう文章を書いて、人間を食べることに失敗してしまう山猫は、どこかで最終的には人にはよっぽどのことがないいと害を与えない動物の野生の本性を表している?あるいは、狩りに来たとは言え森では殺生をしなかったからか?
いろいろな読み方ができる宮沢賢治の「注文の多い料理店」は傑作です。シビレました。
 |
名作の風景-宮沢賢治II -絵で読む珠玉の日本文学(7)- [DVD] |
| フクハラヒロカズ,若林常酔,小原秀一,阿部幸次,宮沢賢治,千葉裕子,新沼謙治,木ノ葉のこ,五輪真弓 | |
| スバック |
 |
宮沢賢治の魅力 注文の多い料理店 |
| 小形眞子,十亀正司,篠崎正嗣,双紙正哉,馬渕昌子,堀沢真巳 | |
| キングレコード |
 |
注文の多い料理店 (角川文庫クラシックス) |
| 宮沢 賢治 | |
|
角川書店 |

















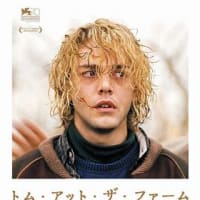








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます