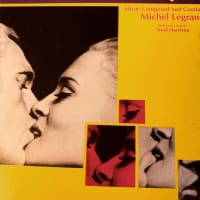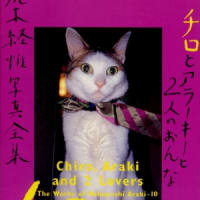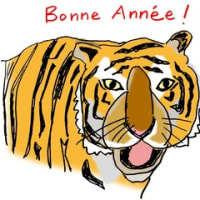当時は探しても無かったのですが、
やっとYouTubeで見つけました。(でもいつ消えるかわからない)
ジョビンの曲の中で、一番好きな曲に
ぜひ、お耳を拝借させてください♪
Antonio Carlos Jobim - Children's Game
この備忘を書いたのは、実に5年前のことでした。
メソッドを学ぶ初々しい(笑)歓びに溢れているかんじが、
今の私とは、また違うようであまり変わっていなくて、
やはり楽しくなります(成長してな~い、笑)
この曲は、直近だと、ジョビン(の妹さんの著書)に関する
著書を読んで書いた備忘録『『偏在する樹木のような』 の備忘が記憶に強い。
フォーレのような美しさ、、、(といったような事が)
山下洋輔氏によって著述されていました。
<以下、2005年の備忘録を、逆順にしてみました>
『憂鬱と官能を教えた学校』

河出書房新社-
菊地 成孔, 大谷 能生
再びアントニオカルロスジョビンのChildren's gameを分析、
発見と感想を。こういった名曲の分析、言及は有識者によって
何度もされていて、もっと詳しく正確に述べられていると思うけれど、
読譜のみが出来てコードやスケール、調性など楽理の概念を
理論的というよりは感覚的にしか意識してこなかった
私の覚えたて(笑)ホカホカ~、、の楽理的な分析、備忘録再び。
殆どのコードを自分自身の耳で取れた事で曲に
肉薄したような喜びを感じるが、まだ正解かどうかはわからない。
(というか売っている楽譜を見れば一目瞭然なんだろうけど・笑)
構成は
◯前奏→メロディA→サビ→メロディA'とシンプル
◯前奏以降を繰り返すかんじ。
◯4分の3拍子←これ、間違い、6/8拍子です(2010年、追記)
サビの部分のコードはE♭m7→D♭△7→D♭m7→B△7で
8、6、6、8、6、6と途中拍子が変わる、(You Tubeでいうと、33秒辺り)
ここ、かなり魅力的。(さらに魅力を増すのは
弦のオブリガートがつく1:30秒を過ぎたあたり)
一見弾き難く思える魅惑的サビ、
私が眉間に皺をよせて音を追っていたのを
トム氏に笑い飛ばされた気がしたほどチャーミングな
メロディの正体は、以下。
メロディはD♭から始めて
そこから5度下の音を7回弾く、途中の1回は先日習ったばかりの
増4度ドミナント。つまり最も不響和な+4と
最も響和するP5(トニック)との組合せ。
メロディ確認のため、サビの1つめの音のみ7音を弾いてみる。
む、7音…?なんだ、正体はダイアトニックメジャースケールだった
つまりドレミファソラシドをD♭から下降して弾く…
(以下単音≠コード)
D♭G♭、C F、 B♭E♭、A♭D♭、F# C、F B♭、E♭A♭。
レ(E♭)の音まで行ったら長2度下がったBから
またドシラソ…♪と弾いていただけ
ほんとうに、子供のピアノ練習のようだ!(笑)
アントニオカルロスジョビンの
children's game(Instrumental Version)を聴いていた。
Antonio Carlos Jobim - Children's Game
気がつけばごく自然に手にとって聴いていたので
ジョビンマニアでもない私だけど
(あ、でもジルベルトよりジョビン派・笑、かも)
彼の曲の中では
How Insensitiveと1、2位を争うほどこの曲を好きだし
強くて静かな情動と輝き、冴えを持った曲だと思う。
立て続けに何十回聴いても、全く飽きる事がない。
前奏、アレンジ、楽器の編成、
メロディー、テンポ、サビのグルーヴ感…
何もかもが完璧なのに、
しかしどこにも力が入ってない。
(ジョビンの音楽は大抵そんなかんじだ)
3分半程の短い曲だけど、聴いている間
ジョビンの宇宙をめいっぱい感じられる。
そういえば、この曲、ちゃんと
弾いた事がなかったな、とピアノに向かってみる。
いや、サビの部分のメロディーが
ちょっと追い難かったんだった。
ところが、いざ鍵盤に手を置くと
あまり何も考えずに指が自然に黒鍵を弾く。
あ、このスケールは、あの時やった
◯◯◯スケール?(まだ少し曖昧)
なるほど。スケールとは、こうして聴覚を始め
視覚的要素を含む身体感覚をまず養うわけだ。
そして曲の分析を
まだ習いたての楽理を一部使ってやってみた。
◯サビのメロディーは5度の下降の連続
◯その時リズムと調性が劇的に変化する
◯ストリングスは2度目のサビから入り
◯その時のサビのメロディを
金管(トランペット?)が奏で
ストリングスのコーラスが半音ずつ下降する。
サビのリズム
3、3、2
3、3、3、3
3、3、2
3、3、3、3
もしくは
(8、6、6、8、6、6
ともカウント出来る。)
クール。
こういった質感を持った作編曲を
私もしたい…いやしよう!
などと強い意志を持って
今宵、決意したのだった。(笑)
<body>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?h=0&user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</body>
やっとYouTubeで見つけました。(でもいつ消えるかわからない)
ジョビンの曲の中で、一番好きな曲に
ぜひ、お耳を拝借させてください♪
Antonio Carlos Jobim - Children's Game
この備忘を書いたのは、実に5年前のことでした。
メソッドを学ぶ初々しい(笑)歓びに溢れているかんじが、
今の私とは、また違うようであまり変わっていなくて、
やはり楽しくなります(成長してな~い、笑)
この曲は、直近だと、ジョビン(の妹さんの著書)に関する
著書を読んで書いた備忘録『『偏在する樹木のような』 の備忘が記憶に強い。
フォーレのような美しさ、、、(といったような事が)
山下洋輔氏によって著述されていました。
<以下、2005年の備忘録を、逆順にしてみました>
『憂鬱と官能を教えた学校』

河出書房新社-
菊地 成孔, 大谷 能生
再びアントニオカルロスジョビンのChildren's gameを分析、
発見と感想を。こういった名曲の分析、言及は有識者によって
何度もされていて、もっと詳しく正確に述べられていると思うけれど、
読譜のみが出来てコードやスケール、調性など楽理の概念を
理論的というよりは感覚的にしか意識してこなかった
私の覚えたて(笑)ホカホカ~、、の楽理的な分析、備忘録再び。
殆どのコードを自分自身の耳で取れた事で曲に
肉薄したような喜びを感じるが、まだ正解かどうかはわからない。
(というか売っている楽譜を見れば一目瞭然なんだろうけど・笑)
構成は
◯前奏→メロディA→サビ→メロディA'とシンプル
◯前奏以降を繰り返すかんじ。
◯4分の3拍子←これ、間違い、6/8拍子です(2010年、追記)
サビの部分のコードはE♭m7→D♭△7→D♭m7→B△7で
8、6、6、8、6、6と途中拍子が変わる、(You Tubeでいうと、33秒辺り)
ここ、かなり魅力的。(さらに魅力を増すのは
弦のオブリガートがつく1:30秒を過ぎたあたり)
一見弾き難く思える魅惑的サビ、
私が眉間に皺をよせて音を追っていたのを
トム氏に笑い飛ばされた気がしたほどチャーミングな
メロディの正体は、以下。
メロディはD♭から始めて
そこから5度下の音を7回弾く、途中の1回は先日習ったばかりの
増4度ドミナント。つまり最も不響和な+4と
最も響和するP5(トニック)との組合せ。
メロディ確認のため、サビの1つめの音のみ7音を弾いてみる。
む、7音…?なんだ、正体はダイアトニックメジャースケールだった
つまりドレミファソラシドをD♭から下降して弾く…
(以下単音≠コード)
D♭G♭、C F、 B♭E♭、A♭D♭、F# C、F B♭、E♭A♭。
レ(E♭)の音まで行ったら長2度下がったBから
またドシラソ…♪と弾いていただけ
ほんとうに、子供のピアノ練習のようだ!(笑)
アントニオカルロスジョビンの
children's game(Instrumental Version)を聴いていた。
Antonio Carlos Jobim - Children's Game
気がつけばごく自然に手にとって聴いていたので
ジョビンマニアでもない私だけど
(あ、でもジルベルトよりジョビン派・笑、かも)
彼の曲の中では
How Insensitiveと1、2位を争うほどこの曲を好きだし
強くて静かな情動と輝き、冴えを持った曲だと思う。
立て続けに何十回聴いても、全く飽きる事がない。
前奏、アレンジ、楽器の編成、
メロディー、テンポ、サビのグルーヴ感…
何もかもが完璧なのに、
しかしどこにも力が入ってない。
(ジョビンの音楽は大抵そんなかんじだ)
3分半程の短い曲だけど、聴いている間
ジョビンの宇宙をめいっぱい感じられる。
そういえば、この曲、ちゃんと
弾いた事がなかったな、とピアノに向かってみる。
いや、サビの部分のメロディーが
ちょっと追い難かったんだった。
ところが、いざ鍵盤に手を置くと
あまり何も考えずに指が自然に黒鍵を弾く。
あ、このスケールは、あの時やった
◯◯◯スケール?(まだ少し曖昧)
なるほど。スケールとは、こうして聴覚を始め
視覚的要素を含む身体感覚をまず養うわけだ。
そして曲の分析を
まだ習いたての楽理を一部使ってやってみた。
◯サビのメロディーは5度の下降の連続
◯その時リズムと調性が劇的に変化する
◯ストリングスは2度目のサビから入り
◯その時のサビのメロディを
金管(トランペット?)が奏で
ストリングスのコーラスが半音ずつ下降する。
サビのリズム
3、3、2
3、3、3、3
3、3、2
3、3、3、3
もしくは
(8、6、6、8、6、6
ともカウント出来る。)
クール。
こういった質感を持った作編曲を
私もしたい…いやしよう!
などと強い意志を持って
今宵、決意したのだった。(笑)
<body>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?h=0&user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</body>