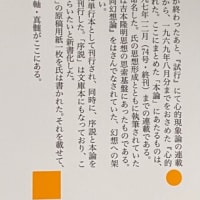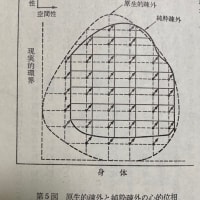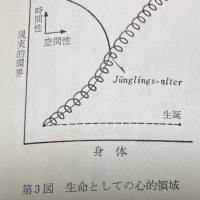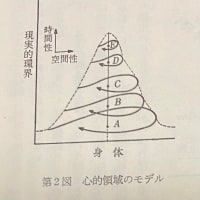言の葉綴り82 ハラリ著作品
③虚構が協力を可能にした
ユヴァル・ノア・ハラリ著作
柴田裕之訳
サピエンス全史・上より抜粋
第1部認知革命
第2章虚構が協力を可能にした
より抜粋
前章で見たとおり、サピエンスは一五万年前にすでに東アフリカで暮らしていたものの、地球上のそれ以外の場所に浸出して他の人類種を絶滅に追い込み始めたのは、七万年ほど前になってからのことだった。それまでの八万年間、太古のサピエンスは外見が私たちにそっくりで、脳も同じくらい大きくかったとはいえ、他の人類種に対して、これといった強みを持たず、とくに精巧な道具も作らず、格別な偉業は何一つ達成しなかった。
それどころか、サピエンスとネアンデルタール人との間の、証拠が残っている最古の遭遇では、ネアンデルタール人が勝利した。約一○万年前、サピエンスの複数の集団が、ネアンデルタール人の縄張りだったレヴァント地方(訳注 地中海東岸の地方)に移り住んだが、揺るぎない足場は築けなかった。敵意に満ちた先住民がいたり、気候が激しかったり、地域特有な馴染みのない寄生虫に出くわしたりしたのかもしれない。理由は何であれ、サピエンスはけっきょく引き揚げ、ネアンデルタール人は中東に君臨し続けた。
学者たちはこのような乏しい実績に照らして、これらのサピエンスの脳の内部構造は、おそらく私たちのものとは異なっていたのだろうと推測するようになった。太古のサピエンスは見かけは私たちと同じだが、認知的能力(学習、記憶、意思疎通の能力)は格段に劣っていた。彼らに英語を教えたり、キリスト教の教義が正しいと信じさせたり、進化論を理解させようとしても、おそらく無駄だったろう。逆に私たちにとって、彼らの言語を習得したり、考え方を理解したりするのは至難の業だろう。
だがその後、およそ七万年前から、ホモ・サピエンスは非常に特殊なことを始めた。そのころ、サピエンスの複数の生活集団が、再びアフリカ大陸を離れた。今回は、彼らはネアンデルタール人をはじめ、他の人類種をすべて中東から追い払ったばかりか、地球上からも一掃してしまった。サピエンスは驚くほど短い期間でヨーロッパと東アジアに達した。四万五○○○年ほど前、彼らはどうにかして大海原を渡り、オーストラリア大陸に上陸した。それまで人類が足を踏み入れたことのない大陸だ。約七万年前から約三万年前にかけて、人類は舟やランプ、弓矢、針(暖かい服を縫うのに不可欠)を発明した。芸術と呼んで差し支えない最初の品々も、この時期にさかのぼるし(図4のシュターデル洞窟のライオン人間を参照のこと)、宗教や交易、社会的階層化の最初の明白な証拠にしても同じだ。

ほとんどの研究者は、これらの前例のない偉業は、サピエンスの認知的能力に起こった革命の産物だと考えている。ネアンデルタール人を絶滅させ、オーストラリア大陸に移り住み、シュターデルのライオン人間を彫った人々は、私たちと同じくらい高い知能を持ち、創造的で繊細だったと、研究者たちは言い切る。仮にシュターデル洞窟のの芸術家たちにであったとしたら、私たちは彼らの言語を習得することができ、彼らも私たちの言語を習得することができるだろう。不思議の国でのアリスの冒険から、量子物理学のパラドックスまで、私たちは知っていることのいっさいを彼らに説明でき、彼らは自分たちの世界観を私たちに教えられるはずだ。
このように七万年前から三万年前にかけて見られた、新しい思考と意思疎通の方法の登場のことを「認知革命」という。その原因は何だったのか? それは定かではない。最も広く信じられている説によれば、たまたま遺伝子の突然変異が起こり、サピエンスの脳内の配線が変わり、それまでにない形で考えたり、まったく新しい種類の言語を使って意思疎通をしたりすることが可能になったのだという。その変異のことを「知恵の木の突然変異」と呼んでもいいかもしれない(訳注 知恵の木は「創世記」に出てくるエデンの園に生えていた木で、アダムとイヴがその実を食べて「目が開け」た。)なぜその変異がネアンデルタール人ではなくサピエンスのDNAに起こったのか? 私たちの知るかぎりでは、それはまったくの偶然だった。だが、より重要なのは「知恵の木の突然変異」の原因よりも結果を理解することだ。サピエンスの新しい言語のどこがそれほど特別だったので、私たちは世界を征服できたのだろう?
それはこの世で初の言語ではなかった。どんな動物も、何かしらの言語を持っている。ミツバチのような昆虫でさえ、複雑なやり方で意思を疎通させる方法を知っており、食物のありかをお互いに伝え合う。また、それはこの世で初の口頭言語でもなかった。類人猿やサルの全種を含め、多くの動物が口頭言語を持っている。たとえば、サバンナモンキーはさまざまな鳴き声(コール)を使って意思を疎通させる。動物学者は、ある鳴き声が、「気をつけろ!ワシだ!」という意味であることを突き止めた。それとわずかに違う鳴き声は、「気をつけろ!ライオンだ!」という警告になる。研究者たちはが最初の鳴き声の録音を一部のサルに聞かせたところ、サルたちはしていることをやめて、恐ろしげに上を向いた。同じ集団が二番目の鳴き声(ライオンだという警告)の録音を耳にすると、彼らはたちまち木によじ登った。サピエンスはサバンナモンキーよりずっと多くの異なる音声を発せられるが、クジラやゾウもそれに引けを取らないほど見事な能力を持っている。オウムは、電話の鳴る音や、ドアのバタンという閉まる音、けたたましく鳴るサイレンの音も真似できるし、アルベルト・アインシュタインが口にできることはすべて言える。アインシュタインがオウムに優っているとしたら、それは口頭言語での表現ではなかった。それでは、私たちの言語のいったいどこがそれほど特別なのか?
最もありふれた答えは、私たちの言語は驚くほど柔軟である、というものだ。私たちは限られた数の音声や記号をつなげて、それぞれ異なる意味を持つ文をいくらでも生み出せる。そのおかげで私たちは、周囲の世界について膨大な量の情報を収集し、保存し、伝えることができる。
サバンナモンキーは仲間たちに「気をつけろ!ライオンだ!」と叫ぶことはできる。だが、現生人類は友人たちに、今朝、川が曲がっている所の近くでライオンがバイソンの群れの跡をたどっているのを見た、と言うことができる。それから、そのあたりまで続くさまざまな道筋も含めて、その場所をもっと正確に説明できる。すると、集団の仲間たちはこの情報をもとに、川に近づいてそのライオンを追い払い、バイソンの群れを狩るべきかどうか、額を集めた相談できる。
これとは別の説もある。私たちの独特の言語は、周りの世界についての情報を共有する手段として発達したという点では、この説も同じだ。とはいえ、伝えるべき情報のうち最も重要なのは、ライオンやバイソンについてではなく人間についてのものであり、私たちの言語は、噂話のために発達したのだそうだ。この説によれば、ホモ・サピエンスは本来、社会的な動物であるという。私たちにとって社会的な協力は、生存と繁殖のカギを握っている。個々の人間がライオンやバイソンの居場所を知っているだけでは十分ではない。自分の集団の中で、誰が誰を憎んでい るか、誰が誰と寝ているか、誰が正直か、誰がずるをするかを知ることのほうが、はるかに重要なのだ。
中略
おそらく、「噂話」説と「川の近くにライオンがいる」説の両方とも妥当なのだろう。とはいえ、私たちの言語が持つ真に比類ない特徴は、人間やライオンについての情報を伝達する能力ではない。むしろそれは、まったく存在しないものについての情報を伝達する能力だ。見たことも、触れたことも、匂いを嗅いだこともない、ありとあらゆる種類の存在について話す能力があるのは、私たちが知る限りではサピエンスだけだ。
伝説や神話、神々、宗教は、認知革命に伴って初めて現れた。それまでも、「気をつけろ!ライオンだ!」と言える動物や人類種は多くいた。だが、ホモ・サピエンスは認知革命のおかげで、「ライオンはわが部族の守護霊だ」という能力を獲得した。虚構、すなわち架空の事物について語るこの能力こそが、サピエンスの言語の特徴として異彩を放っている。
現実に存在しないものについて語り、「鏡の国のアリス」ではないけれど、ありえないことを朝飯前に六つも信じられるのはホモ・サピエンスだけであるという点には、比較的容易に同意してもらえるだろう。サルが相手では、死後、サルの天国でいくらでもバナナが食べられると請け合ったところで、そのサルが持っているバナナを譲ってもらえない。だが、これはどうして重要なのか?
なにしろ、虚構は危険だ。虚構のせいで人は判断を誤ったり、気を逸らされたりしかねない。森に妖精やユニコーンを探しに行く人は、キノコやシカを探しに行く人に比べて、生き延びる可能性が低く思える。また、実在しない守護神に向かって何時間も祈っていたら、それは時間の無駄遣いで、その代わりに狩猟採集や戦闘、密通でもしていたほうがいいのではないか?
だが虚構のおかげで、私たちはたんに物事を想像するだけでなく、集団でそうできるようになった。聖書の天地創造の物語や、オーストラリア先住民の「夢の時代(天地創造の時代)」の神話、近代国家の国民主義の神話のような、共通の神話を私たちは紡ぎ出すことができる。そのような神話は、大勢で柔軟に協力するという空前の能力をサピエンスに与える。アリやミツバチもいっしょに働けるが、彼らのやり方は融通が利かす、近親者としかうまくいかない。オオカミやチンパンジーは
アリよりもはるかに柔軟な形で力を合わせるが、少数のごく親密な個体とでなければ駄目だ。ところがサピエンスは、無数の赤の他人と著しく柔軟な形でで協力できる。だからこそサピエンスが世界を支配し、アリは私たちの残り物を食べ、チンパンジーは動物園や研究室に閉じ込められているのだ。