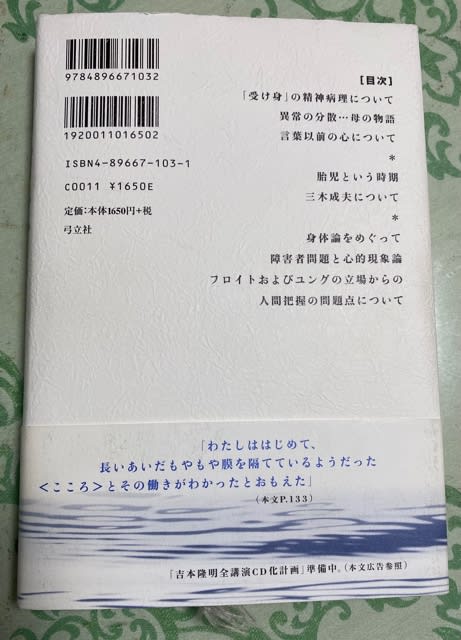言の葉綴り149心とは何か 心的現象論入門 ③Ⅲ身体論をめぐって
吉本隆明著
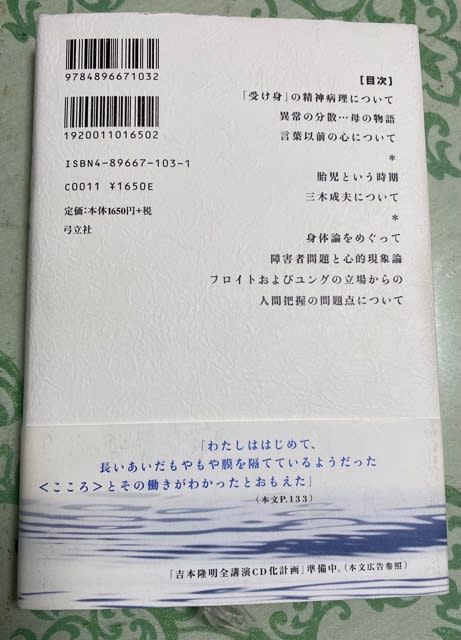
心とは何か 心的現象論入門
吉本隆明著 2001年6月15日第1刷 出版 弓立社 より抜粋
Ⅲ 身体論をめぐって
2
ーー現象学的な身体の根本となるところは、身体というイメージであるあるいはイメージとしての身体ということになります。本質直感にひっかかったイメージとしての身体をだいたい身体というふうにかんがえれば、現象学でつかんでいる身体の像はつかめるんじゃないかとおもいます。
こういう乱暴な云い方をしてはいけないので、それぞれさまざまな人たちがさまざまな言い方をしています。
それで、もう一つだけおもしろいなという云い方をしている人をご紹介しますと、リンサルナという精神医学者です。この人の身体論の中に、おもしろいことが云われています。それは夢ということです。夢ということは、フォイエルバッハやヘーゲル流にいえば、動物としての身体、内部器官と、有機物としての内部器官のごく小部分が働いている時、つまり寝ている時の身体状態において出てくる身体ということです。そのことについて、リンサルナは言及しています。人間の身体の中にある有機的な器官と少数の動物的な器官との混合物がちょっと働いている時、つまり夢の中に出てくる身体とはどういう身体かというと、浮遊している身体だ、と云っています。つまり宙に浮いている身体です。宙を泳いでいるとか、上昇していくとか、あるいは浮いている身体がスーッと落下していく、そういう症状です。人間の動物的器官がごく小部分働いていて、あとは有機的器官しか働いていない。そういう状態における身体のイメージは、宙に浮いているか、上昇している。あるいは落下している。そういうふうに身体、あるいは身体というイメージは存在している、と云っています。
これはたいへんおもしろい身体論です。この身体論があるかないかということで、先ほど云いました肢体の一部分がないかどうかというところまで論及できる。身体論を拡張できるとてもいい基礎が築かれているとおもいます。
それからもう一つ、肢体は不自由じゃないけど精神が不自由だという人もいます。つまり精神がおかしいとか、異常だとか、病気だとか、さまざまな云い方があるでしょうけれども、肢体がないようにじぶんがなくて不自由であるという人と、それから頭の働きが不自由だという人、そういうのも含めまして肢体の不自由、つまり人間の身体不自由というものの概念にまで、身体論を拡張できる基礎というのは、リンサルナのこういう云い方の中にとても大きな示唆が含まれています。
それから、このドイツ観念論、ドイツの古典哲学の系統と現象学の系統とはちがう系統で、もう一つどうしても取り上げなくてはいけない身体論を提出している人がいます。それはフロイトです。
フロイトの身体論の特徴は何かといいますと、さまざまな特徴があるんですが、根本のことだけを申します。人間の内部器官は必ず性的な意味と関係がある。そういうことを云ったのは、フロイトの身体論が初めてです。身体の内部器官は、つまり心臓とか腸とか肛門とか口とかいうものは全部性的な意味がある。つまり性的な意味を帯同させることができる。それが本当の身体の成り立ちなんだ。そういうことを云ったのはフロイトが初めてであり、これもたいへん画期的なものです。例えば、男性が好きな女性に出逢った時に心臓がドキドキするという云いかたはで、本当に好きなんだということを云い表す言葉になります。その手の言葉がどうしても成り立つかといいますと、これは無意識的にだれでも比喩的に使っているわけですけれども、本当は人間の身体の内部器官と
、ものに対してのものの機能、例えば心臓は血液を送ったり集めたりしている、そういう力なんだということと、どういうふうに心臓というのにある性的なエロス的な意味を帯同しているか、ということを意味しているとおもいます。
そのことを意識だてて意味させると、胸がドキドキしているとか心臓がドキドキするということで、ある異性を好きだという暗喩、メタファーになることが成り立つ。それは、たぶんフロイト的に意味づけてしまえば、人間の内在的器官がエロス的な多様環境を必ず持っているんだ、ということに起因するとおもいます。このことを無意識じゃなくて本格的に、真っ向からとり出した身体論をやったのはフロイトです。フロイトを初めとします。
これはある意味でたいへんな真理を含んでいるので、今まで無意識で、だれもがそういうことを漠然と感じたり、言葉で云ったりしたいたにもかかわらず、それをはっきりととり出すことができなかったものを、フロイトが初めてとり出したということができます。このフロイトの考え方は、身体論として除外することができないとおもわれます。
今要約したようなことが、ぼくらが
『心的現象論』の中で身体論をやるばあい、目の前におかれた材料といいますか、素材だったわけです。さてそれじゃ、そこからじぶんの身体論を作ることになります。別に独創的に作ったのじゃなくて、あっちのいいところ、こっちのいいところを全部つなぎ合わせればいいということになります。そのつなぎ合わせ方が、ぼくの『心的現象論』の基本的な考え方に合致していなければ、どんないいことを云ったって意味がないですから、ぼくの基本的な考え方に則して、展開することになっていきました。
何をかんがえたかというと、ヘーゲルやフォイエルバッハがいう概念的な人間の器官というのをまずかんがえました。人間の感覚器官が外界を受け入れる、例えば目が外界を見る作用は、受け入れと受け入れたものを理解する二つの作用があるわけです。感覚器官が受け入れるということは何かといいますと、関係づけだというのがぼくの基本的な考え方です。
これは空間性であり、同時にその空間性とは何がといったら、それは関係づけなんだ、いうのが基本的な考え方です。
それから、受け入れたものを理解する、あるいは了解するということは何かというと、時間性、時間作用だというのがぼくの基本的な考え方です。それに則して何をとりあげればいいかというと、手と足をとりあげればいいじゃないかとかんがえてきました。それで基本的な身体論の骨組みは作れるだろう、とおもったのです。
いちばんいい例は、文学とか芸術などです。例えば文学とか芸術とかは、何でやるか。それは手でやるんだ。手で書くとか手で文字を綴るとかです。するとそのばあい、観念の作用自体は必ずしも手を必要としないようにみえます。つまり手なんか動かさなくても、観念作用を受け入れる、了解することができます。
しかし芸術•文学をとってきますと、それは人間が言葉を操ったり景勝を描き出したりということですけど、そういうばあい、必ず手を動かすことなしにはできないのです。それから、芸術•文学がどのように上達するかというと、それは手でもって文字を書くとか手でもって色を塗るとかというように、手以外のものをいかに高度にしても、決して芸術•文学だけはよくならないのです。芸術•文学がよくなる基本的な要因はあくまでも手を動かすことであって、手を動かすこと以外どんなに習練しても、いい芸術家あるいはいい文学者にはなれないということは当然です。つまり芸術•文学みたいな表現は、必ず手を媒介にしてなされる。手と脳は直結します。つまり手がやることというのは何かといいますと、ぼくのかんがえでは了解性ということなんじゃないかと。つまり時間制を、手が作ろうとするんじゃか、というのがぼくの基本的な考え方になったわけです。
これと対照的に足があります。直立している二本の足が身体にあります
。この足の触知する、あるいは動いていける範囲、人間の身体が持っている空間性あるいは関係性といいましょうか、関係づけるといいましょうか、そういうものを相当するものが足ではないか、あるいはもっと本当を云えば、足と脳との結合•連結です。足の作用というのは人間の空間性あるいは関係づけのある範囲を決めるのじゃないか、というふうにかんかえていったのです。この考え方のなかには、すでに人間の身体が含む時間性と空間性とのイメージが想定されています。
そうしますと、動物ももちろん手を動かします。それからもちろん足で歩きます。そこで動物性と人間性、人間の身体性と動物の身体性、あるいはヘーゲルのいう「動物段階までの身体性」とはなにがちがうのかということになります。手の作用と足の作用が、身体が機能的にかんがえられるかぎりの時間性と空間性、あるいは関係性と了解性の範囲をはるかに超えてできるようになった時に、身体は人間と呼ばれるようになったとかんがえてきました。つまり、もしその身体性が持つ機能的な空間性と機能的な時間性、あるいは機能的な了解性と機能的な行動性、あるいは関係づけの範囲内にとどまるならば、それは動物性といっこうにかわらない。動物もまたそうしているだろうとおもわれるのです。
そうすると、動物と人間との身体性の相違は、たぶん人間のばあいだけ、手の働き足の働き、あるいはその了解の働きと関係づけの働き、あるいは時間性と空間性において、はるかに機能的限界を超えて実現することができる。超えて結びつくことができる。そういうことがありうるとすれば、そういう身体が人間になったんだと、かんかえていいとおもいます。
ここまでかんがえた時に、だいたい基本的なイメージは明瞭になりました。
ぼくの身体のイメージはとても簡単なのです。身体とはさまざまな時間性の度合いとさまざまな空間性の度合い、あるいはさまざまな関係づけの度合いとさまざまな了解の度合いが交錯した存在、それがイメージとしての身体なんだ、という結論になります。
このイメージのなかで何が問題になってきたかといいますと、フォイエルバッハが云った、味覚とか臭覚とか触覚とかという唯物的な、精神性が入っていない感覚と、聴覚•視覚のような、フォイエルバッハに云わせれば精神的な感覚器官とを、非空間性と時間性の度合いとして理解することが、唯一残ることです。その度合いがどこにあるかは云えないまでも、どういう空間性とどういう時間性が結びついたものが聴覚であり視覚であり、それからどういう空間性とどういう時間性の度合いが結びついたものが、嗅覚であり味覚であるかを云うこと、そういう順序を云うことは、わりにかんたんにできるのです。そうした時、だいたいぼくがおもっている身体、イメージとしての身体の基本的な要因は全部そこでできあがったのです。
3
ところで、身体論というのは何が問題なのでしょうか。一つは言語、つまり身体論における言語ということが問題です。それからもう一つ、行為•行動は、イメージとしての身体とどう関係づけをしたらいいのか、ということが残ります。つまり、身体論の究極的なところは、言葉とどう結びつくのかという問題と、行動•行為とどう結びつくのかという問題です。それが、身体論をなぜするのか、なぜそれが重要なのかということの根本の問題になるとおもいます。そうすると、その二つの問題、つまり言語とという問題と行動という問題を、じぶんなりにイメージとしての身体から意味づけられれば、もうお終いということになります。
それは長く云っていると大変ですけど、要約するのは簡単です。まず第一にかんがえなけれはばいけないし、かんがえたことは、身体が言語として表現された時、あるいはイメージとして身体が言語として表現された時と、それから行動•行為として表現された時は、まるで質がちがうんだということ。ですから云ってみますと、まるでちがった質の了解性とちがった質の関係性といいましょうか、重要性といいましょうか、そういうものとかんがえなくちゃいけないとおもいます。
これは混同視してもいけないし、また簡単につないでもいけないことです。つまり言語は独特の時間性の度合いと独特の時間性の質を持ちますし、また独特の空間性の質と度合いを持っているということです。それは行動ということ、行為ということ——それはマルクス流にいえば労働ですけど、つまり対象あるいは自然にたいする働きかけです——とは、まったく時間性の質と空間性の質あるいは度合いがちがうんだということ。ちがう次元あるいは位相にあるということが、基本的な問題になっていきます。それからあとは、その問題を理論づけていけばいいということになります。
もちろん、マルクスが身体論として問題としたのは、行動•行為と身体との関係だけです。それは先ほど申しあげたとおりで、マルクスの云い方だけでは、簡単にいって、肢体不自由とか脳の働きが不自由という身体の行動性あるいは非行動性について、何も云うことができないのです。
そこで、ぼくがどうしてもそれを解きたいとおもったのは、肢体不自由についてぼくも展開していますから、お読みくださればいいとおもいますけれども——例えば一ヶ月前に手を交通事故で落としてしまったとすると、幻の四肢といいますか、幻肢といいまして、落としたあとでも手の完全な形じゃないですけれども、いろんな形があるとおもえることがあります。幻肢というのは、なかなか消えないのです。消えないで存続します。この幻肢という問題のなかに、たぶんマルクスがかんかえなかった、憂いとしての身体の問題がここにかかってくるだろうということが、一ついえるのです。ーー