言の葉50 西行論 ③
ー僧形論ー その2

西行論 著者吉本隆明 発行所(株)講談社 1990年2月10日発行
より抜粋
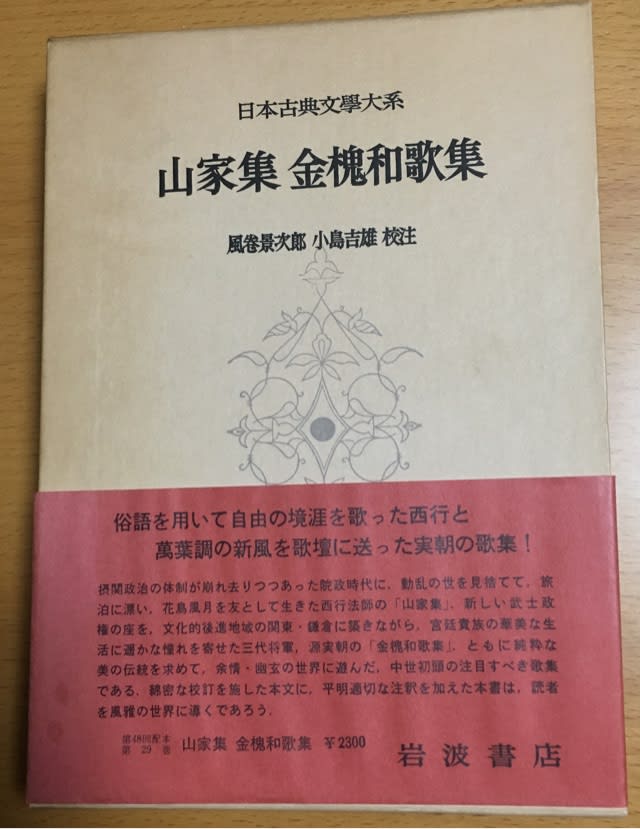
僧形論4より抜粋
………西行の出家の内的な動機を探ろうとすれば、たぶん、出家直前に詠まれたとおもわれる「述懐十首」が、唯一の拠り所である。
一五〇三 いざゝらばさかりおもふもほどもあらじ はこやがみねの花にむつれし
一五〇四 山ふかくこゝろはかねておくりてき 身こそうきよを出やられども
一五〇五 月にいかでむかしのことをかたらせて かげにそいつゝ立もはなれじ
一五〇六 うき世としおもわでも身のすぎにける 月の影にもなづさはりつゝ
一五〇七 雲につきて浮かれのみゆく心をば 山にかけてをとめんとぞ思う
一五〇ハ すてゝのちはまぎれしかたはおぼえぬを 心のみをば世にあらせける
一五〇九 ちりつかでゆがめるみちをなをくなして ゆくゆく人をよにつがえばや
一五一〇 ひとしまんとおもひも見えぬ世にあれば 末にさこそはおほぬきのそら
一五一一 深き山はこけむすいはをたゝみあげて ふりにしかたををさめたるかな
一五一ニ ふりにける心こそなをあわれなり をよばぬ身にもよをおもわする
(「山家集」下・百首)
懸命に出家遁世のモチーフを、内部であれやこれやと思いあぐみながら、詠歌にしたかったらしくて、いずれも難解をきわめている。はじめの歌は、鳥羽院殿の春の花に和やかに馴れしたしんてきた、じぶんの宮廷勤めの盛りも、もはや程なくおわって、しぶんも出家するだろうという感慨を、しずかな華やぐ心でうたっているとおもえる。『西行物語』が、秋もすぎて出家に踏みきったという挿話を編みだしたのは、こんな歌からだったかもしれない。西行にしてみれば、高野の山深くに、じぶんのの心のおき処をきめてからもう、ずいぶん経っているはずだった。「月」という表象は、西行の歌では、遁世の心的世界の表象であることがおおい。かれは遁世の心を鏡にして、いままでの在俗生活の思い出を映しだし、そっと幼少時からの追憶をたどっている。かれの目の前には、出家後の在るべきじぶんの姿に照らしだされた過去の姿を、つき離すでもなく、おぼれるのでもなく、しずかに佇ちつくして思い浮かべている。じぶんの自身の有様がみえる。西行にとって自然は、自然ではなくてことごとく心事の表象であったといえば誇張になろう。わずかではあるが、周密な見事な自然詠をもっているからだ。だが、月を眺め、その光に打たれて立っていた数々の日々にとって、月は、現世のやり切れない愁を打消してくれる境涯の表象であった。西行にも、出家遁世しても、とうていおさまりきれない心があるとすれば、自然の動きと一緒に「うかれのみ行っ」てしまうじぶんの心の在り方であったらしい。
これらの述懐て、いちばん難解なのは、八番目の歌である。このままで解すれば〈ひとしく信愛をよせようという思いもみあたらないような、現在の世の中であるから、最後にはそれこそ大幣をあちこち引きあうような乱れた世のさまになってしまうだろう〉といった意味にうけとれる。それならば、七番目の歌とともに、西行が出家直前に、じぶんに云いきかせた出家の理念と覚悟をのべた歌だということになる。そして強いていえば、九番目の歌もまた、高野山を聖化した理念と護教の歌ともとることができる。〈真言聖地の深い山は、苔むしたおおきな岩をそば立たせて、遁世したたくさんの人間の在俗のときの過去の煩悩を封じ込めているのであるよ〉というほどのことになろうか。西行の出家直前の心の境涯が、これらの「述懐十首」にふくまれているとおりとすれば、西行の出家遁世を、一途に〈死〉にむかって走らせなかったのは、もうひとつ自然の風景に誘われて、どこまでも「うかれ」ていってしまう心を、もてあつかいかねたところにあった。
当方注 一五〇三の歌で、「はこやがみね」は鳥羽上皇の仙洞御所(押小路烏丸殿(三条坊門殿))のこと。京都市中京区二条殿町及び御池之町龍池町付近にあったとされる。
現存する仙洞御所(庭園のみ残っている)は、京都御苑内の京都御所の南東に位置する。
下の映像は宮内庁参観案内より

西行の道心は、本質的なもので、すでに元服のときには、ある心の形を持っていたかもしれない。だが具体的に「世にあらじ」と思い立ったのは、出家の前いくばくもない頃だったとおもえる。その思いを確かめることはできるかもしれぬ。
寄花橘述懐
七ニニ よのうさをむかしがたりになしはてゝ はなたちばなにおもいはてめや
世にあらじと思いたちけるころ、東山にて人々、寄霞述懐と云事よめる
七ニ三 そらになる心は春のかすみにて よにあらじともおもいたつ哉
同心を
七ニ四 世をいとふ名をだにもさはとどめをきて 数ならぬ身のおもひでにせん
よをのがれけるおり、ゆかりありける人のもとにいひをくりける
七ニ六 世のなかをそむきはてぬといひをかん おもひしるべき人はなくとも
九三八 あかつきのあらしにたぐふかねのをとを 心のそこにこたへてぞきく
九四ニ いり日さすやまのあなたはしらねども 心をかねてをくりをつる
(『山家集』中・雑)
鳥羽院に出家のいとま申し侍るとて詠める
惜しむとて惜しまれぬべきこの世かは身を捨ててこそ身をも助けめ
(『玉葉集』第十八)
はや出家遁世して、俗世のはかなさにさいなまれていたときのことを、昔の話であったかのように、花橘を眺めやりながら思い出すような境涯になりたいものだ、とは、西行の出家直前の本心だったことは疑いない。そして、すでに在俗中から出離について語り合い確かめあうグループを西行は持っていた。西行にそういう思いがあることは、鳥羽院北面の親衛として接触できる範囲では、よく知られていたとみられる。ただかれの心の奥の方にしまいこまれていた孤独な決意の質は、他人にはわかりようがなかった。もちろん、わたしたちにもよくわからない。
もともと北面の武士というのは、白河上皇が院政をしいた折に、その強力をささえる武士集団として、院御所の北面に詰所をもって新設された近衛の武士団であった。原則として白河院が個人的に寵用した武士たちから成っていた。官位のうえで四位や五位の武士は、上北面に、六位のものは、下北面に組織された。史家は、この北面の武士たちの性格二つにわけている。ひとつは、京洛周辺の近国の在地小武士団を統御している地縁的な武士の統領が北面に詰めた。もうひとつは、院側近の受領層が、しぶんの本貫地に組織している在地の武士団のうち、精鋭をすぐって上京させ、院殿を固めさせたものである。そして白河院のときすでに下士兵力をそれぞれの北面の武士が動員すれば、千人をこえる勢力になっていたといわれる。
西行は六位の位階をもっていたから、下北面に属していた。律令官制上では兵衛尉で、直接に衛府の武官であったとみられる。またさらに在俗中でもの西行の北面武士としての性格を腑分けすれば、もうすこしはっきりすることができそうである。もと、大徳寺実能家の従郎だということは、ほとんど確実に知られているから、大徳寺家の荘園または本領において組織された在地武士団のうち文武に優れた精鋭のひとりとして、大徳寺家が院政の中枢に近づいたとき、北面の親衛に推されたものとみることができる。もちろん、これは、父左衛門大夫康清、または、それ以前のこととしてもよい。白河院が、北面武士団を設置したのは、西行が生まれるより少し以前にさかのぼるからである。そのばあいには、西行は、父を継いで自然に鳥羽院政の北面をささえる武装力のひとりになっていた、ということになる。こうかんがえてると、西行は、身分制度のうえで、隔絶されていても、鳥羽院に個人的な面識があったし、鳥羽院政を周辺でささえた貴族層や受領層や近畿の武士団の統領たちのあいだにも、その存在をしられていた。こういう武士のひとりが、突然、出家遁世のため、官職を辞退すると申し出たとき、どれほどの波紋をひきおこすものか、よくわからないが、一応は位階や鳥羽院政の雰囲気にに不服あるものとみなされたような気がする。そうかんかえてくると〈身分制にへだてられて、衛府のしがない一武士であるじぶんも、出家遁世したという名分だけは院周辺の官人たちのあいだに残して、せめてわが在俗時代の思い出にしよう〉という三番目の歌は、いくぶんか不服の響き伝えているような気もしてくる。すると逆に〈この俗世にきっぱりと背をむけて、後髪をひかれることなどないと申上げておきましょう。わたしのほんとうの心のうちを誰も知ってくれる人はないとしても〉という四番目の歌は、昂然たる自恃の響きを伝えるようにおもわれる。
ー僧形論ー その2

西行論 著者吉本隆明 発行所(株)講談社 1990年2月10日発行
より抜粋
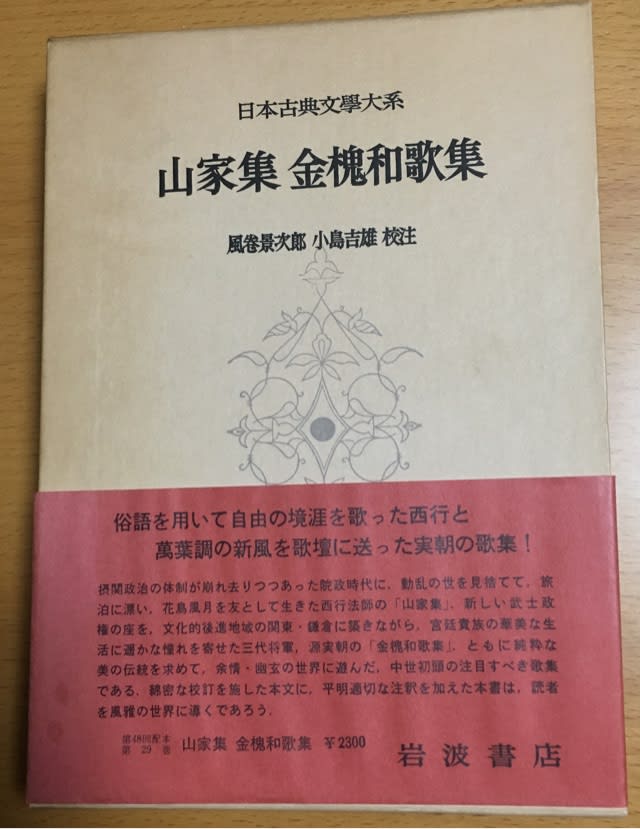
僧形論4より抜粋
………西行の出家の内的な動機を探ろうとすれば、たぶん、出家直前に詠まれたとおもわれる「述懐十首」が、唯一の拠り所である。
一五〇三 いざゝらばさかりおもふもほどもあらじ はこやがみねの花にむつれし
一五〇四 山ふかくこゝろはかねておくりてき 身こそうきよを出やられども
一五〇五 月にいかでむかしのことをかたらせて かげにそいつゝ立もはなれじ
一五〇六 うき世としおもわでも身のすぎにける 月の影にもなづさはりつゝ
一五〇七 雲につきて浮かれのみゆく心をば 山にかけてをとめんとぞ思う
一五〇ハ すてゝのちはまぎれしかたはおぼえぬを 心のみをば世にあらせける
一五〇九 ちりつかでゆがめるみちをなをくなして ゆくゆく人をよにつがえばや
一五一〇 ひとしまんとおもひも見えぬ世にあれば 末にさこそはおほぬきのそら
一五一一 深き山はこけむすいはをたゝみあげて ふりにしかたををさめたるかな
一五一ニ ふりにける心こそなをあわれなり をよばぬ身にもよをおもわする
(「山家集」下・百首)
懸命に出家遁世のモチーフを、内部であれやこれやと思いあぐみながら、詠歌にしたかったらしくて、いずれも難解をきわめている。はじめの歌は、鳥羽院殿の春の花に和やかに馴れしたしんてきた、じぶんの宮廷勤めの盛りも、もはや程なくおわって、しぶんも出家するだろうという感慨を、しずかな華やぐ心でうたっているとおもえる。『西行物語』が、秋もすぎて出家に踏みきったという挿話を編みだしたのは、こんな歌からだったかもしれない。西行にしてみれば、高野の山深くに、じぶんのの心のおき処をきめてからもう、ずいぶん経っているはずだった。「月」という表象は、西行の歌では、遁世の心的世界の表象であることがおおい。かれは遁世の心を鏡にして、いままでの在俗生活の思い出を映しだし、そっと幼少時からの追憶をたどっている。かれの目の前には、出家後の在るべきじぶんの姿に照らしだされた過去の姿を、つき離すでもなく、おぼれるのでもなく、しずかに佇ちつくして思い浮かべている。じぶんの自身の有様がみえる。西行にとって自然は、自然ではなくてことごとく心事の表象であったといえば誇張になろう。わずかではあるが、周密な見事な自然詠をもっているからだ。だが、月を眺め、その光に打たれて立っていた数々の日々にとって、月は、現世のやり切れない愁を打消してくれる境涯の表象であった。西行にも、出家遁世しても、とうていおさまりきれない心があるとすれば、自然の動きと一緒に「うかれのみ行っ」てしまうじぶんの心の在り方であったらしい。
これらの述懐て、いちばん難解なのは、八番目の歌である。このままで解すれば〈ひとしく信愛をよせようという思いもみあたらないような、現在の世の中であるから、最後にはそれこそ大幣をあちこち引きあうような乱れた世のさまになってしまうだろう〉といった意味にうけとれる。それならば、七番目の歌とともに、西行が出家直前に、じぶんに云いきかせた出家の理念と覚悟をのべた歌だということになる。そして強いていえば、九番目の歌もまた、高野山を聖化した理念と護教の歌ともとることができる。〈真言聖地の深い山は、苔むしたおおきな岩をそば立たせて、遁世したたくさんの人間の在俗のときの過去の煩悩を封じ込めているのであるよ〉というほどのことになろうか。西行の出家直前の心の境涯が、これらの「述懐十首」にふくまれているとおりとすれば、西行の出家遁世を、一途に〈死〉にむかって走らせなかったのは、もうひとつ自然の風景に誘われて、どこまでも「うかれ」ていってしまう心を、もてあつかいかねたところにあった。
当方注 一五〇三の歌で、「はこやがみね」は鳥羽上皇の仙洞御所(押小路烏丸殿(三条坊門殿))のこと。京都市中京区二条殿町及び御池之町龍池町付近にあったとされる。
現存する仙洞御所(庭園のみ残っている)は、京都御苑内の京都御所の南東に位置する。
下の映像は宮内庁参観案内より

西行の道心は、本質的なもので、すでに元服のときには、ある心の形を持っていたかもしれない。だが具体的に「世にあらじ」と思い立ったのは、出家の前いくばくもない頃だったとおもえる。その思いを確かめることはできるかもしれぬ。
寄花橘述懐
七ニニ よのうさをむかしがたりになしはてゝ はなたちばなにおもいはてめや
世にあらじと思いたちけるころ、東山にて人々、寄霞述懐と云事よめる
七ニ三 そらになる心は春のかすみにて よにあらじともおもいたつ哉
同心を
七ニ四 世をいとふ名をだにもさはとどめをきて 数ならぬ身のおもひでにせん
よをのがれけるおり、ゆかりありける人のもとにいひをくりける
七ニ六 世のなかをそむきはてぬといひをかん おもひしるべき人はなくとも
九三八 あかつきのあらしにたぐふかねのをとを 心のそこにこたへてぞきく
九四ニ いり日さすやまのあなたはしらねども 心をかねてをくりをつる
(『山家集』中・雑)
鳥羽院に出家のいとま申し侍るとて詠める
惜しむとて惜しまれぬべきこの世かは身を捨ててこそ身をも助けめ
(『玉葉集』第十八)
はや出家遁世して、俗世のはかなさにさいなまれていたときのことを、昔の話であったかのように、花橘を眺めやりながら思い出すような境涯になりたいものだ、とは、西行の出家直前の本心だったことは疑いない。そして、すでに在俗中から出離について語り合い確かめあうグループを西行は持っていた。西行にそういう思いがあることは、鳥羽院北面の親衛として接触できる範囲では、よく知られていたとみられる。ただかれの心の奥の方にしまいこまれていた孤独な決意の質は、他人にはわかりようがなかった。もちろん、わたしたちにもよくわからない。
もともと北面の武士というのは、白河上皇が院政をしいた折に、その強力をささえる武士集団として、院御所の北面に詰所をもって新設された近衛の武士団であった。原則として白河院が個人的に寵用した武士たちから成っていた。官位のうえで四位や五位の武士は、上北面に、六位のものは、下北面に組織された。史家は、この北面の武士たちの性格二つにわけている。ひとつは、京洛周辺の近国の在地小武士団を統御している地縁的な武士の統領が北面に詰めた。もうひとつは、院側近の受領層が、しぶんの本貫地に組織している在地の武士団のうち、精鋭をすぐって上京させ、院殿を固めさせたものである。そして白河院のときすでに下士兵力をそれぞれの北面の武士が動員すれば、千人をこえる勢力になっていたといわれる。
西行は六位の位階をもっていたから、下北面に属していた。律令官制上では兵衛尉で、直接に衛府の武官であったとみられる。またさらに在俗中でもの西行の北面武士としての性格を腑分けすれば、もうすこしはっきりすることができそうである。もと、大徳寺実能家の従郎だということは、ほとんど確実に知られているから、大徳寺家の荘園または本領において組織された在地武士団のうち文武に優れた精鋭のひとりとして、大徳寺家が院政の中枢に近づいたとき、北面の親衛に推されたものとみることができる。もちろん、これは、父左衛門大夫康清、または、それ以前のこととしてもよい。白河院が、北面武士団を設置したのは、西行が生まれるより少し以前にさかのぼるからである。そのばあいには、西行は、父を継いで自然に鳥羽院政の北面をささえる武装力のひとりになっていた、ということになる。こうかんがえてると、西行は、身分制度のうえで、隔絶されていても、鳥羽院に個人的な面識があったし、鳥羽院政を周辺でささえた貴族層や受領層や近畿の武士団の統領たちのあいだにも、その存在をしられていた。こういう武士のひとりが、突然、出家遁世のため、官職を辞退すると申し出たとき、どれほどの波紋をひきおこすものか、よくわからないが、一応は位階や鳥羽院政の雰囲気にに不服あるものとみなされたような気がする。そうかんかえてくると〈身分制にへだてられて、衛府のしがない一武士であるじぶんも、出家遁世したという名分だけは院周辺の官人たちのあいだに残して、せめてわが在俗時代の思い出にしよう〉という三番目の歌は、いくぶんか不服の響き伝えているような気もしてくる。すると逆に〈この俗世にきっぱりと背をむけて、後髪をひかれることなどないと申上げておきましょう。わたしのほんとうの心のうちを誰も知ってくれる人はないとしても〉という四番目の歌は、昂然たる自恃の響きを伝えるようにおもわれる。









