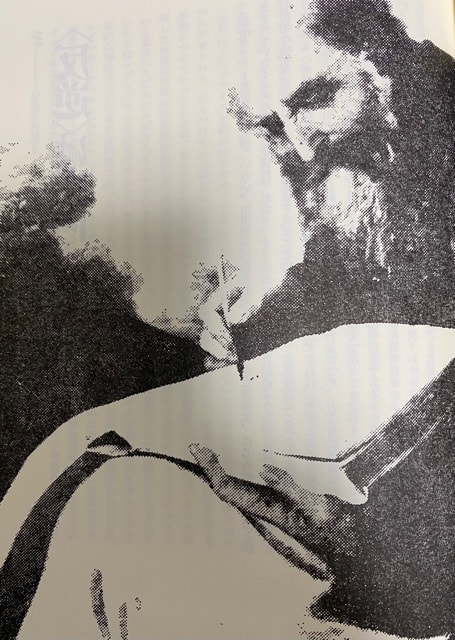128〈信〉の構造2 キリスト教論集成
吉本隆明
⑨喩としてのマルコ伝 言葉 その2
投稿者 古賀克之助
〈信〉の構造2 ——キリスト教論集成
ニ〇〇四年十一月三十日 新装版第一刷発行 著者ー吉本隆明 発行所ー株式会社春秋社
喩としてのマルコ伝 言葉より抜粋
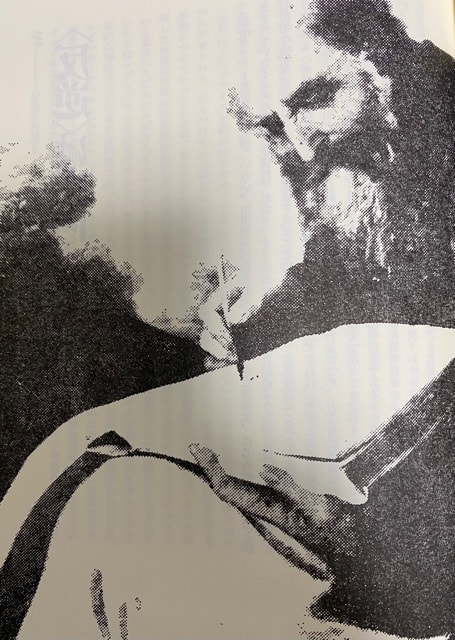
マルコの肖像
喩としてのマルコ伝(その1に続く)
喩がわかるというのは古代では何かであった。それは「神」の口から出た言葉と人のあいだに流布された言葉とを架橋することであった。〈信〉とともにある能力、たぶん人間の秩序を支配する能力がなければ、ふたつの言葉を架橋することができなかった。マルコ伝の主人公イエスは「神の国」へ自由に流通する〈信〉をもっていたが、人間を支配する能力にはまったく欠けていた。いやむしろ、人間を支配する能力に欠けていることが「神の国」に流通する資格であることを教義的にくりかえした。これこそがユダヤ的自然宗教に異議をとなえた主人公の特異な教理的な思想だった。そこで喩がわかる能力という意味はマルコ伝では特異な表われ方をしたとおもわれる。マルコ伝は「このようなたくさんの譬をもって、人々の聞くことができる能力にしたがって言葉を語り、譬によらずしては語らなかった。弟子たちは人がいないときにすべての事を解釈してみせた」(「マルコ伝」第三三ー三四)とかいている。そのまえにもこう書かれている。
「イエスは云った。『きみたちには神の国の奥義を与えるけれど、外の者には、すべて譬でもって教える。これは「見るとき見えても認めない、聴くとき聞こえても悟らない。それがくつがえされて赦されるということがない」(「イザヤ書」第六章九ー一○)という言葉のためである』。(「マルコ伝」第四章一一ー一ニ)
この真意ははかり難い。じぶんたちの教徒には「神の国」の奥義を伝えるが、教義を信じないものには奥義を語ったり見せたりしても、その本意は容易にわからないように譬話で語るのだといっている。そしてこの譬話は「神の国」の教義がわかる度合いに応じてわかるようになされているということになる。これは喩についての修辞論を意味している。
しかしながらこの喩の論議はマルコ伝の(この個処の)成立がいかに新しく、特異なものであるかを証している。ここでは喩が喩によらない言葉よりも難解だという見解がみられる。これは逆でなければならない。喩は言葉の表現の始源のところでは直敍よりももっと直敍であった。直敍が生のままの直敍としてあらわれたのは後になってからである。すでに記述において隠されたところは何もなくなった時代に、いわば反省的な譬話で「神の国」や「神」の教義が語られた。もしもマルコ伝の喩にたいする態度を時間的に理解しないとすれば、当然特異なその教義の構造に帰せられるだろう。そこでは「神」の言葉がわかることは、人間の秩序から疎まれ、罪をきせられ、病みそして貧しくなるということであった。精神の罪人、取税人、廃疾者、貧困者であることが「神の国」の言葉にいたる窄い門であった。この現実的な支配の放棄の条件こそ古代の自然宗教から原始キリスト教をわかつかなめであった。喩がわかることは一方で喩の謎を解することでありながら、一方で喩の時間性を逆倒することになった。喩のほうがわかり難いと主人公がいうのはそのためである。ほんとうは喩がわかりにくいというのは現在のことであって、主人公の時代には属していない。けれどそこでは喩によって、喩を用いて語り、あるいは書くということが難しいとされる。そして喩がわかる度合と教義が理解でき体得される度合とは対応するものとみなされる。これはかなり新しい時代の言語観でないとしたら古代的な逆説としか解しえない。
「イエスはそこを去り、ツロとシドンの地方に行った。家に入って人に知られまいと望んだ。けれど身を隠したままではいられなかった。そこで穢れた霊に憑かれた娘をもった女が、かれについての話をきいて、やって来て足許にひれ伏した。この女はギリシャ人で、シロフェニキア地方の出身であった。彼女はじぶんの娘から悪霊を追いだしてくれるよう請うた。イエスは彼女に云った。『まず子供に飽きるほど喰べさせるべきだ。なぜなら子供のパンをとりあげて小狗に投げてやるのはよくないから』。『そうです主よ。』と彼女は応えた。『けれど食卓の下にいる小狗は子供の喰べ屑を食べます』。そこでかれは彼女に云った。『その言葉を云ったために、そら悪霊はおまえの娘から出ていった』。そして彼女は家に入って見ると、子供は寝台に寝ており、悪霊は離れていた。』(「マルコ伝」第七章二四ー三十)
「まず子供に飽きるほど喰べさせるべきだ」という喩の意味はさまざまに解される。ここはさいわいにマタイ伝(第十九章二一ー二ハ)に対応する個処がある。こういうときマタイ伝はたいていわたしたちよりも遥かに以前に、たぶん遥かに的確にだが通俗的に喩の解釈をやっている。それをみると「わたしはイスラエルの家の失われた羊(亡羊)以外のところに派遣されたのではない」と主人公が言明するところが挿入されている。これから判断すれば、子供にまず飽きるほど喰べさせるべきだというのは、イスラエル人にまず神の恩恵が与えられるべきで、異邦人であるシロフェニキア生まれのギリシャ人に最初に施されるべきではないという意味になる。小狗は異邦人の喩である。けれど娘の母親は、もし子供の食卓の下に小狗がいるとしたら、子供がパンを食べていると同時に食べ屑が小狗のところにも廻ってくるのではありませんかと応える。つまりイスラエル人と同時に異邦人もまた恩恵をうけてもよいのではないかと応えたことになる。マルコ伝によれば、喩がわかるとは教義的な真が
わかることとおなじであった。そして喩がわかったことを喩をもって応答しえた女には信仰の境位として深いことを意味した。そこで「その言葉を云ったために」信仰の深さを開示した女の娘は、即座に治癒を保証されることになった。
マルコ伝のこの個処がマタイ伝によってアレゴリカルに通俗化されることに釈然としないものが残される。また一般にこの感じに耐えるような譬語はマルコ伝には存在しない。子供=イスラエル人、小狗=異邦人であるシロフェニキア生まれのギリシャ人という直喩的な類比を強制したとき、この個処は党派的教義によって矮小化されてしまう。この個処のほんとうの問題は喩がわかるとはどういうことかにあった。マルコ伝の主人公が子供が飽食するまえにパンを小狗にやるのは不都合ではなかろうかというのに対して、応えがあるとすれば何らかの点でこの言葉の意味構成を修正しなければならない。そして修正しながら応えでありうるためには、子供と小狗とが同時に喰べられるシテュエーションを設定する以外にはない。シロの女は、子供の食卓の下にうずくまる小狗というシテュエーションを設定した喩によって応えつくすのである。喩がわかり喩によって応答できるということは、言葉の喩の背後にある世界を理解したことを意味した。
マタイ伝の解釈をまじえた理解は、いちばん時代的に近い同信者によってなされたいちばん正確なものと見做されよう。
だが現在のわたしたちには、そう読まれるどこかに異議がのこるのも、致し方がない。現代が主人公イエスを自分自身としてのイエスという文脈で読むからである。そう読むかぎりまず神の子であるじぶんにかくれた祈りのときを与えよ「神」との交話をさせてくれ疲れているのだ、その時間をまずおまえの娘に与えるのは心の溷濁を回復する時間を失うことでたまらないことだ、というふうに受けとることができる。これにたいし娘の母親は、あなたの安息と「神」との交話の時間を奪うのではなく、こぼれおちる時間を頂戴することでいいのですと応えたのに、主人公は感ずることになる。マルコ伝第四章の譬話は「神」とか「神の国」とかに関連した暗喩あるいは直喩の教条を集めたと記されている。だがその他の個処に無作為に挿入された喩は、暗喩を暗喩自体として読むことを強いている。子供=イスラエル人、小狗=異邦人であるシロフェニキア生まれのギリシャ人という類比も、子供=神の子イエス、小狗=娘とその母親という類比も、暗喩か暗喩自体としてもつ含みを消去してしまう。意味は明確になるのに逆に不満が残される。この不満はわたしたちの現在がもたらす不満である。言葉の時間性からいって暗喩のもつ時間の累積を、特定の時間に指定されることへの不満といってもよい。現在のわたしたちがこの個処にさまざまな解釈可能性をみるとすれば、ひとつには時代と場所を遥かに距ったためにマルコ伝の本意がどこにあるかわからなくなったためだ。だが同時に言語体験の不可避的な累積の上に、わたしたちが独りでに位置しているためでもある。この現存性を一種の歴史性とみなせば、わたしたちはマルコによって記述されたマルコ伝の、マルコ自身による理解をも不満であるというぜいたくで不らちな欲求にまでつき動かされる。
「イエスはまたふたたび海辺で説教をはじめた。たくさんの群衆がかれの傍に集まったので、かれは海に浮かんだ舟に乗って坐った。群衆はみな海岸に沿って陸にいた。かれは譬でたくさんのことを説いたが、その説教のなかでかれらに云った。『聴け、種播く者が播こうとしてでてきた。播くときに種の一部が路に沿って落ちた。種があり鳥がきてそれを啄んだ。別の一部は石のおおい場所に落ちた。そこは土がたくさんなかった。地質が深くないので直ぐに芽が出た。けれど、太陽が現れたときやけて根がないので枯れた。別の一部は茨のなかに落ちた。茨がのびてきて抑えたので、実を結ばなかった。別の一部は豊かな土質のなかに落ちた。のびてひろがり、実を結んで三十倍、六十倍、百倍の収穫があった』。」(「マルコ伝」第四章一ーハ)
この比喩話の中味は、種播く農夫の実景や動作の描写ではない。これはイエスが語ったという文脈を入れなくてもはっきりしている。もっと突っ込んでいえば何かの比喩ではないかと推定はだれにもできる。修辞的に種が路傍に落ちたばあい、石地に落ちたばあい、茨の茂ったところに落ちたばあい、良い土地に落ちたばあいというように、並列並記の条件法の形に整序されているからである。そしてこの文章を比喩として読み下したばあいに、理解に手易い喩の構造が露出してくる。〈悪い環境には育たない〉とか〈適切なところにおかれたものは実を結ぶ〉という言葉で要約されるものである。これは信仰とはかかわりのない喩の構造である。これが主人公の言葉としてマルコ伝の文脈のなかにおかれたとき、はじめて種播く者は神の言葉を宣布する神託者(イエス)の喩として固定的に対応づけられることになる。すると続くすべての修辞の意味はそれに沿って変貌する。この変貌の過程でマルコ伝自体が変貌した異貌の書としての性格を露呈するはずである。いま種播く者を神の言葉を宣布するものとして、この比喩の話の文章を解釈し直してみれば、およそつぎのようになるはずだ。
〈聴きなさい。神の言葉を宣べ伝えようとする者が、宣べ伝えようとして出てきた。神の言葉を路傍で落ちこぼれの種のように漫然とうけとるならば、とりがきてついばむように素早くその言葉は消えてしまう。素地の深くないところに神の言葉が伝えられると根底が浅いのでさっととびついてくるが、障害にあうとすぐに消滅してしまう。さまざまな異端異教異心の乱れたところでは、そちらのほうが繁茂して神の言葉のほうが塞がられて実を結ばない。良い素地のところに宣べ伝えられると神の言葉は根づき葉を出し茂り実を結んで三十倍にも六十倍にも百倍にも広がってゆく。〉
解釈のよしあしはべつに、解釈の可能性の度合いとしてはこれが限界であることがわかる。この理解の仕方は、わたしたちのものである。いいかえれば現在性、異教性、異邦性であり、また同時に話し言葉も書き言葉も文字も異なった場所からの解釈である。これらの条件にもかかわらずこの解釈にはある普遍性があるといってもよい。
マルコ伝自身はこの個処を次のように自家自註している。
「播く者とは神の言葉を播くのである。神の言葉が播かれて路の傍にありというのは、こういう人をいう。即ち聞くときに直ちにサタンがやってきて、その播かれた神の言葉は奪われてしまうのである。おなじように播かれて石地にありというのは、こういう人をいう。すなわち神の言葉をきいて、すぐに喜んで受け入れるけれど、そのなかに根がないのでただしばらく保っているだけで、神の言葉をまもっているため苦難とか迫害にあうときは、すぐに躓いてしまうものである。また播かれて茨のなかにありとは、こういう人をいう。即ち、神の言葉をきいても世間的な心労とか財貨の惑いとかさまざまの欲望が入り込んで神の言葉を塞いでしまうので、遂に実らないのである。播かれて良い土地におちたというのは、こういう人をいう。即ち神の言葉をきいて受けいれ、三十倍も六十倍も百倍も実を結ぶのである。」(「マルコ伝」第四章一四ー二○)
わたしたちが現在かんがえる解釈可能性はただの常識的な妥当性しかない。これにたいしてマルコ伝が自らやっている解釈は自家自注であるために、同時代の宗教的な慣行に引き寄せられている。路の傍に落ちた種は鳥が啄んでいってしまうという喩を「サタンがやってきて」神の言葉をすぐに奪っていってしまうと解釈するのは、マルコ伝自体が身をひたしている同時代の思考法を、自明とする独断なしには不可能である。善き言葉には聖霊が宿り、悪しき言葉にはサタン(悪鬼)が宿り、善き言葉を奪ってゆくのはサタン(悪鬼)の仕業であるとかんがえる習俗がなければ、マルコ伝自身がやっている解釈は成り立たない。おなじように石地に落ちた種という比喩から、障害のあるところでの神の言葉という意味をとることができても、「苦難」や「迫害」に出遇うというような解釈をとるわけにはいかない。じっさいにマルコ伝の著者たちが受けてきた「苦難」や「迫害」の心証なしにはマルコ伝自身による解釈は不可能である。おなじように茨のなかに落ちた種というところから、さまざまな異心がはびこったなかでの神の言葉という意味をとれても、具体的に「世間的な心労とか財貨の惑いとかさまざまの欲望」の暗喩と解釈することはできない。そう受けとるためには解釈者自身が世間的な心労や財貨やさまざまの欲望に、否定的にとくに執着していなければならないだろう。マルコ伝の比喩話のマルコ伝自身による解釈の現在的な解釈可能性からの逸脱と偏倚は、マルコ伝の本質的な性格を解くかぎをなしている。
この意味からすればマルコ伝は、現実的な労苦と弾圧から歪められた自己障害のマルコ伝という表出にほかならなかった。主人公イエスはマルコ伝や類似の福音書がなければこの世に存在しなかったが、マルコ伝や共觀福音書によって生まれたときからすでに歪められていたのだ。歪められないイエスは想像的にさえ存在しないのに、わたしたちがマルコ伝の主人公が歪められているといいうるのは、これらの喩の偏倚から推論してのことである。
(追記)(註)以下略