言の葉64 良寛③ー思想詩2ー
良寛 吉本隆明著 株式会社春秋社
発行所 1992年2月1日発行より
抜粋
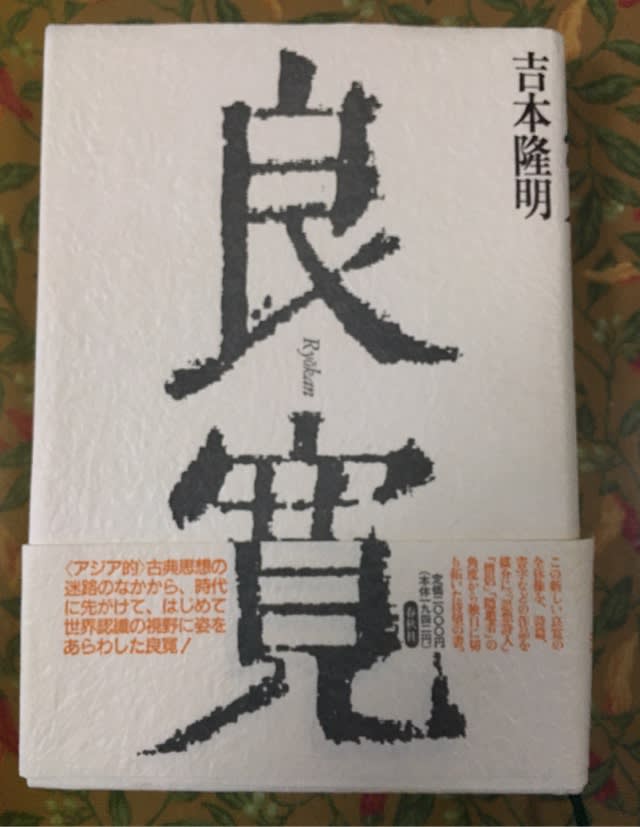
I 良寛
思想詩2

良寛が傾倒した道元禅や、老荘や論語は、いずれも低地アジアに起源を持つ古典古代以前の思想ということができます。おおきく世界史的には〈アジア的〉な思想です。この〈アジア的〉思想は古代から近世にいたるまで、日本の制度や文物におおきな影響を印してきました。この〈アジア的〉な思想について、わたしたちは近代以後と近世以前の人々と違った態度がありうるとすれば、そのひとつはわたしたちが、いわば近代の西洋思想の洗礼をうけていることです。そのうえで良寛がみた仏教や老荘や儒教の思想をみることができることです。良寛とおなじ思想をまえにして、わたしたちが良寛とちがう理解をもちうるとすれば、そこに由来しています。
良寛にとって仏教的な思想や、老荘や儒教の思想は、思想としての全世界でありました。それ以外の世界は思想としては存在しなかったのです。わたしたちにとってヨーロッパの思想も、いわばおなじ視野のなかにはいっています。その世界史的視野のなかで〈アジア的〉思想をうけとることができることが、良寛とわたしたちとちがうところです。またちがわなければならないところだとおもいます。なぜならば良寛は近世末の人ですし、わたしたちは現代にあるのでから。現代にあることに取柄があるとすれば、世界史的視野のなかで、仏教の思想や中国の古典思想をとりあげられるということです。
(中略)
〈アジア的〉な古典思想のなかで、仏教や儒教や老荘はヘーゲルみたいないい方をすれば、おおきな河川の流域にひろがった、いわば低地の農耕地帯に発生した思想ということになります。アジアにも高地があります。それから、小アジアのように、海に口をつけているところもあります。そういう思想と平地の思想は、ちょっとだけちがいます。わたしたちにかかわりが深いのは、河川の流域にひろがった平地で築かれてきた思想です。
また〈アジア的〉という概念には、もうひとつべつの意味があります。ヘーゲルやマルクスが明晰にとりだしたことですが、〈アジア的〉というのは世界史の時間でいいますと、古代の以前に想定される歴史的なひとつの時間を意味しています。つまり〈アジア的〉という概念は地域空間の概念だけではないということです。アジア地方に発生した思想は〈アジア的〉です。しかしそれは地域的な〈アジア〉という意味あいだけではありません。時間的に〈アジア的〉なのです。時間的に〈アジア的〉ということは、古代以前の時期のことを指します。原始時代のつぎにくるのが〈アジア的〉時代、〈アジア的〉世界史の時代ということです。
わたしたちが〈アジア的〉思想というばあい、二重の意味があります。ひとつはアジア地域で発生した思想のことです。しかし、中国で発生して日本へやってきた、あるいはインドで発生し、そして中国を通って日本へ渡った思想だとみただけでは、その思想をみたことになりません。その思想をみるためには、もうひとつ古典古代以前の思想、以前の段階にあった思想としてみなければ、その思想をみたことにならないのです。それが〈アジア的〉な古典思想に影響をうけた近世以前の日本の思想家や詩人たちと、わたしたちがちがうところです。わたしたちの見方がちがうところは、それだけに帰着します。
〈アジア的〉な制度の特徴は、政治的権力が制度を敷くばあい、はじめからおわりまで、宗教から法律の末端にいたるまで、全部じぶんたちの考え方で制度を組み替えようなどとしないことです。まえからあつた共同体の制度を、できるだけそのままに温存して、そのうえに乗っかって政治権力を行使します。つまり既成の制度や習慣や文物にできるなら手をくわえないのです。手をくわえないでそのうえに支配的な共同体をうわ乗せするのです。いわばまえからあった共同体の頭の部分だけを組織
して掠めるのです。それが〈アジア的〉という制度の概念の世界史的特徴です。
古代の大和朝廷についてかんがえてみますと、具体的な過程がどんなであれ、それ以前にあった共同体の政治や宗教の制度をうち壊して、じぶんたちの制度や文物を末端にまで押しつけていくことを、できるかぎりしないで、じぶんたちの利害に反したり、反抗したりしないかぎり、そのままに温存して、そのうえに権力を乗せるというような方法をとっています。そして経済的には貢納、貢物をとる制度を敷きます。貢物をとるには、まえからあった共同体の首長たちに、下から貢物をとらせて、中央に運ばせればよろしいことになります。もちろん各地には直属の三宅というものをおきます。これがわが国における〈アジア的〉な社会や国家の構造といえましょう。以前の共同体のひとつが、勢力を増してそのうえに乗っかるか、他所から到来した勢力が脇からきて、そのうえに乗っかるかはさまざまの可能性がかんかえられるのですが、いつもおなじ形式をとるとみてよろしいことになります。宗教、制度、風俗、習慣の成り立ち方の根本にあるこの特徴は、明治以降、近代西洋の制度を数多くうけいれましたが、現在も構造的に潜在しているにちがいありません。誰もがこれに思いあたる節があるだろうと信じられます。
こういったことは、日本の出家隠遁の思想におおきくかかわりがあるとおもいます。まえからある共同体のうえに、新しい支配の共同体ができ、またそのうえに新しい支配の共同体ができていっても、まえからの底辺にある共同体の制度や宗教や風俗、習慣などは、できるかぎり手をくわえないで温存されるとみなせば、底辺の共同体で太古から受け継がれている宗教や制度や民俗みたいなものは、上層の共同体の勢力あるいは制度がどう変わっても、それとは関係なく保存されるという制度的な距離感覚が根をもつようになります。いちばん新しい共同体の頂点にある思想と、まえからあって、あまり変わっていない思想とは、時代が古いほど、距離感はおおきくなることがわかるでしょう。それから時代が古いほどその隔たりがおおきくなるでしょう。底辺で流布されている思想や、古代から受け継がれている伝統的な宗教や習俗は、制度がどう変わっても「帝力吾において何かあらんや」という感性の距離に遠ざかります。それが〈アジア的〉な古典思想、わが国の隠遁思想の提起する根本的なモチーフになっています。
制度以前にある〈自然〉という規定が〈アジア的〉な制度のもとで遠のいてゆくとき、感性と思惟はどんな態度をとるのかの問題といえましょうか。どんな制度の思想が支配しても、たいして変わりばえしないはずだという強固な認識はなぜでてくるか。思想が制度にぶつかるまえに、山川草木にぶつかり、そこに関心がとどまってしまうだけの充分な感性の距離をもってしまう根拠がここにあります。中世ヨーロッパでは、特別に僧院のなかに籠った特殊な僧侶とか、特異な自然詩人のうちにしか成り立たない制度的な〈無〉の思想ですが、日本の〈アジア的〉な社会では、自然と遊ぶ隠遁思想が制度的な裾野をもってきました。制度にたいする考察などしないでも、何故か〈自然〉思想が成り立ったのです。文学、詩歌のたぐいが人間臭さにぶつからず、自然のなかにじぶんをうつしいれることで成り立ち、政治制度の思想は〈天〉の秩序にかかとを接して権力のピラミッドをこしらえたのです。これが感性的につかまれた〈アジア的〉という制度の概念です。
良寛の性格悲劇を包んでいる思想の雰囲気は、老荘のすぐれた〈自然〉思想でした。それらは制度から退くこと、また道徳から離脱することに根拠をあたえるものでした。天地山川は、何もしないのにそのままで清らかで安穏であるところに、老荘は「無為」のよさを位置づけました。かれらは「仁義」が生まれるようになって、かえって天下が「惑乱」したと説いています。「生」は天地からゆだねられたものであり、「死」は天然という巨室に眠ることだとと荘子はかんがえました。良寛を動かしたこれらの思想は基本的には〈制度以前〉の思想だという性格をもっています。良寛はそれを認識したというよりもその思想を生きたのです。わたしたちはその思想の性格を認識することができます。それは、けっして現代が良寛にくらべて偉いからではありません。ただヨーロッパの思想の近代の洗礼をうけたあとでわたしたちは、良寛に傾倒し、その思想をそのまま浮かびあがらせて眺める視野をうることができるからです。
道元の思想から逸脱したあとの良寛は、『正法眼蔵』が禁じた詩人文学者として後半生をおくりました。そして良寛の後半生を支配したのは、おなじように道元が排した荘子などの思想に近いものでした。
荘子、老子、孔子の思想を先入観なしにならべてみますと、こういうことがわかります。老子、荘子は、南中国の思想といったらわかりやすいとおもうのですが、制度にたいする考察とか、道徳にたいする考察がほとんど皆無ということです。つまり、さきほどの言葉でいえば、(原始的)段階の末から(アジア的)段階の初期にわたる時期に、人間の考えが直面した問題をおもくみていることがわかります。それが老子や荘子の思想です。ここには制度、道徳という思想はむしろないのです。それは排する以前に存在自体がないのです。道徳とか、善悪とか、喜怒哀楽とかいうものはどうしてできてくるのか。それは「天」から逃げようとするからだ。人間が「天」から逃げて、人間本位になろうとするから、道徳とか喜怒哀楽とか、政治制度とかがでてくる。それはむしろだめな考え方だ。だから道徳を説く聖人がいるから大泥棒がでてくるのだ(「聖生れて大盗起る」ー『荘子』ー)といういい方をするのです。つまり、制度や道徳にたいする考慮からは、荘子や老子は自由であり、むしろそういうものが無化される根拠を提示しようととしています。
孔子には制度にたいする考察が道徳にたいする考察といっしょに二重に含まれています。人間はどんなふうに道徳に依拠していくべきかという考えと、どんなふうに制度に処すべきかという考えとが二重になっています。それは(アジア的)思想のなかでは、中期ないし後期に位置づけられる考えをおおく保存しているからです。制度、善悪、道徳、人格にたいする考察が『論語』にはおおくなされています。『論語』には「徳は孤ならず、必ず鄰あり」みたいな言葉がたくさんあります。これはたしかに道徳の言葉のようにみえます。〈徳ある人間は、けっして孤立することはない。かならず支持する人間がでてくるものだ〉というように理解できましょう。しかし、これは、同時に制度の意味を含蓄する言葉でもあります。つまり〈徳を原理として国家共同体を治めるなら、隣国の共同体はかならず親和をもとめて近づいてくるものだ〉ということを意味しています。
『論語』を読むにはたぶん、この制度と道徳とのふたつの眼鏡が必要です。言葉が二重性としてあるからです。これは『論語』にとって根本的なことのようにおもわれます。古典学者は〈徳の高い人間は、孤立することなく、かならず隣人が慕い寄ってくるものだ〉というように説いてきました。それは同時に、共同体を治める原理としての「徳」を意味しているのです。〈君主というものが、徳をもって共同体あるいは小国家を治めるならば、隣の国、共同体は、かならずじぶんたちのところへ仲良くしようというふうにいってくるはずだ〉ということをが、制度としての解釈になります。制度的と個人道徳的との両方を、いわば二重の含みをもって読むべき時間に『論語』は位置しているのです。』アジア的〉という概念のなかで『論語』を読んでいきますと、道徳と制度が未分化であった時代が蘇ってきます。国王はどのように民衆を治めなければならないかというふうな、個人意志としての道徳を、制度的倫理として混融して考えていた時代にできあがったものだからです。「朋あり、遠方より来たる。また楽しからずや」というばあいに、〈仲のよい友達が遠くの方からやって来て、一杯飲みながらお喋言りするといったことは、楽しいじゃないか〉という意味にはちがいないでしょうが、それだけではありません。「友」というのは〈友人としての共同体、つまり〈隣邦〉とか〈同盟国〉ということです。そういう〈共同体〉が遠方から来た、つまり〈遠方の小国家あるいは共同体が、じぶんの方へ仲良くしよう、と同盟をしよう、というふうにやって来た、それはいいことじゃないか〉といっているとおもわれます。
老荘の思想は南中国で、むしろインドやセイロンに近いところで生まれた思想です。そこでは初期の〈アジア的〉原理がつよく保存されています。制度あるいは道徳以前の〈自然〉な意識で生きていた時代の共同体の思想をよりおおく保存しているです。中国の古典思想のなかでは荘子はもっとも緻密で整っと構成をもっています。良寛は道元禅つまり初期仏教禅の思想を放棄したとき、たぶん荘子によりおおく後半生の支柱を求めたのでしょう。詩人としての良寛を方向づけたものは、荘子の考え方であったようにおもわれます。荘子の「無為」に解放されて、じぶんの若いときからの資質である風光に慰謝する情念を追及してゆきました。
良寛 吉本隆明著 株式会社春秋社
発行所 1992年2月1日発行より
抜粋
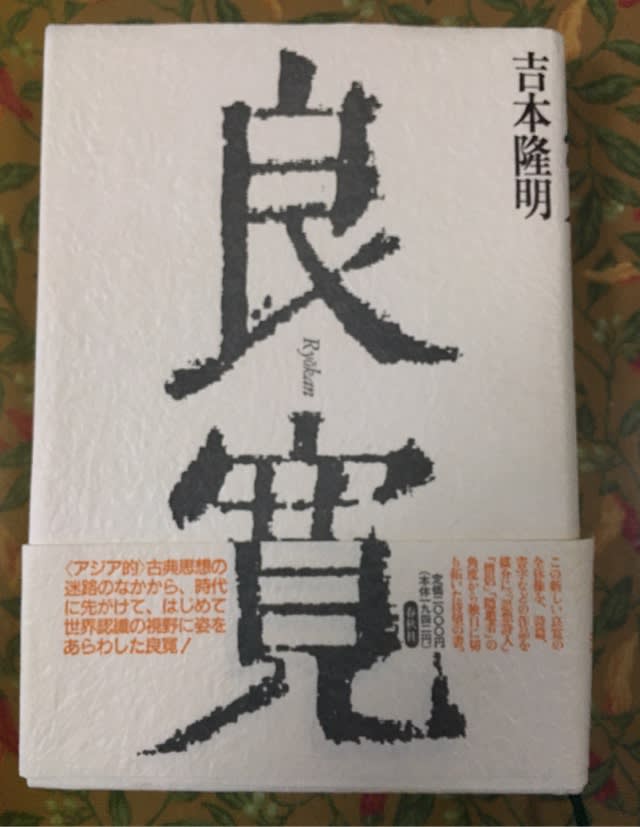
I 良寛
思想詩2

良寛が傾倒した道元禅や、老荘や論語は、いずれも低地アジアに起源を持つ古典古代以前の思想ということができます。おおきく世界史的には〈アジア的〉な思想です。この〈アジア的〉思想は古代から近世にいたるまで、日本の制度や文物におおきな影響を印してきました。この〈アジア的〉な思想について、わたしたちは近代以後と近世以前の人々と違った態度がありうるとすれば、そのひとつはわたしたちが、いわば近代の西洋思想の洗礼をうけていることです。そのうえで良寛がみた仏教や老荘や儒教の思想をみることができることです。良寛とおなじ思想をまえにして、わたしたちが良寛とちがう理解をもちうるとすれば、そこに由来しています。
良寛にとって仏教的な思想や、老荘や儒教の思想は、思想としての全世界でありました。それ以外の世界は思想としては存在しなかったのです。わたしたちにとってヨーロッパの思想も、いわばおなじ視野のなかにはいっています。その世界史的視野のなかで〈アジア的〉思想をうけとることができることが、良寛とわたしたちとちがうところです。またちがわなければならないところだとおもいます。なぜならば良寛は近世末の人ですし、わたしたちは現代にあるのでから。現代にあることに取柄があるとすれば、世界史的視野のなかで、仏教の思想や中国の古典思想をとりあげられるということです。
(中略)
〈アジア的〉な古典思想のなかで、仏教や儒教や老荘はヘーゲルみたいないい方をすれば、おおきな河川の流域にひろがった、いわば低地の農耕地帯に発生した思想ということになります。アジアにも高地があります。それから、小アジアのように、海に口をつけているところもあります。そういう思想と平地の思想は、ちょっとだけちがいます。わたしたちにかかわりが深いのは、河川の流域にひろがった平地で築かれてきた思想です。
また〈アジア的〉という概念には、もうひとつべつの意味があります。ヘーゲルやマルクスが明晰にとりだしたことですが、〈アジア的〉というのは世界史の時間でいいますと、古代の以前に想定される歴史的なひとつの時間を意味しています。つまり〈アジア的〉という概念は地域空間の概念だけではないということです。アジア地方に発生した思想は〈アジア的〉です。しかしそれは地域的な〈アジア〉という意味あいだけではありません。時間的に〈アジア的〉なのです。時間的に〈アジア的〉ということは、古代以前の時期のことを指します。原始時代のつぎにくるのが〈アジア的〉時代、〈アジア的〉世界史の時代ということです。
わたしたちが〈アジア的〉思想というばあい、二重の意味があります。ひとつはアジア地域で発生した思想のことです。しかし、中国で発生して日本へやってきた、あるいはインドで発生し、そして中国を通って日本へ渡った思想だとみただけでは、その思想をみたことになりません。その思想をみるためには、もうひとつ古典古代以前の思想、以前の段階にあった思想としてみなければ、その思想をみたことにならないのです。それが〈アジア的〉な古典思想に影響をうけた近世以前の日本の思想家や詩人たちと、わたしたちがちがうところです。わたしたちの見方がちがうところは、それだけに帰着します。
〈アジア的〉な制度の特徴は、政治的権力が制度を敷くばあい、はじめからおわりまで、宗教から法律の末端にいたるまで、全部じぶんたちの考え方で制度を組み替えようなどとしないことです。まえからあつた共同体の制度を、できるだけそのままに温存して、そのうえに乗っかって政治権力を行使します。つまり既成の制度や習慣や文物にできるなら手をくわえないのです。手をくわえないでそのうえに支配的な共同体をうわ乗せするのです。いわばまえからあった共同体の頭の部分だけを組織
して掠めるのです。それが〈アジア的〉という制度の概念の世界史的特徴です。
古代の大和朝廷についてかんがえてみますと、具体的な過程がどんなであれ、それ以前にあった共同体の政治や宗教の制度をうち壊して、じぶんたちの制度や文物を末端にまで押しつけていくことを、できるかぎりしないで、じぶんたちの利害に反したり、反抗したりしないかぎり、そのままに温存して、そのうえに権力を乗せるというような方法をとっています。そして経済的には貢納、貢物をとる制度を敷きます。貢物をとるには、まえからあった共同体の首長たちに、下から貢物をとらせて、中央に運ばせればよろしいことになります。もちろん各地には直属の三宅というものをおきます。これがわが国における〈アジア的〉な社会や国家の構造といえましょう。以前の共同体のひとつが、勢力を増してそのうえに乗っかるか、他所から到来した勢力が脇からきて、そのうえに乗っかるかはさまざまの可能性がかんかえられるのですが、いつもおなじ形式をとるとみてよろしいことになります。宗教、制度、風俗、習慣の成り立ち方の根本にあるこの特徴は、明治以降、近代西洋の制度を数多くうけいれましたが、現在も構造的に潜在しているにちがいありません。誰もがこれに思いあたる節があるだろうと信じられます。
こういったことは、日本の出家隠遁の思想におおきくかかわりがあるとおもいます。まえからある共同体のうえに、新しい支配の共同体ができ、またそのうえに新しい支配の共同体ができていっても、まえからの底辺にある共同体の制度や宗教や風俗、習慣などは、できるかぎり手をくわえないで温存されるとみなせば、底辺の共同体で太古から受け継がれている宗教や制度や民俗みたいなものは、上層の共同体の勢力あるいは制度がどう変わっても、それとは関係なく保存されるという制度的な距離感覚が根をもつようになります。いちばん新しい共同体の頂点にある思想と、まえからあって、あまり変わっていない思想とは、時代が古いほど、距離感はおおきくなることがわかるでしょう。それから時代が古いほどその隔たりがおおきくなるでしょう。底辺で流布されている思想や、古代から受け継がれている伝統的な宗教や習俗は、制度がどう変わっても「帝力吾において何かあらんや」という感性の距離に遠ざかります。それが〈アジア的〉な古典思想、わが国の隠遁思想の提起する根本的なモチーフになっています。
制度以前にある〈自然〉という規定が〈アジア的〉な制度のもとで遠のいてゆくとき、感性と思惟はどんな態度をとるのかの問題といえましょうか。どんな制度の思想が支配しても、たいして変わりばえしないはずだという強固な認識はなぜでてくるか。思想が制度にぶつかるまえに、山川草木にぶつかり、そこに関心がとどまってしまうだけの充分な感性の距離をもってしまう根拠がここにあります。中世ヨーロッパでは、特別に僧院のなかに籠った特殊な僧侶とか、特異な自然詩人のうちにしか成り立たない制度的な〈無〉の思想ですが、日本の〈アジア的〉な社会では、自然と遊ぶ隠遁思想が制度的な裾野をもってきました。制度にたいする考察などしないでも、何故か〈自然〉思想が成り立ったのです。文学、詩歌のたぐいが人間臭さにぶつからず、自然のなかにじぶんをうつしいれることで成り立ち、政治制度の思想は〈天〉の秩序にかかとを接して権力のピラミッドをこしらえたのです。これが感性的につかまれた〈アジア的〉という制度の概念です。
良寛の性格悲劇を包んでいる思想の雰囲気は、老荘のすぐれた〈自然〉思想でした。それらは制度から退くこと、また道徳から離脱することに根拠をあたえるものでした。天地山川は、何もしないのにそのままで清らかで安穏であるところに、老荘は「無為」のよさを位置づけました。かれらは「仁義」が生まれるようになって、かえって天下が「惑乱」したと説いています。「生」は天地からゆだねられたものであり、「死」は天然という巨室に眠ることだとと荘子はかんがえました。良寛を動かしたこれらの思想は基本的には〈制度以前〉の思想だという性格をもっています。良寛はそれを認識したというよりもその思想を生きたのです。わたしたちはその思想の性格を認識することができます。それは、けっして現代が良寛にくらべて偉いからではありません。ただヨーロッパの思想の近代の洗礼をうけたあとでわたしたちは、良寛に傾倒し、その思想をそのまま浮かびあがらせて眺める視野をうることができるからです。
道元の思想から逸脱したあとの良寛は、『正法眼蔵』が禁じた詩人文学者として後半生をおくりました。そして良寛の後半生を支配したのは、おなじように道元が排した荘子などの思想に近いものでした。
荘子、老子、孔子の思想を先入観なしにならべてみますと、こういうことがわかります。老子、荘子は、南中国の思想といったらわかりやすいとおもうのですが、制度にたいする考察とか、道徳にたいする考察がほとんど皆無ということです。つまり、さきほどの言葉でいえば、(原始的)段階の末から(アジア的)段階の初期にわたる時期に、人間の考えが直面した問題をおもくみていることがわかります。それが老子や荘子の思想です。ここには制度、道徳という思想はむしろないのです。それは排する以前に存在自体がないのです。道徳とか、善悪とか、喜怒哀楽とかいうものはどうしてできてくるのか。それは「天」から逃げようとするからだ。人間が「天」から逃げて、人間本位になろうとするから、道徳とか喜怒哀楽とか、政治制度とかがでてくる。それはむしろだめな考え方だ。だから道徳を説く聖人がいるから大泥棒がでてくるのだ(「聖生れて大盗起る」ー『荘子』ー)といういい方をするのです。つまり、制度や道徳にたいする考慮からは、荘子や老子は自由であり、むしろそういうものが無化される根拠を提示しようととしています。
孔子には制度にたいする考察が道徳にたいする考察といっしょに二重に含まれています。人間はどんなふうに道徳に依拠していくべきかという考えと、どんなふうに制度に処すべきかという考えとが二重になっています。それは(アジア的)思想のなかでは、中期ないし後期に位置づけられる考えをおおく保存しているからです。制度、善悪、道徳、人格にたいする考察が『論語』にはおおくなされています。『論語』には「徳は孤ならず、必ず鄰あり」みたいな言葉がたくさんあります。これはたしかに道徳の言葉のようにみえます。〈徳ある人間は、けっして孤立することはない。かならず支持する人間がでてくるものだ〉というように理解できましょう。しかし、これは、同時に制度の意味を含蓄する言葉でもあります。つまり〈徳を原理として国家共同体を治めるなら、隣国の共同体はかならず親和をもとめて近づいてくるものだ〉ということを意味しています。
『論語』を読むにはたぶん、この制度と道徳とのふたつの眼鏡が必要です。言葉が二重性としてあるからです。これは『論語』にとって根本的なことのようにおもわれます。古典学者は〈徳の高い人間は、孤立することなく、かならず隣人が慕い寄ってくるものだ〉というように説いてきました。それは同時に、共同体を治める原理としての「徳」を意味しているのです。〈君主というものが、徳をもって共同体あるいは小国家を治めるならば、隣の国、共同体は、かならずじぶんたちのところへ仲良くしようというふうにいってくるはずだ〉ということをが、制度としての解釈になります。制度的と個人道徳的との両方を、いわば二重の含みをもって読むべき時間に『論語』は位置しているのです。』アジア的〉という概念のなかで『論語』を読んでいきますと、道徳と制度が未分化であった時代が蘇ってきます。国王はどのように民衆を治めなければならないかというふうな、個人意志としての道徳を、制度的倫理として混融して考えていた時代にできあがったものだからです。「朋あり、遠方より来たる。また楽しからずや」というばあいに、〈仲のよい友達が遠くの方からやって来て、一杯飲みながらお喋言りするといったことは、楽しいじゃないか〉という意味にはちがいないでしょうが、それだけではありません。「友」というのは〈友人としての共同体、つまり〈隣邦〉とか〈同盟国〉ということです。そういう〈共同体〉が遠方から来た、つまり〈遠方の小国家あるいは共同体が、じぶんの方へ仲良くしよう、と同盟をしよう、というふうにやって来た、それはいいことじゃないか〉といっているとおもわれます。
老荘の思想は南中国で、むしろインドやセイロンに近いところで生まれた思想です。そこでは初期の〈アジア的〉原理がつよく保存されています。制度あるいは道徳以前の〈自然〉な意識で生きていた時代の共同体の思想をよりおおく保存しているです。中国の古典思想のなかでは荘子はもっとも緻密で整っと構成をもっています。良寛は道元禅つまり初期仏教禅の思想を放棄したとき、たぶん荘子によりおおく後半生の支柱を求めたのでしょう。詩人としての良寛を方向づけたものは、荘子の考え方であったようにおもわれます。荘子の「無為」に解放されて、じぶんの若いときからの資質である風光に慰謝する情念を追及してゆきました。









