言の葉54 西行論⑦
ー歌人論ー その3
西行論 著者吉本隆明 発行所(株)講談社 1990年2月10日発行
より抜粋
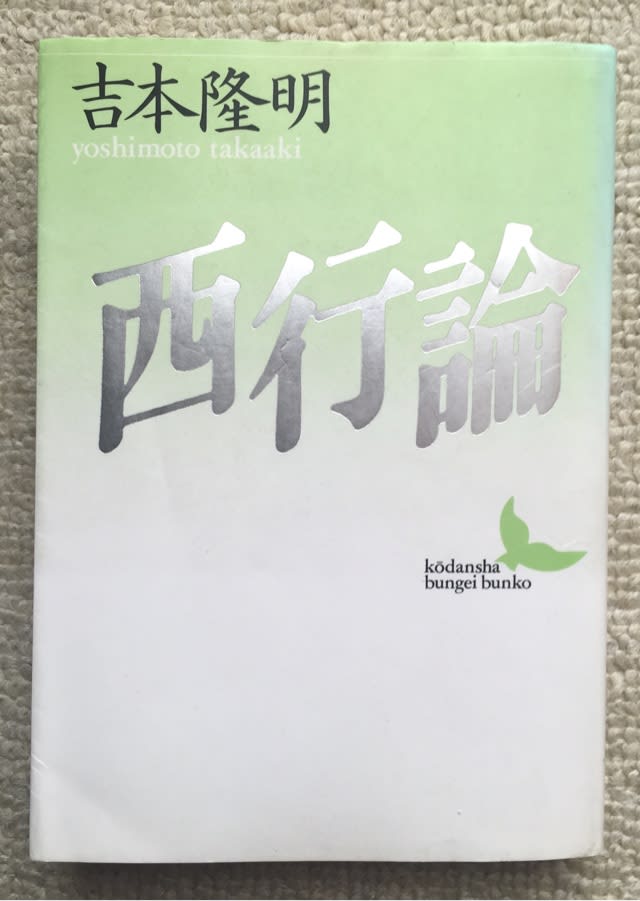
歌人論(4)「花」と「月」3より抜粋
西行の「月」の歌は特徴的であった。ひとくちにいえば信仰の証としての「月」の歌といえるものを、ひとつの分野として開拓したと言うべきものだった。それは景物の要めにある「月」と、その景物の「月」を眺めやる心のあいだに、信仰といえる心の状態を認知し、その境位を歌に詠んだことを意味している。もちろんそれだけならば時にひとつやふたつ信仰の心を「月」に託した歌はないことはなかった。ただはっきりと「月」の意味と情緒を信仰の心の暗喩として詠むことを、じぶんの詠歌のひそかな部立てとした歌人が、かれのほかいなかったのだ。
三五三 ゆくゑなく月に心のすみすみて はてはいかにかならんとすらん
(『山家集』秋・上)
三六七 ながむればいなや心のくるしきに いたくなすみそ秋のよの月
(同)
返し
七三三 すむといひし心の月しあらはれば この世もやみのはれざらめやは
(『山家集』中・雑)
月前述懐
七七三 月をみていづれのとしの秋までか この世にわれがちぎりあるらん
(同)
七月十五日夜、月あかゝりけるに、ふなをかにまかりて(※1註)
七七四 いかでわれこよひの月を身にそへて しでの山路の人をてらさん
(同)
大みねのしむせんと申所にて、月をよみける(※註2)
一一〇四 ふかき山にすみける月を見ざりせば 思出もなき我身ならまし
(『山家集』下・雑)
一四〇七 雲はれて身にうれへなき人の身ぞ さやかに月のかげはみるべき
(同)
一四一〇 心をばみる人ごとにくるしめて 何かは月のとりどころなる
(同)
一四一ニ ながめきて月いかばかりしのばれん このよしくものほかになりなば
(同)
一四一三 いつかわれこのよのそらをへだゝらん あはれあはれと月をおもひて
(同)
ハハ あはれなる心のをくをとめゆけば月ぞおもひのねにはなりける
(『聞書集』)
同行に侍ける上人、月のころ天王寺にこもりたりときゝて、いひつかはしける
ハ五三 いとヾいかににしへかたぶく月かげを つねよりもけに君したふらん
(『山家集』中・雑)
見月思西と云事
ハ七〇 山端にかくるゝ月をながむれば われと心のにしにいるかな
(同)
易住無人の文の心を
ハ七二 西へ行月をやよそにおもふらん 心にいらぬ人のためには
(同)
観心
ハ七六 やみはれて心のそらにすむ月は にしの山べやちかくなるらん
(同)
ある人、よをのがれきた山でらにこもりゐたりときゝて、たづねまかりたりけるに、月のあかゝりければ
七五四 よをすてゝたにそこにすむ人見よと みねのこのまを分る月影
(同)
一〇四一 この世にてながめられぬる月なれば まよはんやみもてらさゞらめや
(同)
二ハ 山のはにいづるもいるもあきの月うれしくつらき人のこころか
(『聞書残集』)
当方(※註1)山家集 金槐和歌集
日本古典文文学体系29発行所 岩波書店 頭注より
7月15夜…盂蘭盆会の夜。ふなおか…船岡山。山城国愛宕郡、今、京都市上京区紫野の西。火葬場があった。
日本大地図 中巻 日本名所大地図1
企画・発行 ユーキャン より
大徳寺の南、金閣寺の東に位置する

当方(※註2)同じく頭注より
大峰…大和国大峰山。修験道の霊地。しむせん(しんせん)…吉野郡上北山村深仙。大日岳と釈迦が岳との中間。入山者に正灌頂が施す所。深き山…深仙を同音で深山としそれを訓み込んだ。
日本大地図 上巻 日本分県大地図
企画・発行 ユーキャン より
奈良県の大峰山脈

いつか臨終のときがきてこの世の空をへだたるとき、月を「あはれあはれ」と思うことだろうと詠んでいる歌に、すべては象徴される。「月」を秋の景物としての「月」から、この世のこころと来世のこころとを映し、境界にあってそのふたつを、ひとつの鏡に合わせている形而上的存在にまで高める歌をはじめて確立した。また「月」が澄むということに誘われて心が澄むということは、来世への鍵となるもので、身とこころに憂いがないものだけが澄む「月」に象徴される来世の世界に入りきれるものとかんがえられている。西に月が傾いてゆくことは、心が西方浄土に傾いてゆくことと同義であった。そして後世を願う出家として、「月」のひかりをじぶんの身につけて、死者が浄土へゆく路を照らしてやりたいとかんがえた。こんな「月」のうたは釈教歌としてときにないことはなかったが、ひとりの歌人が精力を傾けて詠んだものとしては、同時代にもそれ以前にも存在しなかったのである。
西行の信仰の「月」の歌は優れた歌とはいえない。むしろ西行ほどの歌人が、どうしてこんな歌を作ってしまうのかと思える歌だといってもいいすぎではない。どうしても信仰の境位を「月」になぞらえてみたり、「月」を来世を願うとぎ澄ました心に擬したりしたいあまり、類型的でもあり、また理念の戯れでもあるような、ありきたりの歌にしているといえる。だが逆にいえば、とても優れた歌になりそうもないモチーフを「月」に仮託して詠んでいるところに、西行がひそかに心のなかにつくった部立てがあった。それは釈教ともちがうし、叙景の歌ともちがう。「月」を中心に含んだ景観に寄託する心の構えを、景観にむかって狭ばめ、信仰の境位のように昇華させてゆくものであった。
「月」の歌がいちばん優れているのは『古今集』だといえよう。それは「月」が景観として鑑賞され、風雅とみなされるようになったことと関わりがある。
『古今集』の月の歌の例示
夏の夜はまだ宵ながらあけぬるをくものいづこに月宿るらん
(巻第三・夏 深養父)
夕月夜おぐらのやまになく鹿のこゑのうちにや秋はくるらん
(巻第五・秋下 貫之)
大空の月のひかりしきよければかげ見し水ぞまずこほりける
(巻第六・冬 読人しらず)
あさぼらけ有明の月と見るまでに吉野のさとにふれる白ゆき
(巻第六・冬 坂上是則)
あまの原ふりさけ見れば春日なるみかさの山にいでし月かも
(巻第九・羇旅 安倍仲麿)
夕月夜おぼつかなきを玉くしげふたみの浦はあけてこそみめ
(巻第九・羇旅 藤原かねすけ)
飽かなくにまだきも月の隠るるか山の端遁げていれずもあらなん
(巻第十七・雑上 業平朝臣)
これらはどれも「月」を景観の中心として眺めて、感懐を託したものだ。そして「月」の景観を景観として描写するというよりも、深い思い入れを歌に詠んでいる。ひとところに座して「月」を眺める風習をもたなくとも、思いを入れることはその都度できるはずだが、歌に詠むこと、とくに静止の点に視座をおいて「月」の景観に思い入れた感懐を歌に詠むことは、鑑賞の風習やそれに類似の習俗がなければできないとおもえる。
(中略)
ー歌人論ー その3
西行論 著者吉本隆明 発行所(株)講談社 1990年2月10日発行
より抜粋
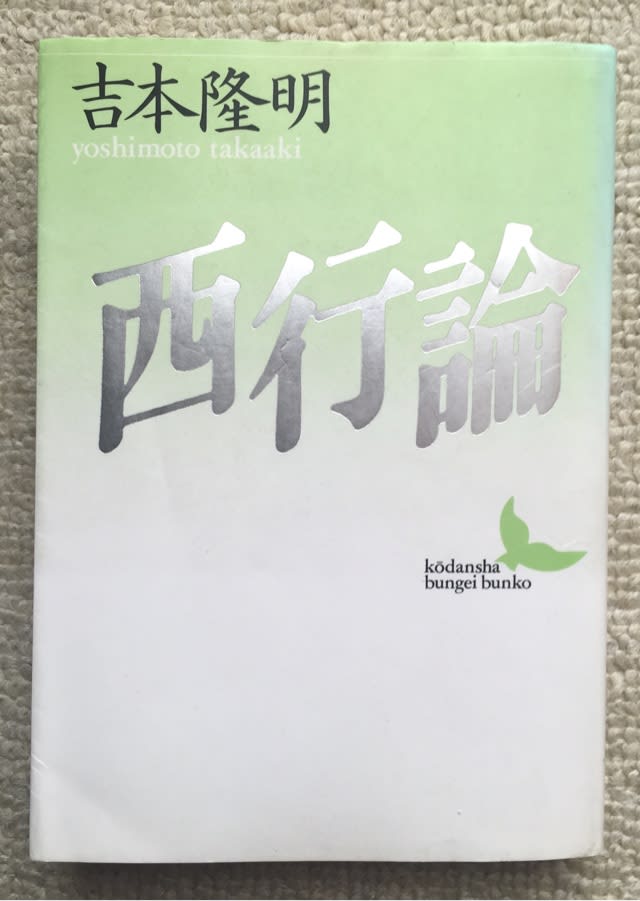
歌人論(4)「花」と「月」3より抜粋
西行の「月」の歌は特徴的であった。ひとくちにいえば信仰の証としての「月」の歌といえるものを、ひとつの分野として開拓したと言うべきものだった。それは景物の要めにある「月」と、その景物の「月」を眺めやる心のあいだに、信仰といえる心の状態を認知し、その境位を歌に詠んだことを意味している。もちろんそれだけならば時にひとつやふたつ信仰の心を「月」に託した歌はないことはなかった。ただはっきりと「月」の意味と情緒を信仰の心の暗喩として詠むことを、じぶんの詠歌のひそかな部立てとした歌人が、かれのほかいなかったのだ。
三五三 ゆくゑなく月に心のすみすみて はてはいかにかならんとすらん
(『山家集』秋・上)
三六七 ながむればいなや心のくるしきに いたくなすみそ秋のよの月
(同)
返し
七三三 すむといひし心の月しあらはれば この世もやみのはれざらめやは
(『山家集』中・雑)
月前述懐
七七三 月をみていづれのとしの秋までか この世にわれがちぎりあるらん
(同)
七月十五日夜、月あかゝりけるに、ふなをかにまかりて(※1註)
七七四 いかでわれこよひの月を身にそへて しでの山路の人をてらさん
(同)
大みねのしむせんと申所にて、月をよみける(※註2)
一一〇四 ふかき山にすみける月を見ざりせば 思出もなき我身ならまし
(『山家集』下・雑)
一四〇七 雲はれて身にうれへなき人の身ぞ さやかに月のかげはみるべき
(同)
一四一〇 心をばみる人ごとにくるしめて 何かは月のとりどころなる
(同)
一四一ニ ながめきて月いかばかりしのばれん このよしくものほかになりなば
(同)
一四一三 いつかわれこのよのそらをへだゝらん あはれあはれと月をおもひて
(同)
ハハ あはれなる心のをくをとめゆけば月ぞおもひのねにはなりける
(『聞書集』)
同行に侍ける上人、月のころ天王寺にこもりたりときゝて、いひつかはしける
ハ五三 いとヾいかににしへかたぶく月かげを つねよりもけに君したふらん
(『山家集』中・雑)
見月思西と云事
ハ七〇 山端にかくるゝ月をながむれば われと心のにしにいるかな
(同)
易住無人の文の心を
ハ七二 西へ行月をやよそにおもふらん 心にいらぬ人のためには
(同)
観心
ハ七六 やみはれて心のそらにすむ月は にしの山べやちかくなるらん
(同)
ある人、よをのがれきた山でらにこもりゐたりときゝて、たづねまかりたりけるに、月のあかゝりければ
七五四 よをすてゝたにそこにすむ人見よと みねのこのまを分る月影
(同)
一〇四一 この世にてながめられぬる月なれば まよはんやみもてらさゞらめや
(同)
二ハ 山のはにいづるもいるもあきの月うれしくつらき人のこころか
(『聞書残集』)
当方(※註1)山家集 金槐和歌集
日本古典文文学体系29発行所 岩波書店 頭注より
7月15夜…盂蘭盆会の夜。ふなおか…船岡山。山城国愛宕郡、今、京都市上京区紫野の西。火葬場があった。
日本大地図 中巻 日本名所大地図1
企画・発行 ユーキャン より
大徳寺の南、金閣寺の東に位置する

当方(※註2)同じく頭注より
大峰…大和国大峰山。修験道の霊地。しむせん(しんせん)…吉野郡上北山村深仙。大日岳と釈迦が岳との中間。入山者に正灌頂が施す所。深き山…深仙を同音で深山としそれを訓み込んだ。
日本大地図 上巻 日本分県大地図
企画・発行 ユーキャン より
奈良県の大峰山脈

いつか臨終のときがきてこの世の空をへだたるとき、月を「あはれあはれ」と思うことだろうと詠んでいる歌に、すべては象徴される。「月」を秋の景物としての「月」から、この世のこころと来世のこころとを映し、境界にあってそのふたつを、ひとつの鏡に合わせている形而上的存在にまで高める歌をはじめて確立した。また「月」が澄むということに誘われて心が澄むということは、来世への鍵となるもので、身とこころに憂いがないものだけが澄む「月」に象徴される来世の世界に入りきれるものとかんがえられている。西に月が傾いてゆくことは、心が西方浄土に傾いてゆくことと同義であった。そして後世を願う出家として、「月」のひかりをじぶんの身につけて、死者が浄土へゆく路を照らしてやりたいとかんがえた。こんな「月」のうたは釈教歌としてときにないことはなかったが、ひとりの歌人が精力を傾けて詠んだものとしては、同時代にもそれ以前にも存在しなかったのである。
西行の信仰の「月」の歌は優れた歌とはいえない。むしろ西行ほどの歌人が、どうしてこんな歌を作ってしまうのかと思える歌だといってもいいすぎではない。どうしても信仰の境位を「月」になぞらえてみたり、「月」を来世を願うとぎ澄ました心に擬したりしたいあまり、類型的でもあり、また理念の戯れでもあるような、ありきたりの歌にしているといえる。だが逆にいえば、とても優れた歌になりそうもないモチーフを「月」に仮託して詠んでいるところに、西行がひそかに心のなかにつくった部立てがあった。それは釈教ともちがうし、叙景の歌ともちがう。「月」を中心に含んだ景観に寄託する心の構えを、景観にむかって狭ばめ、信仰の境位のように昇華させてゆくものであった。
「月」の歌がいちばん優れているのは『古今集』だといえよう。それは「月」が景観として鑑賞され、風雅とみなされるようになったことと関わりがある。
『古今集』の月の歌の例示
夏の夜はまだ宵ながらあけぬるをくものいづこに月宿るらん
(巻第三・夏 深養父)
夕月夜おぐらのやまになく鹿のこゑのうちにや秋はくるらん
(巻第五・秋下 貫之)
大空の月のひかりしきよければかげ見し水ぞまずこほりける
(巻第六・冬 読人しらず)
あさぼらけ有明の月と見るまでに吉野のさとにふれる白ゆき
(巻第六・冬 坂上是則)
あまの原ふりさけ見れば春日なるみかさの山にいでし月かも
(巻第九・羇旅 安倍仲麿)
夕月夜おぼつかなきを玉くしげふたみの浦はあけてこそみめ
(巻第九・羇旅 藤原かねすけ)
飽かなくにまだきも月の隠るるか山の端遁げていれずもあらなん
(巻第十七・雑上 業平朝臣)
これらはどれも「月」を景観の中心として眺めて、感懐を託したものだ。そして「月」の景観を景観として描写するというよりも、深い思い入れを歌に詠んでいる。ひとところに座して「月」を眺める風習をもたなくとも、思いを入れることはその都度できるはずだが、歌に詠むこと、とくに静止の点に視座をおいて「月」の景観に思い入れた感懐を歌に詠むことは、鑑賞の風習やそれに類似の習俗がなければできないとおもえる。
(中略)













