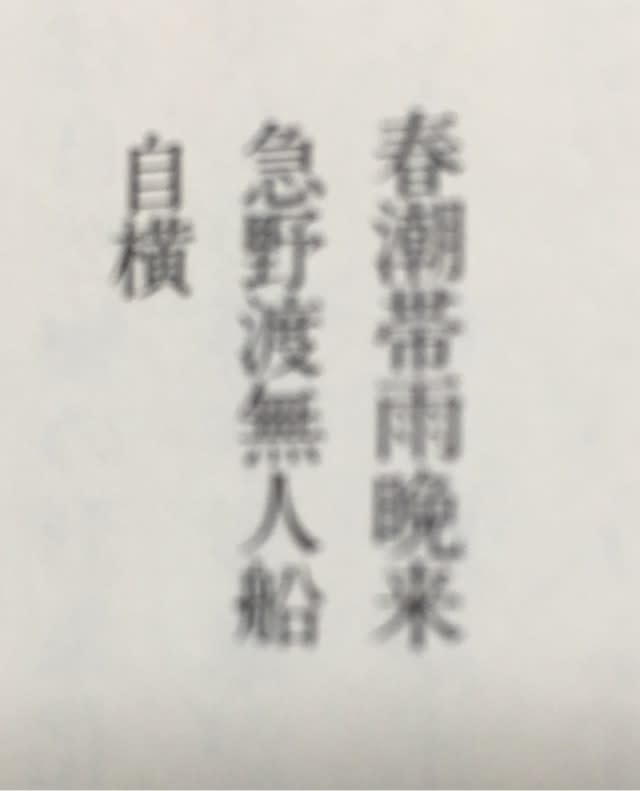71良寛⑩漱石のなかの良寛
4 最後の漱石
良寛 吉本隆明著 株式会社春秋社
発行所 1992年2月1日発行より
抜粋

IIー「良寛 」以後
漱石のなかの良寛
4 最後の漱石 より

漱石は大正三年ごろ良寛の詩というよりも、書にひかれたとおもいます。漱石も書がうまい人ですが、良寛の書に魅せられたとおもいます。そこからだんだん良寛に傾倒していったでしょう。漱石には良寛が心のなかにいつでもひっかかっている存在であり、禅についての漱石の関心は、良寛を調べていったり、良寛の書に親しんだりしていくあいだに、だんだん深まっていったとかんがえられるのです。
さきほどの『門』という主人公宗助が、鎌倉の禅寺を訪ねていくちょうどそのことと対応するような詩を、明治四十三年九月に作っています。作った年月としていいますと、『門』という作品は明治四十三年ですが、だいたい九月以前に書かれていますから、『門』はそのときすでに書かれてすこしたっているわけです。漱石はもともと胃が悪かった人ですが、八月二十四日に大きな吐血をして死にそうになり、意識が半分もうろうと、不明になってしまうのです。そして、じぶんでは、生きかえったのか、死んじゃったのかわからないような、もうろうとした病床の状態を続けるわけです。それがすこしよくなってすぐに作ったのが、「無題」という詩だとおもいます。そのときどういう詩を書いているかというと、
円覚會つて参ず棒喝の禅
瞎児何処にか機縁に触れん
青山拒まず庸人の骨
首を九原より回らせば月天に在り
ちょうど、漱石が吐血して意識不明になって、それで意識がさめてやっとたすかったというふうになってからしばらく経って作った漢詩です。これがちょうど、『門』で宗助が鎌倉の禅寺へ行ったっていうことに対応する実際の体験のことを詠んだ、そういう作品です。吐血して生死の境をさまよってやっと生きかえったときに、じぶんが参禅したときのことを思い浮べて、作っているわけです。
円覚寺にかってじぶんが参禅に行ったんだが、ばかな人間で、すこしも禅の機縁といおうか、悟りのきっかけを得ることなしに(ちょうど『門』の宗助と同じなんですけども)終わってしまった、というのです。「青山拒まず庸人の骨」というのは、けれども人間の死んだあとはいる墓地(「青山」というのは墓所、墓です)は「庸人の骨」、じぶんみたいな平凡な人間の骨だって、けっして拒まないでいれてくれるものだ。吐血して意識不明になり、どうもひとたび墓へはいって骨になった、そういうところまで、じぶんは生死の境を越えていってしまったような体験をした、といっているとおもいます。「首を九原より回らせば月天に在り」というのはどうでしょう。この「九原」というのは別の言葉で墓のことです。だから「しぶんは墓のなかから首をもたげてみると、月が空にかかっていた」と歌っているのです。生死の境をさまよって、意識不明なった、そんなときの気持を、詩であらわしていることになります。そうしてかって円覚寺にいって参禅したときには、ちっともじぶんは〈悟り〉のきっかけを得ることができなかったが、病気をして生死の境をさまよい、そのときなんだか墓のなかでひとたび〈死〉というものに恐れ気なく触れて、そこから空にかかった月を眺めたっていう気持になったような気がする。病気をして生死の境をさまよってはじめて、じぶんが、若いときに悟れなかった、そういう〈悟り〉に似たような気分を味わったようだと唱っているとおもいます。「門」のなかで宗助が〈坐禅〉にこだわって、そして鎌倉にやってきて、心の不安も解消しないで帰ってきたという体験を、ちょうど作者自身の体験として詠んで、そのとき得られなかった悟りが、胃の病気で死に目にあって得られたような境地になった、といっているのです。
もっと切実に良寛に関連して、大正五年に作った詩があります。大正五年といいますのは、もう漱石の晩年といっていいくらいで、晩年の漢詩です。ですから、もうほとんど漱石の最後にたどりついた場所みたいなものをあらわしているようにおもいます。
大愚到り難く志成り難し
五十の春秋瞬息の程
道を観るに言無くして只静に入る
詩を拈りて句有れば独り静を求む
超超たり天外去雲の影
籟籟たり風中落葉の声
忽ち見る閑窓虚白の上
東山月出でて半江明かなり
意味をいってみます。じぶんは「大愚」という名を師家からもらった良寛の境地にはとてもたどりつけなかったし、またじぶんからなろうとおもった、そういうものにもなりえなかった。五十歳の春秋が、もう息をするまもなく過ぎてしまった。じぶんのたどった道、これからの道をみてみると、言葉もなにもなく、ただ静かになるだけだ。そこで詩をひねって言葉や句が浮かんでくると、そうやってじぶんはすがすがしさを求めているのだ。「超超たる」というのは、はるかなということですから、はるかな空の涯の方には雲が行く影がみえる。また、風がしょうしようと鳴って落葉の声がしている。じぶんの部屋の静かな窓をみてみると、その外には東の山の方に月がでて、川の半分が月に照らされて明るくなっているというのです。じぶんの境地と、それからじぶんがとうとう良寛のような境地まで行けないできてしまったなというのです。でも静かになろうとおもって詩を作ったり、それから、じぶんの道をかえりみると、そこには雲の影も浮かんでいるし、また風も落葉のところに声を発している。窓の外をみると、月も東の方の山にかかっているし、川には月の光が半分照らしている。それはいってみれば、じぶんなりに、まあ充たされたとはいえないまでも、静かなある境地だといえばいえるかもしれないということでしょう。
これはもう漱石が晩年に近いころの漢詩です。伝記的にいいますと、漱石は修善寺で胃病にかかり、そしてそのあと吐血して生死の境をさまよって以降、「則天去私」つまり「天のおもむくままにまかせて、小さなじぶんというようなものを捨て去ってしまう」という〈境地〉にはいったとされます。漱石の「則天去私」は、いってみればこういう漢詩に表現された境地だといえましょう。この境地は禅宗の坊さんがいう悟りの境地ではありません。禅家のいっている境地が、ほんとの意味があるかどうかは、またいろいろ疑問のあるところです。漱石みたいに、そのことに関心がありながら、じぶんは「門」のなかにははいれなかった。そんな心の在り方がほんとの〈悟り〉に近かったかもしれないのです。そこが、漱石のたどりついた〈坐〉の境地をあらわしています。

漱石の〈坐〉の境地を漱石の作品でみようとすると、ただひとつ該当するのは『明暗』という作品だとおもわれます。それはどんなふうにあらわれたでしょうか。『明暗』は、ただひとつの解答のようにみえながら、未完の小説です。『明暗』をおわらないうちに、漱石は亡くなってしまいました。いま残されている『明暗』は、もう半分ぐらいすすんでいたのかなとおもえるところもありますが、存外入口のところまでかなとおもえるところもあるんです。『明暗』は、もともと物語の多様な筋があったり、起伏があったりという作品ではありません。たいした物語は起こりそうもないわけです。そうみなすと、もう相当程度まで書きすすんだことになっているのかとおもえます。また逆に、まだ筋の進展がないじゃないかとかんがえると、あんがい序の口のところで、作者が病気になって、死んでしまったともかんがえられるのです。ただいえることは、『明暗』には、この『門』の宗介が感じるような、動揺の過程、それを鎮めようと苦しむ過程、ついに偶然のことから解決してしまうといった不安をかきたてる要素は、なにもなくなっていることです。主人公がいて不安を感ずるとか、不安にかきたてられるとか、作品自体が読む人に不安をあたえるとか、そんなところは『明暗』のなかにはあらわれませんし、またこれから『明暗』がおわりまで書きつがれたとしても、たぶんあらわれないとだけいえるのではないでしょうか。ですから、そういう意味では、『明暗』が『門』に較べたらはるかに、晩年の漱石の〈坐〉の境地を物語っているとかんがえられます。
漱石の作品は、いってみればたいへん深刻な作品で、いまの言葉でいえばとても〈根暗〉です。人間の心にある不安とか恐怖とか、あるいは背徳とか罪の意識とか、そんなものをぎりぎり追いつめているのが漱石の作品のおおきな特徴なんです。
『明暗』になって、おおきな主役を設定して、その人物の不安とか罪の意識とかを追求していく形はなくなるのです。すべての登場人物は、どんな人間も、あるひとつの距離からみると、同一なんじゃないか。逆にいえば、全部の人間が全部同じような距離に、おなじようにみえるそういう場所はどこかにあるんじゃないか、こういう認識を垣間見せるところが『明暗』にはあります。
『明暗』の主人公は津田というんですが、これは平凡な生活の何の苦労もないサラリーマンの主人公です。そしてなんら特徴がないんです。この主人公は胃が悪いといわれて、胃を手術しようかというところからはじまるわけです。その手術の金を誰からか借りなければということで、親父や妹にあたるんだけれど、お金は借りられそうもない。そんなところから作品はすすんでゆきます。それから津田にはお延という若い奥さんがいます。その奥さんは芝居の約束をしていて、その芝居の約束の日が、ちょうど津田の手術する日にあたってしまう。そうすると津田のほうはどうせたいした手術じゃないんだから、おまえまえからの約束の芝居に行ってもいいよといいます。すると、奥さんのほうはさすがに、夫の手術の日に芝居に行っちゃうということができなくて、病院についていくのですが、晴れ着を着て病院にくるのです。そして手術が始まりそうになるのに、そわそわしていかにも芝居に行きたそうにしたりする平凡な女性です。手術がおわって津田が行ってもいいというと、奥さんはもう手術がおわってでてきて安心だから、じゃ行ってくるわといい残して芝居にでかけてしまいます。つまりなんの心ばえのない平凡な女に描かれています。
そうすると、その夫婦は平凡などこにでもいる夫婦で、特別仲のいいわけでもなく、そうかといって破局がくるほど仲が悪いわけでもありません。そのばあい、夫が手術をやっとおわって寝ているというのに、芝居へ行っちゃう奥さんをべつに批判的に描いているわけでもありません。また津田という主人公を美化して描いているわけでもありません。いってみれば、津田という主人公もふつうの男、それから、夫の手術の日に、手術がおわったら約束の芝居に行っちゃう奥さんもべつにとくに悪い細君でもないし、とくにいい細君でもない。そういう津田と奥方を両方とも同一の距離で眺めている。作者の眼にみえない眼からかんがえますと、その眼にみえない眼からみれば、津田もそれからその奥方もみんな同一にみえる。どちらがいい人間だとかどちらが悪い人間だとか、そういうふうにはすこしも描かれてない。両方とも同一にみえるという場所に、ひとつの〈眼〉があって、その〈眼〉から眺めているとおもえるのです。
病院に津田の妹が見舞いにくるのですが、この妹は津田がお金を貸してくれというと、そんなにかんたんに貸そうとしないのです。しかし、兄貴が頭を下げるんなら貸してあげてもいいとかんがえています。津田のほうは頭を下げるくらいならおまえなんかから金は借りないと妹にいいます。そこで兄妹のいい争いが起こるのです。そこでも津田と妹のどちらが悪いとか、どちらがいい人間だとか描かれていません。そして両方ともごく平凡で、両方ともいつ、どこにでもいるふつうの兄妹のように描かれています。そのふつうの人である兄と妹の両方を、同じところから見ているひとつの〈眼〉があり、そこからいい争う兄妹は描かれています。
それからまた、津田の友人で小林という社会主義者の男がでてきます。その男はよく津田をおまえなんか親の世話で学校へ行って、のうのうと結婚して、のうのうと勤めて、それで足りない分は親からいまでも金を送ってもらってのうのうと暮らしている。世の中そういうやつばっかりいない。といったたぐいのことをいっては、津田から金をせびっていきます。津田の学校時代の友達なのです。そうすると漱石は、そのばあいにも、金をせびっていく社会主義者の小林という男を美化して描いているわけでもないし、また、とくにこれはつまらない男をだっていうふうに描いているわけではありません。また津田のほうを小林に較べていい男だっていうふうに描いているわけでもないし、とくにだらしない暮らしをしている男だっていうふうに描いているのでもありません。小林と津田を較べると、そこでもふたりを同じ距離から、ごくふつうの人として描いているひとつの〈眼〉を想定することができます。
『明暗』という作品には、対象となるふたりの人物みたいなものが、いつも想定できます。そのふたりずつの人物に、いつでも双方をおなじひとつの距離からみている眼にみえない眼がひとつのあります。そこから登場人物は視られ、描かれているといえます。そうすると、それぞれの一対の登場人物をおなじ距離から眺めている眼にみえない眼の場所がいくつもあるはずですが、そのいくつもある場所を、またこんどは等距離からみているもうひとつのおおきな眼があるとかんがえられます。そのおおきな眼からみると、全部の登場人物は全部同一にみえる、そんな場所が想定できそうです。
漱石はたぶん『明暗』という作品で、たったひとつの最後に残るおおきな〈眼〉を漠然と想定していて、その〈眼〉を、漱石は、たどりついたじぶんなりの境地だとかんかえているようにおもわれるのです。禅がいう〈悟り〉とはすこしちがうんですが、しかし、全部の人間を特別なふうに扱わないし、また特別な人間ともおもわないし、またどんな人間でもごくふつうの人間としてみられるひとつのおおきな〈眼〉のようなものを漱石は「則天去私」つまり「天に則って私を去る」という言葉で意味させようとしていたかもしれないとおもいます。それはたぶん、漱石が関心をもった〈坐禅〉というもの、あるいは良寛の〈大愚〉という〈境地〉とはだいぶちがっているのですが、漱石なりのひとつの〈境地〉で、漱石がやっと最後のところ、おもい悩んだあげくたどりついた場所だという気がいたします。
4 最後の漱石
良寛 吉本隆明著 株式会社春秋社
発行所 1992年2月1日発行より
抜粋

IIー「良寛 」以後
漱石のなかの良寛
4 最後の漱石 より

漱石は大正三年ごろ良寛の詩というよりも、書にひかれたとおもいます。漱石も書がうまい人ですが、良寛の書に魅せられたとおもいます。そこからだんだん良寛に傾倒していったでしょう。漱石には良寛が心のなかにいつでもひっかかっている存在であり、禅についての漱石の関心は、良寛を調べていったり、良寛の書に親しんだりしていくあいだに、だんだん深まっていったとかんがえられるのです。
さきほどの『門』という主人公宗助が、鎌倉の禅寺を訪ねていくちょうどそのことと対応するような詩を、明治四十三年九月に作っています。作った年月としていいますと、『門』という作品は明治四十三年ですが、だいたい九月以前に書かれていますから、『門』はそのときすでに書かれてすこしたっているわけです。漱石はもともと胃が悪かった人ですが、八月二十四日に大きな吐血をして死にそうになり、意識が半分もうろうと、不明になってしまうのです。そして、じぶんでは、生きかえったのか、死んじゃったのかわからないような、もうろうとした病床の状態を続けるわけです。それがすこしよくなってすぐに作ったのが、「無題」という詩だとおもいます。そのときどういう詩を書いているかというと、
円覚會つて参ず棒喝の禅
瞎児何処にか機縁に触れん
青山拒まず庸人の骨
首を九原より回らせば月天に在り
ちょうど、漱石が吐血して意識不明になって、それで意識がさめてやっとたすかったというふうになってからしばらく経って作った漢詩です。これがちょうど、『門』で宗助が鎌倉の禅寺へ行ったっていうことに対応する実際の体験のことを詠んだ、そういう作品です。吐血して生死の境をさまよってやっと生きかえったときに、じぶんが参禅したときのことを思い浮べて、作っているわけです。
円覚寺にかってじぶんが参禅に行ったんだが、ばかな人間で、すこしも禅の機縁といおうか、悟りのきっかけを得ることなしに(ちょうど『門』の宗助と同じなんですけども)終わってしまった、というのです。「青山拒まず庸人の骨」というのは、けれども人間の死んだあとはいる墓地(「青山」というのは墓所、墓です)は「庸人の骨」、じぶんみたいな平凡な人間の骨だって、けっして拒まないでいれてくれるものだ。吐血して意識不明になり、どうもひとたび墓へはいって骨になった、そういうところまで、じぶんは生死の境を越えていってしまったような体験をした、といっているとおもいます。「首を九原より回らせば月天に在り」というのはどうでしょう。この「九原」というのは別の言葉で墓のことです。だから「しぶんは墓のなかから首をもたげてみると、月が空にかかっていた」と歌っているのです。生死の境をさまよって、意識不明なった、そんなときの気持を、詩であらわしていることになります。そうしてかって円覚寺にいって参禅したときには、ちっともじぶんは〈悟り〉のきっかけを得ることができなかったが、病気をして生死の境をさまよい、そのときなんだか墓のなかでひとたび〈死〉というものに恐れ気なく触れて、そこから空にかかった月を眺めたっていう気持になったような気がする。病気をして生死の境をさまよってはじめて、じぶんが、若いときに悟れなかった、そういう〈悟り〉に似たような気分を味わったようだと唱っているとおもいます。「門」のなかで宗助が〈坐禅〉にこだわって、そして鎌倉にやってきて、心の不安も解消しないで帰ってきたという体験を、ちょうど作者自身の体験として詠んで、そのとき得られなかった悟りが、胃の病気で死に目にあって得られたような境地になった、といっているのです。
もっと切実に良寛に関連して、大正五年に作った詩があります。大正五年といいますのは、もう漱石の晩年といっていいくらいで、晩年の漢詩です。ですから、もうほとんど漱石の最後にたどりついた場所みたいなものをあらわしているようにおもいます。
大愚到り難く志成り難し
五十の春秋瞬息の程
道を観るに言無くして只静に入る
詩を拈りて句有れば独り静を求む
超超たり天外去雲の影
籟籟たり風中落葉の声
忽ち見る閑窓虚白の上
東山月出でて半江明かなり
意味をいってみます。じぶんは「大愚」という名を師家からもらった良寛の境地にはとてもたどりつけなかったし、またじぶんからなろうとおもった、そういうものにもなりえなかった。五十歳の春秋が、もう息をするまもなく過ぎてしまった。じぶんのたどった道、これからの道をみてみると、言葉もなにもなく、ただ静かになるだけだ。そこで詩をひねって言葉や句が浮かんでくると、そうやってじぶんはすがすがしさを求めているのだ。「超超たる」というのは、はるかなということですから、はるかな空の涯の方には雲が行く影がみえる。また、風がしょうしようと鳴って落葉の声がしている。じぶんの部屋の静かな窓をみてみると、その外には東の山の方に月がでて、川の半分が月に照らされて明るくなっているというのです。じぶんの境地と、それからじぶんがとうとう良寛のような境地まで行けないできてしまったなというのです。でも静かになろうとおもって詩を作ったり、それから、じぶんの道をかえりみると、そこには雲の影も浮かんでいるし、また風も落葉のところに声を発している。窓の外をみると、月も東の方の山にかかっているし、川には月の光が半分照らしている。それはいってみれば、じぶんなりに、まあ充たされたとはいえないまでも、静かなある境地だといえばいえるかもしれないということでしょう。
これはもう漱石が晩年に近いころの漢詩です。伝記的にいいますと、漱石は修善寺で胃病にかかり、そしてそのあと吐血して生死の境をさまよって以降、「則天去私」つまり「天のおもむくままにまかせて、小さなじぶんというようなものを捨て去ってしまう」という〈境地〉にはいったとされます。漱石の「則天去私」は、いってみればこういう漢詩に表現された境地だといえましょう。この境地は禅宗の坊さんがいう悟りの境地ではありません。禅家のいっている境地が、ほんとの意味があるかどうかは、またいろいろ疑問のあるところです。漱石みたいに、そのことに関心がありながら、じぶんは「門」のなかにははいれなかった。そんな心の在り方がほんとの〈悟り〉に近かったかもしれないのです。そこが、漱石のたどりついた〈坐〉の境地をあらわしています。

漱石の〈坐〉の境地を漱石の作品でみようとすると、ただひとつ該当するのは『明暗』という作品だとおもわれます。それはどんなふうにあらわれたでしょうか。『明暗』は、ただひとつの解答のようにみえながら、未完の小説です。『明暗』をおわらないうちに、漱石は亡くなってしまいました。いま残されている『明暗』は、もう半分ぐらいすすんでいたのかなとおもえるところもありますが、存外入口のところまでかなとおもえるところもあるんです。『明暗』は、もともと物語の多様な筋があったり、起伏があったりという作品ではありません。たいした物語は起こりそうもないわけです。そうみなすと、もう相当程度まで書きすすんだことになっているのかとおもえます。また逆に、まだ筋の進展がないじゃないかとかんがえると、あんがい序の口のところで、作者が病気になって、死んでしまったともかんがえられるのです。ただいえることは、『明暗』には、この『門』の宗介が感じるような、動揺の過程、それを鎮めようと苦しむ過程、ついに偶然のことから解決してしまうといった不安をかきたてる要素は、なにもなくなっていることです。主人公がいて不安を感ずるとか、不安にかきたてられるとか、作品自体が読む人に不安をあたえるとか、そんなところは『明暗』のなかにはあらわれませんし、またこれから『明暗』がおわりまで書きつがれたとしても、たぶんあらわれないとだけいえるのではないでしょうか。ですから、そういう意味では、『明暗』が『門』に較べたらはるかに、晩年の漱石の〈坐〉の境地を物語っているとかんがえられます。
漱石の作品は、いってみればたいへん深刻な作品で、いまの言葉でいえばとても〈根暗〉です。人間の心にある不安とか恐怖とか、あるいは背徳とか罪の意識とか、そんなものをぎりぎり追いつめているのが漱石の作品のおおきな特徴なんです。
『明暗』になって、おおきな主役を設定して、その人物の不安とか罪の意識とかを追求していく形はなくなるのです。すべての登場人物は、どんな人間も、あるひとつの距離からみると、同一なんじゃないか。逆にいえば、全部の人間が全部同じような距離に、おなじようにみえるそういう場所はどこかにあるんじゃないか、こういう認識を垣間見せるところが『明暗』にはあります。
『明暗』の主人公は津田というんですが、これは平凡な生活の何の苦労もないサラリーマンの主人公です。そしてなんら特徴がないんです。この主人公は胃が悪いといわれて、胃を手術しようかというところからはじまるわけです。その手術の金を誰からか借りなければということで、親父や妹にあたるんだけれど、お金は借りられそうもない。そんなところから作品はすすんでゆきます。それから津田にはお延という若い奥さんがいます。その奥さんは芝居の約束をしていて、その芝居の約束の日が、ちょうど津田の手術する日にあたってしまう。そうすると津田のほうはどうせたいした手術じゃないんだから、おまえまえからの約束の芝居に行ってもいいよといいます。すると、奥さんのほうはさすがに、夫の手術の日に芝居に行っちゃうということができなくて、病院についていくのですが、晴れ着を着て病院にくるのです。そして手術が始まりそうになるのに、そわそわしていかにも芝居に行きたそうにしたりする平凡な女性です。手術がおわって津田が行ってもいいというと、奥さんはもう手術がおわってでてきて安心だから、じゃ行ってくるわといい残して芝居にでかけてしまいます。つまりなんの心ばえのない平凡な女に描かれています。
そうすると、その夫婦は平凡などこにでもいる夫婦で、特別仲のいいわけでもなく、そうかといって破局がくるほど仲が悪いわけでもありません。そのばあい、夫が手術をやっとおわって寝ているというのに、芝居へ行っちゃう奥さんをべつに批判的に描いているわけでもありません。また津田という主人公を美化して描いているわけでもありません。いってみれば、津田という主人公もふつうの男、それから、夫の手術の日に、手術がおわったら約束の芝居に行っちゃう奥さんもべつにとくに悪い細君でもないし、とくにいい細君でもない。そういう津田と奥方を両方とも同一の距離で眺めている。作者の眼にみえない眼からかんがえますと、その眼にみえない眼からみれば、津田もそれからその奥方もみんな同一にみえる。どちらがいい人間だとかどちらが悪い人間だとか、そういうふうにはすこしも描かれてない。両方とも同一にみえるという場所に、ひとつの〈眼〉があって、その〈眼〉から眺めているとおもえるのです。
病院に津田の妹が見舞いにくるのですが、この妹は津田がお金を貸してくれというと、そんなにかんたんに貸そうとしないのです。しかし、兄貴が頭を下げるんなら貸してあげてもいいとかんがえています。津田のほうは頭を下げるくらいならおまえなんかから金は借りないと妹にいいます。そこで兄妹のいい争いが起こるのです。そこでも津田と妹のどちらが悪いとか、どちらがいい人間だとか描かれていません。そして両方ともごく平凡で、両方ともいつ、どこにでもいるふつうの兄妹のように描かれています。そのふつうの人である兄と妹の両方を、同じところから見ているひとつの〈眼〉があり、そこからいい争う兄妹は描かれています。
それからまた、津田の友人で小林という社会主義者の男がでてきます。その男はよく津田をおまえなんか親の世話で学校へ行って、のうのうと結婚して、のうのうと勤めて、それで足りない分は親からいまでも金を送ってもらってのうのうと暮らしている。世の中そういうやつばっかりいない。といったたぐいのことをいっては、津田から金をせびっていきます。津田の学校時代の友達なのです。そうすると漱石は、そのばあいにも、金をせびっていく社会主義者の小林という男を美化して描いているわけでもないし、また、とくにこれはつまらない男をだっていうふうに描いているわけではありません。また津田のほうを小林に較べていい男だっていうふうに描いているわけでもないし、とくにだらしない暮らしをしている男だっていうふうに描いているのでもありません。小林と津田を較べると、そこでもふたりを同じ距離から、ごくふつうの人として描いているひとつの〈眼〉を想定することができます。
『明暗』という作品には、対象となるふたりの人物みたいなものが、いつも想定できます。そのふたりずつの人物に、いつでも双方をおなじひとつの距離からみている眼にみえない眼がひとつのあります。そこから登場人物は視られ、描かれているといえます。そうすると、それぞれの一対の登場人物をおなじ距離から眺めている眼にみえない眼の場所がいくつもあるはずですが、そのいくつもある場所を、またこんどは等距離からみているもうひとつのおおきな眼があるとかんがえられます。そのおおきな眼からみると、全部の登場人物は全部同一にみえる、そんな場所が想定できそうです。
漱石はたぶん『明暗』という作品で、たったひとつの最後に残るおおきな〈眼〉を漠然と想定していて、その〈眼〉を、漱石は、たどりついたじぶんなりの境地だとかんかえているようにおもわれるのです。禅がいう〈悟り〉とはすこしちがうんですが、しかし、全部の人間を特別なふうに扱わないし、また特別な人間ともおもわないし、またどんな人間でもごくふつうの人間としてみられるひとつのおおきな〈眼〉のようなものを漱石は「則天去私」つまり「天に則って私を去る」という言葉で意味させようとしていたかもしれないとおもいます。それはたぶん、漱石が関心をもった〈坐禅〉というもの、あるいは良寛の〈大愚〉という〈境地〉とはだいぶちがっているのですが、漱石なりのひとつの〈境地〉で、漱石がやっと最後のところ、おもい悩んだあげくたどりついた場所だという気がいたします。










 [user_image 7f/
[user_image 7f/