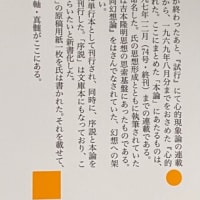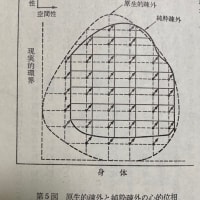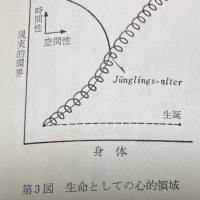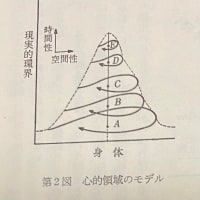言の葉107〈非知〉へ——〈信〉の構造「対話篇」
④新共同訳「聖書」を読む

〈非知〉へ——〈信〉の構造
「対話篇」一九九三年一二月二五日発行 著者吉本隆明 発行所株式会社 春秋社
より抜粋

④新共同訳「聖書」を読む
対話者 小川国男
聖書の元の形を探る より抜粋
吉本 今度出た新共同訳聖書は、原文から翻訳したものですか。
小川 ヘブライ語とギリシャ語のテキストから直接にやりました。ぼくは、部分的にですが原文と日本語を突き合わせる現場へ立ち合わせてもらったのですが、聖書の元の形がある程度わかったような気がして、これまで考えていたのとはちょっと違うんじゃないかと思いました。ことに旧約は、昔も今もユダヤ教の聖典ですけれども、それをキリスト教の宗教家は、キリスト教のほうへぐっと引きつけてしまって、キリストのことを予言している本だという観点で解釈をつけます。——それも一つの読み方ですが、たとえばヘブライ大学に長年留学なさった日本人の学者の意見を聞くと違うんですね。つまりユダヤ教のはう人たちは、われわれが日本史や国文学を習う、その態度で読むというんです。あるいは日本人より科学的かもしれません。彼らは、ここは将来現れるキリストの予言が書いてある、ここはキリストのこの場面を預言したものだという、そういう前提に拠ってはいないのですね。それを聞いて、旧約の大きさと雑多さとかがかえってわかったような気がしました。それを追々お話しいたしますけれども。
吉本 ぼくの全体の印象をいいますと、旧約のほうは、読みやすくなってたすかったなと思ったんです。日本でいえば『古事記』の現代語訳を読むと同じように読むみたいな感じで、誰でもでこれから入っていくと、結構波瀾万丈の物語が書かれていますから、なかなかいいんじゃないかという印象を受けました。
しかし新約のほうは、値打が半分ぐらいに下がったんじゃないかという感じがしないでもなかったですね。どうでしょうか。ぼくも、たとえばマタイ伝は、何回も読んでいるんですけども、昔の文語訳ので暗唱しているところ、「われ地に平和を投ぜんために来れりと思ふな」とか、ああいうさわりのところをずっと読んでみたんです。これはかなり気が抜けた(笑)。逆に言えば、こちらの主観的な思い入れの中で自分のほうに引き寄せて読んでいたところが、言ってみれば正常に戻されたということかもしれないんですけどね。これは、でも聖書の輸入史というか、移植の歴史の中ではやむをえないといいましょうか。こういう、ちょっと気の抜けた段階を通っていくのは、ある意味ではしかたがないことなんで、それはいいことなのかなあみたいに思い返しもしました。まあ、いろんなことを考えさせられましたですね。
小川 たとえば「天国はパン種のごとし」というのがありますね。古いラゲ訳では、「天国はパン種のごとし、女これを取りて三斗の粉の中に隠せば」というふうになっています。ぼくはポイントは「隠す」というところにあると思うんです。ところが今、奥さん方が台所でふくらし粉を「隠す」とは言いません。「まぜる」ですよ。「隠す」という言葉はおかしい、と。で、「まぜる」にしたようです。でもこれはちょっと賛成できないですね。
吉本 そうですね。それはちょっと……。
小川 参考までに英訳を読んでみましたら、〃bury〃って書いてあるんですね。つまり「埋める」。天国でもいいし、真理でもいいけども、キリストはそれを世の中に隠すんだということですね。そういう意味があるんだろうと思うんですよ。「まぜる」というと、なんか入れてかき回すような感じになってしまって、そういうところが少しずつマイナス点になりますから、全体として迫力がなくなるということじゃないかと思いますね。
現代語訳はわかりやすくということなんですが、あちらを立てればこちらは立たずで、問題が出てくるんですね。
たとえばヘブライ語もヨーロッパの言葉と同じで主語は省いていないんです。所有形も、「私の本」とか「私の神」とか「私のパン」というふうになります。日本語ではそれはおかしいというんではずしていくんですが、これも問題になるんです。「私の神」というのと「神」というのでは、意味が違うんですね。聖書にはご存じのようにたくさんの神があって、それをヤハウェを私の神と決めているわけですから、漠然と一つの神があったということじゃないんです。だからしっこいぐらいにだからしっこいぐらいに「私の神」「私の神」と言っているのは、やっぱり翻訳しなきゃいけないとぼくは考えるようになりました。
一人称でもそうですが、二人称代名詞は、日本語にはやたらと語彙が多いでしょう。「おまえ」とか「貴様」とか「あなた」とか「きみ」とか。その中で何を使うかという問題があって、かなり厄介なんですよ。キリストが「きみたち」と言うのはおかしいというので、「あなたたち」で妥協しました。弟子のことを「あなたたち」と言いますと、なんか女子大の先生みたいな感じになります(笑)。
ヘボンが翻訳を始めた一八六○年代というのは、部分訳はあったんですが、全訳は中国語の漢訳聖書しかなかった。それで文語訳聖書の漢文くずしの文体ができた。歯切れがいいですね。名訳で、これはすでに聖書の古典ですね。
今の二人称の問題でいえば、中国語というのは都合がいい。「汝」だけなんですよ。奴隷が王様に言うのも「汝」で、王様が奴隷に言うのも「汝」。女が使おうが男が使おうが「汝」でいいんですよ。ですから、そこのところは実にスパッといってます。
他に、よく問題になった言葉に「燔祭」という言葉があるんです。燔祭というのは、ギリシャ語にするとホロコーストだそうです。家畜を焼く祭りということで、意味もほぼ合っていた。いい単語だったんですが、学者方は厳密でしてね。中国の燔祭とユダヤ教の家畜を灰になるまで焼いてしまう祭りは違うというんです。それで「焼き尽くす献げ物」なんていう新語をつくったんですが、焼き尽くす献げ物というと定まった意味がない。説明的になり、まとまりの悪い言葉になります。元の方がよかったとも言えるんです。そういう試行錯誤がいっばいあるもんですからね、とうとう十八年もかかってしまったんです、これを一冊訳すのに。
信仰をドラマとして読む より抜粋
小川 吉本さんも「マチウ書試論」で論じておられるけど、つまり福音書がフィクションであるということね。ぼくはフィクションでいっこうにかまいませんけど、フィクションならどういうフィクションかということですね。聖書はその意味でもプロトタイプだと思うんです。フィクションとは何かという問いに根本的な答えている本だと思います。
吉本 「マチウ書試論」からどのくらいたってからでしょうか、「喩としての
マルコ伝」は、もっぱらマルコ伝の中から、いわゆる比喩を取り上げて、個々にも、全体としても、これはあることのメタファーなんだという観点で書いていたと思います。メタファーの最大の頂点はイエスが十字架にかかる時に、神よ、なぜ自分を見棄てたのかいうふうにして、これはぼくの勝手な解釈だと、弟子たちがどんどん離れていくということと、最後には厳しい状況の中で、自分が自分に背くというんでしょうか、あるいは自分が自分に背かれるいうんですか、それが、神になぜわれを見棄て給うかという言葉に凝縮されていて、十字架にかかる時のその言葉が、マルコ伝の比喩としての頂点なんだという論旨になっていたと思うんです。そこいらへんまでので見解がぼくなんかの理解の最後のところで、それ以降はちっとも理解を深めているとかいうことはないわけなんです。
小川 吉本さんね、「わが神、わが神、なんぞわれを棄て給ひしや」というところ、吉本さんのお考えをもう少し説明していただけますか。
吉本 これは無信仰な人が——無信仰というか不信仰な人間が福音書を一つの表現として見ていった場合、しかもキリスト教自体にあるいは聖書自体に対する関心が、先程言いましたようにダブルバインドが聖書の根本なんだというように感じている、そういう感じ方の延長線で行きますと、たとえばその前に、ペテロが、お前は十字架にかかろうとしているやつの弟子じゃないかと言われて、いや、そうじゃない、そうじゃないって三度否定したみたいな、そういう否定をペテロがやること。ユダはその前にやる。それでどんどん全部が離反していく。そして最後に、じゃ、イエスという主人公はマルコ伝の中でどうなっちゃうんだろうかといったら、最後は結局、「わが神、わが神、なんぞわれを見棄て給ふや」っていうことで、自分が自分の信仰から背かれるといいますか、そういう場面に最後に主人公が到達して、そしてこのドラマといいましょうか、マルコ伝の文学は終わっちゃう。そういう結末になるわけですね。だから今度は、小川さんが考えられれば、きっと復活ということがちゃんとあるんで、そのことが重要だという問題が出てくるんだと思うんですけども、僕らが考えるドラマはここが頂点なんだということになるんですね。
小川 そうすると、復活の問題は、後からつけた飾りだということですか。
吉本 物語の起承転結があるとすれば、転結の結をどうしてもつけなきゃいけないから、復活みたいなのが入ってくるんで、転までのところだったら、ここが頂点だといいましょうか、そういうことのように読むわけです。これは日本でいえば浄土教もそうで、法然の弟子でも一番の弟子だった幸西という人がいるわけです。幸西は完全に転向しちゃうんですね。今の言葉を使う使えば、最後には一念義ということになるんですよ。つまり、念仏なんか一生に一度称えればいいのよっていうことになるわけです。そういう教義を流布するわけです。法然なんか、その手の教義を、邪道だって盛んに戒めるわけですね。幸西はもっと進んで神官の娘と結婚しちゃう。それまでは、幸西というのは、法然の弟子で、著書もあるし、同時代で一番著名な人なんですけど、そうしちゃう。
親鸞は首の皮ひと筋か、髪ひと筋で思いとどまるんですね。でもほとんど一念義なんですよ。つまり一念でいいんだということです。たけれども、なお余剰があるんなら、阿弥陀仏の報恩のために念仏を唱えればいい。だから一念でいいか多念でいいかってそういう論議のしかた自体があんまりよくないんだ。一念ででいいんだけども、余韻があれば、生涯のうちに何度でも念仏を唱えるという、こういうことになるんだというところで、思いとどまるわけです。そういうのがぼくはものすごく好きなんです。なんていうんでしょうか、あとは幸西はもちろん駄目ですけども、親鸞だって、妻帯はするし、肉は食べるし、やることなすこと全部当時の僧侶の概念からはみ出しているんですが、ただの一点で踏みとどまります。そこはたとえば、福音書の中でイエスが最期の場面で、本当ならばもう、神を怨んで十字架にかかっていいところなんだけども。一歩手前で踏みとどまるみたいなところがあるでしょう。そういう、信仰のドラマといいましょうか、何かを信じるということはいったいどういうことなんだというドラマとして読みたい、そういうことなんです。
小川 なるほど、それでは「わが神、わが神、なんぞわれを棄て給ひしや」というのは、フィクションだとお思いにはなりますか。
吉本 その言葉自体は、たとえば詩篇の中のダビデの歌の中から出てきていると思うんですね。言葉は同じだと思うんです。だけども「わが神、わが神、なんぞわれを見棄て給ふや」という、落ち込みながらなお訴えているみたいな、そういう最低のところまで落ち込まされ、信じている神から悲運を集中させられながらでも、最後に訴えているみたいな、そういう自己離反のしかた、それはたぶんはじめから旧約聖書を一貫して流れているもののように思えるんです。新約書がどこでそれを集約するか、あるいは鋭くそれを取り出すかということがキリスト教の問題のように思います。
小川 おっしゃる通りだと思います。
吉本 そこのところが、ぼくなんかにとっても普遍的な問題になってきます。別に宗教の信仰だけでなくて、理念の信仰であってもいいわけです。それから男女の愛情みたいなことでも、たぶんどっかでそういうぎりぎりのところにさらされているみたいなところがあって、そこをどう通れるのか通れないのか、そこで止まっちゃうのか、あるいはそういうところは通らなくてもいい道があるんだということなのか、なんとなくひっかかっている問題のように思うんです。
小川 集約的な頂点ということは、吉本さんは、そこをお読みになって、そこだというわけで喝采なさるわけでしょう。
吉本 そうなんですね。
小川 そうすると、こだわるようですが、これはやっぱりフィクションということになりますからね。
吉本 はい。「マチウ書試論」では、これはフィクションなんだ、主人公もフィクションなんだという観点をとっているわけです。しかし、「喩えとしてのマルコ伝」というところでは、フィクションであるかどうかはあんまり問題じゃないんじないかってなっているような気がします。この思考の型というか情念の型といいましょうか、あるいは理念の型というか信仰の型といいましょうか、そのことが問題なんで、フィクションであるかどうかいうのはあんまり問題にならないんじゃないかなってところに突き進んじゃって、ぼく自身が言葉の表現の問題だってところに行っちゃっている気がします。今の新約聖書学者は、たぶん福音書を読む場合、ここはフィクションの部分、ここは実在のイエスという人物の歴史的な記述の部分というふうに、分けていくやり方をしていると思うんですが、ぼくにとってはそれはあんまり問題にならないんじゃないかなという感じなんですね。