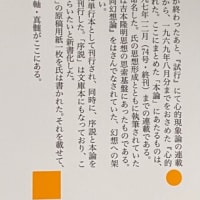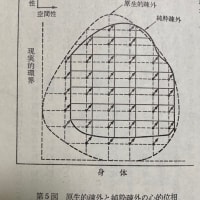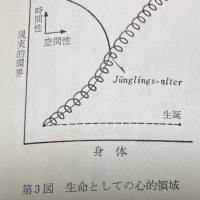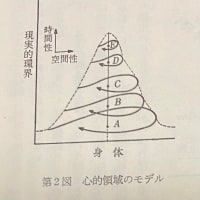言の葉綴り136 新・書物の解体学
吉本隆明著
辺見じゅんの『闇の祝祭』

新・書物の解体学 著者吉本隆明
1992年9月1日発行 株式会社メタローグより
辺見じゅん『闇の祝祭』
辺見じゅんの歌集『闇の祝祭』の特色は何だとおもうかと訊ねられたら、印象の消えないうちなら、すぐに下句の起こし方の特異さ、下句の位置の原始性、それがひとりでに短歌の声調を短詩の方に近づけていることをあげるとおもう。
かりがねの
伊吹の山をわたるとき
滅びゆくもの清しと思ふ
大津絵の
鬼にかつぎし鉦の音の
光でとよむ
桃のおぼろ世
腋くらし鳥の翔び発つあさまだき
厨に菜種油こぼるる
をみならは花のゆらぎに似てゆるる
雪ふれば雪の暗きしづまり
この種の下句の特異な歌は、半分以上を占めるとおもう。下句の起こし方、呼吸、リズムの非短歌性といったものが、わたしに『万葉』東歌の声調をすぐに連想させた。
3351 筑波嶺に雪かも降らる否をかも かなしき
子ろが布干さるかも
3425 下野安蘇の河原よ 石踏まず空ゆと来ぬよ
汝が心告(の)れ
3451 風の音の遠き我妹が着せし衣
手本のくだり紕(まよ)ひ来にけり
この印象の類似を何とか言葉にすれば、語音とリズムの響き合いからくる高揚が、下句のところで、もう一度やってくるから、一首の歌がふたつの呼吸を含んでいるともいうべきものになっている。東歌がそうなっているのは、わたしどもの解釈では短歌がまだ古歌謡のうたい方を保存しているため、複数の付け合いの呼吸がのこされているからだ、ということになる。
辺見じゅんさんの歌が『闇の祝祭』まできて、このリズムの複核性をあらわにしてきたのは、どんな理由によるのだろうか。わたしには現代短歌の声調を無意識のうちに壊して、短詩性に近づこうとしているのではないか、と思われてならない。このことを直接本人に訊ねてみたことがあった。答えは見掛けのうえでは逆で、この歌集ほど短歌を短歌として意識して作ったことはなかったということであった。これはじつに興味ぶかいことに思われた。
そこでじぶんの理解をもう少し先まで延長してみたくなった。この歌人の歌のモチーフの奥深くにあるのは広義で、そして原始的な意味での巨大家族の意識のようにおもえる。まだ部族以上には共同体をつくれなかった太古に、姪も甥も氏族の子供みな娘や息子と呼ばれ、叔(伯)父や叔(伯)母もまた父や母と呼ばれた時代があった。そのおおきな家族の親和性と暗さのようなものが、辺見じゅんの人間関係をうたうモチーフに潜在していて、人間をうたうことと家族をうたうことが同一の色濃い執着と思い入れに充たされている。重苦しくくらい情念の世界だが、同時に濃厚な親和感が充ち溢れている。この特異な感性の世界から『闇の祝祭』の複核的な初源性はやってくるのではないかと思われてくる。
ふるさとの古井に水の動かねば
祖母の小櫛のくらきくれない
滅びたるものに寄りゆく雪の秀に
野太き声の父帰り来よ
越後路は雪のまほろばはろばろと
わが形代のとほき夕映え
木には木の鳥には鳥の鬱あるや
いもうとの死に若葉しづくす
書き沈む父の背中に沼ありて
この世あの世の万燈絵かな
これもまた限りが無く深い底と、終りがない時間の無意識の向うまで続く歌物語のモチーフのようにおもえる。この歌人のなかでは過去をうたい語ることと現在をうたっていることとがおなじであり、歌の物語のなかでは大過去と過去と現在完了とが境界のない混融された時間のなかに一体になっている。また近親をうたうこととまったく別の地域の住人をうたうことが同一化されて、どんな山里も都会もおなじ感性の空間に包まれてしまう。わたしにはそれが未開の部族社会の時代の習俗を、無意識の夢の痕傷として指しているように感じられる。(角川書店刊)