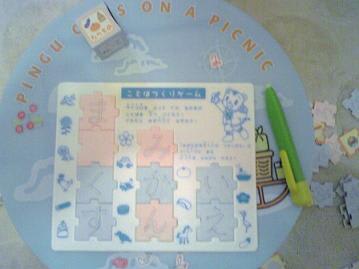今日から息子は幼稚園。
今週はまだ半日保育ですが、私の頭は切り替わったようです
早速、教育的内容のブログを書きたいと思います
今回の内容は、「知能」についてです。
私の一番好きな考え方は、「ガードナーの8種の知能」(多重知能理論)です。
 言語的知能
言語的知能
 論理数学的知能
論理数学的知能
 音楽的知能
音楽的知能
 身体運動的知能
身体運動的知能
 空間的知能
空間的知能
 対人的知能(他者理解知能)
対人的知能(他者理解知能)
 個人内知能(自己理解知能)
個人内知能(自己理解知能)
 博物学的知能(自然理解知能)
博物学的知能(自然理解知能)
上記の8つに分かれます。
詳しい内容に関しては、日能研の「ユーリカ!きっず」のページにも載っていましたのでそれを参考にして下さい。
世間で行われている知能検査のほとんどは、「 言語的」「
言語的」「 論理・数学的」「
論理・数学的」「 空間的」の3つの知能に関する問題に偏っているように感じます。
空間的」の3つの知能に関する問題に偏っているように感じます。
我が子が受けた知能検査はビネー式ですが、やはり「概念(言葉の意味)」「図形(物の形)」「記号(数・音・色)」の領域で判断されます。
学校教育に関して考えれば、8種の知能のうち ~
~ までが中心ではないでしょうか。
までが中心ではないでしょうか。
でも、実際に社会に出てから活躍している人を見るとどうでしょう??

 の知能が発達している人が意外と多いのではないでしょうか?
の知能が発達している人が意外と多いのではないでしょうか?
「早期教育」「幼児教育」と言うと、どうしても

 に偏ってしまう気がします。
に偏ってしまう気がします。
でも本当に大切なのは、偏った勉強だけをするのではなくいろんな経験をさせることなのではないでしょうか。
ガードナー氏も「多重知能学習(多種多様の機会が与えられる教育)が大切だ」とおっしゃっています。
幼児教室に通わせることや家で勉強をさせることが悪い、と言っているのではありません。
それだけではなく、自然に触れさせる、社会のルールやマナーを教える、人との接し方を教える・・・とか、そういうことも大事だと思うのです。
最近の子供たちを見ていて思うのですが、「自分」のことをわかっていない子が意外と多いです。
 の知能と言えるでしょうか…。
の知能と言えるでしょうか…。
自分はどういう人間なのか・・・もっと簡単な部分で「本当は何をしたいのか」「将来どういう方向に進みたいのか」など…。
こういうこともわかっていないんです。
「わからない」「知らない」を、そのままにしてしまう子も増えています。
調べてみようとか、考えてみようとか・・・そういうことが面倒なようです
そうならない為にも、幼児期に注意してほしいことがあります。
子供が疑問に思ったことに対して、親がスルーしないで下さい。
一緒に考えたり調べたり、きちんと向き合ってあげてほしいのです。
親がわからないことも、たくさん質問してくると思います。
そういうときは正直に「ママもわからないから、一緒に調べよう!」と言ってあげて下さい。
幼児期は、本当にたくさんのことを吸収します。
その成果が出るのは、もっともっと先です。
子供が大きくなってから後悔しても遅いのです。
今から、しっかり子供と向き合ってあげましょう
最後までお読みいただき、ありがとうございました
↓ 少しでもお役に立てましたら、応援クリックしていただけると嬉しいです
 にほんブログ村
にほんブログ村
今週はまだ半日保育ですが、私の頭は切り替わったようです

早速、教育的内容のブログを書きたいと思います

今回の内容は、「知能」についてです。
私の一番好きな考え方は、「ガードナーの8種の知能」(多重知能理論)です。
 言語的知能
言語的知能 論理数学的知能
論理数学的知能 音楽的知能
音楽的知能 身体運動的知能
身体運動的知能 空間的知能
空間的知能 対人的知能(他者理解知能)
対人的知能(他者理解知能) 個人内知能(自己理解知能)
個人内知能(自己理解知能) 博物学的知能(自然理解知能)
博物学的知能(自然理解知能)上記の8つに分かれます。
詳しい内容に関しては、日能研の「ユーリカ!きっず」のページにも載っていましたのでそれを参考にして下さい。
世間で行われている知能検査のほとんどは、「
 言語的」「
言語的」「 論理・数学的」「
論理・数学的」「 空間的」の3つの知能に関する問題に偏っているように感じます。
空間的」の3つの知能に関する問題に偏っているように感じます。我が子が受けた知能検査はビネー式ですが、やはり「概念(言葉の意味)」「図形(物の形)」「記号(数・音・色)」の領域で判断されます。
学校教育に関して考えれば、8種の知能のうち
 ~
~ までが中心ではないでしょうか。
までが中心ではないでしょうか。でも、実際に社会に出てから活躍している人を見るとどうでしょう??

 の知能が発達している人が意外と多いのではないでしょうか?
の知能が発達している人が意外と多いのではないでしょうか?「早期教育」「幼児教育」と言うと、どうしても


 に偏ってしまう気がします。
に偏ってしまう気がします。でも本当に大切なのは、偏った勉強だけをするのではなくいろんな経験をさせることなのではないでしょうか。
ガードナー氏も「多重知能学習(多種多様の機会が与えられる教育)が大切だ」とおっしゃっています。
幼児教室に通わせることや家で勉強をさせることが悪い、と言っているのではありません。
それだけではなく、自然に触れさせる、社会のルールやマナーを教える、人との接し方を教える・・・とか、そういうことも大事だと思うのです。
最近の子供たちを見ていて思うのですが、「自分」のことをわかっていない子が意外と多いです。
 の知能と言えるでしょうか…。
の知能と言えるでしょうか…。自分はどういう人間なのか・・・もっと簡単な部分で「本当は何をしたいのか」「将来どういう方向に進みたいのか」など…。
こういうこともわかっていないんです。
「わからない」「知らない」を、そのままにしてしまう子も増えています。
調べてみようとか、考えてみようとか・・・そういうことが面倒なようです

そうならない為にも、幼児期に注意してほしいことがあります。
子供が疑問に思ったことに対して、親がスルーしないで下さい。
一緒に考えたり調べたり、きちんと向き合ってあげてほしいのです。
親がわからないことも、たくさん質問してくると思います。
そういうときは正直に「ママもわからないから、一緒に調べよう!」と言ってあげて下さい。
幼児期は、本当にたくさんのことを吸収します。
その成果が出るのは、もっともっと先です。
子供が大きくなってから後悔しても遅いのです。
今から、しっかり子供と向き合ってあげましょう

最後までお読みいただき、ありがとうございました

↓ 少しでもお役に立てましたら、応援クリックしていただけると嬉しいです