前回の続きになりますが、2歳からの教育について書きたいと思います。
2歳と言えば・・・「魔の2歳児」ですよね
私はずっとmixiで日記を書いてきているので、我が子が2歳の頃はどんな感じだったか読み返してみました。
書いてあるのは、「酷い反抗期」とか「毎日イライラ」なんて内容がいっぱい
親にとっては本当に大変な時期でしたが、子供にとってはすごい成長期なんですよね。
いろんなことを吸収していたんだと思います。
それでは、2歳からの具体的な遊びを紹介します。
この時期は「覚える」ということがとても楽しく感じるようです。
先ずは、子供の好きなものを覚えることから始めましょう。
我が子は「鉄道」が大好きでした。
鉄道図鑑やDVDなどを見て、新幹線や特急などの名前をほとんど覚えてしまいました。
それを利用した遊びが、メモリーゲーム(トランプの神経衰弱)です。
我が家では、鉄道のカードを作って遊んでいました。

数字・50音・アルファベットなどを覚えるにも良い時期です。
小さい子供というのは「写真記憶」のような感じで物を覚えるらしいので、目で見て暗記する方法が効果が高いようです。
子供が好きなものがあれば、それを使うとラクだと思いますよ。
我が子の場合はとにかく「鉄道」だったので、50音も鉄道カードを作りました。

これで50音は完璧
次に数字についてですが、教えるときに注意しなければならないことがあります。
それは、ただ数字を言うのではなく、きちんと物を数えさせること。
「数は50まで言えるんだけど、物を数えられないんだよね…」と、悩んでいるママさんが結構いました。
そうならない為に、先ずは物を数えさせることから始めましょう。
幼児期は、大きな数字なんて言えなくていいんです。
「1」から「10」までの数をきちんと把握できていれば大丈夫です
10までの物の数をきちんと数えられるようになったら、簡単なたし算に挑戦してみましょう。
↓ 私は、こんなものを使っていました。

数字カードを渡し、その数だけボールを入れます。
次にもう1枚数字カードを渡し、その数のボールを追加します。
ボールを全て出し、何個あるか数えます。
使った数字カードも一緒に置き、その横にボールを置かせて、合わせて何個という計算を教えます。
こうすれば、たし算の概念が理解できますよね。
この方法は、かけ算の概念を教えるときにも役立ちます。
かけ算の場合は、例えば「2個セットが3個ある」なら、2個入っている入れ物を3個用意して説明します。
そして、全部で6個になると教えてみてください。
九九を教える前に、必ずかけ算の概念を教えましょうね。
あとは、図形の力もつけていくと良い時期です。
見本通りに積み木を組み立てるというような、目で見てそれを形にする練習をしてみましょう。
↓ あるプレイランドに置いてあった玩具です。

これはちょっと高度なので、2歳後半ぐらいからやってみて下さいね。
他には、「すごろく」などもいいですよ。
サイコロを使うので数字にも強くなりますし、何個進むとかも理解できます。
それに、勝ち負けも経験できますしね
しつけ面でも、2歳というのは大切な時期です。
社会のルールを教え始める必要があると思います。
例えば、我が家では電車でのおでかけを頻繁にしていたので、電車の中でのルールをしっかり教えました。
当たり前ですが、騒がない、隣の人に迷惑をかけない(体をぶつけない)、イスに座るときは靴を脱ぐ、などなど。
あと、公園などの遊具で遊ぶときなどになりますが、順番を守ること。
危険なことは何かを教え、そういうことはしないということ。
言っても言ってもなかなかできないこともありますが、根気よく教えましょう。
ここで教えたことは、その場ではなかなかできなくても、後々効果が出てきますよ
次回は、3歳からの教育について書く予定です。
最後まで読んでくださってありがとうございました
↓ ランキングに参加しています。下のバナーをクリックしていただけると嬉しいです
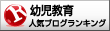
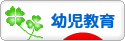 にほんブログ村
にほんブログ村
2歳と言えば・・・「魔の2歳児」ですよね

私はずっとmixiで日記を書いてきているので、我が子が2歳の頃はどんな感じだったか読み返してみました。
書いてあるのは、「酷い反抗期」とか「毎日イライラ」なんて内容がいっぱい

親にとっては本当に大変な時期でしたが、子供にとってはすごい成長期なんですよね。
いろんなことを吸収していたんだと思います。
それでは、2歳からの具体的な遊びを紹介します。
この時期は「覚える」ということがとても楽しく感じるようです。
先ずは、子供の好きなものを覚えることから始めましょう。
我が子は「鉄道」が大好きでした。
鉄道図鑑やDVDなどを見て、新幹線や特急などの名前をほとんど覚えてしまいました。
それを利用した遊びが、メモリーゲーム(トランプの神経衰弱)です。
我が家では、鉄道のカードを作って遊んでいました。

数字・50音・アルファベットなどを覚えるにも良い時期です。
小さい子供というのは「写真記憶」のような感じで物を覚えるらしいので、目で見て暗記する方法が効果が高いようです。
子供が好きなものがあれば、それを使うとラクだと思いますよ。
我が子の場合はとにかく「鉄道」だったので、50音も鉄道カードを作りました。

これで50音は完璧

次に数字についてですが、教えるときに注意しなければならないことがあります。
それは、ただ数字を言うのではなく、きちんと物を数えさせること。
「数は50まで言えるんだけど、物を数えられないんだよね…」と、悩んでいるママさんが結構いました。
そうならない為に、先ずは物を数えさせることから始めましょう。
幼児期は、大きな数字なんて言えなくていいんです。
「1」から「10」までの数をきちんと把握できていれば大丈夫です

10までの物の数をきちんと数えられるようになったら、簡単なたし算に挑戦してみましょう。
↓ 私は、こんなものを使っていました。

数字カードを渡し、その数だけボールを入れます。
次にもう1枚数字カードを渡し、その数のボールを追加します。
ボールを全て出し、何個あるか数えます。
使った数字カードも一緒に置き、その横にボールを置かせて、合わせて何個という計算を教えます。
こうすれば、たし算の概念が理解できますよね。
この方法は、かけ算の概念を教えるときにも役立ちます。
かけ算の場合は、例えば「2個セットが3個ある」なら、2個入っている入れ物を3個用意して説明します。
そして、全部で6個になると教えてみてください。
九九を教える前に、必ずかけ算の概念を教えましょうね。
あとは、図形の力もつけていくと良い時期です。
見本通りに積み木を組み立てるというような、目で見てそれを形にする練習をしてみましょう。
↓ あるプレイランドに置いてあった玩具です。

これはちょっと高度なので、2歳後半ぐらいからやってみて下さいね。
他には、「すごろく」などもいいですよ。
サイコロを使うので数字にも強くなりますし、何個進むとかも理解できます。
それに、勝ち負けも経験できますしね

しつけ面でも、2歳というのは大切な時期です。
社会のルールを教え始める必要があると思います。
例えば、我が家では電車でのおでかけを頻繁にしていたので、電車の中でのルールをしっかり教えました。
当たり前ですが、騒がない、隣の人に迷惑をかけない(体をぶつけない)、イスに座るときは靴を脱ぐ、などなど。
あと、公園などの遊具で遊ぶときなどになりますが、順番を守ること。
危険なことは何かを教え、そういうことはしないということ。
言っても言ってもなかなかできないこともありますが、根気よく教えましょう。
ここで教えたことは、その場ではなかなかできなくても、後々効果が出てきますよ

次回は、3歳からの教育について書く予定です。
最後まで読んでくださってありがとうございました

↓ ランキングに参加しています。下のバナーをクリックしていただけると嬉しいです

























