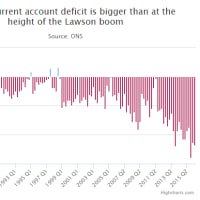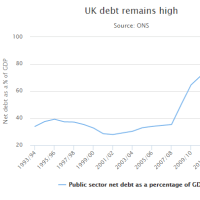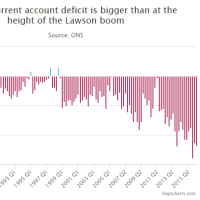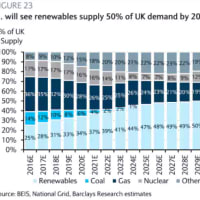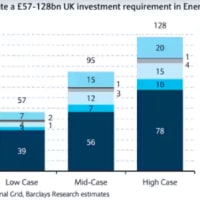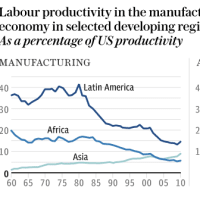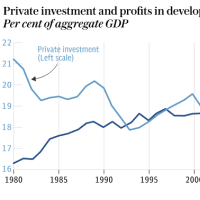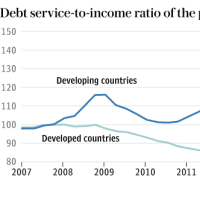The best painkiller of all
(一番の鎮痛剤)
By Max Pemberton
Telegraph: 7:30AM GMT 29 Oct 2012
うーんうーん、思ったよりも薄っぺらくてガーンでありますが、それでも勿体無いのであぷします。


(一番の鎮痛剤)
By Max Pemberton
Telegraph: 7:30AM GMT 29 Oct 2012
A forgotten piece of research shows that there should be a lot more to pain relief than dishing out pills
忘れ去られた研究論文によれば、薬よりももっと沢山の鎮痛法があるはずなのだそうです。
Dr Henry Beecher was an anaesthetist who treated soldiers injured during the Second World War. When he arrived at the front line, he found horrific injuries including limbs blown off and shrapnel embedded in bodies. He quickly set about arranging for patients to be triaged on the severity of their wounds, so that those with the worst injuries could be given morphine and other painkilling drugs first.
ヘンリー・ビーチャー医師は第二次世界大戦の負傷兵を治療した麻酔医でした。
前線に到着した時、ビーチャー医師は手や足が吹き飛ばされたり、体中に様々な破片が刺さっているといった、恐ろしい傷を目の当たりにしました。
最も酷い外傷の患者が先ずモルヒネなどの鎮痛剤を投与されるように、彼は迅速にトリアージ体制を布きました。
But over the weeks and months, he began to notice something very strange. More than half of the soldiers reported little or no pain, despite their terrible wounds. They did not request analgesia. Pain management simply wasn’t the priority Dr Beecher thought it would be, and he couldn’t understand why.
しかし時間が経つにつれ、ビーチャー医師は非常に奇妙なことに気付き始めました。
負傷兵の半数以上が重傷にも拘らず痛みがない、または殆どないと言っていました。
負傷兵は鎮痛剤を求めませんでした。
医師が考えていたのとは異なり、疼痛管理は全く優先事項ではなかったのです。
彼にはその理由が理解出来ませんでした。
These men were not in shock – they were still able to feel pain: in fact, Beecher noted that they complained about the uncomfortable insertion of intravenous lines in their arms just as much as other, less severely injured, patients.
これらの負傷兵はショック状態にあったわけではありませんし、まだ痛覚はありました。
実際、ビーチャー医師は彼らも他の負傷兵(より軽度の傷を負った)と同じく、腕の点滴の痛みについて不満を言っていたと記しています。
What puzzled Beecher in particular was that the patients he had treated at home in peace time would routinely request analgesia for similar or far less devastating injuries and complained bitterly if they didn’t receive it.
ビーチャー医師が特に不思議だったのは、平時に国内で治療した患者は、同様、または遥かに軽度の外傷にも必ず鎮痛剤を求めており、もらえないと酷く文句を言っていたことです。
This didn’t make any sense, but what he eventually realised was that he wasn’t taking into account the power of the mind in such situations. He came to understand that, for the soldiers, a severe injury was actually a good thing – it meant they would be discharged from the army and could return home. For civilians, however, it was a bad thing; a disruption to their life and routine and possible financial hardship.
これは全く理解しかねることでしたが、そのような状況における精神の力を考慮していなかったことにビーチャー医師はやがて気付きました。
兵士達にとって、重傷を負ったことは実は良いことだった、つまりこれで彼らは除隊となり家に帰ることが出来るということなのだ、ということを医師は理解したのです。
しかし一般市民にとって、怪我をすることは悪いことです。
暮らしや習慣を乱すものであり、生活を苦しくすることすらあることなのです。
Beecher saw that it is not necessarily the magnitude of the injury that was important in how a person experiences pain, but the circumstances in which it occurred. He wrote his findings up in a research paper and it was published shortly after he returned home. For a brief period, it caused a stir. Other doctors came forward to say that they had noticed similar things. It helped to spark theories about how pain is perceived and moderated by the mind.
ビーチャー医師は、痛みの経験の仕方において重要なのは、必ずしも外傷の重症度ではなく、外傷を負った状況こそが重要なのだと理解しました。
彼は発見事項を論文して、帰国直後に発表しました。
短期間ですが、彼の論文は話題になりました。
他の医師達も同じようなことに気付いていた、と申し出ました。
精神による痛みの感じ方や和らげ方に関する理論が生まれる助けになりました。
However, these theories have fallen from fashion. Indeed, the only reason I know about Beecher’s hypothesis is because a wily old anaesthetist told me it when I was at medical school, while lamenting how, because of advances in the range and efficacy of drugs, this aspect of pain management had been forgotten. It is now nothing more than a historical footnote in textbooks.
しかし、これらの理論は廃れてしまいました。
そう、私がビーチャー医師の仮説について知っている唯一の理由は、私の医学校時代に或るしたたかな麻酔医が、薬品の種類や効能の進歩によりこのような疼痛管理の側面が忘れ去られてしまったことを嘆きながら、これについて話してくれたからです。
今では教科書の脚注に過ぎません。
But research published last week adds further weight to Beecher’s theories about the importance of the mind in the perception of pain and, I hope, will reignite an interest from researchers and clinicians. The study by neuroscientists at Ohio State University found in a laboratory trial that mice that had undergone neurosurgery and then had other mice around as companions, recovered more quickly than mice left to recover alone.
とはいえ、先週発表された研究結果は、疼痛の知覚における精神の重要性に関するビーチャー医師の理論に更なる重みを加えました。
私はこれが研究者や臨床医の関心を再燃させることを願っています。
オハイオ州立大学の神経科学者等がマウスを使ってラボで行った研究によって、神経外科処置を受けたマウスは、一匹だけにされた場合よりも、他のマウスと一緒にされた場合の方が速く快復することが判明しました。
The mice with a '’companion’’ suffered less nerve-related pain and inflammation. What’s interesting is that this study clearly demonstrates a direct physiological effect – a reduction in the period the mice experienced inflammation – resulting from simply a change in social circumstances (in this case, having a companion.) The researchers have suggested that this could have important implications for how we manage pain, particularly neuropathic pain, which is associated with nerve injury and affects about 6 per cent of us.
「仲間」と一緒のマウスの方が神経系の痛みや炎症は少なく済みました。
興味深いのは、この研究が、マウスが炎症を経験する期間が短縮する、という直接的な生理的作用が起こるのをはっきりと立証したことです。
これは神経損傷に関連する、我々のうちの約6%が見舞われている疼痛の管理方法(特に神経系の痛み)に重要な意味あいを持っているかもしれない、と研究者等は言います。
In recent years, we doctors have been far too happy simply to dish out pills without thinking more about the wider issues at play in the experience of pain. It is far easier to prescribe painkillers, and see the satisfied patient leave the surgery clutching the prescription, than explore what might be happening to them socially and emotionally, and how this influences their experience of pain or discomfort.
この数年間、私達医者は、痛みの経験で働いているより広範な問題についてこれ以上考えることなく、ただ薬を処方することに満足し過ぎていました。
鎮痛剤を処方して、満足した患者が処方箋を握りしめて診察室を出て行くのを眺める方が、社会的に、そして感情的に彼らに起こっているかもしれないことを熟考し、これが痛みなどの経験にどのように影響しているのかを考えるよりも、遥かに楽なのです。
I often think that this is why complementary medicine is so popular with patients with chronic pain, especially those for whom conventional medicine has failed to manage their symptoms. It’s not just simply the fact that people believe it’s going to work and so it does – the placebo effect – it is also that the practitioner will sit down to talk to the patient in depth about their life. This interaction, I am convinced, helps as much as anything else.
よく思うのですが、補完医学が慢性痛に悩む患者、特に通常の治療では症状を管理出来ない患者にあれほど人気がある理由はこれなのでしょう。
上手く行くと信じてそれが本当になる(プラシーボ効果)ということだけでなく、施術者が患者の暮らしについてじっくりと話を聞くことなのです。
この交流こそが他の何物とも同じくらい助けになっているのだ、と私は確信しています。
The problem with painkillers is that they are not always effective in the long term and have a multitude of side-effects, especially in higher doses. But by providing emotional support, pain might be better managed than by simply upping the painkillers. Beecher recognised long ago that what is going on around the patient is as important to them as what’s going on inside.
鎮痛剤の問題は長期間に亘って常に効果があるわけではない、しかも様々な副作用があるということ(特に量が多い場合)です。
しかし感情的なサポートを提供することは、ただ鎮痛剤を口に放り込むだけよりも、痛みをより良く管理するかもしれません。
ビーチャー医師は随分前に、患者の周囲で起こっていることは、患者の内部で起こっていることと同じくらい重要である、ということに気付いたのです。
うーんうーん、思ったよりも薄っぺらくてガーンでありますが、それでも勿体無いのであぷします。