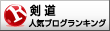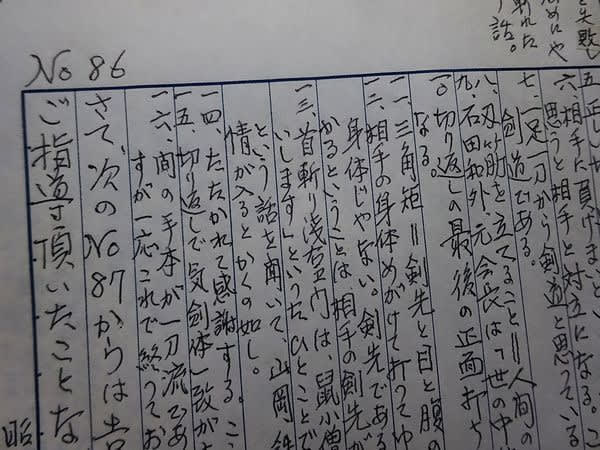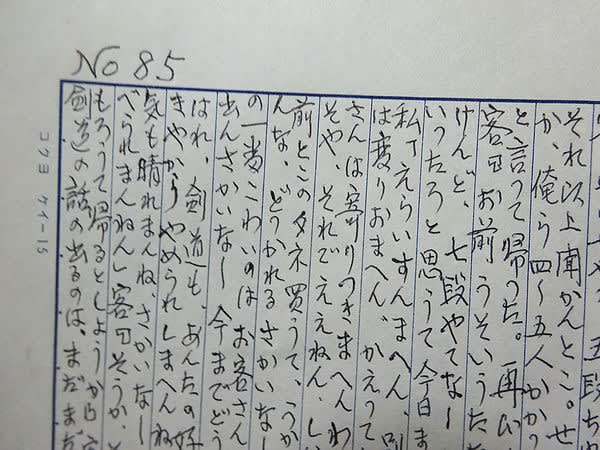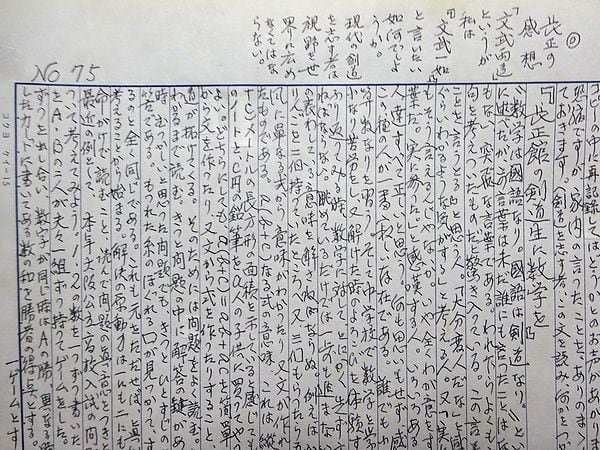整える姿勢に似ている。但し両足はゴルフの場合、左右に開くところが違うが)、少し切先を手前に引き、地から離し、丁度日本剣道形の四本目の仕太刀の巻き返し面を打つ時の手首をくるりと廻し(右手首下、左手首上で自分からは左上頭上に廻しあげ振りかぶる=この際、切先に重心をおき、丁度分胴をふり回し、その先に張力が集中するように)打つように反動をつけつつ、両足のひざを曲げて腰も下げ、振りかぶった両手の手首をやわらかくして、眼の前から胸まで丸く下げ、この反動で切先が正面打ちのように前の方へゆく時、手元をぐっと前に押し出すと同時に両手のひざを伸ばし、腰も伸ばし、スット一歩右足を前にスリ足で踏み出し(左足も右足に従い=いわゆる送り足で)下図の曲線を手首をやわらげて両握りの手で画き最後に足腰でふんばって重い木刀をとめるのです。

実際にやってお見せしますと“なるほど”とすぐ判るのですが、文章で説明するとなると大変むつかしく私の解説も廻りくどくてお判りにくいと思いますが、要は竹刀や普通の木刀で正面打ちの素振りをやるのとは目的が違うという事をご理解願いたいのです。
○重い木刀は何のための木刀か、それは足腰を鍛えるための木刀であるという事が判っていただければ幸いです。
○さて次に今度はぐっと突くように、とめた木刀を反対に自分の左の方へ木刀の先を廻し、くるっと反動を利用し、ふりかぶって、前回同様左図のように振り降ろし、ぐっと手元、足腰ともに伸ばし木刀を前に突き出してとめます。今度は又右の方へ廻してやる、また左の方へ廻して行い、続けて足腰を鍛えるのです。やって頂ければ、これほど足腰に力が入るものはないくらい強力に足腰を鍛える事が出来ます。
「ホ」のあたりで両手をぐっと伸ばします。木刀がほとんど水平近くに下りる瞬間、ぐっと前方に突くようにして足腰を伸ばし、ぐっと木刀を前に出し手の内を締めて止める。

○以上の他、もう一つ、振りかぶらずに、この木刀をつかって足腰を鍛える方法があります。それは先ず始めの木刀を持った姿勢は前項で申し上げたようにゴルフの構え(足だけ違う=前項通り)から始めるのです。まず重い木刀の先に重心がかかるように両手首をやわらかくし、反動をつけ、切先を自分の顔あたりまで上げると同時に両ひざを曲げ腰を落としざま手元を下げ、上図の「ホ」の所のように、ぐっと手元もひざも腰も伸ばして前を突きとめる方法です。即ちこれは振りかぶらず上図のように切先を反動で動かし、突き止めて足腰をぐっと鍛えるのです。以上、長々と書きましたがお判りにくい方はまた今度お会いした時やって見せたいと思っています。この木刀を頂いた時、約30分やらされ、ぐたぐたになったなつかしい想い出があります。四国一周される時、私を連れて下さった関係上、この木刀を下さったので、末長く大切に道場に置いてあります。
【粕井注記】
現在、この木刀は粕井誠が井上館長から預かり、一部補修の上、奈良の自宅に大切に保管している。

(上は小野派一刀流の木刀)


(呈 長井先生 七十六才 誠宏作)

(全国武者修行記念・下に一部、欠け剥がれがあったので、とんぼ堂で補修した)


(重さ 2,312g)

実際にやってお見せしますと“なるほど”とすぐ判るのですが、文章で説明するとなると大変むつかしく私の解説も廻りくどくてお判りにくいと思いますが、要は竹刀や普通の木刀で正面打ちの素振りをやるのとは目的が違うという事をご理解願いたいのです。
○重い木刀は何のための木刀か、それは足腰を鍛えるための木刀であるという事が判っていただければ幸いです。
○さて次に今度はぐっと突くように、とめた木刀を反対に自分の左の方へ木刀の先を廻し、くるっと反動を利用し、ふりかぶって、前回同様左図のように振り降ろし、ぐっと手元、足腰ともに伸ばし木刀を前に突き出してとめます。今度は又右の方へ廻してやる、また左の方へ廻して行い、続けて足腰を鍛えるのです。やって頂ければ、これほど足腰に力が入るものはないくらい強力に足腰を鍛える事が出来ます。
「ホ」のあたりで両手をぐっと伸ばします。木刀がほとんど水平近くに下りる瞬間、ぐっと前方に突くようにして足腰を伸ばし、ぐっと木刀を前に出し手の内を締めて止める。

○以上の他、もう一つ、振りかぶらずに、この木刀をつかって足腰を鍛える方法があります。それは先ず始めの木刀を持った姿勢は前項で申し上げたようにゴルフの構え(足だけ違う=前項通り)から始めるのです。まず重い木刀の先に重心がかかるように両手首をやわらかくし、反動をつけ、切先を自分の顔あたりまで上げると同時に両ひざを曲げ腰を落としざま手元を下げ、上図の「ホ」の所のように、ぐっと手元もひざも腰も伸ばして前を突きとめる方法です。即ちこれは振りかぶらず上図のように切先を反動で動かし、突き止めて足腰をぐっと鍛えるのです。以上、長々と書きましたがお判りにくい方はまた今度お会いした時やって見せたいと思っています。この木刀を頂いた時、約30分やらされ、ぐたぐたになったなつかしい想い出があります。四国一周される時、私を連れて下さった関係上、この木刀を下さったので、末長く大切に道場に置いてあります。
【粕井注記】
現在、この木刀は粕井誠が井上館長から預かり、一部補修の上、奈良の自宅に大切に保管している。

(上は小野派一刀流の木刀)


(呈 長井先生 七十六才 誠宏作)

(全国武者修行記念・下に一部、欠け剥がれがあったので、とんぼ堂で補修した)


(重さ 2,312g)