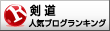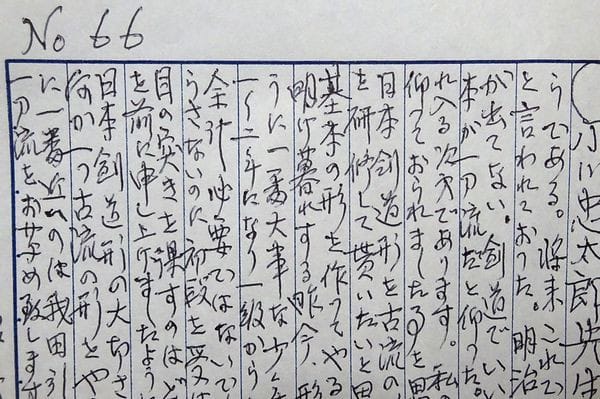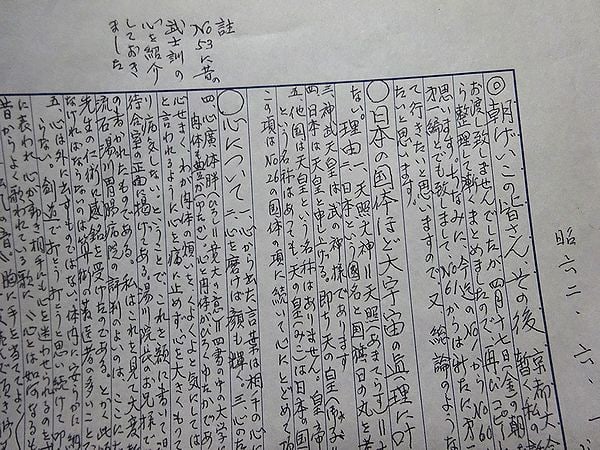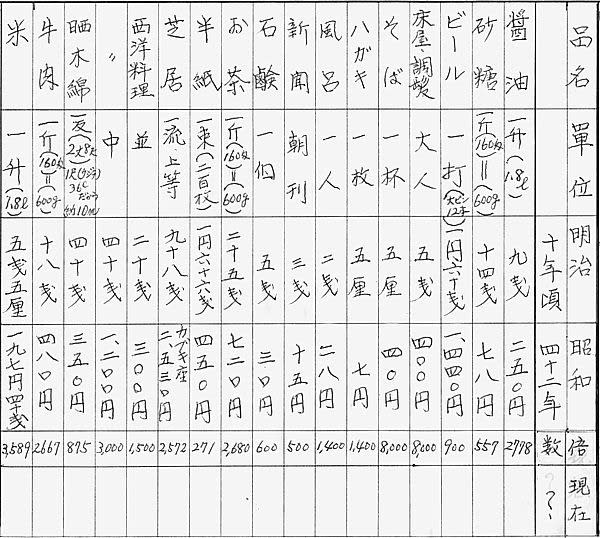ここでいう日本的とは、例えば出来るだけ私情をいれず、その催しの概説をのべ、
公演の意義にふれ、さらには公演にいたるまでの関係各位の労をたたえる、
といった“ごあいさつ”をさす。日本人のあいだでなら、それで十分足りる。
私ども日本人は、日常そういうことに忍耐するように馴らされている。
更に言えば、言語というものは、魅力のないものだとあきらめてもいるのである。
この場合、友人が心を暗くしたのは、そのスピーチを
地元のアメリカ人と共に聴かされたということだった。
たとえが悪いが、立小便をしている父親の姿を、年頃の娘が、
たまたま街角で友達と一緒に見てしまった心境に似ている。
言語は、ひとりごとである場合以外は、他者のものでもある。
聴かされる側にとって、自分の時間と体力と、それに相手の言語が喚起(かんき)する
想像力という三つのエネルギーを話し手に提供しているのである。
魅力のない言語は拷問にひとしい。
然も人間は言語こそ、この世の魅力の最高のものだ、と、誰れもが意識の底に思っている。
乳幼児は言語こそ発せられないが、たえず母親の言葉によって
聴覚を通し大脳に快く刺激をうけつづけている。
人間が最初に出会う“芸術”は絵画でもなく音楽でもなく言語なのである。
やがて言語の意味を解するようになると、母親が話してくれるお伽噺に
宇宙のかがやきと同質のものを感じてしまう。(中略)
話し手の正直さこそが言語における魅力をつくるだすということである。
それが唯一の条件でないにせよ、正直さの欠けた言語はただの音響にすぎない。
幕末以来、日本の外交態度について、欧米人から、この民族は不正直だといわれつづけてきた。
私は日本人は不正直だとは決して思わないが、然し正直であろうとすることについての
練度が不足していることはたしかである。
ナマな正直はしばしば下品で悪徳でさえある。
ユーモアを生み、相手との間を水平にし、安堵をあたえ、言語を魅力的にする。
もしニューヨークでの歌舞伎の開幕前のスピーチで、えらい人が、
じつをいうと私は日本人のくせに歌舞伎には関心がうすく、身巧者ではないのです。」
と正直に言ったとしたら、もっとすばらしかったろう。
たとえば以下のように。
「・・・・・私が半生無関心でいつづけたあいだに、歌舞伎は世界に出てしまったのです。
ぜひきょうは皆さんのまねをして、私も後ろの席で見ます。
芝居が終わったあと、どこがおもしろかったのか、こっそり耳打ちしていただけないでしょうか」
先日、英国のチャールズ皇太子のさまざまなスピーチが日本じゅうを魅力した。
言ってみれば練度の高い正直さというべきものだろうか。
言語化された人格がひとびとの心をとらえたばかりか、
その背後の英国文明の厚味まで感じさせてしまったのである。
日本人は喋り下手だといわれているが、それ以上に、正直さに欠けているのでないか。
政界のやりとりをみると、ついそう思ってしまう。終り。
以上は昭和61年6月2日サンケイの「風塵抄」から。