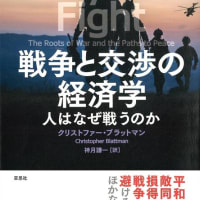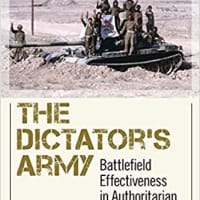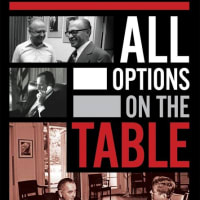現代の外交において、「宥和(appeasement)」ほど悪名高いものはないかもしれません。この汚名の起源は、いうまでもなく「ミュンヘンの教訓」にあります。イギリスのチェンバレン首相が、ナチス・ドイツのヒトラー総統の野心に対抗せず、それを許してしまったことは大失敗であり、これが後の第二次世界大戦争の発端となってしまった。したがって、宥和政策は、外交において妥協や譲歩は禁物であるという警句的な「一般命題」を含意する否定的なものなのです。ところが、近代外交において、宥和は肯定的な意味合いを持っていたというと、皆さんは驚くかもしれません。実は19世紀から20世紀の初め頃まで、世界の覇権国であった「大英帝国」は、その基本的な外交戦略において、宥和をしばしば使っていたのです。そして、大英帝国が長続きした1つの理由は、この宥和政策にあったと主張する有力な研究があります。それが軍事史の大家であるポール・ケネディ氏(イェール大学)による著書『戦略と外交(Strategy and Diplomacy: 1870-1945)』(Fontana Press, 1984)です。

ケネディ氏の著作は、日本ではベスト・セラーを記録した『大国の興亡』(草思社、1993年〔原著1987年〕)が有名ですが、上記書は、専門家以外には、ほとんど知られていないでしょう。『戦略と外交』においてケネディ氏が言いたい1つのことのは、大英帝国は宥和政策に支えられていたことです。かれはこう主張しています。
「なぜ帝国はかくも長きにわたり継続したのか…イギリスの大半のエリートの政治文化、すなわち極端を嫌い、理性的な議論に訴え、政治の合理性に信念を抱き、妥協の必要性を認めることは、なぜ大英帝国がそれほど長続きしたのかを説明する、たいへん重要な部分を形成するかもしれない…長い目で見れば、いったん経済的、戦略的潮目が変わってしまった際に、可能な限り世界大の帝国をいかに維持するかにおける根本的問題に関して、この柔軟で理性的で妥協を模索する政策は、断固として『屈服しない』ものより、好ましくなかったのだろうか」(『戦略と外交』202、216-217ページ)。
ケネディ氏によれば、「『宥和』の伝統は、もともと否定的ではなく肯定的な概念だった」のです(前掲書、215ページ)。この概念を逆転させてしまったのが、「ミュンヘン宥和」と第二次世界大戦でした。イギリス外交において1939年まで、宥和は好ましい政策として活用されていたのです。それでは、ここでいう「宥和」とは、どのようなものなのでしょうか。かれは、このように定義しています。「『宥和』は、不満を合理的な交渉と妥協を通して、認めたり満たしたりすることによる国際紛争を解決する手段であり、したがって、費用が高く血まみれになり、場合によってはたいへん危険な武力衝突に頼ることを防ぐ政策を意味する」ということです(前掲書、15-16ページ)。そして、これは「国益としての平和」として、1930年代まで、イギリスの全般的な戦略を構築していました。もちろん、こうした戦略がイギリスで無批判だったわけではありません。「左派」や「理想主義者」は、ヨーロッパ大陸における紛争に巻き込まれることを忌避していました。他方、「右派」や「リアリスト」は、宥和が、その前提に永久的な調和という考えを置くユートピア主義であり、国家の弱みを見せる政策だと批判していました(前掲書、19-21ページ)。
こうした宥和政策への批判があるにもかかわらず、19世紀後半から20世紀の前半頃まで、イギリスが宥和を基調とする戦略をとってきたのには、わけがありました。第1は国内的要因です。イギリスの政治家は、国民からの福祉への高まる要求に応えなければなりませんでした。教育、貧困、保険、年金などを手厚く提供するということです。その結果、かれらは古典的な「大砲(軍備)かバター(福祉)か」のトレードオフに対処しなければなりませんでした。第2はイギリスの国力の衰退です。この時期にイギリスは、産業や通商、植民地、海軍と軍事一般において、世界的なポジションを相対的に悪化させていたのです。イギリスは、これらの問題を宥和政策をとることで解決しようとしました。具体的には、コミットメントの縮小、敵対主義の排除、戦争につながりかねない対立の回避です。こうした政策の端的な例が、アメリカに対する宥和でした(前掲書、23-24ページ)。この対米宥和については、過去のブログ記事で触れましたので、詳しくは、そちらに譲り、ここではイギリスの海軍と部隊は、アメリカの勢力圏になる西半球から撤退したことだけ述べるにとどめます。
イギリスの宥和戦略は、ヒトラーの登場により破綻します。戦間期において、宥和政策は左派の広い支持を集めており、右派が時折疑念を示したり批判をしたりする程度でした。ところが、独裁者のヒトラーに対する宥和は、間違いであり危険な政策になったのです。ナチス・ドイツの一連の侵略行動は、安上がりで、平和的な、非介入主義の対外政策が、特定の状況下では妥当でないことを明らかにしたのです。世界情勢での地位を徐々に失いつつある小さな島国であるイギリスにとって、軍事的、経済的な負担は重すぎて背負えないため、宥和は「自然な」政策でした。ところが、この外交パターンは、ヒトラーの侵略によって粉々にされました。そして「宥和」は、誇るべき言葉から恥ずべき言葉になったのです。皮肉なことに、宥和に対する意味合いの逆転は、後のイギリスに悲劇をもたらします。1956年のスエズ危機において、アンソニー・イーデン首相は、自らの政策で宥和を断固拒否しました(前掲書、31-39ページ)。その結果は、外交的な失敗でした。
現代の国際政治において、われわれは宥和政策をどのように理解すればよいのでしょうか。リアリストは概して宥和に批判的だと思われがちですが、実は、そうでもありません。リアリズムの伝統をくむ国際関係理論は、肯定か否定かの二項対立を超えた宥和に対する1つの見方を示しています。その分析枠組みを提供したのが、ロバート・ジャーヴィス氏です。かれは、認知心理学を応用した国際関係研究の金字塔である著作『国際政治における認識と誤認(Perception and Misperception in International Politics)』(プリンストン大学大学出版局、1976年)において、紛争の2つのモデルを提供しました。1つは「スパイラル・モデル(spiral model)」です。これは国家が恐怖や不安により動機づけられて攻撃的な行動をとっている場合にあてはまります。こうした状況では、抑止や強制の威嚇は、相手の恐怖心をさらに高めてしまい、作用・反作用の悪循環を発生させる結果、対立はどんどん悪化するだけです。したがって、ここでの紛争解決や危機管理を成功させる政策は、相手の恐怖や不安を和らげることです。すなわち、便宜をはかったり宥和をしたりする政策が有効なのです。もう1つは「抑止モデル(deterrence model)」です。これは国家が現状打破の拡張や略奪的な野心によって動機づけられて侵略的な行動をとっている場合にあてはまります。こうした状況では、便宜をはかったり宥和をしたりすると、相手に拡張行動をエスカレートする機会を与えることになり、対立はかえって悪化します。したがって、ここでの紛争解決や危機管理を成功させる政策は、信頼のおける威嚇により潜在的侵略国が現状打破の目的を達成できなくする抑止になります。
リアリストのスティーヴン・ウォルト氏(ハーバード大学)は、これら2つのモデルを引き合いに出しながら、ウクライナ危機において、アメリカやヨーロッパの同盟国は、ロシアを宥和すべきだと主張していました。かれは、ロシアには「抑止モデル」は当てはまらないといいます。ウクライナに武力を提供する政策は、プーチン大統領が無慈悲な侵略者であり、旧ソ連帝国を再構築しようとしていることを前提として、ロシアに対しては対決姿勢で臨むべきだという発想を反映しています。しかし、ウォルト氏は、むしろ「スパイラル・モデル」がロシアにあてはまると見ています。少し長くなりますが、かれの2015年2月時点での分析を以下に引用します。
「ロシアはナチス・ドイツや現代の中国のような野心的台頭国ではない…衰退する大国(ロシア)がまだ保持している国際的影響力にしがみついているのであり、国境付近の控えめな影響圏を維持しようとしているのだ…プーチンとその取り巻きは、ウクライナを含む世界中で「体制転換」を促進するアメリカの努力も純粋に懸念している…無慈悲な野心ではなく消えない不安がウクライナに対するロシアの反応にある。さらに、ウクライナ危機はロシアの大胆な行動から始まっていなかった…それはアメリカと欧州連合が、ウクライナをロシア圏から外して、西側の影響圏に組み込もうとした時に始まった…モスクワはこのプロセスに手段を尽くして戦いを挑むことを何度も明らかにした。アメリカの指導者は、領土の収奪ではなくロシアの不安から明らかに生じた、これらの警告を軽く無視したのだ。プーチンの強権的反応を予測できなかったアメリカの外交担当者の失敗は、顕著な外交的無能をさらけだす行為だった…もしわれわれは『スパイラル・モデル』状況にいるのなら、ウクライナを武力で強化することは事態を悪化させるだけだろう…それは単に紛争を悪化させるだけであり、ウクライナの人々をさらに苦しめることになる」(Stephen Walt Makes the Case for Appeasing Russia, Atlantic Council, February 14, 2015)。
その後、ウォルト氏はフォーリン・ポリシー誌のブログ記事「リベラリストが招いたウクライナ危機」(2022年1月19日)において、再度、ウクライナ危機の分析と解決を以下のように述べています。
「ウクライナ情勢は悪く、ますます悪化している。ロシアは侵攻の構えを見せており、NATOが決してこれ以上東方に拡大しない完全な保証を要求している。交渉は明らかに成功していないし、アメリカとそのNATO同盟国は、ロシアが侵略を推し進めてきた場合に、同国に代償を支払わせることを考え始めている。本当の戦争が今や現実味を帯びてきており、それは全ての当事者とくにウクライナ市民にとって、広範囲にわたりさまざまな影響をもたらすだろう。
西側では、NATO拡大を擁護するとともに、プーチンだけにウクライナ危機の非難を浴びせることが当たり前だ…しかしプーチンだけにウクライナをめぐる現在進行している危機の責任があるのではないし、かれの行為や性格に道徳的な怒りをぶつけることは戦略ではない。さらなる強力な制裁を課しても、かれが西側の要求に屈することは引き出せないだろう。とにかく不快であるが、アメリカとその同盟国は、ウクライナが地政学的にどう連携するかは、ロシアにとって死活的利益すなわち武力を使ってでも守ろうとする利益であり、このことはプーチンが旧ソ連の過去のノスタルジーに愛着を抱く無慈悲な専制主義者になったからではないことを知らなくてはならない。大国は国境付近に配置された地政学的な武力に決して無関心ではいられないし、ロシアは、たとえ他の誰が責任者になろうとも、ウクライナの政治的連携には深く神経をとがらせるだろう。アメリカとヨーロッパ諸国が、このような基本的な現実を受け入れようとしないことは、世界が今日において、このような混乱に陥った大きな理由なのだ。そして、プーチンは、大きな譲歩を銃口を突き付けて引き出そうとすることにより、この問題をさらに難しくしてしまった。たとえ、かれの要求が総じて理にかなったものであったにせよ(そしていくつかはそうではなかったが)、アメリカと他のNATO諸国は脅迫によるかれの試みを拒絶する十分な理由がある…脅迫されたことを許すシグナルを送ることは、脅迫者が新しい要求を突き付けることを促してしまうのだ。
この問題をうまく切り抜けるには、双方がこの交渉を脅迫のように見えるものから、相互に見返りを得るようなものに一段と見えるよう変えなければならないだろう...打つ手に乏しいにもかかわらず、アメリカの交渉チームは、ウクライナが将来のどこかの時点でNATOに加盟するオプションを保持することを、見たところ今だに主張しているが、この結果こそモスクワがまさに拒絶したいことなのだ。もしアメリカとNATO諸国がこれを外交により解決したいのならば、現実的な譲歩をしなければならないだろうし、望むものすべてを手に入れることなどできないだろう。わたしはあなた以上にこの状況が好きではないが、それは合理的な限界を超えてNATOを愚かにも拡大したことへの払うべき代償なのだ。
ウクライナはイニシアティヴをとって、いかなる軍事同盟にも加盟しない中立国として振る舞う意思を声明すべきである。同国は、NATOの加盟国にならないこと、あるいはロシアが主導する集団安全保障条約機構に加わらないことを公式に宣言すべきである…もしキエフが自分自身でそのように動けば、アメリカとNATO同盟国がロシアの脅迫に屈したと非難されることはないだろう。
ウクライナ人にとって、ロシアがすぐ隣にいる中立国として暮らすことは、まったくもって理想的な状況ではない。しかし、自国の地政学的位置を考えれば、それはウクライナが現実的に望みうる最善の結果なのだ…1992年から2008年すなわちNATOが愚かにもウクライナを同盟に加えるだろうことを公表したこの年まで、ウクライナがうまく中立を保っていたことは思い出すに値する。この期間のいかなる時点においても、同国は侵略の深刻なリスクに直面していなかった。だが、反ロシアの感情がウクライナの大部分で高まっている今となっては、この可能性のある出口ランプに連れて行ける可能性は少なくなっている。
この全体の不幸な物語における最大の悲劇的要素は、それが回避可能だったことだ。しかし、アメリカの政策立案者は自由主義の驕りを抑え、リアリズムの不快だが死活的な教訓を十分に理解するまで、かれらは将来において同じような危機によろよろと入り込んでいきそうだ」。
国家の指導者の意図を完全に理解することはできませんが、ウォルト氏は、ウクライナ危機の事例を時系列的に分析することで、プーチンが不安から攻撃的な行動にでたと判断しています。これが正しいとするならば、ウクライナ危機を解決するには、ロシアに対する何らかの「宥和」が、脅迫による譲歩ではないバーゲニングに求められるということです。そして、このことはリアリズムの国際関係理論から処方される政策なのです。宥和政策は「ミュンヘンの再来はこめんだ」という単純な「歴史の教訓」の推論から否定されることが多いようですが、「スパイラル・モデル」の状況においては、紛争の鎮静化や戦争へのエスカレーションの防止に効果が見込めます。歴史学者であるケネディ氏と政治学者であるジャーヴィス氏が、宥和戦略の是非に新しい知見を与えてくれました。そして、政策に関連づけられた理論研究を重視するウォルト氏により、宥和政策は現在の国際情勢分析に応用されました。われわれの宥和政策の理解は、「歴史学と政治学の対話」により深まったといえるのではないでしょうか。
ウクライナ危機は予断を許さない緊張した状態が続いています。将来の出来事を予測することは困難を伴うものですが、ウォルト氏は、政治学者として、とるべき政策を明らかにする自らの社会的役割を自覚しながら、上記のような発言を行っているのだと思います。ウクライナ危機を平和的に解決するカギを「リアリストの外交戦略」が握っているとするならば、それが遅きに失していないことを願うばかりです。

ケネディ氏の著作は、日本ではベスト・セラーを記録した『大国の興亡』(草思社、1993年〔原著1987年〕)が有名ですが、上記書は、専門家以外には、ほとんど知られていないでしょう。『戦略と外交』においてケネディ氏が言いたい1つのことのは、大英帝国は宥和政策に支えられていたことです。かれはこう主張しています。
「なぜ帝国はかくも長きにわたり継続したのか…イギリスの大半のエリートの政治文化、すなわち極端を嫌い、理性的な議論に訴え、政治の合理性に信念を抱き、妥協の必要性を認めることは、なぜ大英帝国がそれほど長続きしたのかを説明する、たいへん重要な部分を形成するかもしれない…長い目で見れば、いったん経済的、戦略的潮目が変わってしまった際に、可能な限り世界大の帝国をいかに維持するかにおける根本的問題に関して、この柔軟で理性的で妥協を模索する政策は、断固として『屈服しない』ものより、好ましくなかったのだろうか」(『戦略と外交』202、216-217ページ)。
ケネディ氏によれば、「『宥和』の伝統は、もともと否定的ではなく肯定的な概念だった」のです(前掲書、215ページ)。この概念を逆転させてしまったのが、「ミュンヘン宥和」と第二次世界大戦でした。イギリス外交において1939年まで、宥和は好ましい政策として活用されていたのです。それでは、ここでいう「宥和」とは、どのようなものなのでしょうか。かれは、このように定義しています。「『宥和』は、不満を合理的な交渉と妥協を通して、認めたり満たしたりすることによる国際紛争を解決する手段であり、したがって、費用が高く血まみれになり、場合によってはたいへん危険な武力衝突に頼ることを防ぐ政策を意味する」ということです(前掲書、15-16ページ)。そして、これは「国益としての平和」として、1930年代まで、イギリスの全般的な戦略を構築していました。もちろん、こうした戦略がイギリスで無批判だったわけではありません。「左派」や「理想主義者」は、ヨーロッパ大陸における紛争に巻き込まれることを忌避していました。他方、「右派」や「リアリスト」は、宥和が、その前提に永久的な調和という考えを置くユートピア主義であり、国家の弱みを見せる政策だと批判していました(前掲書、19-21ページ)。
こうした宥和政策への批判があるにもかかわらず、19世紀後半から20世紀の前半頃まで、イギリスが宥和を基調とする戦略をとってきたのには、わけがありました。第1は国内的要因です。イギリスの政治家は、国民からの福祉への高まる要求に応えなければなりませんでした。教育、貧困、保険、年金などを手厚く提供するということです。その結果、かれらは古典的な「大砲(軍備)かバター(福祉)か」のトレードオフに対処しなければなりませんでした。第2はイギリスの国力の衰退です。この時期にイギリスは、産業や通商、植民地、海軍と軍事一般において、世界的なポジションを相対的に悪化させていたのです。イギリスは、これらの問題を宥和政策をとることで解決しようとしました。具体的には、コミットメントの縮小、敵対主義の排除、戦争につながりかねない対立の回避です。こうした政策の端的な例が、アメリカに対する宥和でした(前掲書、23-24ページ)。この対米宥和については、過去のブログ記事で触れましたので、詳しくは、そちらに譲り、ここではイギリスの海軍と部隊は、アメリカの勢力圏になる西半球から撤退したことだけ述べるにとどめます。
イギリスの宥和戦略は、ヒトラーの登場により破綻します。戦間期において、宥和政策は左派の広い支持を集めており、右派が時折疑念を示したり批判をしたりする程度でした。ところが、独裁者のヒトラーに対する宥和は、間違いであり危険な政策になったのです。ナチス・ドイツの一連の侵略行動は、安上がりで、平和的な、非介入主義の対外政策が、特定の状況下では妥当でないことを明らかにしたのです。世界情勢での地位を徐々に失いつつある小さな島国であるイギリスにとって、軍事的、経済的な負担は重すぎて背負えないため、宥和は「自然な」政策でした。ところが、この外交パターンは、ヒトラーの侵略によって粉々にされました。そして「宥和」は、誇るべき言葉から恥ずべき言葉になったのです。皮肉なことに、宥和に対する意味合いの逆転は、後のイギリスに悲劇をもたらします。1956年のスエズ危機において、アンソニー・イーデン首相は、自らの政策で宥和を断固拒否しました(前掲書、31-39ページ)。その結果は、外交的な失敗でした。
現代の国際政治において、われわれは宥和政策をどのように理解すればよいのでしょうか。リアリストは概して宥和に批判的だと思われがちですが、実は、そうでもありません。リアリズムの伝統をくむ国際関係理論は、肯定か否定かの二項対立を超えた宥和に対する1つの見方を示しています。その分析枠組みを提供したのが、ロバート・ジャーヴィス氏です。かれは、認知心理学を応用した国際関係研究の金字塔である著作『国際政治における認識と誤認(Perception and Misperception in International Politics)』(プリンストン大学大学出版局、1976年)において、紛争の2つのモデルを提供しました。1つは「スパイラル・モデル(spiral model)」です。これは国家が恐怖や不安により動機づけられて攻撃的な行動をとっている場合にあてはまります。こうした状況では、抑止や強制の威嚇は、相手の恐怖心をさらに高めてしまい、作用・反作用の悪循環を発生させる結果、対立はどんどん悪化するだけです。したがって、ここでの紛争解決や危機管理を成功させる政策は、相手の恐怖や不安を和らげることです。すなわち、便宜をはかったり宥和をしたりする政策が有効なのです。もう1つは「抑止モデル(deterrence model)」です。これは国家が現状打破の拡張や略奪的な野心によって動機づけられて侵略的な行動をとっている場合にあてはまります。こうした状況では、便宜をはかったり宥和をしたりすると、相手に拡張行動をエスカレートする機会を与えることになり、対立はかえって悪化します。したがって、ここでの紛争解決や危機管理を成功させる政策は、信頼のおける威嚇により潜在的侵略国が現状打破の目的を達成できなくする抑止になります。
リアリストのスティーヴン・ウォルト氏(ハーバード大学)は、これら2つのモデルを引き合いに出しながら、ウクライナ危機において、アメリカやヨーロッパの同盟国は、ロシアを宥和すべきだと主張していました。かれは、ロシアには「抑止モデル」は当てはまらないといいます。ウクライナに武力を提供する政策は、プーチン大統領が無慈悲な侵略者であり、旧ソ連帝国を再構築しようとしていることを前提として、ロシアに対しては対決姿勢で臨むべきだという発想を反映しています。しかし、ウォルト氏は、むしろ「スパイラル・モデル」がロシアにあてはまると見ています。少し長くなりますが、かれの2015年2月時点での分析を以下に引用します。
「ロシアはナチス・ドイツや現代の中国のような野心的台頭国ではない…衰退する大国(ロシア)がまだ保持している国際的影響力にしがみついているのであり、国境付近の控えめな影響圏を維持しようとしているのだ…プーチンとその取り巻きは、ウクライナを含む世界中で「体制転換」を促進するアメリカの努力も純粋に懸念している…無慈悲な野心ではなく消えない不安がウクライナに対するロシアの反応にある。さらに、ウクライナ危機はロシアの大胆な行動から始まっていなかった…それはアメリカと欧州連合が、ウクライナをロシア圏から外して、西側の影響圏に組み込もうとした時に始まった…モスクワはこのプロセスに手段を尽くして戦いを挑むことを何度も明らかにした。アメリカの指導者は、領土の収奪ではなくロシアの不安から明らかに生じた、これらの警告を軽く無視したのだ。プーチンの強権的反応を予測できなかったアメリカの外交担当者の失敗は、顕著な外交的無能をさらけだす行為だった…もしわれわれは『スパイラル・モデル』状況にいるのなら、ウクライナを武力で強化することは事態を悪化させるだけだろう…それは単に紛争を悪化させるだけであり、ウクライナの人々をさらに苦しめることになる」(Stephen Walt Makes the Case for Appeasing Russia, Atlantic Council, February 14, 2015)。
その後、ウォルト氏はフォーリン・ポリシー誌のブログ記事「リベラリストが招いたウクライナ危機」(2022年1月19日)において、再度、ウクライナ危機の分析と解決を以下のように述べています。
「ウクライナ情勢は悪く、ますます悪化している。ロシアは侵攻の構えを見せており、NATOが決してこれ以上東方に拡大しない完全な保証を要求している。交渉は明らかに成功していないし、アメリカとそのNATO同盟国は、ロシアが侵略を推し進めてきた場合に、同国に代償を支払わせることを考え始めている。本当の戦争が今や現実味を帯びてきており、それは全ての当事者とくにウクライナ市民にとって、広範囲にわたりさまざまな影響をもたらすだろう。
西側では、NATO拡大を擁護するとともに、プーチンだけにウクライナ危機の非難を浴びせることが当たり前だ…しかしプーチンだけにウクライナをめぐる現在進行している危機の責任があるのではないし、かれの行為や性格に道徳的な怒りをぶつけることは戦略ではない。さらなる強力な制裁を課しても、かれが西側の要求に屈することは引き出せないだろう。とにかく不快であるが、アメリカとその同盟国は、ウクライナが地政学的にどう連携するかは、ロシアにとって死活的利益すなわち武力を使ってでも守ろうとする利益であり、このことはプーチンが旧ソ連の過去のノスタルジーに愛着を抱く無慈悲な専制主義者になったからではないことを知らなくてはならない。大国は国境付近に配置された地政学的な武力に決して無関心ではいられないし、ロシアは、たとえ他の誰が責任者になろうとも、ウクライナの政治的連携には深く神経をとがらせるだろう。アメリカとヨーロッパ諸国が、このような基本的な現実を受け入れようとしないことは、世界が今日において、このような混乱に陥った大きな理由なのだ。そして、プーチンは、大きな譲歩を銃口を突き付けて引き出そうとすることにより、この問題をさらに難しくしてしまった。たとえ、かれの要求が総じて理にかなったものであったにせよ(そしていくつかはそうではなかったが)、アメリカと他のNATO諸国は脅迫によるかれの試みを拒絶する十分な理由がある…脅迫されたことを許すシグナルを送ることは、脅迫者が新しい要求を突き付けることを促してしまうのだ。
この問題をうまく切り抜けるには、双方がこの交渉を脅迫のように見えるものから、相互に見返りを得るようなものに一段と見えるよう変えなければならないだろう...打つ手に乏しいにもかかわらず、アメリカの交渉チームは、ウクライナが将来のどこかの時点でNATOに加盟するオプションを保持することを、見たところ今だに主張しているが、この結果こそモスクワがまさに拒絶したいことなのだ。もしアメリカとNATO諸国がこれを外交により解決したいのならば、現実的な譲歩をしなければならないだろうし、望むものすべてを手に入れることなどできないだろう。わたしはあなた以上にこの状況が好きではないが、それは合理的な限界を超えてNATOを愚かにも拡大したことへの払うべき代償なのだ。
ウクライナはイニシアティヴをとって、いかなる軍事同盟にも加盟しない中立国として振る舞う意思を声明すべきである。同国は、NATOの加盟国にならないこと、あるいはロシアが主導する集団安全保障条約機構に加わらないことを公式に宣言すべきである…もしキエフが自分自身でそのように動けば、アメリカとNATO同盟国がロシアの脅迫に屈したと非難されることはないだろう。
ウクライナ人にとって、ロシアがすぐ隣にいる中立国として暮らすことは、まったくもって理想的な状況ではない。しかし、自国の地政学的位置を考えれば、それはウクライナが現実的に望みうる最善の結果なのだ…1992年から2008年すなわちNATOが愚かにもウクライナを同盟に加えるだろうことを公表したこの年まで、ウクライナがうまく中立を保っていたことは思い出すに値する。この期間のいかなる時点においても、同国は侵略の深刻なリスクに直面していなかった。だが、反ロシアの感情がウクライナの大部分で高まっている今となっては、この可能性のある出口ランプに連れて行ける可能性は少なくなっている。
この全体の不幸な物語における最大の悲劇的要素は、それが回避可能だったことだ。しかし、アメリカの政策立案者は自由主義の驕りを抑え、リアリズムの不快だが死活的な教訓を十分に理解するまで、かれらは将来において同じような危機によろよろと入り込んでいきそうだ」。
国家の指導者の意図を完全に理解することはできませんが、ウォルト氏は、ウクライナ危機の事例を時系列的に分析することで、プーチンが不安から攻撃的な行動にでたと判断しています。これが正しいとするならば、ウクライナ危機を解決するには、ロシアに対する何らかの「宥和」が、脅迫による譲歩ではないバーゲニングに求められるということです。そして、このことはリアリズムの国際関係理論から処方される政策なのです。宥和政策は「ミュンヘンの再来はこめんだ」という単純な「歴史の教訓」の推論から否定されることが多いようですが、「スパイラル・モデル」の状況においては、紛争の鎮静化や戦争へのエスカレーションの防止に効果が見込めます。歴史学者であるケネディ氏と政治学者であるジャーヴィス氏が、宥和戦略の是非に新しい知見を与えてくれました。そして、政策に関連づけられた理論研究を重視するウォルト氏により、宥和政策は現在の国際情勢分析に応用されました。われわれの宥和政策の理解は、「歴史学と政治学の対話」により深まったといえるのではないでしょうか。
ウクライナ危機は予断を許さない緊張した状態が続いています。将来の出来事を予測することは困難を伴うものですが、ウォルト氏は、政治学者として、とるべき政策を明らかにする自らの社会的役割を自覚しながら、上記のような発言を行っているのだと思います。ウクライナ危機を平和的に解決するカギを「リアリストの外交戦略」が握っているとするならば、それが遅きに失していないことを願うばかりです。