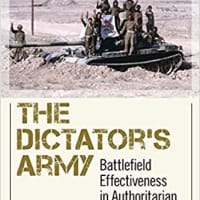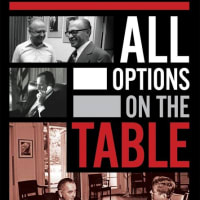第二次世界大戦後の長期にわたる国際関係の基軸であった冷戦は、30年以上前に、平和的に終わりました。冷戦の終結は、国際関係論に大きな衝撃を与えました。なぜならば、あらゆる政治学者や国際関係研究者にとって、冷戦の終結は驚くべき出来事であり、いかなる社会科学の理論でも予測できなかったからです。こうした世界政治における大事件は、当然のように、関連する研究分野に多大なインパクトを与えました。政治学や国際関係研究全般においては、冷戦終焉の予測に失敗した既存の理論、とりわけリアリズムの有効性に対する懐疑的な見方が興隆しました。同時に、冷戦を終わらせた要因を特定する事例研究にも、多くの学者が取り組みました。さらには、国際関係理論の修正や再構築の試みが盛んになりました。
これまでの冷戦終結をめぐる国際関係研究の展開は、3つの段階に分けることができそうです。第1の論争は、冷戦が終わることを予測できなかった理論に対する批判と擁護の応酬です。ここで強く攻撃されたのは「リアリズム」でした。第2の論争は、冷戦の終結をもたらした「原因」をめぐるものです。ゴルバチョフが打ち出した「新思考」の役割を重視する研究が次々と提出される一方で、レーガン政権の対ソ強硬策の影響を明らかにする学術成果も数多く発表されました。これらの研究を後押ししたのが、1980年代から1990年代初頭における米ソの政策決定を内情を明らかにする新しい資料の解禁でした。第3の論争は、冷戦の終焉がもたらした国際政治の変化と、冷戦終結を超えた国際政治の継続性をそれぞれ探究する近年の試みです。この最新の学際的な研究成果が、素晴らしい政治学者だったヌノ・モンテーロ氏(イェール大学)と新進気鋭の歴史学者であるフリッツ・バーテル氏(テキサスA&M大学)により編まれた『崩壊前後―世界政治と冷戦の終焉―』(ケンブリッジ大学出版局、2021年)です(上記の研究区分は、同書のイントロダクションから)。ここでモンテーロ氏を「過去形」で紹介したのは、誠に残念ですが、若くしてお亡くなりになったからです。わたしは、単極世界のグランド・セオリー(大理論)を構築した時から、かれには注目しており、また、核拡散に関する共同研究は自分の論文でも引用して、その卓越した研究成果を取り入れていました。モンテーロ氏は間違いなく世界の国際関係研究をけん引するであろう有望な政治学者だったので、急逝が惜しまれます。心よりご冥福をお祈りします。
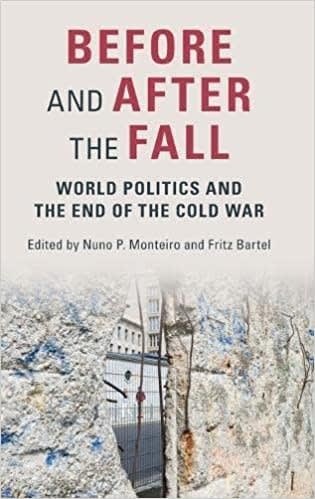
このブログ記事では、冷戦終結に関する上記の3つの研究の波を、わたしが注目する学術書や論考を取り上げながら、追っていきたいと思います。第1の論争に言及するのに欠かせないのが、リチャード・ルボウ氏(キングス・カレッジ)とトーマス・リッセ・カッペン氏(ベルリン自由大学)が編集した『国際関係理論と冷戦の終結(International Relations Theory and the End of the Cold War)』(コロンビア大学出版局、1995年)でしょう。本書においてルボウ氏は、「ソ連の衰退に対する反応は、いかなるリアリストの理論でも把握されなかった」と手厳しく批判しています(前掲書、36ページ)。ただし、このアンソロジーが、リアリズムを全面的に否定しているかといわれれば、そうではありません。同書の終章において、リチャード・ハーマン氏(オハイオ州立大学)は、この共同研究を次のようにまとめています。「リアリズムがソ連の対外政策の変化を予測できなかったことを理由に、それを否定するのは公正ではない。これは対外政策の理論ではないのだ。その一方で、リアリズムは大国間関係における変化に(国際)システムが与える影響を予測することを期待されるものである」(前掲書、264ページ)と的確に指摘しています。
それでは、国際システムが冷戦の終結に及ぼした影響は、どのように説明されるのでしょうか。この難問に1つの答えをだしたのが、ケネス・オーエ氏(マサチューセッツ工科大学)です。かれは『国際関係理論と冷戦の終結』に寄稿した「冷戦を説明すること―核による平和への形態学的・行動論的適用―」において、リアリズムは中途半端な理論なので冷戦終結の事例では検証できないことを留保しながらも、国際システムがソ連の行動に与えた影響を理論的に説明しています。すなわち、国際システムが安定していたからこそ、ソ連はその生き残りを強く懸念することなく、軍縮や東欧支配の放棄、経済改革などの大胆な政策変更に挑むことができたと主張しています。「国際環境の性質、とりわけ核兵器の展開とそれによる長期のシステム中枢の平和は、ソ連内部の政治的・経済的自由化の重要な許容原因(permissive cause)であった」ということです(前掲論文、58ページ)。
国家は外部の国際環境に適応しようとします。すなわち、国際システムが危険か平穏かにより、国家がとる行動は変わるということです。前者の場合、国家は安全保障のために中央集権化を進め、国民の自由を制限して結束を図ると同時に資源を集中管理しようとします。他方、後者の場合、国家は分権化を進め、政治的・経済的なリベラリズムの体制をとるようになります。1980年代、ソ連は核大国であった反面、経済が停滞していました。当時のソ連は生産性で日本やEC、アメリカに後れを取っていました。また、GNP比で15%近い軍事費や投資さらには東欧支配を維持する補助金や援助などが、消費を圧迫していました。このような状況において登場したゴルバチョフをはじめとする新思考者たちは、東欧をソ連圏から解放すると共に軍備を縮小することにより、西欧諸国との関係改善と経済成長の回復を目指したのです。衰退するソ連が、縮小戦略と国内改革を追求できたのは、核兵器の存在が「西側からの侵攻という主要な伝統的脅威」を消滅させたからだということです(前掲論文、74-76ページ)。こうした構造主義的な因果理論によるソ連の政策変化の分析は、論理的な説得力を持つものですが、経験的な検証において、やや弱いといえるかもしれません。
冷戦終結の第2論争でわたしが注目するのは、戦略理論家のハル・ブランズ氏(ジョンズ・ホプキンス大学)による『大戦略は何が良いものか(What Good Is Grand Strategy? Power and Purpose in American Statecraft from Harry S. Truman to George W. Bush)』(コーネル大学出版局、2014年)とセレステ・ウォランダー氏(米ロ基金)が執筆した論文「西側の政策とソ連の崩壊("Western Policy and the Demise of the Soviet Union")」(Journal of Cold War Studies, Vol. 5 No. 4, Fall 2003, pp. 137-177)です。ブランズ氏は、レーガン大統領のソ連に対する「大戦略」が成功したことを重視しています。レーガンは、ソ連が見た目より弱いことを見抜いており、政治、経済、軍事、イデオロギーの領域でソ連に圧力をかけることにより、その弱みを利用しました。その目的は、ソ連を崩壊させることではなく、アメリカに有利な条件で、ソ連の行動を穏健にすると同時に冷戦の緊張を和らげることでした。この大戦略の1つの柱が、アメリカの大幅な軍事力の増強でした。レーガンは軍事力でソ連に有利な立場になることにより、それをテコにしてソ連を軍備管理に応じさせようとすると共に、ソ連を軍拡競争に引き込むことで、同国に余分な軍事費を使わせて、その経済にダメージを与えようとしたのです。「戦略防衛構想(SDI: Strategic Defense Initiative)」や西欧へのパーシングⅡなどの中距離核戦力の展開は、その主要な手段でした。こうしたレーガン政権の強硬策は、ソ連の政策変更を促しました。ゴルバチョフ政権は、INF全廃条約に合意して、アメリカより大幅な中距離核戦力の廃棄を余儀なくされました。かれは後に、パーシングⅡが「われわれのこめかみに突き付けられた拳銃だった」と書き残しています。また、SDIについて、ソ連の高官は「攻撃的兵器の増強で対抗できるだろうが、資源がますます希少になりつつある中での新たな大幅な支出になるであろう」と危惧しました(前掲書、121ページ)。また、レーガンは対話による安心供与策も活用しました。たとえば、1986年にかれは「われわれはソ連に敵対的な意図を持っていない」と説いています。一方で、ゴルバチョフは「われわれがどこかで引き下がらなければ…結局、負けることになるだろう」とクレムリンの同志に語り、国連での大幅な通常戦力の削減の発表やアフガニスタンからの撤退などを縮小政策をとるに至りました(前掲書、131-132ページ)。1980年代後半の米ソ関係は「アメリカの政策は繰り返し譲歩ばかりを引き出そうとする」と不平をいうゴルバチョフに対して、シュルツ国務長官が「わたしはあなたに同情してむせび泣いています」と返した逸話に象徴されています(前掲書、133ページ)。こうして冷戦は終結したのです。
冷戦終結の「勝利史観」や「レーガン勝利学派」に異議を申し立てる研究が、ウォランダー氏の論考です。この論文の目的は、ソ連崩壊の原因を明らかにすることですが、それは同時に、冷戦の終焉にも関連するものです。ここで彼女が主張したいことは明確であり、「西側はいかなる直接的意味においても、ソ連崩壊を引き起こさなかった…もしわれわれがソ連衰退の単一の基底にある原因を重要度から優先順位をつけるのであれば、それは国内的経済システムの弱さと崩壊であった…西側はソ連崩壊の原因ではなかったが、ソ連の衰退には限られた特定の仕方で貢献した」というロジックです(前掲論文、137ページ)。その最大の1つの根拠は、レーガン政権の軍事力の強化が、ソ連の経済を圧迫するはずの軍事費の増加をもたらしていないことです。ソ連の軍事支出は、1980年代にアメリカが急激に軍事費を増額させたにもかかわらず、ほぼ同額か、ほんのわずかな増加に留まっています。このことは、彼女によれば、軍事的負担が1980年代のソ連の経済成長を妨げた根拠になりません。ソ連の経済危機が、軍事費がほとんど変化していないにもかかわらず発生したのは、それ以外に原因があることを示しています。それはソ連の生産性の低さということです。それにもかかわらず、ソ連は軍事的負担を軽減するために、核戦力ならびに通常戦力を大幅に削減しました。その結果、ソ連の兵器購入は1988年から1991年にかけて約30%減り、軍事研究開発費も22%削減されました(前掲論文、160ページ)。こうした軍事的負担の軽減は、資本投資や消費に再分配することで経済成長につなげられるはずですが、ウォランダー氏は、ソ連経済の欠陥を是正することにならなかっただろうと主張します。なぜならば、ソ連経済の根本的問題は「国家統制」という政治経済の制度に起因するからです(前掲論文、148ページ)。確かに、ソ連は自らの壊滅的な経済の弱みで崩壊したという説明は筋が通っていますが、それを許容した環境的要因(国際システムの影響)を加味しなければ、冷戦終結からソ連解体の全体的ストーリーは完結しないと思います。アメリカとの軍縮交渉において、ソ連政治局のガイドラインは「戦略的安定」というフレーズを繰り返し使っていました(前掲論文、160ページ)。このエビデンスは、オーエ氏が的確に指摘したように、ソ連が自らの安全保障を前提条件にして、一連の経済改革を実行していたことを示唆しています。
冷戦終結に関する研究は、第三波を迎えています。それは冷戦の終焉を「データポイント」として捉えるのではなく、国際政治のパターンの1つの事象として、その連続性の中で観察する研究です。ジョシュア・シフリンソン氏(ボストン大学)は『崩壊前後』に寄稿した論文「背後に置き去りにし続けること―アメリカ、ソ連の衰退そして冷戦の終わりにおけるヨーロッパの安全保障―」において、「継続されたアメリカの競争は、冷戦の終結にもかかわらず、百戦錬磨のリアリストのパースペクティヴからすれば、道理にかなったものだ」と主張しています。かれの分析の特徴は、パワーシフトにある台頭国と衰退国の相互作用を理論的に説明していることです。パワーの衰退に直面している国家がとり得る選択肢は、①コミットメントの縮小、②現状を継続すること、③予防行動をとることです。他方、台頭国は自らが優位になったチャンスを活かして、しばしば「リスク回避の収奪者」として行動します。すなわち、台頭国は衰退国が絶望して「予防戦争」に走ることがないよう注意しながら、後者の犠牲のもとで自らの利益を最大化するように振る舞うのです。冷戦前後の米ソ(ロ)関係でいえば、アメリカの戦略は「ロシアを後方に置き去りにし続けながらも、自暴自棄になったり危険な存在になったりするまでは突き放さないこと」でした(『崩壊前後』88ページ)。具体的には、アメリカの対ソ(ロ)政策は、1980年代中頃まではソ連と競争で優位に立つことであり、レーガン政権の後期では、軍備管理でソ連と協力することに移行して、ブッシュ政権の初期には競争に戻ったものの、1990年のドイツ統一と1991年のソ連崩壊をめぐる外交では再度協力に向かったのです。
アメリカは1980年中頃までは、INFや戦略兵器削減交渉において、自国に有利な非対称的削減を実現するために、ソ連に圧力をかけました。また、アメリカはソ連の経済成長を鈍化させるために、同国が西側諸国のテクノロジーを入手したり、借り入れを行ったりできないよう制限をかけました。要するに「ソ連が力尽きるのを助長した」ということです(『崩壊前後』86-87ページ)。ただし、ソ連はまだ恐ろしい軍事力を持っていたので、1989年の東欧の革命に対して、アメリカの政策立案者たちは、その変革をゆっくりと漸進的なものにするよう模索しました。その後、ソ連が国境を超えて軍事力を投射しないことを受けて、アメリカはNATOを存続させたまま、ソ連が譲歩してドイツ統一を実現しました。また、ソ連の対外コミットメントの縮小から生じた力の真空を埋めるように、アメリカはNATOの東方拡大に乗り出すことになります。アメリカはパワーシフトから得た優越的地位を利用して、自国の利益に沿うようなヨーロッパの安全保障秩序を構築したのです。このように冷戦終結前後のアメリカの行動は、パワー極大化の論理と一致しているということです(『崩壊前後』93ページ)。
冷戦終結をめぐる研究は、上記のように、3つの波を経て進展しました。こうした研究動向からいえそうなのは、第1に、国際政治におけるパワーをめぐる競争は、冷戦前後でも継続して行われているということです。リアリズムは冷戦の終焉を予測できなかったものの、その仮説のあいまいさは依然として弱点ですが、国家間の競争のパターンを説明する理論として強力なようです。第2に、アメリカがソ連に勝利した事実は、揺るがないのではないでしょうか。ただし、それはアメリカの大戦略が人為的に引き起こしたのか、それともパワーシフトによりソ連が自滅したのかは、議論の余地が残ります。私見では、冷戦の終焉のような稀な大規模の出来事は、核革命により大戦争が起こりにくい国際システムにおいても、かなりの程度が指導者の国政術(statecraft)に左右されると思わざるを得ません。いずれにせよ、この30年間に蓄積された冷戦終結の研究は、われわれの世界政治に対する理解を深めたことは確かでしょう。
これまでの冷戦終結をめぐる国際関係研究の展開は、3つの段階に分けることができそうです。第1の論争は、冷戦が終わることを予測できなかった理論に対する批判と擁護の応酬です。ここで強く攻撃されたのは「リアリズム」でした。第2の論争は、冷戦の終結をもたらした「原因」をめぐるものです。ゴルバチョフが打ち出した「新思考」の役割を重視する研究が次々と提出される一方で、レーガン政権の対ソ強硬策の影響を明らかにする学術成果も数多く発表されました。これらの研究を後押ししたのが、1980年代から1990年代初頭における米ソの政策決定を内情を明らかにする新しい資料の解禁でした。第3の論争は、冷戦の終焉がもたらした国際政治の変化と、冷戦終結を超えた国際政治の継続性をそれぞれ探究する近年の試みです。この最新の学際的な研究成果が、素晴らしい政治学者だったヌノ・モンテーロ氏(イェール大学)と新進気鋭の歴史学者であるフリッツ・バーテル氏(テキサスA&M大学)により編まれた『崩壊前後―世界政治と冷戦の終焉―』(ケンブリッジ大学出版局、2021年)です(上記の研究区分は、同書のイントロダクションから)。ここでモンテーロ氏を「過去形」で紹介したのは、誠に残念ですが、若くしてお亡くなりになったからです。わたしは、単極世界のグランド・セオリー(大理論)を構築した時から、かれには注目しており、また、核拡散に関する共同研究は自分の論文でも引用して、その卓越した研究成果を取り入れていました。モンテーロ氏は間違いなく世界の国際関係研究をけん引するであろう有望な政治学者だったので、急逝が惜しまれます。心よりご冥福をお祈りします。
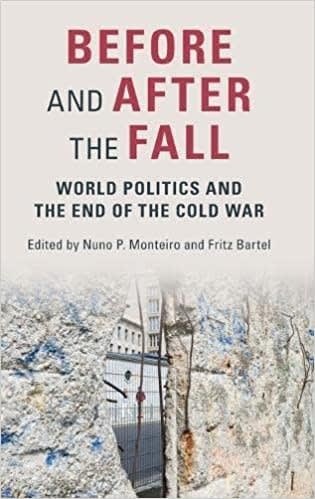
このブログ記事では、冷戦終結に関する上記の3つの研究の波を、わたしが注目する学術書や論考を取り上げながら、追っていきたいと思います。第1の論争に言及するのに欠かせないのが、リチャード・ルボウ氏(キングス・カレッジ)とトーマス・リッセ・カッペン氏(ベルリン自由大学)が編集した『国際関係理論と冷戦の終結(International Relations Theory and the End of the Cold War)』(コロンビア大学出版局、1995年)でしょう。本書においてルボウ氏は、「ソ連の衰退に対する反応は、いかなるリアリストの理論でも把握されなかった」と手厳しく批判しています(前掲書、36ページ)。ただし、このアンソロジーが、リアリズムを全面的に否定しているかといわれれば、そうではありません。同書の終章において、リチャード・ハーマン氏(オハイオ州立大学)は、この共同研究を次のようにまとめています。「リアリズムがソ連の対外政策の変化を予測できなかったことを理由に、それを否定するのは公正ではない。これは対外政策の理論ではないのだ。その一方で、リアリズムは大国間関係における変化に(国際)システムが与える影響を予測することを期待されるものである」(前掲書、264ページ)と的確に指摘しています。
それでは、国際システムが冷戦の終結に及ぼした影響は、どのように説明されるのでしょうか。この難問に1つの答えをだしたのが、ケネス・オーエ氏(マサチューセッツ工科大学)です。かれは『国際関係理論と冷戦の終結』に寄稿した「冷戦を説明すること―核による平和への形態学的・行動論的適用―」において、リアリズムは中途半端な理論なので冷戦終結の事例では検証できないことを留保しながらも、国際システムがソ連の行動に与えた影響を理論的に説明しています。すなわち、国際システムが安定していたからこそ、ソ連はその生き残りを強く懸念することなく、軍縮や東欧支配の放棄、経済改革などの大胆な政策変更に挑むことができたと主張しています。「国際環境の性質、とりわけ核兵器の展開とそれによる長期のシステム中枢の平和は、ソ連内部の政治的・経済的自由化の重要な許容原因(permissive cause)であった」ということです(前掲論文、58ページ)。
国家は外部の国際環境に適応しようとします。すなわち、国際システムが危険か平穏かにより、国家がとる行動は変わるということです。前者の場合、国家は安全保障のために中央集権化を進め、国民の自由を制限して結束を図ると同時に資源を集中管理しようとします。他方、後者の場合、国家は分権化を進め、政治的・経済的なリベラリズムの体制をとるようになります。1980年代、ソ連は核大国であった反面、経済が停滞していました。当時のソ連は生産性で日本やEC、アメリカに後れを取っていました。また、GNP比で15%近い軍事費や投資さらには東欧支配を維持する補助金や援助などが、消費を圧迫していました。このような状況において登場したゴルバチョフをはじめとする新思考者たちは、東欧をソ連圏から解放すると共に軍備を縮小することにより、西欧諸国との関係改善と経済成長の回復を目指したのです。衰退するソ連が、縮小戦略と国内改革を追求できたのは、核兵器の存在が「西側からの侵攻という主要な伝統的脅威」を消滅させたからだということです(前掲論文、74-76ページ)。こうした構造主義的な因果理論によるソ連の政策変化の分析は、論理的な説得力を持つものですが、経験的な検証において、やや弱いといえるかもしれません。
冷戦終結の第2論争でわたしが注目するのは、戦略理論家のハル・ブランズ氏(ジョンズ・ホプキンス大学)による『大戦略は何が良いものか(What Good Is Grand Strategy? Power and Purpose in American Statecraft from Harry S. Truman to George W. Bush)』(コーネル大学出版局、2014年)とセレステ・ウォランダー氏(米ロ基金)が執筆した論文「西側の政策とソ連の崩壊("Western Policy and the Demise of the Soviet Union")」(Journal of Cold War Studies, Vol. 5 No. 4, Fall 2003, pp. 137-177)です。ブランズ氏は、レーガン大統領のソ連に対する「大戦略」が成功したことを重視しています。レーガンは、ソ連が見た目より弱いことを見抜いており、政治、経済、軍事、イデオロギーの領域でソ連に圧力をかけることにより、その弱みを利用しました。その目的は、ソ連を崩壊させることではなく、アメリカに有利な条件で、ソ連の行動を穏健にすると同時に冷戦の緊張を和らげることでした。この大戦略の1つの柱が、アメリカの大幅な軍事力の増強でした。レーガンは軍事力でソ連に有利な立場になることにより、それをテコにしてソ連を軍備管理に応じさせようとすると共に、ソ連を軍拡競争に引き込むことで、同国に余分な軍事費を使わせて、その経済にダメージを与えようとしたのです。「戦略防衛構想(SDI: Strategic Defense Initiative)」や西欧へのパーシングⅡなどの中距離核戦力の展開は、その主要な手段でした。こうしたレーガン政権の強硬策は、ソ連の政策変更を促しました。ゴルバチョフ政権は、INF全廃条約に合意して、アメリカより大幅な中距離核戦力の廃棄を余儀なくされました。かれは後に、パーシングⅡが「われわれのこめかみに突き付けられた拳銃だった」と書き残しています。また、SDIについて、ソ連の高官は「攻撃的兵器の増強で対抗できるだろうが、資源がますます希少になりつつある中での新たな大幅な支出になるであろう」と危惧しました(前掲書、121ページ)。また、レーガンは対話による安心供与策も活用しました。たとえば、1986年にかれは「われわれはソ連に敵対的な意図を持っていない」と説いています。一方で、ゴルバチョフは「われわれがどこかで引き下がらなければ…結局、負けることになるだろう」とクレムリンの同志に語り、国連での大幅な通常戦力の削減の発表やアフガニスタンからの撤退などを縮小政策をとるに至りました(前掲書、131-132ページ)。1980年代後半の米ソ関係は「アメリカの政策は繰り返し譲歩ばかりを引き出そうとする」と不平をいうゴルバチョフに対して、シュルツ国務長官が「わたしはあなたに同情してむせび泣いています」と返した逸話に象徴されています(前掲書、133ページ)。こうして冷戦は終結したのです。
冷戦終結の「勝利史観」や「レーガン勝利学派」に異議を申し立てる研究が、ウォランダー氏の論考です。この論文の目的は、ソ連崩壊の原因を明らかにすることですが、それは同時に、冷戦の終焉にも関連するものです。ここで彼女が主張したいことは明確であり、「西側はいかなる直接的意味においても、ソ連崩壊を引き起こさなかった…もしわれわれがソ連衰退の単一の基底にある原因を重要度から優先順位をつけるのであれば、それは国内的経済システムの弱さと崩壊であった…西側はソ連崩壊の原因ではなかったが、ソ連の衰退には限られた特定の仕方で貢献した」というロジックです(前掲論文、137ページ)。その最大の1つの根拠は、レーガン政権の軍事力の強化が、ソ連の経済を圧迫するはずの軍事費の増加をもたらしていないことです。ソ連の軍事支出は、1980年代にアメリカが急激に軍事費を増額させたにもかかわらず、ほぼ同額か、ほんのわずかな増加に留まっています。このことは、彼女によれば、軍事的負担が1980年代のソ連の経済成長を妨げた根拠になりません。ソ連の経済危機が、軍事費がほとんど変化していないにもかかわらず発生したのは、それ以外に原因があることを示しています。それはソ連の生産性の低さということです。それにもかかわらず、ソ連は軍事的負担を軽減するために、核戦力ならびに通常戦力を大幅に削減しました。その結果、ソ連の兵器購入は1988年から1991年にかけて約30%減り、軍事研究開発費も22%削減されました(前掲論文、160ページ)。こうした軍事的負担の軽減は、資本投資や消費に再分配することで経済成長につなげられるはずですが、ウォランダー氏は、ソ連経済の欠陥を是正することにならなかっただろうと主張します。なぜならば、ソ連経済の根本的問題は「国家統制」という政治経済の制度に起因するからです(前掲論文、148ページ)。確かに、ソ連は自らの壊滅的な経済の弱みで崩壊したという説明は筋が通っていますが、それを許容した環境的要因(国際システムの影響)を加味しなければ、冷戦終結からソ連解体の全体的ストーリーは完結しないと思います。アメリカとの軍縮交渉において、ソ連政治局のガイドラインは「戦略的安定」というフレーズを繰り返し使っていました(前掲論文、160ページ)。このエビデンスは、オーエ氏が的確に指摘したように、ソ連が自らの安全保障を前提条件にして、一連の経済改革を実行していたことを示唆しています。
冷戦終結に関する研究は、第三波を迎えています。それは冷戦の終焉を「データポイント」として捉えるのではなく、国際政治のパターンの1つの事象として、その連続性の中で観察する研究です。ジョシュア・シフリンソン氏(ボストン大学)は『崩壊前後』に寄稿した論文「背後に置き去りにし続けること―アメリカ、ソ連の衰退そして冷戦の終わりにおけるヨーロッパの安全保障―」において、「継続されたアメリカの競争は、冷戦の終結にもかかわらず、百戦錬磨のリアリストのパースペクティヴからすれば、道理にかなったものだ」と主張しています。かれの分析の特徴は、パワーシフトにある台頭国と衰退国の相互作用を理論的に説明していることです。パワーの衰退に直面している国家がとり得る選択肢は、①コミットメントの縮小、②現状を継続すること、③予防行動をとることです。他方、台頭国は自らが優位になったチャンスを活かして、しばしば「リスク回避の収奪者」として行動します。すなわち、台頭国は衰退国が絶望して「予防戦争」に走ることがないよう注意しながら、後者の犠牲のもとで自らの利益を最大化するように振る舞うのです。冷戦前後の米ソ(ロ)関係でいえば、アメリカの戦略は「ロシアを後方に置き去りにし続けながらも、自暴自棄になったり危険な存在になったりするまでは突き放さないこと」でした(『崩壊前後』88ページ)。具体的には、アメリカの対ソ(ロ)政策は、1980年代中頃まではソ連と競争で優位に立つことであり、レーガン政権の後期では、軍備管理でソ連と協力することに移行して、ブッシュ政権の初期には競争に戻ったものの、1990年のドイツ統一と1991年のソ連崩壊をめぐる外交では再度協力に向かったのです。
アメリカは1980年中頃までは、INFや戦略兵器削減交渉において、自国に有利な非対称的削減を実現するために、ソ連に圧力をかけました。また、アメリカはソ連の経済成長を鈍化させるために、同国が西側諸国のテクノロジーを入手したり、借り入れを行ったりできないよう制限をかけました。要するに「ソ連が力尽きるのを助長した」ということです(『崩壊前後』86-87ページ)。ただし、ソ連はまだ恐ろしい軍事力を持っていたので、1989年の東欧の革命に対して、アメリカの政策立案者たちは、その変革をゆっくりと漸進的なものにするよう模索しました。その後、ソ連が国境を超えて軍事力を投射しないことを受けて、アメリカはNATOを存続させたまま、ソ連が譲歩してドイツ統一を実現しました。また、ソ連の対外コミットメントの縮小から生じた力の真空を埋めるように、アメリカはNATOの東方拡大に乗り出すことになります。アメリカはパワーシフトから得た優越的地位を利用して、自国の利益に沿うようなヨーロッパの安全保障秩序を構築したのです。このように冷戦終結前後のアメリカの行動は、パワー極大化の論理と一致しているということです(『崩壊前後』93ページ)。
冷戦終結をめぐる研究は、上記のように、3つの波を経て進展しました。こうした研究動向からいえそうなのは、第1に、国際政治におけるパワーをめぐる競争は、冷戦前後でも継続して行われているということです。リアリズムは冷戦の終焉を予測できなかったものの、その仮説のあいまいさは依然として弱点ですが、国家間の競争のパターンを説明する理論として強力なようです。第2に、アメリカがソ連に勝利した事実は、揺るがないのではないでしょうか。ただし、それはアメリカの大戦略が人為的に引き起こしたのか、それともパワーシフトによりソ連が自滅したのかは、議論の余地が残ります。私見では、冷戦の終焉のような稀な大規模の出来事は、核革命により大戦争が起こりにくい国際システムにおいても、かなりの程度が指導者の国政術(statecraft)に左右されると思わざるを得ません。いずれにせよ、この30年間に蓄積された冷戦終結の研究は、われわれの世界政治に対する理解を深めたことは確かでしょう。