イベント参加レポです。
3日に倉敷運動公園陸上競技場で開催された、山口素弘氏の「名蹴会サッカークリニック」を観に行ってきました。極めて近所にあるスタジアムであるため、最初にネットで見かけた時は「都合が合えば行ってみるか、近所だし」と思っていたのですが、岩政まつり1日目が入ったために、微妙なタイムラグと、時刻表ばかり見ていました。岡山のNHKを出る。駅は近いが時間との戦い。何とすぐに乗れました。さて、最寄の球場前駅へ向けて乗り換える倉敷駅でもなぜかスムーズに時間が運ぶ。


到着したのが13:05。球場前駅の目の前にスタジアムがありますが、予定では13時から開会式。遠くからそんな雰囲気が見える。到着した時はトークショーが始まっていました。何と屋内ではなく、ピッチ横に長机とイスを並べた青空トークショーです。倉敷JCの理事長さん?がMCを務めており、山口氏がしゃべっていました。横を見ると、J2岡山の木村社長の姿。そういえばポスターに写真があったなと。
ひょっとして、来季の岡山の監督の含みもあったりしてと勝手に誇大妄想しながら、話に聞き入る。山口氏は現在、日本協会技術委員(強化部会員)として、Jリーグ・アンダー22選抜のコーチとして活躍されています。トークの内容ももっぱら育成の話ばかりで、すっかり日本協会の顔でした。こりゃ次期監督の可能性は低いなと自分で納得。


個人的に良かった事があります。それは近所であるこのスタジアムのピッチに入れて、天然芝に触れた事。シャルムの試合で何度も来ていますが、ボランティアをしている訳でなし、ピッチに近づく事がなかったのでちょっと感動しました。Cスタは「岡山の」ですが、ここは「地元、近所の」になるのでうれしさも格別。待ち受けか何かで使えないかと、思わずスマホで芝を撮影する始末。
あと、教室のお手伝いで水島FCの選手達が来ていました。ファジはJ2、水島さんはJ5とカテゴリは違っていますが、前にも書きましたが、もし違う流れで時代が流れていたら、立場が逆だったかもしれないとしみじみ思いました。それにしても両クラブが同席するのは極めて稀で、珍しい景色を見せてもらいました。入口で、熊代会長をお見かけし、お孫さんを抱かれた奥さん(今もマネージャー?)が挨拶くれました。お元気そうです。


今回のサッカークリニックは、倉敷JCさんと、名蹴会という団体が主催されています。名蹴会?・・・余り聞きなれなかった名前ですが、後で以下のとおり調べてみました。
【一社)日本サッカー名蹴会】
「日本のサッカー界において輝かしい功績を残したプレーヤーが中心となり、2010年9月27日に発足した会です。会員選出には、「国際Aマッチ50試合以上出場」「JSL(Jリーグの前身)とJリーグ発足前の海外リーグでの出場試合数合計200試合以上」「Jリーグ(J1)と海外1部リーグ(FIFAランキング50位以内の国)での出場試合数合計400試合以上」のいずれかを満たしていることが条件となります。」
引用:名蹴会公式HP
名誉会長が釜本氏、会長が金田喜稔氏、副会長が都並氏とJ2福岡の井原監督ですね。いろいろ調べてみると、国籍を「日本」に限定していないようですが、外国籍選手の入会できるかは不明だそうです。2010年9月に発足し、運営で日本青年会議所(JC)が全面協力。強制入会ではないため、入会基準を満たす者(公式発表では58名)のうち入会の意思を示しているのは発足時点で24名。サッカーを通じた社会貢献を目指し、Jリーグ選手OB会とも連携してサッカー教室やチャリティーイベントなどを主催する予定。
どうやらJC系の団体のようですね。深読みすると、40歳定年制の若手経営者の集まりである青年会議所と連携するのは、プロサッカー選手のセカンドキャリアを考えるといい話なのかもしれません。名蹴会に限らず、選手会やOB会などどんどん連携されてはいかがでしょうか。他にも経済団体があり、それらが集まる経済団体組織として、岡山にも岡山県経済団体連絡協議会という組織があります。全国レベルでもあるはず。
木村社長が、「30年後はあらゆるスポーツを無料で行ける教室をやりたい」と言われていました。確か少し前に「●●年後に県下に無料のサッカー教室を作りたい」と言われていたように思いますが、当ブログ的には少し進歩した話に聞こえました。ただ、地域のあらゆるスポーツ団体と連携する「協働」ではなく、自分達で運営するという形がちょっと気になるがまぁいいや。構想もいいですが、まずは現実的に異競技「交流」を「スタート」された方がいいんじゃないと思ってみたり。
例えばこの記事では他の多くのJクラブが継続事業として、サッカー以外の競技を主催しています。うーむまだ岡山の名前が無いですね。まずはこの辺からなのかな。


その後、サッカー教室が始まりました。トップアスリート事業は、通常1時間ちょっとですが、この名蹴会の教室は2時間くらいされてたのかな。子ども達の楽しい時間が長い事はいい事ですが、山口氏がちょっときつそうな表情だったのが印象的でした。その後はサイン会でしたが、やはりちょっとお疲れモードが伝わってきました。お疲れ様です。いくらMCが山口氏は日本代表選手時代に、伝説のループシュートを決めたとか説明があっても、やはり子どもたちはピンときていないだろなぁと思いましたが、それでも目を輝かせてサインをもらう倉敷のサッカー少年たちの表情を見ると良かったなぁと思いました。
浅口レポです。
先日、浅口市鴨方町の六条院小学校で、晴れの国トップアスリート事業による子どものバレー教室が開催され、観に行ってきました。地元のまちづくり委員会が実施する活動ですが、今年も昨年に引き続いて、岡山シーガルズが講師としてやってきました。今回は大楠、森田2選手と神田コーチの3人で去年よりも1人少なかった様子。まあ、参加児童も去年よりやや少なかったので、参加者数に合わせたのかなと。


この日は雨模様でしたが、バレーボールに雨は関係ありません。いかん、この日も室内シューズを忘れてしまいました。皆さんはいているのに・・・ 今度のシーガルズのファン感までには購入するとしよう。準備作業で、ネットのポールから準備すべきなのかという話が出ていましたが、実際持ってみると思いです。とても小学生の体育館にあるタイプとは思えない重さ。
開会式で、応援団・浅口の田代表が挨拶されていました。シーガルズの3人が挨拶した後、練習開始です。まずは半コートでランニング、その後念入りなストレッチです。当ブログとしては、今年ジップアリーナで目の当たりにした中身の濃いストレッチ風景が目に焼き付いているので、子供にもしっかりストレッチさせるんだなと実感。その後、スポ少の経験者グループから離れて、神田コーチが初心者グループに丁寧に指導していました。


終了とともに恒例のサイン会です。このサイン会が「学校訪問」の象徴シーンだと思います。普及コーチではこういうシーンはありません。つまり、子どもたちに夢は余り与えられないという事ではないかと個人的に認識してしまいます。強化だけが目的の練習会ならばわかりますが、今回のこの教室はどちらかというと、あこがれの選手に習いたいという目的。県の制度名も「トップアスリート」ですから、少なくともコーチはトップアスリートではないと思います。


「今年から2部なんじゃのう」という声はついに1回も聞こえなかったです。たぶん皆さん去年1部から2部に降格した事を知らないんでしょうが、いいような悪いような不思議な感覚でした。コアな人がおられたら「1年で1部へ」とか口にされるでしょうが、考えてみれば地域に根差すスポーツクラブであれば、カテゴリも関係ないのかなと思ってみたり。


聞くと、地域のまちづくり委員会のこの教室も10年ずっと開催されているとか。途中湯郷ベルが来た年もありましたが、一昨年まではファジがずっと来ていました。ただ、最初の頃は選手(当時ネクスト)が8名来ていましたが、最後の2年は普及コーチが3、4人来るという内容になっていました。毎週火曜日のスクール浅口校と変わらない内容、やはりこの教室は選手に来てもらって、子どもたちに夢を与えて欲しいという意向で、シーガルズに講師が変更になったのではと。真相はわかりませんが、この日のサイン会に並ぶ子ども達の表情を見ていると、来年もシーガルズなのかなと思いました。今年も、同じ週末にもう1校来ていたようです。皆様お疲れ様でした。
岡山シーガルズ公式FBページ「浅口教室①」:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1589952291066827&id=557416967653703
〃 「浅口教室②」:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1589936947735028&id=557416967653703
公財)岡山県体育協会トップアスリート派遣事業ページ:http://www.okayama-taikyo.or.jp/dispatch/
子どものスポーツ教室in浅口関連⑨(シーガルズ):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20161015
〃 ⑧(ファジ):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20151207
〃 ⑦(ファジ):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141223
〃 ⑥(ファジ):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20131122
〃 ⑤(ベル):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20130227
〃 ④(ファジ):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20111031
〃 ③(ファジ):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20101101
〃 ②(ファジ):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20091106
〃 ①(ファジ):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20081217
リスペクト(事例紹介)コラムです。
昨日の日経新聞の「フットボールの熱源」に、あのトヨタがサッカー事業に絡む話題が載っていました。トヨタ本体及び関連会社の社員が、巡回サッカー教室のコーチになるって斬新な企画ですね。でも、素晴らしい事だと思います。元々サッカーとイコールではない、世界のトヨタの社員がサッカーの普及活動に関わっていくというのは本当に画期的な事だと思います。以下、抜粋して紹介。


日本サッカー協会とパートナーシップ計約を結んだトヨタ自動車が、未就学児童にスポーツの楽しさを知ってもらう活動を支援。その取り組みの形態が興味深い内容。
トヨタの販売店、レンタリース店、部品共販店のスタッフが日本協会の公認キッズリーダーの資格を取得し、各都道府県のサッカー協会が展開している幼稚園、保育園への巡回指導を支援。各協会による巡回指導はまだ全国の幼稚園・保育園の8.7%しかカバーできず。キッズリーダーの資格は計3時間の講習・実技で取得できるものの、平日に幼稚園・保育園に行ける巡回指導員が不足。トヨタの販売会社は全国に376あり、販売店は5,000を超える数。既に約50の販売会社が巡回指導を視察し、現在は各社が活動に参加するかどうかの意思確認中とか。トヨタは年内に100社の参加を目標に設定。
「販売店が生き残っていくには地域との結びつきが必要。地域に根差した販売店にしよう」とトヨタは提唱。今回の取り組みにより、販売店と園児の保護者、地域や学生のリクルートにもつながる効果を期待。
「巡回指導を視察して、子ども達の笑顔を見ると心が動かされ、この活動に参加したい気持ちが強くなった」と、プロジェクトを推進するトヨタマーケティングジャパンのメディア総括室のコメント。地域の子どもを元気にする事が地域の大人の活力を生むと締めくくっています。
素晴らしい事業ですね。もう少し詳しく知りたいという事で調べてみたら、サッカーキングにもう少し専門的に書かれていた記事がありました。Jリーグ百年構想に沿った活動でもある事がよくわかりました。以下、抜粋して紹介。
【JFAとトヨタがJYDパートナーシップ契約…全国の幼稚園・保育園でサッカー巡回指導実施へ:サッカーキング】
日本サッカー協会(JFA)は17日、トヨタ自動車㈱と「JFA Youth & Development Programme(JYD)」パートナーシップ契約を締結したことを発表。JYDは、「JFA2005年宣言」の理念とビジョンに基づき、継続的な日本サッカーの発展のためにさらなる普及や次世代選手の育成を促進することを目的としたプロジェクトで、2016年1月より展開。今回のパートナーシップ契約締結により、トヨタはJYDオフィシャルサポーターとして全国の未就学児童を対象とした「サッカー巡回指導」の支援、活動に関わることとなるとか。
具体的な活動としては、トヨタの全国各販売店、共販店、レンタリース点のスタッフが中心となり、「JFA公認キッズリーダー」のライセンスを取得し、各都道府県のサッカー協会と連携しながら、地域の幼稚園・保育園等に対してサッカーならびに身体を動かすことの楽しさを伝えるための授業を実施する予定。
「子どもたちの健康と、将来スポーツで活躍できる選手の育成を考えており、決してサッカーだけの選手を取り込もうとして始めたわけでは無い。外遊びが少なくなり、ゲームをする子が増えた。小さい頃に外で遊ぶ、この身体を動かすことの喜びを知り、将来は日本の社会に貢献できる心身ともに健康な人材を育てるということが目標」と、サッカー界にとどまらず、スポーツ界全体や日本の社会に貢献することが目標だと、JFA田嶋会長の説明。
サッカーキング該当記事:https://www.soccer-king.jp/news/release/20170517/588584.html
今後は、地域の幼稚園児・保育園児とサッカーを楽しむトヨタ・ディーラーのスタッフの姿が見られるかも知れません。JFAはこれまでも巡回指導活動を行ってきたが、平日昼の活動のため指導者不足が課題となっており、トヨタとの契約で人材確保を目指す様子。少子化の影響もあり育成年代の選手登録が減少傾向に転じる中での新たな取り組み。この取り組みは2017年7月から開始されるとのこと。’20年までに、日本の市区町村全てにあたる1741の市区町村への巡回、10年後の2027年には、日本の幼稚園・保育園施設の全てにあたる48,631の施設への巡回を目標に掲げているとのことです。
これって、今後はトヨタ以外、車業界以外にも広がっていく可能性があるという事ですね。まあ、これがJリーグの事業であれば、トヨタはJ2名古屋の親企業とかいろいろしがらみがあるのかもしれませんが、JFAなのでいいのかな。今後は平日が休業日の例えば不動産業界とか参画したりして。
J2岡山のスポンサーにもトヨタ関係の企業の名前が観られますが、そのうち、地元のあそこのトヨタのディーラー社員が、近くの幼稚園で巡回サッカー教室をやってるというシーンが見られるかもしれませんね。頑張って下さい。
リスペクト(事例紹介)コラムです。
先日、スポナビのコラムに懐かしいキーワードが出てきました。「フェライン」という言葉ですが、読者の皆さん、ご存じでしょうか。これを知っている方は相当スポーツ文化や、総合型地域SCに詳しい方です。以前のこの記事で当ブログで紹介しましたが、その後もネット上ではほとんど出てこない言葉です。そのコラムを以下、抜粋して紹介。


【Jクラブの存在意義をあらためて考える】
今年は、DAZN元年でもあり、こんな機会だからこそ、5年後、10年後を見据えた健全で地域に密着したクラブ経営を目指して欲しい。それを実現するためにも、Jクラブがそれぞれのホームタウンに暮らす人々にとってどのような存在であるべきか、今一度考えることが重要。かつてJリーグを発足するにあたり手本にしたドイツ・ブンデスリーガに所属するクラブの在り方を、あらためて掘り下げて紹介。きっと、Jクラブがホームタウンの地域住民からの帰属意識を高める上で、非常に重要なヒントとなるのではないか。
【ドイツのクラブはすべてが「フェライン」】
日本ではJ1からJ3までの54クラブのうち53クラブは、株式会社という運営形態。暗黙のうちにどこのクラブもプロ化する段階で株式会社を設立するのが実情。一方ドイツでは、ドイツ国内に存在する約25,000のサッカークラブが「フースバルフェライン」(レヴァークーゼンのみ唯一の例外)。
ふースバルはサッカー、フェラインとは本来「一つになる」という意味を内包し、仲間や同志の集まりを意味。英語ではアソシエーション、日本語では協会、社団に相当し、日本では特定非営利活動法人(NPO)に近い存在。ちなみにその中でも、法人格のあるものを登記法人「eingetragener Verein(e.V.)」と言い、フースバルフェラインはすべてがこの「e.V.」。
フェラインはある特定の目的を持った人間が最低7人集まれば簡単に設立可能。申請が比較的簡潔であることに加え、公益性の認証を受ければ、税制上の優遇処置や、小規模であれば、フェライン会員が所得税控除を受けられる処置も。設立の目的も自由であることから、ドイツには趣味趣向に合わせて、消防団、自然保護、青少年育成、子育て、病人、高齢者介護、合唱、オーケストラ、音楽隊、スポーツ、観光、民族、園芸など、多種多様なフェラインが存在。ちなみにスポーツを目的とした「スポーツフェライン」は、ドイツ国内に約9万存在するが、そのうちの約25,000がフースバルフェラインで全体の約1/4。
ちなみに今では、ブンデスリーガに所属する多くのクラブは、トップチームを運営する営利団体を保有。ドイツサッカー協会(DFB)が'98年より運営会社の設立を許可したことで、'99年にはドルトムントがボルシア・ドルトムント有限株式合資会社を、また'02年にはバイエルンがバイエルン・ミュンヘン㈱を設立。そして'16-17シーズン現在では、31の運営会社が設立(1部14社、2部6社、3部6社、4部5社)。ちなみにDFBが運営会社設立を認めた大きな理由としては、各クラブがトップチームに関して営利団体として利益を追求する事が、リーグ全体にとっても有益であると判断した事。また、トップチームのパフォーマンスがフェライン自体の存続に関わってくると、フェライン本来の公益性を損ねてしまう恐れがあるため、トップチームの運営を別にすることで、フェラインへの経済的なリスクを軽減できることも重要な要因。なお、ブンデスリーガ1部18クラブ('15-16シーズン)のうち16クラブが黒字となっていることからも分かるように、この運営形態はリーグにも好影響を与えていると言える。
【フェラインの会員になるメリットは?】
フェラインとは会員のもの。本来フェラインの活動は原則会員が支払う会費によって運営され、ブンデスリーガに所属するフースバルフェラインに言及すると、それら会費の収入に加えて、試合の興行収入やスポンサーからの広告収入、放映権の分配金などもフェラインの収益。
フェラインはJクラブが運営する「ファンクラブ」とは全く違う存在。会員はあくまでもフェラインの一員であって、サービスを受ける「お客様」ではないので、会員になることのメリットを問われても、クラブの一員になり、アイデンティティーを共有することができる事のみ。その代わり、会員は年に1回行われる会員総会で投票する1票の権利を与えられることになる。これは公平にすべての会員がフェラインの決定事項に関与できることを意味しており、会員の最大の特徴。
ドイツにもいわゆるファンクラブは多く存在。フォルトゥナ・デュッセルドルフにも100を超えるファンクラブが登録。彼らはフォルトゥナが規定している内容に沿って申請を出すことで、フォルトゥナ側から正式にその存在が認められることになるが、これはあくまでもファンが自分たちの意思で立ち上げたもの。
【アクティブ会員とパッシブ会員】
フェラインの会員は、厳密にはアクティブ会員とパッシブ会員が存在。フォルトゥナの約22,000人の会員のうち、トップチームやアカデミーでプレーする選手や監督コーチ陣、またフロントスタッフなどはアクティブ会員に分類され、それ以外の方々がパッシブ会員に分類。ただしこの2つの立場に上下関係はなく、同じフェラインに属する会員として存在。
選手もフェラインの会員なのだから、本来一般の会員とフラットな関係であることが理想。フォルトゥナではそういった分け隔たりのない会員同士の交流を積極的に実施。選手達もその意味をしっかりと理解して参加することで、選手であってもファンであっても、お互いが顔の見える存在、意見を交換できる立場でいられるよう努力。フォルトゥナという1つのアイデンティティーを共有。
ちなみにフォルトゥナではさらに、定期的な会員フォーラムを実施。フェラインの方針に対し、可能な限り多くの会員の声をくみ取れるような対話の場を提供。これにより、たとえ自分がパッシブ会員であっても、その「フェライン=コミュニティー」に所属していると実感。その中でも公平な振る舞いができ、時に納得がいかないことがあれば意見することで、帰属意識は向上。会員はフェラインのお客様ではなく、フェラインの一部。そのようにして、自分の生活が「社会=コミュニティー=フェライン」の中にあると実感できることが、元々ある帰属意識をフェラインへの強いアイデンティティーへと育てる大きな要素になるのではないか。
【本当の意味での「自分のクラブ」に】
フォルトゥナでは3カ月に1回のペースで会員フォーラムを開催。フェライン側の役職者と一般会員がフラットな場でクラブ運営に関するディスカッションを行うことが目的。Jクラブが地域密着を目指す上で重要なことは、ビッグネームの選手を連れてきて、ファンを喜ばせることではなく、スター選手による一時的な観客数の増加よりも、その地域の方々に、本当の意味で自分のクラブだと思ってもらうことの方が重要。
このシンプルな答えが分かっているようで分かっていないクラブが、残念ながら日本にはまだまだ多いのではないか。確かにお金を払って試合を観に来てくれる方々は、大切なお客様だが、お客様であると同時に、クラブを成長させていくための支援をしてもらう支援者であるべき。彼らの声を聞き、彼らとともに歩むことで、共通のアイデンティティーが生まれ、そしてそのコミュニティー(=クラブ)の結束が強まっていく。ドイツ人は地域愛が非常に強いが、そういった本質的な部分をクラブ側が理解し、サポーターと良い相互関係を築くことが、スタジアムを満員にすることにつながっている。
まずはJクラブで働くスタッフや、プレーする選手達の意識改革が必要。DAZN元年である今こそ、そういった人材育成や取り組みに、時間と労力を費やしていくべき。全国に広がるプロサッカークラブが、それぞれの地域で人々の生活を豊かにする。そんな存在になっていって欲しい。そういう意味でもドイツの「フェライン」の在り方は、Jリーグ全体にとっても非常に参考になるマインドだと思うと締めくくっています。
スポナビ該当コラム:http://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201702240004-spnavi
読めば読むほど、当ブログの論調と一致します。Jリーグは少し前に、極端にアメリカ(MLS)に傾いた時期がありました。その時にドイツ派だった傍士氏は理事から退任され、商業主義とともにアメリカに傾倒しました。今は少しはより戻しが起こっているのでしょうが、アメリカ派はまだ存在しておるのではと個人的に推測しています。村井チェアマンは本当はどちらのでしょうか。本音はドイツだと信じていますが。
簡単に見れば、トップチームの株式会社と、それ以外の公益法人の両立という事で、実はJリーグでもそういうクラブが増えていっています。そういう面では公益法人を運営できないのは、Jリーグにふさわしいクラブにはなれないのか。あと、フェラインはソシオ制度にも似ていますね。また、このフェラインの存在価値は、日本でいうと後援会にもつながります。というと、後援会組織を運営できないところはJリーグクラブにふさわしくないという事なのかと。会員は単なるお客さんではなく、クラブを構成する一員。これは大事ですね。当ブログでよく言ってきた「チェック機能」も働いています。「横からものを言われたくないから後援会を作らない」という価値観があれば、それは極めて愚かなもの。自ら自分の成長を止めている行為で、とても100年は続かないでしょう。
あと、最近「Jクラブの付加価値」で取り上げてきた「ホームタウンミーティング」がまさに、上で言う「会員フォーラム」ですね。「会を開いてもらっている」「忙しいから誰も出席できない」と思っているところはしんどいなぁ。まさに「わしらファースト」。
このコラムでは「まずはJクラブで働くスタッフや、プレーする選手達の意識改革が必要」とありますが、読者の皆さんはどう思われますか? 「言いたい事をズバリ言ってもらった」なのか、「うちのクラブはフロントも選手も、しっかりファン・サポーターをリスペクトし、地域に根付いていますよ」なのか。
100年続く地域に根差した公共財となるJクラブになれるかどうかは、「帰属意識」がどこまで生めるかではないでしょうか。単にスタジアムに観に行くだけの存在をキープさせているだけではそのうち、時代の流れとともに消えていくのではないかと。あくまで一般論ですが。
「総合型地域スポーツクラブ・地域振興」カテゴリ:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/c/e0683bb785e8a608b9c7931217a72003
ドイツサッカー関連③(フェライン関連):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140724
〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140720
〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140711
研修会レポです。
昨日、三木記念ホールで開催された、おかやまスポーツプロモーション研究会(SPOC研究会)のシンポジウムに参加してきました。まずは、今朝の山陽新聞朝刊に「スポーツによる地域活性化探る 岡山でシンポ、事例報告や講演」というタイトルの記事です。以下、抜粋して紹介。

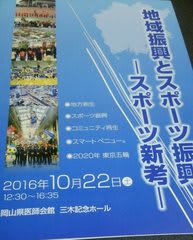
スポーツを生かしたまちづくりについて考えるシンポジウム「地域振興とスポーツ振興―スポーツ新考」(SPOC研究会、山陽新聞社主催)が22日に岡山市内で開催。約100人が参加し、事例報告などを通じてスポーツによる地域活性化の可能性を探った。
「地域に対してスポーツが果たす役割とは何か?」をテーマにしたパネルディスカッションでは、群馬県神流町観光アドバイザーの細谷啓三氏が、過疎高齢化が進む町に活力を生んだトレイルランの大会を紹介。島根県のNPO法人・出雲スポーツ振興21事務局長の矢田栄子氏は、体育施設の管理運営で得た財源でスポーツ教室の開催などに取り組んでいることを説明。本紙で今年1~6月に連載した企画「スポーツ新考 地域戦略を探る」を担当した久万真毅記者は、取材の成果を報告。
コーディネーターである岡山大大学院教育学研究科の高岡講師は「スポーツそのものに即効性があるのではなく、スポーツを起点に住民同士がつながり、意識が変わることで地域が変わる」と総括。細谷、矢田両氏は「自分たちは裏方に回り、多くの住民を頼って巻き込むことが重要」と強調。おかやまスポーツプロモーション研究会の梶谷代表や日本体育・スポーツ経営学会会長の柳沢和雄筑波大教授による講演も開催。シンポは県内の産学官民の有志でつくる同研究会の発足2周年記念事業。
山陽新聞該当記事:http://www.sanyonews.jp/article/435455/1/?rct=okayama_sports
三木記念ホールという事で、名前で検索して出た地図を元に岡山衛生会館へ行ってみるが、県民局の工事中のビルしかなく、こりゃおかしいと再度細かく調べてみると、岡山県医師会の方の三木記念ホールで西口でした。大幅な移動ロスで、少し遅刻して会場入り。梶谷会長さんの開会挨拶の真っ最中でした。できてまだ日が浅いのか、キレイなホールでしたね。このホールでも前座席の背中を出すとテーブルになり、セミナーにはうってつけの座席です。周りを見渡してみても、余り知った顔は無し。SPOC研究会のメンバーさんばかりなのかな。以前の時に行った時は、サッカー関係の方見かけましたが、今回はいなかったなぁと。人数もあの時の半分くらいでした。次はもう少し周知されてもいいのではと。
まずは梶谷代表からそのまま、オープニングセッションとして、「SPOC研究会の2年間とこれから」というタイトルで、2014年10月に発足してから2年間の活動報告です。いただいた立派なリーフレットにいろいろと書かれてありました。おかやま円卓会議とおかやま地域発展協議体という2つの組織の支援も受けるようです。この辺りはよくわかりません。
「同士の会」でご一緒する方がおられるので、こっそり行ったつもりでしたが、早速にMN氏に見つかってしました(苦笑)。何度も、「同士の会でAT氏と出会えて良かった。ありがとう」と言われております。やはり、マンパワーの結集がパワーを生み出すのですね。それは11年前の「一木会」の時からわかっている事です。読者の皆さんのほとんどは訳わからない話と思いますが、自己満足なのでわからなくていいです(笑)。


第2部はパネルディスカッションです。当ブログでもお馴染みの岡大T岡講師がコーディネータ役で、以下の3人のパネリストと演題です。
①「特集 スポーツ新考の取材を通して見出された地域とスポーツの幸せな関係」 講師:山陽新聞社特集班 久方真毅氏
②「神流マウンテンラン&ウォークが町にもたらした変化」 講師:群馬県神流町観光アドバイザー 細谷啓三氏
③「自立した組織が展開する地域スポーツ振興」 講師:出雲スポーツ振興21事務局長 矢田栄子氏
コーディネーター 高岡敦史氏
パネルディスカッションというよりは、個人的には3つの講演会という印象でした。3つの先進事例を聞いた格好ですね。出雲の団体はスポーツ庁が先進モデルと設定している規模の大きい総合型地域SCのようです。確かに大人数の雇用があるそうです。山陽新聞の話は確かに当ブログでも連載時はよく読んでいましたが、最後の方は行政側にかなりシフトした内容だったと記憶しています。マウンテンランの話を聞いていたら、去年だったかTVドラマで放送されていた「ナポレオンの村」を思い出してしまいました。最後に高岡コーディネーターが総括して、キーワードとしては「スポーツを拠点として、人がつながり変わっていく」という事を言われていました。


第3部の特別講演は、「<スポーツの振興>と<スポーツによる振興>の関係-生活者論の視角から-」という演題で、日本体育・スポーツ経営学会会長、筑波大の柳沢和雄教授のお話でしたが、これが一番面白かったです。前半ですが。
スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことでは、文化度が問われるようですね。そして、「鹿島の経験」という事でJ1鹿島がどのようにしてできていったかを詳しく解説されました。県立カシマサッカースタジアムの周辺20キロ圏人口は約27万人と、等々力競技場の1/50なのに、ホーム入場者数は'98年平均で約1万7千人で等々力よりも7千人多い状態。来場率は1万人対で636人で、等々力の10人の60倍だそうです。
J1鹿島の成り立ちは、まず貧困からの解放で工業地帯が作られ、開発が旧住民と新住民の格差を生んだ。街づくり懇談会が組織されたタイミングで、Jリーグから住友金属にプロリーグ参加意向の打診があった。地域と工業地帯で「サッカーによる町おこし」が生まれて、専スタを建設。その後田舎のままの道路事情の改善を図るために、日韓W杯で開催地に立候補して、インフラ整備を行ったとか。


なかなか堅苦しい内容で難しかったです。その柳沢教授の話の中で、一つだけ耳に留まった言葉があります。「中央と周辺の格差」です。スポーツ振興を図るのはいいが、中央だけ部分的に進めてはいけない、格差が生まれていい結果につながらないという内容。「岡山でも岡山駅西口でスポーツ振興を図ろうとされていますが、同じ話に思える」と、そういう言い方をされました。おやっと思いました。
つまり、岡山総合グラウンドのおひざ元である岡山駅西口、奉還町商店街の活性化を図っているが、東口も含めて全体で活性化を図るべきという話でしょう。当ブログでも「支援の第4の極である「商店・商店街」に対して、理想は奉還町だけでなく、岡山市商店会連合会等を通じて、表町など市全体の商店街を相手にするべき」とコメントしております。そういえば、この日も東口を歩いていた時に、「東口にはノボリとか、ファジの何も無いよなぁ」と思ってはいました。まあ、何が正解なのかは正直わかりません。


第2部にありましたが、スポーツによる地域振興、総合型地域スポーツクラブづくりも、民間主導型と行政主導型があると思います。今回のお話はどちらかといえば後者でした。スポーツによる地域振興ばなしは、当ブログも読者の方にとって範囲が広いと思って書いていますが、この日のパネリストのお話は更に広かったです。プロチームによる専門的なところから、一般市民のちょっとした軽運動まで切り口があると思いますが、どちらかといえば後者。当ブログでは切り口として、やや手の届きにくさを感じました。この辺りの部分はT岡講師とSPOC研究会の皆さんにしっかりお任せしたいと思います。当ブログではJリーグ百年構想など、もう少し専門的な切り口で関わっていきたいと思います。お疲れ様でした。
SPOC研究会(チーム岡山)関連⑪:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20160702
〃 ⑩:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150423
〃 ⑨:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150316
〃 ⑧:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150214
〃 ⑦:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141207
〃 ⑥:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141107
〃 ⑤:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141030
〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20091213
〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090819
〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090818
〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090227
今日、Cスタでファジのホーム金沢戦がありました。その模様は明日。
浅口レポです。
先日、浅口市内で開催された子どものスポーツ教室のお誘いを受けて、遊びに行ってきました。県のトップアスリート派遣事業を活用して、地域のまちづくり委員会が開催している教室で、今回初めて岡山シーガルズを招いて実施されたそうです。
会場は浅口市内の小学校体育館で、初めて中に入りましたが、とにかく大きい。市内でも一番立派な体育館だとか。早くから子ども達や父兄さんが参集されていました。


ほどなくして、シーガルズ登場。どの選手が来るのかと楽しみにしていましたが、神田コーチと3人の選手(№9:竹田、№23:東、№27:楢崎)でした。まずは開会式。主催者側の挨拶の後に、4人がそれぞれ挨拶をしましたが、どの選手もとにかく挨拶が上手い。今までの観たパターンは、一言二言ばかりでしたが、シーガルズの選手の挨拶はとにかく上手く、クオリティの高さを感じました。どの選手も場馴れしているなと実感。たぶん、巡回教室に回る選手はある程度決められているのかもしれませんが、それにしても上手かったなと。あれでこそ地域を代表するトップチームだなと。この日は寄島干拓地で市民体育祭があった関係で、浅口市長さんが途中から登場でした。


練習に入りましたが、ここでも上手さを感じました。まずは全員でランニング、しっかりとストレッチです。その間も選手から指導の声がかかる。よくどこのスポーツ教室でも見られるミニゲームは結局無し。ずっと実戦練習。2コートで半分半分で4ブロック。何と、レベルを4種類に分けて教えるのです。一番下のレベルは神田コーチ。自分でレベルを判定して、4人のどこに行くかは子ども本人が選ぶのですが、最初神田コーチのところの集まりが少なかったので、少し声をかけて形にされました。子供はやっぱ選手がいいのかなと思ってみたり。


上のグループの練習は横で観ている父兄が「すごい!」と口にするほどハード。レシーブでしたが、結構きついボールを打ってましたね。ただ、ボールに触って遊んでもらうのではなく、4人はそれぞれにマイクを手に途中何度も、説明を加えていました。
あれは教えてもらった子ども達も大きな収穫なのではないでしょうか。いいスクールだと思いました。ふと、毎年笠岡でシーガルズ主催で各地からバレー部員が集まって行う、大型合同合宿を思い出しました。こういうハイレベルで実りがある教室だから、あれほどシーガルズの「教え」を慕って、他県からも大人数が集まってくるんだなと。


閉会式で、選手に総評をしゃべってもらいましたが、これまた皆さん上手い挨拶。最後に参加チームごとに記念品(ミニタオル)贈呈です。子ども達はそのミニタオルを手にテーブルに列を作る。サイン会です。4人並んでサインをしていました。この光景を見ると、こういうスポーツ教室は選手が参加すべきで、教えてもらった選手に後でサインをもらってファンになり、今度試合を観に行こうと思うという好循環になるという。
もう一つ感心したのが、情報(開示)発信の早さ。すさまじい早さでした。3日後くらいには公式FBページに出ていました。何でもその週末はもう1つ開催していたのですね。聞いた話では、浅口地域には幼稚園とか、毎年?よく来ているとか。そうなんだと。
岡山シーガルズ公式FBページ「浅口教室①」:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1214513331944060&id=557416967653703
〃 ②:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1217014138360646&id=557416967653703


あれっ、そういえばこの教室は、ずっと何年もファジ(ネクスト)を招いてやっていたはずなのに、今年はシーガルズ? また違う機会で呼ぶのか。今度様子を尋ねてみるとしよう。確か、この事業は選手に来て欲しいんだよなぁと言われていた気がしますが・・・
公財)岡山県体育協会トップアスリート派遣事業ページ:http://www.okayama-taikyo.or.jp/dispatch/
子どものスポーツ教室in浅口関連⑧:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20151207
〃 ⑦:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141223
〃 ⑥:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20131122
〃 ⑤:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20130227
〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20111031
〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20101101
〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20091106
〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20081217
事例紹介コラムです。現在、山陽新聞朝刊に、もう何か月も続くシリーズもので「地域戦略を探る スポーツ新考」がありますが、ずっと読んでいます。最初の頃はファジやベル、シーガルズの紹介でしたが、そのうち長く岡山マラソンの特集、そして広く様々なスポーツが取り上げられました。そして最近は、当ブログでも以前に何度も紹介したきよねSC(きよね夢てらす)が登場しています。これも流そう。少し紹介してみます。


高梁川の河川敷の芝グラウンドは約3万㎡で、サッカーコート3面分に相当。総社市清音地区(旧清音村)の総合型地域スポーツクラブ(SC)「きよねスポーツクラブ」の活動拠点の一つで住民主導で運営するクラブのシンボル。元々は旧清音村が管理していたが、豪雨で水かさが増すたびに表土が流され、手入れが必要であったことが課題。
天然芝は住民有志が音頭を取り、’00年から3年がかりで手張り。作業には延べ1,700人が参加し、シート状の天然芝を設営。現在は、様々なスポーツの練習場として使用。業者に任せた方が安いが、自分達で作ったグラウンドだからこそ、より愛着を感じる事が大事と、住民組織のコメント。きよねSCの年間運営費1,600万円のうち、7割は自分達で工面。行政の補助が3割で済むのは、住民の支援があるから。
クラブハウス「きよね夢テラス」の管理は週末の2日間、住民有志37人が交代で実施。マネジメント会員で、年間1万円の会費を自ら負担して、この仕事を担当。報酬はクラブハウスの入り口に掲示される名札のみ。それでも「自分達のクラブハウスだから、自分達で守らないといけない」という意識が強い。岡山県内SCで唯一のクラブハウスの構造も、自分達で決定。全ての部屋に目が届くように、建物全体を八角形とし、部屋の仕切りをガラス製に。子ども達が部屋に閉じこもらずに交流して欲しいと、中央にはホールを設置。駐車場は300人のボランティアで煉瓦を敷き詰め、石積みの花壇も芝生の庭も、窓のカーテンも手作りし、建物名も自分達で命名。


「清音には住民のマンパワーがある。その熱意がクラブ経営の原動力になり、地域を元気にするというスポーツが持つ潜在的な力を引き出している」と元Jリーグ理事で広島経済大の藤口教授のコメント。
Jリーグが清音に注目する理由は、芝生の広場を作る事、好きなスポーツを楽しめるクラブを充実させる事、スポーツを通して世代を超えた輪を広げる事。で、Jリーグ百年構想に合致。「清音村の皆さん、緑の芝生はみんなの憩いの場所」と書かれた川淵元チェアマンの色紙が掲示されていると締めくくっています。
そして、今度は「目指せ 清音のコモンズ」というタイトルの記事です。とにかく、きよねSCの記事に関しては、読み応えがあるものを随時紹介していきます。以下、抜粋して紹介。


地域の課題と向き合い、住民のニーズを把握し、解決に向けて立ち上がる。日本の総合型地域SCのモデルとなった欧州のクラブでは、スポーツを楽しむだけでなく、子育てから青少年の健全育成や高齢者福祉といった社会問題にも取り組むケースが多い。岡山県内でもきよねSCが子育て支援事業を実施。
きよねSCの母体であるNPO法人が運営する「なかよし広場こっこ」。子育ての拠点を作る国の事業の県内第1号として’02年からから活動しており、清音夢てらす完成に合わせて入居。対象は0~3歳児と保護者や妊婦。子どもを無料で遊ばせ、育児相談にも対応。
きよね夢テラスから東へ1.5kmにある清音ふるさとふれあい広場の有効活用について、総社市からきよねSCで相談を受け、子ども達を外で自由に遊ばせる空間として公園に外遊びの基地を作る話が持ち上がったのが’14年。
順天堂大の黒須教授は「欧州のクラブは公益に貢献するコモンズ(共有財産)として認知。地域の課題に主体的に取り組むクラブが増えれば、社会に欠かせない存在になっていく。日本のクラブも『地域のコモンズ』を目指すべき」と指摘。この外遊びの基地は今春オープン。
という内容でした。まずは聞きなれない「コモンズ」という言葉。調べてみましたが、いいページが出てきませんでした。当ブログでは昔から「公器」「公共材」という言葉を長く使用してきました。最近では山陽新聞や村井チェアマンからも聞く言葉。まあ、どこが先に使ったのかは不明ですが。コモンズとは公共財という意味なのでしょう。
日本のクラブも「地域のコモンズ」を目指すべきとありますが、個人的にはここ数年増えた総合型地域SCが本当に公共財なのかと思える事があります。昔の記事で触れたように、総合型地域SCは、スポーツチームをピラミッドの頂点に置くJリーグで言う「総合スポーツクラブ」タイプと、行政主導でフラットな総合型地域SCタイプと2タイプあると言ってきました。それが8年ほど前の話。それから国の主導で総合型地域SCがあっという間に増えましたが、ほとんどが後者のようです。決して欧州、ドイツのようなクラブではないような気がします。自主運営にして行政の負担を軽減する目的の、極めて汎用的でフラットな組織です。それが果たしてドイツのようなスポーツ文化を作れているのか疑問です。
清音の事例は前者に近いと思いますが、県内に後者に近いクラブがどれくらいあるのかと思います。当ブログで後者の一番の理想とする先進モデルは、NPO法人 湘南ベルマーレSCです。岡山にも湘南さんみたいなクラブができないものでしょうか。また、きよね夢てらすで、当ブログの師匠、傍士さんにお会いしたいですね。
きよね夢てらす公式HP:http://kiyoneyumeterasu.jimdo.com/
きよねスポーツクラブ公式HP:http://kiyone-sports-culb.jimdo.com/
きよね夢てらす関連③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20121112
〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20121104
〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20070121
事例紹介コラムです。
まだまだ、異競技交流ネタが続きます。Jクラブが設立した総合型地域スポーツクラブですが、何年か前に紹介した時と比べて、大きく変化していました。クラブ数も増えたし、活動する種目も大幅に増えています。単にアカデミー部門を切り離したと思っていたクラブもいつの間にかサッカー以外の競技の教室をしっかりしています。サッカーだけしかできていないところは論外。クラブ内の事業で異競技をやっているところも素晴らしいですが、別法人にして、Jリーグ百年構想を実現しているところは最も素晴らしいです。クラブ名の横には当ブログの記事をリンクさせています。結構紹介していましたね。以下、抜粋して紹介。


【J1】
・湘 南: NPO法人 湘南ベルマーレスポーツクラブ: http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20060707
(J2湘南の下部組織を運営)
・C大阪: 一般社団法人 セレッソ大阪スポーツクラブ: http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20110226
(サッカースクール・育成機関事業を運営)
・神 戸: 一般社団法人 ヴィッセル神戸スポーツクラブ: http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20111229
(アクティブライフ、アスレチッククラブを運営)
【J2】
・札 幌: 一般社団法人 コンサドーレ北海道スポーツクラブ: http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140218
(サッカースクール、女子サッカーの他にトライアスロン、アイスホッケー、ミニバレーの他ウィンタースポーツなど多くの競技)
・山 形: 一般社団法人 山形県スポーツ振興21世紀協会: http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20121111
(アカデミーなどの運営、女子駅伝部)
・群 馬: NPO法人 ザスパスポーツクラブ: http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20130207
(下部組織、ジュニアゴルフ、剣道、フィットネス、幼児スポーツ、健康スポーツなど)
・東京V: 一般社団法人 東京グリーンスポーツリンク:
(サッカースクール、バレーボールやトライアスロン)
・横浜C: 一般社団法人横浜FCスポーツクラブ: http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20130221
(下部組織、女子サッカー、チアリーディング、卓球、ヨガ、英会話)
・松 本: NPO法人 松本山雅スポーツクラブ
(サッカーの普及活動)
・讃 岐: NPO法人 カマタマーレスポーツクラブ:
(バレーボール、ソフトテニス、チアダンス、キッズダンス、ヨガ、健康教室など)
・愛 媛: 一般社団法人 愛媛FCスポーツクラブ
(レクバレー、ヨガ、ストレッチ教室など)
・北九州: NPO法人 北九州フットボールクラブ
(下部組織、テニス、ソフトテニス、ラグビー)
・長 崎: 一般社団法人 V.V.NAGASAKIスポーツクラブ: http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150126
(ソフトボール、バレーボール、トライアスロン、テニス、ソフトテニス、硬式野球、バスケットボールなど)
【J3】
・鳥 取: NPO法人 やまつみスポーツクラブ: http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20121028
(J3鳥取の下部組織を運営)
こんな感じでした。J3クラブなど、まだ拾いあげきれていないところもあるかもしれません。漏れている情報があったら教えてください。Jクラブは、最初にJリーグ入りを目指すと、まず任意法人から公益法人に法人化します。その後、営利活動を行うということで株式会社化します。運営会社が株式会社となって枝分かれした後の、公益法人を廃止するのか、幽霊法人化してしまうのか、山形さんのように新たな使命を持って歩み始めるのかに分かれます。いまだに幽霊法人化したままのところが見受けられますが、アカデミー部門でも任せたらいいのにと思います。サッカーだけやってればいいというものではありません。
後発ですが、讃岐さんや長崎はいい動きですね。それにしても山雅さんはどういうテーマでも名前が出てきますね。やはり、J1昇格を目指すJ2クラブは山雅さんをお手本とすべきですね。「わしらが一番じゃ」ではダメでしょう。
Jクラブの総合型地域SC関連:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140218
事例紹介コラムです。
昨日の異競技交流の記事を書くために、各クラブの公式HPを見ていくうちに、いつの間にか久しぶりにレッズランドの公式HPに行き当たりました。2010年に実際に視察で行っておりますが、この5年間で競技が増えたなぁという印象です。5年前に行った時には無かったであろうという競技がいくつかあったので、リスペクトのためにも今回紹介させていただきます。


【セパタクロー教室】
東南アジア発祥のスポーツ「セパタクロー」の体験教室が昨年10月よりスタート。サッカーに通じる「蹴球」の一種で、「バトミントンコートで行う、バレーボールの足バージョン」。基本ルールは、3人対3人で対戦し、足を使って、ボールを3タッチ以内で、相手コートに打ち返すというスポーツ。
レッズランドでは昨年7月に開催した「スポーツ&ネイチャーフェスタ」で登場した時に好評だったため、サッカーやフットサルのボールコントロール技術向上にもつなげられること、スポーツとしてのセパタクローの普及・育成への想いなどから、このたび日本セパタクロー協会の全面協力を得て「教室」としてスタート。
・主 催: レッズランド
・協 力: 一般社団法人 日本セパタクロー協会
・日 時: 2015年10月~12月 毎月第1・3・5日曜日の15:00~16:30(90分)
※2016年1月以降の開催日は12月に決定。
・場 所: レッズランド内フットサル場
・対 象: 小学生以上(性別やレベルは問わず)
・募 集: 各回24名
・参加費: (1回・税込)1,000円⇒年内は体験期間として100円(保険代として)
・指導者: 矢野順也(日本セパタクロー協会アンバサダー)
※1995年~2003年まで日本代表。2002年、第14回アジア競技大会で銅メダル。以降、日本代表コーチ。
レッズランド公式HP該当ページ:http://www.redsland.jp/news/20150926-01.html
フットゴルフとは「サッカーボールを蹴ってゴルフをする」という事で、サッカー(フットボール)とゴルフ、この異なるスポーツを融合した新しいスポーツ。サッカーボールの5号球を使い、ゴルフコースで9ホール、または18ホールをラウンド。2009年にオランダでルール化されると、2012年にはハンガリーで第1回W杯を開催。欧米を中心にすでに30カ国以上で楽しまれており、急速に普及している注目のスポーツ。今月にアルゼンチンで第2回W杯が開催。
当日は、J1浦和で選手として活躍し、現在はクラブスタッフ、そして日本代表として今月開催のW杯に出場する堀之内聖選手が参加。レッズランドのフィールドに設けた体験コースは3ホール。このコースを使って、代表選手がプレーを披露。
・日 時: 2015年12月23日(祝) 13:00~15:00
・場 所: レッズランド内フリースペース
・参加費: 無料
・参加プレーヤー:堀之内聖(浦和レッズスタッフ/フットゴルフワールドカップ日本代表)及びフットゴルフW杯日本代表数名(予定)
レッズランド公式HP該当ページ:http://www.redsland.jp/news/20151219-01.html


【レディアの森プロジェクト】
2015年10月、レッズランドは施設内の魅力の1つである「デイキャンプエリア」「アグリフィールド」において、『みんなでつくろう!レディアの森プロジェクト』をスタート。このプロジェクトは子供たちからファミリー層まで老若男女を問わず、多くの皆さんが集い、交流し、コミュニケーションを図りながら、これからのホームタウンについて語り合って欲しいという想いから発足。
目的としては、老若男女を問わず多くの人々が交流し、コミュニケーションを図ることでホームタウンについて語らい、考え、レッズランドからこの地域の活力(幸せ)を発信。自然を体感してもらい、その活動を通じて、子供たちの健全な発育や育成をサポートしていくこと。 この日はレッズローズ等を使った「フラワーアレンジメント教室」を開催。教室のあとは、「レディアの森」へ移動し、レッズローズの植栽を実施。
また、レディアの森プロジェクトの第1弾としてデイキャンプエリアのオリジナルかまど作りがスタート。当日はレッドダイヤモンズ後援会のスチュワードが11名、同運営委員が4名、さらに今後のデイキャンプエリアを整備していく上で指導・アドバイスを担当する「ボーイスカウトさいたま南地区協議会」代表が参加。かまどができた後は、実際にかまどを使ってのBBQ体験。
レッズランド公式HP該当ページ:http://www.redsland.jp/rl_201510_redia_forest.html
という感じでした。レッズランドは2005年に開設されましたが、その式典で川淵チェアマン(当時)が感激して泣いたというエピソードがあるくらい、Jリーグの中で付加価値がかなり高い施設で、かつてのJリーグ百年構想を象徴するトップ施設です。確か開設当時に、テニススクールの講師をあのクルム伊達公子選手が務めていたのを覚えています。セパタクローにフットゴルフですか、スポーツ文化のトレンドをよく追われていますね。また、今度レッズランドに行ってみようかな。様々なJクラブの関係者さんが当ブログに観に来ておられると思いますが、騙されたと思って一度観に行ってみて下さい。「サッカーだけやってればええんじゃ」という価値観が変わると思います。
レッズランド公式HP:http://www.redsland.jp/
J1浦和関連:28 / 27 / 26 / 25 / 24 / 23 / 22 / 21 / ⑳ / ⑲ / ⑱ / ⑰ / ⑯ / ⑮ / ⑭ / ⑬ / ⑫ / ⑪ / ⑩ / ⑨ / ⑧ / ⑦ / ⑥ / ⑤ / ④ / ③ / ② / ①
レッズランド関連⑥:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20100208
〃 ⑤:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20100205
〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20080713
〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20060521
〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20050924
〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20050909
浅口レポです。
先日、浅口市三ツ山スポーツ公園多目的広場にて、まちづくり委員会(地元財界関係)主催による、子どものスポーツ教室が開催されました。今年も県体協を通じてファジアーノへ派遣要請がされたようですが、昨年に続いて今年も普及コーチが来られました。普及コーチの出前教室は通常事業であり、毎週火曜日に浅口市フットサル場で、普及コーチによるスクール浅口校が開催されているので、ごく普通の光景なので、記事にしなくても良かったのですが、もう7年もされているまちづくり事業なので、今年も記事にする事にしました。


今年はいつもの三ツ山スポーツ公園のメイングランドではなく、フットサル場の多目的広場での開催でした。いつものグランドでは地元のソフトボール大会が行われていました。委員さん達が参集され、受付がスタートしました。浅口地区のスポ少の子ども達が順番に集まってきました。そして、ファジアーノのコーチも登場。今回はコーチ、コーチ、コーチの3人です。
会場準備ですが、大人達(ご父兄も一緒に)で大人用ゴールを運びましたが、これが無茶苦茶重たい。昔ながらのゴールなのでしょうが、他の2つの子ども用ゴールを運ぶのかと思ったら、「コーンで代用しますので」と。すいません、田舎の旧式ゴールで。


委員長さんの開会あいさつで開会式スタート。続いてご来賓の地元女性教育長さんが挨拶されましたが、さすが教育者、女性でも覇気がありました。その後、コーチが紹介され、さっそくスクールがスタートです。
見覚えのある顔が登場。ファジボラであり、応援団・浅口のメンバーでもあるママさん、亀さん親子です。次男君が参加しているようですが、長男君はすっかり大きくなって、笠岡の高校生で来シーズンからファジボラにも参加する予定だとか。


ほどなくして教室は終了。閉会式です。コーチからの講評とともにPRタイムとして、「2015 2日間短期ウィンターサッカースクール」のPR説明がありました。内容は下にあるとおりです。
全員で集合写真を撮って終わりましたが、サイン会はありません。2年前までは最後にサイン会が行われ、子ども達がうれしそうに列に並んでいく光景がありましたが、何となく委員さん達の表情に「来年はシーガルズもいいな」という空気が流れていました。元々、子どものスポーツ教室は、サッカー競技に限定している訳ではなかったのですが、応援団・浅口のメンバーさんも何人もおられる関係で、ずっとサッカー競技でした。今年の委員会でも「女子バレーやバスケをやるのもいいのではないか」という提案が出されたと聞いています。個人的には来年もファジアーノでお話を伝えてはいますが、来年はどうなるのかなと。もし、シーガルズの選手達がやってくれば、おじさんばかりの委員さん達の目尻が下がるのは目に見えますね。そのためにも、もし来年ファジアーノであれば、ぜひ選手を派遣して欲しいですね。
【2015 2日間短期ウィンターサッカースクール】
・開催日: 12月25日(金)・12月26日(土)
・会 場: 岡山会場:ファジアーノフットサルパーク、倉敷会場:ヘルスピア倉敷
・クラス: 両会場とも U-6、U-8、U-10、U-12
・定 員: 各クラス:岡山会場で15名、倉敷会場で18名
・参加費: 一般生:4,200円(税込)、スクール生:3,800円(税込)
・条 件: 2日間の日程に参加可能
・参加賞: 修了証と記念写真を進呈
・期 間: 12月14日(月)必着
※詳細はクラブ公式HPを確認ください。
公財)岡山県体育協会トップアスリート派遣事業ページ:http://www.okayama-taikyo.or.jp/dispatch/
子どものサッカー教室in浅口関連⑦:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141223
〃 ⑥:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20131122
〃 ⑤:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20130227
〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20111031
〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20101101
〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20091106
〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20081217
















