この地の社名はの後ろに聳えるボンボン山に因んだものである。一説には四五尺に伸びた鹿の袋角をボボンという。この地でよく鹿を射たのでその名を採ったという。また、ボンボン渓岸に集団をなして住んでいることより社名が起こったという。
ボンボン村は遠い昔別の場所(詳細不明)から移住し、2010年で100年になるとのことで、2008年に訪問した時、この地に住み雑貨店を営む吉川さんは一大イベントを執り行いたいと意気込んでおられた。
この地にすむ原住民の方々が言う「神社」である梵梵大麻奉斎殿は大同郷英士村にあった。現在は梅園となっており、神社の遺跡を示すものは何も残っていない。神社の場所を案内して頂いたのは、この土地に住む顔阿清さん(日本名は山口君子、タイヤル族名はサビロキンで岩に咲く花という意味)であった。当地の梵梵教育所で6年生まで勉強し、結婚式は着物を着て神社前で挙式を挙げたと流暢な日本語で語って頂いた。
奉祭殿の廻りには派出所およびその宿舎があったとのこと。当時の教育所には日本から3名の先生が駐在所で勤務の傍ら教育所での教鞭を行っていたと語っておられた。当時、原住民を対象とする教育所などで、教師の職務は蕃地駐在警察官史の職務範囲に包括されていた。
今回の訪問で警察官の夫人が原住民の殖産を図るために田植えの指導も行ったとの話も伺えることが出来た。

神社はちょうど左崖下辺りにあった

ちょうど、この民家の裏になる

当時の梵梵大麻奉斎殿である
ボンボン村は遠い昔別の場所(詳細不明)から移住し、2010年で100年になるとのことで、2008年に訪問した時、この地に住み雑貨店を営む吉川さんは一大イベントを執り行いたいと意気込んでおられた。
この地にすむ原住民の方々が言う「神社」である梵梵大麻奉斎殿は大同郷英士村にあった。現在は梅園となっており、神社の遺跡を示すものは何も残っていない。神社の場所を案内して頂いたのは、この土地に住む顔阿清さん(日本名は山口君子、タイヤル族名はサビロキンで岩に咲く花という意味)であった。当地の梵梵教育所で6年生まで勉強し、結婚式は着物を着て神社前で挙式を挙げたと流暢な日本語で語って頂いた。
奉祭殿の廻りには派出所およびその宿舎があったとのこと。当時の教育所には日本から3名の先生が駐在所で勤務の傍ら教育所での教鞭を行っていたと語っておられた。当時、原住民を対象とする教育所などで、教師の職務は蕃地駐在警察官史の職務範囲に包括されていた。
今回の訪問で警察官の夫人が原住民の殖産を図るために田植えの指導も行ったとの話も伺えることが出来た。

神社はちょうど左崖下辺りにあった

ちょうど、この民家の裏になる

当時の梵梵大麻奉斎殿である

















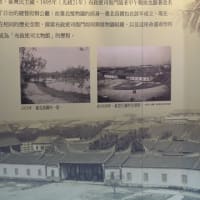







英士村の向こうの瑪崙に行ったことがありますか、そこも神社の遺跡があります。私のブログに写真があります。
http://iktshingna.blog132.fc2.com/blog-entry-787.html
コメント有難うございます。まだ私のブログでも紹介していない所ですが、初めて訪問したのは6-7年前でしょうか。その時は、廻りはうっそうとした草木で遺跡の存在さえ確認できない状態でした。私の好きな神社遺跡の一つでもあります。この名は「バロン社」と言い、神社は「濁水祠」と呼ばれました。
また、色々教えて下さい。
なお、このの近くには砲台があったようですが、おわかりでしたら教えて下さい。