年間ベストもやっているんだからオールタイムもやろうぜと数え始めたら、シリーズものを1タイトルに数えてもアッという間に100オーバー。こういうのは所詮は自己満足。考えているときがいちばんシアワセなんだヨ~といいつつ、ノンフィクションなど30タイトルほど削って100に納めてみました。
投票の結果ではない(脳内会議はしない)ので、順不同。「傑作/名作と思った」「読んで面白かった」「誰もが読むべき」というような基準ではなく、「文学的な評価とか世間的な評判はおいといて、自分が好きで何回も読み直している」という本のリストです。
なので「★★★★★」は買ってから最低5回は読み返しているという意味で、「★」は買ったときに1回読んだこっきりということになります。ただ20年前に買って3回読んだ本と、1月前に買って2回読んだ本だと2回の方が面白い本ということになりそうですね。(2013.01.01)
 「ベルガリアード物語/マロリオン物語」
「ベルガリアード物語/マロリオン物語」 デイヴィッド・エディングス ★★★★★
王道ファンタジーの定番。神話級の戦いと詐欺とユーモアにあふれた1冊。分厚くてもつい最初から最後まで一気に読んでしまいます。
「エレニア記/タムール記」 ディヴィッド&リー・エディングス ★★★★★
一癖も二癖もある騎士たちと女神と巫女と盗賊の英雄譚。マロリオンを読み終わって、そのまま勢いでこちらも最初から最後まで……。
「魔術師の帝国~リフトウォー・サーガ」 レイモンド・E・フィースト ★★★★
これも面白いけれど、やや固め。人死にが多いのも壮快感を欠く遠因かな。
「異世界の帝王」 H・ビーム・パイパー ★★★★★
平凡な警官が平行世界に飛ばされ、剣と銃の世界で大出世の北米版太閤記。主人公が未成年ではないだけで、やっていることはライトノベルと同じ。
「ニューヨークの魔法使い」 シャンナ・スウェンドソン ★★★
現代のニューヨークにも魔法使いや妖精がいるんだよという、ちょっとユーモラスなパラノーマル・ロマンス。
「ドラキュラ紀元」 キム・ニューマン ★★
ドラキュラがイギリスを支配した世界での切り裂きジャックもの。虚実入り乱れる多数の登場人物のからみが醍醐味。読むのにパワーが要る大作なので、読み直しは控えめ。
「アルテミス・ファウル」 オーエン・コルファー ★★★
犯罪組織の二代目は天才少年で、ひそかに人類社会を監視している妖精たちを利用して金儲けを企むという話。ライバルの天才少女が現れて、これからさらに面白くなりそう。児童文学枠だけれど角川文庫版も。
「ルーグナ城の秘密」 ピアズ・アンソニー ★★★★
英語文化圏のダジャレとボーイ・ミーツ・ガールでびっしり埋まったファンタジー「魔法の国ザンス」の3冊目。シリーズとしては飽きてしまったのだけれど、3冊目のこの話は今でも好きなので単体でカウントしてます。
「妖怪アパートの幽雅な日常」 香月日輪 ★★★★★
児童文学特有のお説教臭いところと息の抜けた笑いどころの組み合わせが絶妙なシリーズ。気軽に読める少年の成長譚。
「それがどうしたっ」 赤井紅介 ★★★
悪魔の少女に翻弄される少年と幼馴染みの少女の物語。いわゆるラノベ的な三角関係というより、藤子マンガの居候もの的な話。
「ドラゴンになった青年」 ゴードン・R・ディクスン ★★★★★
シリーズ化した続編やニコイチで作られたアニメ版はさておいて、突如として異世界に飛ばされた主人公が、同じく飛ばされて行方不明のガールフレンドを探すのだけれど、その過程でひとくせもふたくせもある仲間が集まり、最後は「ここは任せて先に行け」の王道パターン。
「コロボックル物語」 佐藤さとる ★★★★★
最初に読んだのは小学生の時。それから定期的に読み返しているけれど、今読んでも面白い。面白いのはやはり1冊目の「だれも知らない小さな国」から4冊目の「ふしぎな目をした男の子」までなのだけれど、コロボックル童話や「小さな国のつづきの話」も後日譚や外伝枝篇としては愉しく読めます。
 「ハルカ 天空の邪馬台国」
「ハルカ 天空の邪馬台国」 桝田省治 ★★★★
古代の邪馬台国に救世主として召喚されてしまった少年が、ヒミコの巫女である少女ハルカと共に戦う、ちょっとエッチなボーイ・ミーツ・ガールの異世界冒険譚。「炎天の邪馬台国」と合わせて2冊で完結。
「鴨川ホルモー」 万城目学 ★★★
今もなお京都市中の大学生によって継承されている、式神を操って闘わせるホルモーと呼ばれる奇妙な戦闘競技の物語。
「滅びのマヤウェル」 岡崎裕信 ★★★★
人が呼吸をしたり食事や睡眠を取るように、他の能力者を殺さないと生きていけない少女と男装の少女が同居する話。
「夏の鬼 その他の鬼」 早見裕司 ★★★
人ではないモノたちの姿を見ることのできる少女と仲間たちの日々の物語。都市伝奇。
「魔法科高校の劣等生」 佐島勤 ★★★★
魔法がテクノロジーとして浸透している社会で、おおやけの基準では劣等生としか分類できないけれど実戦・実務基準では優等生以上の主人公が、才色兼備の妹とイチャラブしながらテロリストやマフィアを殲滅していく学園小説。
「塵骸魔京」 海法紀光 ★★
今も世界の闇の部分に潜んでいる怪物たちと、それを狩る者たちの戦いに巻き込まれた少年の物語。18禁ゲームのノベライズで、ゲームでは深く語られなかった少女を中心に語られる。
「ドリトル先生航海記」 ヒュー・ロフティング ★★★★★
動物の言葉をしゃべれる獣医さんの冒険譚。お金に困ってサーカスをやるはめに陥ったり、巨大な蛾に乗って月まで冒険したり。
「鬼切り夜鳥子」 枡田省治 ★★★★
妖怪退治の陰陽師の霊に取り憑かれてしまった、元気な少女の妖怪退治話。とにかくよく脱ぐ。
「アレクシア女史、倫敦で吸血鬼と戦う」 ゲイル・キャリガー ★
行き遅れた貴族のお嬢さんがパラソル片手に吸血鬼や狼男を粉砕して回って女王陛下の拝謁を賜る、パラノーマル・ロマンス小説でスチームパンク。
「憑き物おとします」 佐々木禎子 ★★
幽霊が普通の人間に見えるようになってしまった日本で、霊障専門の保険会社に雇われることになった青年と、勝手に付いてきたイケメンの死神と、ゴスロリ守護霊の物語。
「百合×薔薇」 伊藤ヒロ ★
超能力を持った少女ばかりが集う女学校に潜り込んだ女装の少年が、お姉様と慕われるようになり、クラスのみならず学園を、やがては近隣の学園を束ねていく物語。男の娘版番長マンガのようなもの。
「はたらく魔王さま!」 和ヶ原聡司 ★★
勇者との戦いに負けて異世界に逃れた魔王が、ボロアパートで四天王の生き残りと同居しつつ、ハンバーガーショップでバイトしたりして地道に再起を図る話。
「駆逐艦キーリング」 セシル・スコット・フォレスター ★★★★★
第二次大戦のさなか、アメリカからイギリスまでの輸送船団を護衛することになった、駆逐艦キーリングのクラウス艦長の数日間の不眠不休の戦い。とにかく目玉焼きとコーヒーが欲しくてたまらなくなる話。
「レッド・オクトーバーを追え」 トム・クランシー ★★
冷戦時代、ソ連の新型原子力潜水艦<レッド・オクトーバー>が密かに叛乱を起こして消息を絶つ。ラミウス艦長の目的は亡命か、それともアメリカへの先制核攻撃か? 米ソの部隊が追跡を開始するが……。
「ナヴァロンの要塞」 アリステア・マクリーン ★★★
第二次世界大戦中の1943年、難攻不落の要塞に登山家キース・マロリー大尉指揮する特殊部隊が挑む。
「囮のテクニック」 ダドリ・ポープ ★★★★★
第二次大戦中、対潜水艦作戦本部に配属された元・駆逐艦乗りの物語。船団護衛とか暗号解読とかの基礎を叩き込んでくれる本。
「戦国鉄砲商人伝」 橋本忍 ★★★★
鉄砲商人から見た織田信長の物語。
「化物語」 西尾維新 ★★★
吸血鬼の力を得てしまった少年が、周囲の少女たちの遭遇する怪異にかかわっていく物語。本筋以外の余談が醍醐味。
「丘ルトロジック」 耳目口司 ★
オカルト肯定派の高校生集団が世界を革命しようとする話で、死屍累々。
「ソリッドファイター【完全版】」 古橋秀之 ★★★★
格闘ゲームにのめり込んでいる高校生が主役のゲーム小説だけれども、いちばん目立っているのがタケちゃん先生である。開発スタッフであろうとプレイヤーであろうとゲームにかける一途な思いは熱いのだ。
「千の剣の舞う空に」 岡本タクヤ ★★
MMORPGの世界で最強のプレイヤーをさがす青春ストーリー。その結末は身も蓋もなかったけれど。
「暴風ガールズファイト」 佐々原史緒 ★
マイナー球技にかける少女たちの青春ストーリー。ラクロスって面白いのね。2巻で終わるのが残念。
「マリア様がみてる」 今野緒雪 ★★★
女子校の生徒会を舞台にした成長物語。読み出すと癖になる。
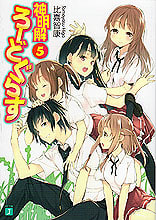 「神明解ろーどぐらす」
「神明解ろーどぐらす」 比嘉智康 ★★★★★
下校こそが人生のすべてという主人公が、とことんまで“下校”を追求し堪能して勝ち組になる話。
「ベン・トー」 アサウラ ★★★★
閉店間際のスーパーマーケットで、売れ残りの半額弁当争奪戦に命をかける狼たちの物語。レトロゲームのネタ多し。
「いとみち」 越谷オサム ★★★
本州最北端のメイドカフェでバイトすることになった、内気な女子高生と仲間たちの物語。
「俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた件」 七月隆文 ★★
ハイソな女性陣と庶民のカルチャーギャップを楽しむ話。
「のうりん」 白鳥士郎 ★★★
農業高校を舞台に、まっとうな農業問題をアニパロとオゲレツなシモネタをたっぷり振りかけて語るおバカたちの青春記。
 「ほうかごのロケッティア」
「ほうかごのロケッティア」 大樹連司 ★★★★
南の孤島で成層圏までロケットを打ち上げることになった高校生たちの物語。
「“文学少女”と恋する挿話集」 野村美月 ★★★
本を愛してやまない文学少女を中心に巻き起こる、恋のエピソードの数々を日常系ミステリのテイストで。
「子ひつじは迷わない」 玩具堂 ★★
生徒会に持ち込まれる謎の数々を解決することを期待されているのは、隣の部屋でごろごろしている文芸部の少女であったけれど……。
「夜は短し歩けよ乙女」 森見登美彦 ★★
「黒髪の乙女」に思いを寄せる「先輩」は、偶然の出会いを演出しようと彼女の姿を追い求めて大学内外を走り回るのだが、そこでさまざまな事件に遭遇してしまい……。
「アンの娘リラ」 L・M・モンゴメリ ★★★★★
赤毛のアンのシリーズの最終巻。ヨーロッパでどこかの国の皇太子が暗殺されたことをきっかけに大きな戦争が始まり、小さなカナダの町からも大勢の若者が兵士として旅立つこととなり……という状況下での銃後の物語。
「俺はまだ恋に落ちていない」 高木幸一 ★★
友人から「つき合ってみれば」と紹介された彼の妹2人は、美少女ながらなかなかの食わせ物だった……。
「クジラの彼」 有川浩 ★★★
自衛隊を主な舞台とした、激甘なラブストーリー短編集。
「にわか高校生探偵団~理由(わけ)あって冬に出る」 似鳥鶏 ★★★
フルートを吹く幽霊やらストーカーに追われる女子高生やら、たった1人の美術部員の葉山くんはしばしばトラブルに巻き込まれます。七転八倒したあげくに文芸部部長である伊神さんに助けを求めるのだけれど、彼はどうしてもっと早く呼んでくれなかったかと怒るのだ……。
「シアター!」 有川浩 ★★★★★
放漫経営で解散の危機にある劇団を、まっとうな金銭感覚を持つ社会人がテコ入れする話。
「ひきこもり探偵」 坂木司 ★★
テレビ化もされた、『青空の卵』からの始まる3部作の日常系ミステリ。引きこもりの青年とその友人の、どちらが依存しているのかいないのか分からない関係が、さまざまな事件が解決されていくうちに輪が広がっていく。
「赤朽葉家の伝説」 桜庭一樹 ★
地方の名家の興亡を、女三代の行き方を通じて描いた、ミステリ風に描かれた伝奇小説のような文芸作品。
 「大誘拐」
「大誘拐」 天藤真 ★★★★
最後の大仕事として大金持ちの老婆を誘拐しようとした3人組が逆に振り回され、国家と警察相手の大博打に引きずり込まれる話。「身代金はきりよく100億や! ビタ一文負からんで」
「ステップファザー・ステップ」 宮部みゆき ★★★
雷に打たれた泥棒が転がり込んだのは、親に捨てられた中学生の双子だけが住む家だった……。
「ワーキング・ホリデー」 坂木司 ★★★★
元ヤンキーにしてホストのヤマトの前に姿を現したのは、彼が存在すら知らなかった実の息子だった……。
ちょっとおばさんっぽい小学生男子と、元ホストで今は宅配業者となった男の不器用な家族の物語。
「ダディフェイス」 伊達将範 ★★★
インディ・ジョーンズかハムナプトラかというトレジャーハント・ストーリーにラブコメを載せてしまい、そこに年の差が9歳といういびつな親子関係をぶちこんだもの。メデューサ編で大長編化して大風呂敷を広げたあげくシリーズ途絶。読者は悶絶。
「信長新記」 佐藤大輔 ★★★★
織田信長が本能寺の変で死ななかったら……というIFものの先駆けにして金字塔。何度も何度も出版社を代えながら再版されるものの、これまた関ヶ原の戦いのクライマックスにてシリーズ中断。読者は悶絶。
 「マージナル・オペレーション」
「マージナル・オペレーション」 芝村裕吏 ★★★★
仕事を探していて傭兵になってしまったニート青年が、ひょんなことから面倒を見ることになってしまった少年少女を引きつれ、世界各地で傭兵稼業をしていく。子供に戦争なんてさせたくないけれど、それが現状でいちばんマシな「生きるための仕事」なんです。
「凶鳥」 佐藤大輔 ★★★
起死回生の秘密兵器を求めて、撃墜したUFOの回収部隊を送り込んだナチスドイツが、ゾンビと戦うことになる話。映像化したらB級ホラー戦争映画の決定版になりそうな予感。
「エンダーのゲーム」 オースン・スコット・カード ★★★
蜂型の異星人との戦いが続く時代。軍の教育施設に集められた幼い子供たちが、厳しい訓練とシミュレーション・ゲームの繰り返しの中から世界の未来を見いだす話。
「ガンパレード・マーチ」 榊良介 ★★★
幻獣と呼ばれる謎の敵との戦いに世界中が巻き込まれ、人類の勢力圏がわずかなものとなっている時代。極東の端にまで追い詰められた人類は、高校生を速成教育で前線に投入して時間稼ぎをする間に、軍の再編を試みているのだが……。
「遙かなる星」 佐藤大輔 ★★★★
キューバ危機から核戦争へと突入。米ソが荒廃してしまった中、かろうじて沖縄以外の被害を最小限にとどめることができた日本は、生存本能の赴くままに宇宙をめざした。宇宙は無限の可能性を秘めた開拓地ではなく、滅亡からのシェルターに過ぎない。かくして土木工事を進めるかのごとく、宇宙開発が推進されるのだが……。
「反逆者の月」 ディヴィッド・ウェーバー ★
月は巨大な宇宙船でした。遥か太古に銀河帝国の宇宙戦艦で反乱が起こり、今でも地上では地球人に紛れ込んだ異星人の反乱軍と船員の子孫たちが争い続けていたのです……。
「女子高生=山本五十六」 志真元 ★★★★
太平洋戦争を再現した巨大MMORPGが完成。授業の単位としても認められるということで学生もぞろぞろ参加。そんな中、日本陣営のリーダー的存在である山本五十六の中の人としてスカウトされたのは、女子高生だった……。
 「A君(17)の戦争」
「A君(17)の戦争」 豪屋大介 ★★★★
いじめられっ子のA君は異世界に召喚されてしまい、なぜか魔族の軍を率いて人間の侵略に立ち向かえといわれてしまう。いつも逆境に追い詰められると窮鼠猫を噛むとなるのがA君なのだが……。
「彩雲国物語」 雪乃紗衣 ★★★
彩雲国初の女性官吏となった秀麗の半生を描いた、大河ファンタジー官僚小説。おちゃらかなドタバタコメディとかロマンス小説のふりをしているけれど欺されてはいけない。最後の大団円までじっと我慢の大長編。
「翼の帰る処」 妹尾ゆふ子 ★★★
病弱で早く隠居したいと願う青年官吏が、なぜか本人の意に反して立身出世を続けるはめとなり、それに合わせて仕事の内容も量も激化していつも死にかけという大河ファンタジー小説。
「ダブルスター」 R・A・ハインライン ★★★★
次の太陽系政府選挙の結果次第では戦争も始まるという情勢下で、最有力の首相候補が誘拐されてしまう。当座の替え玉として抜擢されたのは、売れない役者のロレンゾだったが……。
「戦士志願」 ロイス・マクマスター・ビジョルド ★★★★★
帝国宰相の世継ながら戦士としては失格の烙印を押された少年が、傷心の旅行で次から次にトラブルに巻き込まれ、解決しようとするたびに話が大きくなっていき、ついには宇宙戦争に介入するはめに……。
「地球への追放者」 K・H・シェール ★★★★★
違法実験の罪で辺境の未開惑星に追放された科学者にして宇宙艦隊の提督が、その未開惑星<地球>に潜入している異星人の陰謀に気づくという、スパイアクション風SF。原子力戦闘機とかバンバン飛んでいるところに時代を感じます。
「太陽の簒奪者」 野尻抱介 ★★
女子高生が観測した天体現象は、異星文明による太陽簒奪計画の発端だった……という、清く正しいSFで、がちがちの理系ヒロインが活躍する話。
「首都消失」 小松左京 ★★★★
東京一円がいきなりドーム状の霧に覆われて連絡が途絶し、それによって生じた政治・経済・軍事的トラブルに残された人々が立ち向かう。
ラーゼフォンの東京ジュピターがそのまんま。政治・経済・軍事がメインなので、SFなのに科学的分析とか解決は二の次というのが特色。
「テクニカラー・タイムマシン」 ハリィ・ハリスン ★★★★★
タイムマシンを発明したから、過去の世界で映画を作ろう!という、セットを組むよりタイムマシンの開発に投資した方が安かった……という馬鹿話だけれど、タイムトラベルの基本は押さえたドタバタSF。地引き網で引き揚げた三葉虫でバーベキューパーティとか愉しそう。
「中継ステーション」 クリフォード・D・シマック ★★★★
アメリカの田舎に世捨て人のように暮らしている男は、実は銀河文明が星々の間を行き来するために使用している転送システムの中継ステーションの管理人であったが、いつまでも歳をとらない男に米国政府が気づき……。
「海底牧場」 アーサー・C・クラーク ★★★★
広場恐怖症で働けなくなった宇宙飛行士が、海底牧場でクジラの世話をしながら再起する。
「この胸いっぱいの愛を」 梶尾真治 ★★
航空機事故で過去の世界に飛ばされた人々の運命を描いた梶尾真治の短編「鈴谷樹里の軌跡」を映画化し、その映画をもとに長編小説化したもの。リリカルで時代を超えた恋愛小説。
「天のさだめを誰が知る」 D・R・ベンセン ★★★
宇宙船のトラブルから第一次大戦前夜の地球に遭難した異星人たちの地球体験記。ファーストコンタクト&仮想歴史もの。
「忠誠の誓い」 ラリイ・ニーヴン&ジェリー・パーネル ★★★★
単独で都市に匹敵する人口と機能を備えた巨大居住施設のスタッフが周囲との軋轢の中から妥協点を模索していく。
「星のダンスを見においで」 笹本祐一 ★★★★★
荒唐無稽なスペオペ時代の宇宙海賊話を正しく受け継ぎ、それに現代のハードなメカニックや艦隊戦闘の描写を組み込んだ傑作。
「時の果てのフェブラリー」 山本弘 ★★★
時空間に異常が発生し、外界と切り離されてしまった特異空間に挑む調査隊には、1人の幼い少女が加わっていた……。
「未来の二つの顔」 J・P・ホーガン ★★★★★
世界規模のインフラ管理を巨大コンピューターに任せてしまって大丈夫か? それを確認するため、スペースコロニー1つ丸ごと使用した実験が開始されたが、それはいつしか人間と人工知能の戦争となっていた。
「アンドロメダ病原体」 マイクル・クライトン ★★★★★
墜落した人工衛星から未知の細菌が拡散し、1つの街の住人がたった2人を残して全滅した。乳飲み子とアル中の老人。その共通点は何か? ワイルドファイア計画が動き出した……。
「星を継ぐもの」 ジェイムズ・P・ホーガン ★★★★
月面の洞窟から発見された死体は、有史以前の人間のものだと判明。彼は人間なのか。どこから来たのか。科学者たちが、その死の謎に挑む。
「竜の卵」 ロバート・L・フォワード ★★★
人類が初めて接触した知的生命は、高重力の中性子星上に誕生していた。調査船が地表を観測するために発したビームが彼らに与えた影響とは……。
「ドリームパーク」 ニーヴン&バーンズ ★★★★★
ホログラフィと役者が用意された大がかりなセットでは、今、南洋の宝探しゲーム、ライブRPGが始まろうとしていた。だが、その舞台裏では警備員が殺され、貴重な薬品が盗まれていた。犯人はRPG参加者の中にいる。
だが、ゲームは世界に中継され、その収益は会社に膨大な利益をもたらすため中止はできない。
「竜の歌い手」 アン・マキャフリー ★★★★★
移民先でトラブルに合って銀河文明から取り残された人々が、巨大な竜と竜騎士が惑星外から降り注ぐ糸胞の侵蝕と戦う大河小説の外伝的シリーズ。才能がありながら周囲に認められず阻害されてきた少女が、竪琴師の長に見いだされ才能を開花させていく中で居場所を見つける物語。
「サターン・デッドヒート」 グラント・キャリン ★★★★
太古に異星人が残したと思しき遺産争奪戦に駆り出されることになった考古学教授の冒険譚。平凡な学者が稀代の冒険家へと豹変していくプロセスを楽しみます。
「クジラのソラ」 瀬尾つかさ ★★
銀河文明からオーバーテクノロジーを与えられる代償は、コンピュータを使った宇宙艦隊戦ゲームの勝者を星の世界に送り出すこと。
今、今回のゲームに参加するため、世界中から強豪チームが集結する。
 「南極点のピアピア動画」
「南極点のピアピア動画」 野尻抱介 ★★
バーチャルアイドルとニコニコ動画によって生まれたのは星の世界への道。世界中どこにでも、民間だろうと公的機関だろうとVOCALOID“初音ミク”……ではなく、小隅レイの信奉者はいるのだ。
「虚船」 松浦秀昭 ★★
宇宙人の侵略から江戸の民を守る、空奉行の戦い。隠密同心+謎の円盤UFO。
「星虫年代記」 岩本隆雄 ★★★
世界中に降りそそいだ流星雨とともに出現した星虫と呼ばれる生き物は、人々の額にぴたりと張りつくと宿主の知覚能力を飛躍的に上昇させたのだが……。
「神の目の小さな塵」 ラリー・ニーブン&ジェリー・パーネル ★★★
人類の版図の外側から進入してきた謎の宇宙船の臨検に赴いた帝国戦艦<マッカーサー>は、その中から異星人の死体を発見する……。
「大宇宙の墓場~太陽の女王号」 アンドレ・ノートン ★★★
交易船に配属された若き船乗りの冒険。
「コンラッド消耗部隊」 リチャード・エイヴァリー ★★★★★
宇宙移民の最前線に投入される、高い能力を持ちながら使い捨てにされるのが前提の調査チームの冒険譚。
「サマーウォーズ」 岩井恭平 ★★★
映画の隙間を丁寧に埋めつつ再構成。
「海竜めざめる」 ジョン・ウィンダム ★★★
海底よりの侵略者は海月のような海底戦車で沿岸の寒村を蹂躙していくが、その魔の手は間もなく世界全土へと伸びていく。極地の氷が突如として溶け始め、海面が上昇を始めたのだ……。
「群青神殿」 小川一水 ★★★
原因不明の海難事故が続き、やがて世界中の海運が停止状態に陥ってしまう……。
「青い世界の怪物」 マレイ・ラインスター ★★★★
あの漁船だけ豊漁が続くのは何故なのか? その秘密を探ろうとレーダー装置の人気がうなぎ登りになるが、それはフィリピン近海に潜む虚空からの侵略の発端に過ぎなかった……。
「物理の先生にあやまれっ!」 朝倉サクヤ ★★★★
世界各国に出現した巨大ロボットがバトルロイヤルを繰り広げるはずが、なぜか主人公ハーレムになってしまう話。
「超妹大戦シスマゲドン」 古橋秀之 ★★
世界各国から集まった兄・姉が妹をコントローラーで操縦して戦わせるというバカ話。バカが一周して石川賢のゲッターロボみたいな宇宙大戦になってしまうのには言葉もなく。
「宇宙をかける少女」 瀬尾つかさ ★
アニメのノベライズだけれど原作を超えてます。
 明かなファンタジー世界ではなく現代社会やよく似た歴史上の場所を舞台としているのに、妖怪や幽霊や魔法による事件が起きていて、その存在を公権力が認識していて対策する部署を設置しているものを思いつくまま。
明かなファンタジー世界ではなく現代社会やよく似た歴史上の場所を舞台としているのに、妖怪や幽霊や魔法による事件が起きていて、その存在を公権力が認識していて対策する部署を設置しているものを思いつくまま。 「神のまにまに」
「神のまにまに」 「レイセン」 林トモアキ
「レイセン」 林トモアキ 「かみあり」 染屋カイコ
「かみあり」 染屋カイコ 「英国パラソル奇譚」 ゲイル・キャリガー
「英国パラソル奇譚」 ゲイル・キャリガー









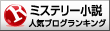
 「魔王ダンテ」永井豪(1971)
「魔王ダンテ」永井豪(1971) 異論のある人には申し訳ないけれど、この覚え書きでいうところの「ライトノベル」とは、「中高生を主な購買層として刊行されている文庫サイズの書籍で、表紙や本文イラストにそのとき流行のマンガやアニメ的な絵が採用されている」とパッケージ論として定義しています。
異論のある人には申し訳ないけれど、この覚え書きでいうところの「ライトノベル」とは、「中高生を主な購買層として刊行されている文庫サイズの書籍で、表紙や本文イラストにそのとき流行のマンガやアニメ的な絵が採用されている」とパッケージ論として定義しています。















 「ベルガリアード物語/マロリオン物語」 デイヴィッド・エディングス ★★★★★
「ベルガリアード物語/マロリオン物語」 デイヴィッド・エディングス ★★★★★ 「ハルカ 天空の邪馬台国」 桝田省治 ★★★★
「ハルカ 天空の邪馬台国」 桝田省治 ★★★★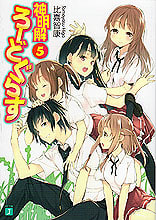 「神明解ろーどぐらす」 比嘉智康 ★★★★★
「神明解ろーどぐらす」 比嘉智康 ★★★★★ 「ほうかごのロケッティア」 大樹連司 ★★★★
「ほうかごのロケッティア」 大樹連司 ★★★★ 「大誘拐」 天藤真 ★★★★
「大誘拐」 天藤真 ★★★★ 「マージナル・オペレーション」 芝村裕吏 ★★★★
「マージナル・オペレーション」 芝村裕吏 ★★★★ 「A君(17)の戦争」 豪屋大介 ★★★★
「A君(17)の戦争」 豪屋大介 ★★★★ 「南極点のピアピア動画」 野尻抱介 ★★
「南極点のピアピア動画」 野尻抱介 ★★









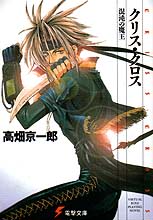



















 【1982】
【1982】









