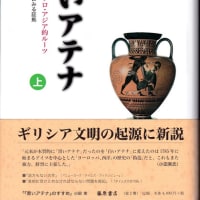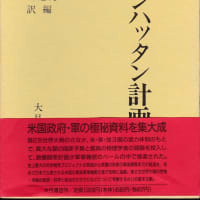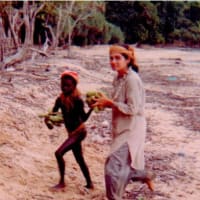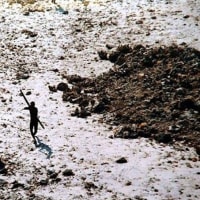▲ 白石太一郎 『考古学からみた倭国』 2009 青木書店 定価7000円+税
青木書店のホームページをのぞいても、この本の収録論文がわからない。大型書店が近くにあって、頁がめくれる大都市の人はいいが、この手の価格が高い本は、悩んだ末に、決断して買うのだから、もう少し出版元もサービスしてくれないとなぁ。
青木書店のホームページの著作案内に論文名を掲載するだけで、この本の売り上げは伸びるとおもうよ。
この本の目次
収録論文名
倭国の形成と展開
考古学からみた聖俗二重首長制
古代王権における女性の役割
山ノ上古墳と山ノ上碑の再検討
倭国王墓造営地変遷の意味するもの
百舌鳥・古市古墳群とヤマト王権
白鳥の帰るところ
古墳からみた継体朝の成立
王墓からみた倭王の性格
日本列島における国家形成と加耶
日本列島の文明化をめぐって
もう一つの倭・韓交易ルート
沖ノ島祭祀とヤマト王権
馬と渡来人
横穴式石室の誕生
群集墳としての高安千塚
前方後円墳の終焉
吉備における前方後円墳の終焉
備後の横口式石槨をめぐって
畿内との比較からみた関東の終末期大型方墳
叡福寺古墳の再検討
古墳の終末と古代国家
墓と他界観
須恵器の歴年代
近世の大名家墓所と古墳
妃たちの古墳
今城塚古墳の横穴式石室基礎地形
高松塚古墳の今後を考える
二十数年ぶりの関西
・
・
総頁557頁のボリューム感のある大冊になっている。
塙書房から刊行されている古代史関係の本は、著者のライフワークの集成という重厚長大な本に仕上がっているものが多く、従って価格は、相応のものとなる。1万円~2万円までのものが多いか。現役時代も買うのに苦しんだ塙書房の本だったのだが、その点、青木書店のものは、塙書房と比べればなんとか手に入る価格設定だ。
とはいっても、7000円+税であるから、7560円だ。半額程度に落ちてきたら買おうと、はやる心を抑えてはや●●年。
このほど、想定の範囲の価格で入手できることに。もっとも、大分前から六一書房では、安くなっていたのを知らないでいたのは迂闊だった。
上の論文一覧をみると、その都度白石太一郎論文に注意を払っていたつもりであったが、読んでいないものが圧倒的に多い。『考古学研究』、『季刊考古学』、『国立歴史民俗博物館研究報告』 『日本考古学』 を眺めている程度では、いまや情報収集はかなわず、畿内周辺の特別展示図録などにも留意しないと、あっという間に、考古学資料の鮮度が落ちて、賞味期限切れの発想で考えることになってしまうようだ。しかし老人の慰みといっても、常に後追いの姿勢に甘んじるのはちょいと癪に障るのだが。
資料の分析・使用法の原点に立ち止まって、情報過疎でも一発大逆転の歴史展望を拓けないのか?・・・と妄想老人は、日々、手元にある数少ない考古・歴史資料をこねくり回しているのだ。
古墳の年代論、年代決定論などについて、論文や発言も多く、古墳時代の開始については、考古学の分野では白石太一郎の早い時期から唱えていた年代観の方へ収斂していく流れがある今日、白石太一郎の著作は、都出比呂志、などとともに読み返したい論文が多いのである。
これで、白石太一郎の主要な論文集3点のうち2点
『古墳と古墳群の研究』 2000年 塙書房
『考古学からみた倭国』 2009年 青木書店
また『東アジアと江田船山古墳』 2002年 雄山閣などから、白石太一郎の6世紀前半、磐井の乱終結頃までの考古学論考が整いつつある。
古墳時代の祭祀・儀礼・文化史的分野は、『古墳と古墳時代の文化』を参照しなければならないが、これは、後日に果たすことにして、
これら白石太一郎と、
都出比呂志 『前方後円墳と社会』 2005年 塙書房
の考古学研究者二人
と
古代史文献研究者の二人の最近刊行の著作
前之園亮一 『「王賜」銘鉄剣と五世紀の日本』 2013年 岩田書院
鈴木靖民 『倭国史の展開と東アジア』 2012年 岩波書店
を私の中で、激突・脱史学化させ、今では死語化しているかも知れない「無意識的に前提している歴史認識の条件・要件の再吟味=脱構築」をはかり、無前提にしているかも知れない、「国家」という脱神話化されない謎を考えたいとも思う。この過程で、「国家の暴力の謎」も解かれるのではないだろうか。
国家という終着駅・終着点・終着社会を求めない、国家に抗する社会の視点が、古代史研究の歴史認識に存在してもいいじゃないか。
という、「いいじゃないか仮説」が、存在してもいいじゃないか!? こんな古代史が構想できるだろうか。
つづく
前日・前々日とgooにブログ記事をUPしているのだが、gooブログ・ジャンルの本の登録表示が出ない。見出し登録画像も表示もない。これは、何だろう? 『アメリカ帝国の悲劇』、『アメリカ帝国への報復』などという言葉と本の紹介は、禁句なのだろうか。米国の著名な研究者の著作であるのに。 摩訶不思議!? 有害語句としてフィルタリングされて、テロリズムを煽るような本であると勝手に機械が作動(誤解するようになっていて)、アップロードを阻止する力が働いているのではと推察されるのだが。何度も登録作業を繰り返したのだが、表示が改まらなかった。時間をかなり浪費してしまった。
フィルタリングというコンピュータ・セキュリティ・防御システムを利用して、読んではいけない本の現代版 「焚書」 が行われてはいないだろうか。ブログ更新された本の目次表示や、本の写真が、gooブログ更新枠に表示されないのである。これは、おかしい。