
雨の一日です。しばし大きな予定は無く淡々と仕事をこなしていく日々です。
名古屋と言うのは東京や大阪とは異なり町名が行政的に整理されていないため古来から残っている地名が多いのだそうです。またいわずと知れた織田、徳川、豊臣の3武将だけでなく加藤清正、前田利家、柴田勝家、山内一豊、福島正則といった名だたる武将の出身地と言うことで戦国時代の中心地であっただけでなく近世江戸時代を作った場所ともいうことが出来るでしょう。では名古屋そのものはどこから来ているかというと筆者は根古屋=豪族の根城から来たのではということ。また昔は波越と表記されていたこともあり潮が押し寄せる限界点であったのではないかと言う名残もありそう。もともと名古屋は土地自体が低く、名古屋駅の周辺も沼地であったようですがそんな名残も知名に内包していそうです。愛知の地名もあゆち=あゆ(東風)の吹く土地という可能性が高いとのことであるが実施のところはまだ色々と説はありそうです。
面白そうな地名としては
御器所(ごきそ)・・・熱田神宮に献上する陶磁器を作成した場所から 御器所八幡宮で長く手の戦い前に戦勝祈願をしたとか
道徳・・・尾張藩が農民に与えた田んぼの名前が道徳新田だったところから。道義を持って徳を施すように農業を奨励したことから
極楽・・・名古屋は元々庄内川や木曽川の氾濫に苦しめられており、山深からず水多からずのこの場所を極楽とした。
主税(ちから)・・・このあたりに屋敷を持っていた野呂瀬主税から。もともと主税というのは今の税務署のような存在でとても権力があったと言うことからちからと言う名前があてがわれたとのこと。
撞木(しゅもく)・・・鐘を鳴らす仏具の一種であるが町筋が行き止まり構造を持ったT字構造であることから
長者町繊維街・・・家康が清洲から名古屋に本拠地を移す際に長者が移り住んだ地域 明治以降の繊維産業の発展により問屋が集まるようになったためその名が残っている。
則武・・・もともとこのあたりを収めていた人物名に由来する名前ですがいまは陶磁器の代名詞に。
名古屋の市のマーク自体も丸に八で面白いと思います。終わり八郡がまとめられたからなど色々と説はあるようですが末広がりの八と言うのは縁起の良いマークであるように思います。

 | 名古屋 地名の由来を歩く (ベスト新書) |
| クリエーター情報なし | |
| ベストセラーズ |
名古屋と言うのは東京や大阪とは異なり町名が行政的に整理されていないため古来から残っている地名が多いのだそうです。またいわずと知れた織田、徳川、豊臣の3武将だけでなく加藤清正、前田利家、柴田勝家、山内一豊、福島正則といった名だたる武将の出身地と言うことで戦国時代の中心地であっただけでなく近世江戸時代を作った場所ともいうことが出来るでしょう。では名古屋そのものはどこから来ているかというと筆者は根古屋=豪族の根城から来たのではということ。また昔は波越と表記されていたこともあり潮が押し寄せる限界点であったのではないかと言う名残もありそう。もともと名古屋は土地自体が低く、名古屋駅の周辺も沼地であったようですがそんな名残も知名に内包していそうです。愛知の地名もあゆち=あゆ(東風)の吹く土地という可能性が高いとのことであるが実施のところはまだ色々と説はありそうです。
面白そうな地名としては
御器所(ごきそ)・・・熱田神宮に献上する陶磁器を作成した場所から 御器所八幡宮で長く手の戦い前に戦勝祈願をしたとか
道徳・・・尾張藩が農民に与えた田んぼの名前が道徳新田だったところから。道義を持って徳を施すように農業を奨励したことから
極楽・・・名古屋は元々庄内川や木曽川の氾濫に苦しめられており、山深からず水多からずのこの場所を極楽とした。
主税(ちから)・・・このあたりに屋敷を持っていた野呂瀬主税から。もともと主税というのは今の税務署のような存在でとても権力があったと言うことからちからと言う名前があてがわれたとのこと。
撞木(しゅもく)・・・鐘を鳴らす仏具の一種であるが町筋が行き止まり構造を持ったT字構造であることから
長者町繊維街・・・家康が清洲から名古屋に本拠地を移す際に長者が移り住んだ地域 明治以降の繊維産業の発展により問屋が集まるようになったためその名が残っている。
則武・・・もともとこのあたりを収めていた人物名に由来する名前ですがいまは陶磁器の代名詞に。
名古屋の市のマーク自体も丸に八で面白いと思います。終わり八郡がまとめられたからなど色々と説はあるようですが末広がりの八と言うのは縁起の良いマークであるように思います。











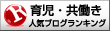


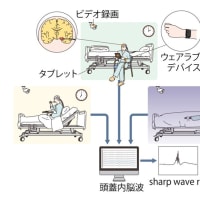

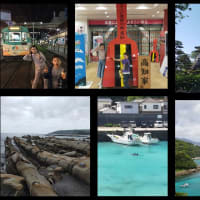
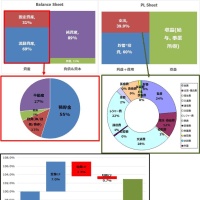











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます