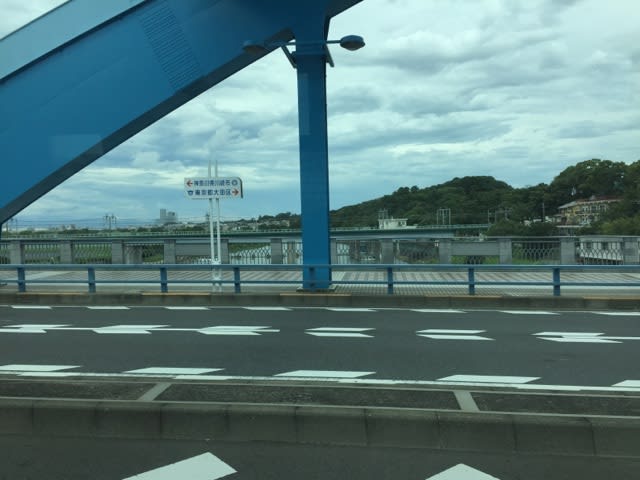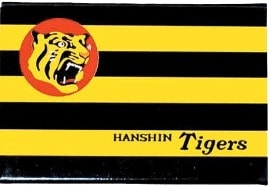以前にもブログで書いたが、ブログをやっているとテレビの影響が凄いことに驚かされる。最初は2016年10月TBS系のバラエティー『櫻井・有吉あぶない夜会』に俳優の織田裕二氏が出てきたときのこと。織田氏が取り上げたのが『シナモンガム』である。かつてはロッテの板ガムにもシナモン味があり、トライデントも発売していたのだが、現在は輸入品しかない、これはおかしいと言った内容で偶然OAを見ていた。

そして驚いたのは翌朝である。私はgooブログを使っているが、翌朝に前日のpv数(クリック数)とuu数(来訪者)が出る。通常はpvが300、uuが120人程度だが、その日はpvが917、uuが317と驚くべき数なのである。

まあ、この時は16年3月にまさに『シナモンガム』というブログを書いていたからである。しかし、その後、通販でシナモンガムを買った続編を書いたら現在も『シナモンガム ブログ』で検索すると私のブログが出てくる。

ところが、同じようなことがまた起きた。9月18日OAの『マツコの知らない世界』でステンドグラスが取り上げられた。駅のステンドグラスを紹介する際に持っていたテロップに『三鷹台駅』が載っていた。わずか10秒ほどしか出ておらず、出演者もコメントでは全く触れていないのに私のブログのpvが3369、uuが471と跳ね上がっていて、特に『三鷹台駅(1)』というブログを見た人が139と伸びていた。さらに『三鷹台駅 ステンドグラス』で検索するとまた私のブログが出てくる。
私のブログの読者も2年前からはかなり増加したが、やはりテレビの影響力の凄さを改めて実感した。