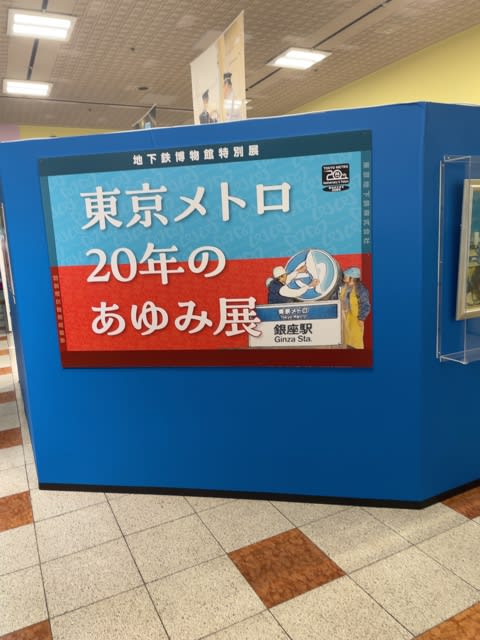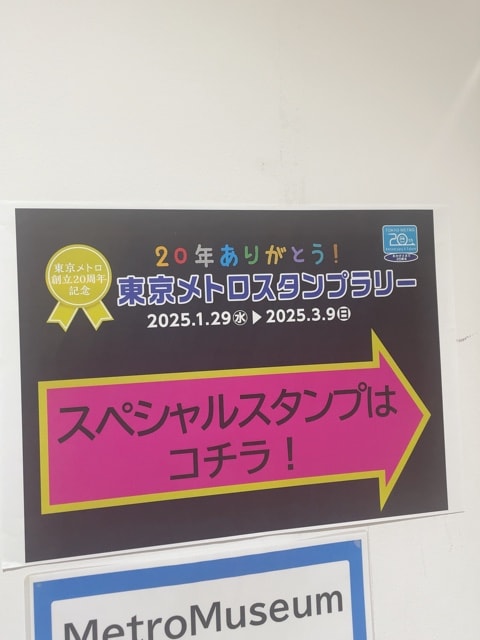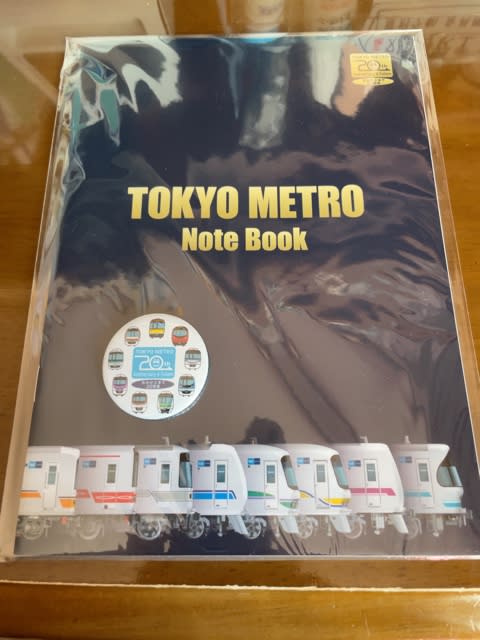『東京の坂、日本の坂』その235。峰岡町三丁目公園から坂を下ると左側に横浜新道の峰岡IC出口が現れる。ということは先ほどの公園はこの隧道の上にあったことになる。

再び坂道を登り、右に行く道を歩く。峰岡第二公園の先を右に曲がるが、これもかなりの坂道。登り切ったあたりが『峰坂』である。長いダラダラと続く下り坂である。この辺りの昔の地名が『大字雉子字峰』であったことが坂の名前の由来である。



少し降りたあたりに道祖神、横には横浜市が設置した標識、さらに自治会が設置した石碑が建てられている。『むかしこの道は八王子に通じた唯一の交通路でした。年貢米や生糸を馬の背に往来し、旅人は榎の木に馬を繋ぎ、休息したところです』とあった。


坂を降りていくうちにだんだん狭くなってくる。国道16号線に出るところには保土ヶ谷郵便局、隣は警察署など行政機関が集まっていた。さらにまっすぐ行き、雉子川を渡ると星川駅に到着した。



ここまでかなり歩いていたので流石に電車にて移動することにした。星川駅から2駅乗り、上星川駅で下車する。


まずは北口に降りてまっすぐいくと国道16号線、これを渡る。地図によると歩道橋の横の道をいくのあるのでまっすぐ緩やかな坂を登って行くと道がT字路となり、左は行き止まりのため、右にいく。

この辺りは崖が目の前にあり、さらにその上に家が建っていてよくこんなところに住むなあと思う。


左に登る階段はかなり荒れていて段々が崩れかけている。構わず登ると折り返すように続いているが段の横から草が生え、これは間違いだろうということに気づいた。


階段を降りて16号線まで戻る。歩道橋の下に左に行く違う道を発見、これを左に登り始める。先ほどのなかよし坂やレンガ坂もきつかったが、こちらも大したもの。折り返しながら登って行くため、どこが頂上かわからない。ただ、踊り場で休んでいると上から学生がたくさん降りてくるので多分学校があるのだろう。


小休止をしていた時にふと一軒家の表札を見ると『𩵋屋』とある。名前は『うおや』か『さかなや』と読ますのだろうが、珍しいためネットで調べても出てこない。かなりの珍名さんなのだろう。


この坂道が『釜台つづら坂』長さが450mあり、幅は住宅地開発に伴い8mに拡幅されているがきつい坂である。実際の曲がり角は4つ、255段ある。坂道の真ん中に電信柱が立っているのも珍しい。(以下次回)