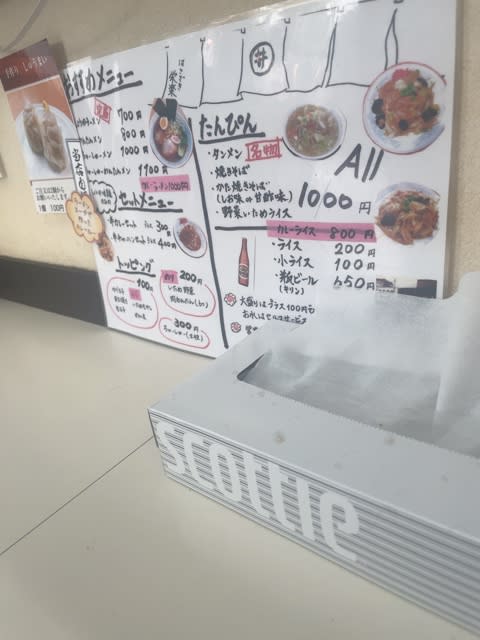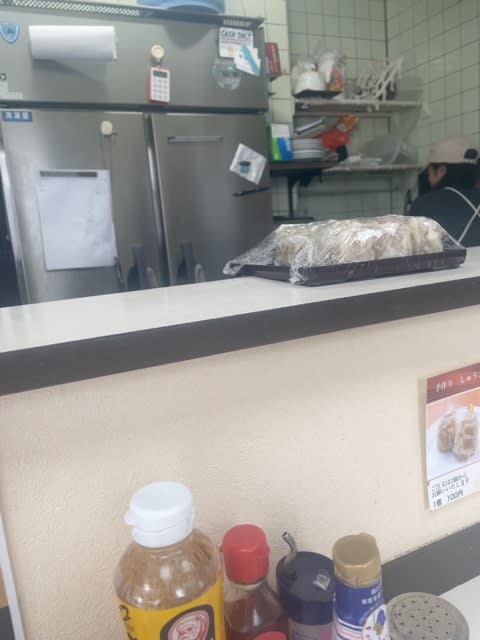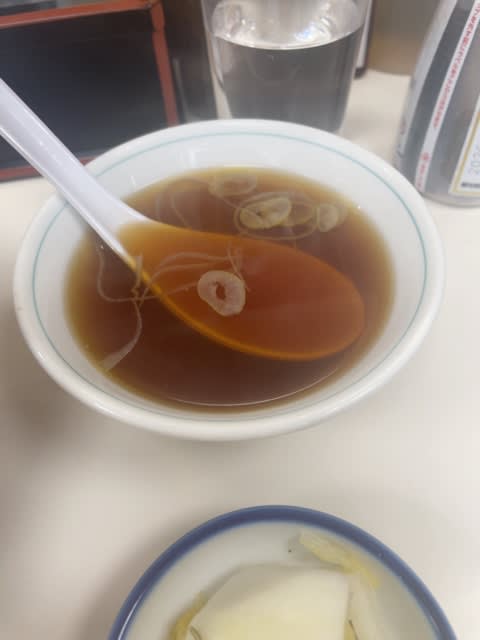^_^

神代植物公園は1961年に開園した都立植物園である。あまり歳を取ることに喜びも感じなくなったが、65歳以上になると入場料は250円と安くなる。入口で特に身分証などが求められることはないため、『65歳となる生年(例えば昭和33年、戌年など』を覚えていれば安く入場できることを最近知った。

園内に入るといつの間にか樹木の葉が若葉から青葉に変わっていることに気づく。春に咲いたたんぽぽが綿毛となって風が吹くのを待っている風景に遭遇する。

その数はとても数えられるようなものではない。ある小学校の調べによると一つの花から275個の種子が取れるとのことなので例えば100個の花らタネが飛ぶと27500個、それが風に乗って蒔かれるのだから、どれだけの数のたんぽぽが増えるのだろうか、などと考えてしまった。

バラ園に到着、やはり4月のうちは殆どのバラは開花していない。たまに花壇に咲いているバラの花もいいが、広大な敷地を一つずつ見て回る気もなく、藤棚の方に行く。



フジの花は今が盛りで紫色の花がブドウの房のように咲き乱れている。種類によって房の長さが違うようで『紫美短藤』はその名の通り花が短くまとまって咲く。白いフジもあってじっと観ていたが蜜を求める蜂や虻が多かった。



シャクナゲ園は白やピンク、赤などさまざまな色の花が咲き乱れて美しい。私のような素人には『シャクナゲ』『ボタン』『シャクヤク』の区別がなかなか付かないが、花をよく観るとツツジの花がぐるりと輪のように咲いているのがシャクナゲであることは理解した。


正門の方に歩くとツツジ園となる。美しく刈り込んだ木にさまざまな品種が花をつけ、一面に白やピンク、薄紫など様々な色の花が並ぶ。近年、1.5mほど高い展望台が設けられ、僅かな高さを上るだけだが、ドローンを使ったように眺めはいい。

少し戻るように歩くとボタン・シャクヤク園、ボタン(牡丹)の花を見ているといかにも中国風で艶やかだが、花もかなり大きくくどい感じもする。赤紫や黄色の大きな花を美しく咲かせていた。シャクヤクは数株が花を付けていたが、5月連休あたりには開花する花が多いのだろう。



正門近くでは山野草展が開催中。美しいが儚げな花が鉢に植えられている。私はオダマキやチシマリンドウのような紫色の花が好きだが、可憐に咲いていた。

野草のコーナーにはシャガやキエビネ、ホウチャクソウなどが大木の下草として咲いている。
(ホウチャクソウ)

(シャガ)


(ハンカチノキ)



下を見ながら歩くとスズランが白い可愛らしい花を付けている。近づくと良い香り、我が家にも咲いているが、愛らしい花である。

その先にはもみじ園、うめ園などがある。まだ、収穫には早いが青梅の子供たちを確認した。神代植物公園は歩いているとあっという間に5000歩は歩くことができる散歩には持ってこいの場所である。しかもこの時期は様々な花が咲いていて目も楽しませてくれる。
『元三大師像』にお参りし、深大寺そばを頂いた後、神代植物公園に向かう。途中には水車小屋やそば観音、滝などがあり、坂を上ると深大寺門が出てくる。

神代植物公園は1961年に開園した都立植物園である。あまり歳を取ることに喜びも感じなくなったが、65歳以上になると入場料は250円と安くなる。入口で特に身分証などが求められることはないため、『65歳となる生年(例えば昭和33年、戌年など』を覚えていれば安く入場できることを最近知った。


園内に入るといつの間にか樹木の葉が若葉から青葉に変わっていることに気づく。春に咲いたたんぽぽが綿毛となって風が吹くのを待っている風景に遭遇する。


その数はとても数えられるようなものではない。ある小学校の調べによると一つの花から275個の種子が取れるとのことなので例えば100個の花らタネが飛ぶと27500個、それが風に乗って蒔かれるのだから、どれだけの数のたんぽぽが増えるのだろうか、などと考えてしまった。


バラ園に到着、やはり4月のうちは殆どのバラは開花していない。たまに花壇に咲いているバラの花もいいが、広大な敷地を一つずつ見て回る気もなく、藤棚の方に行く。




フジの花は今が盛りで紫色の花がブドウの房のように咲き乱れている。種類によって房の長さが違うようで『紫美短藤』はその名の通り花が短くまとまって咲く。白いフジもあってじっと観ていたが蜜を求める蜂や虻が多かった。




シャクナゲ園は白やピンク、赤などさまざまな色の花が咲き乱れて美しい。私のような素人には『シャクナゲ』『ボタン』『シャクヤク』の区別がなかなか付かないが、花をよく観るとツツジの花がぐるりと輪のように咲いているのがシャクナゲであることは理解した。



正門の方に歩くとツツジ園となる。美しく刈り込んだ木にさまざまな品種が花をつけ、一面に白やピンク、薄紫など様々な色の花が並ぶ。近年、1.5mほど高い展望台が設けられ、僅かな高さを上るだけだが、ドローンを使ったように眺めはいい。


少し戻るように歩くとボタン・シャクヤク園、ボタン(牡丹)の花を見ているといかにも中国風で艶やかだが、花もかなり大きくくどい感じもする。赤紫や黄色の大きな花を美しく咲かせていた。シャクヤクは数株が花を付けていたが、5月連休あたりには開花する花が多いのだろう。




正門近くでは山野草展が開催中。美しいが儚げな花が鉢に植えられている。私はオダマキやチシマリンドウのような紫色の花が好きだが、可憐に咲いていた。


野草のコーナーにはシャガやキエビネ、ホウチャクソウなどが大木の下草として咲いている。

(ホウチャクソウ)

(シャガ)

(キエビネ)
シダレザクラの先はユリノキのような巨木、近くには遠くからハンカチを振っているように見えるハンカチノキが大きな白い苞葉を揺らせていた。中国産で珍しいことから『植物界のパンダ』の異名がある。
シダレザクラの先はユリノキのような巨木、近くには遠くからハンカチを振っているように見えるハンカチノキが大きな白い苞葉を揺らせていた。中国産で珍しいことから『植物界のパンダ』の異名がある。

(ハンカチノキ)



下を見ながら歩くとスズランが白い可愛らしい花を付けている。近づくと良い香り、我が家にも咲いているが、愛らしい花である。


その先にはもみじ園、うめ園などがある。まだ、収穫には早いが青梅の子供たちを確認した。神代植物公園は歩いているとあっという間に5000歩は歩くことができる散歩には持ってこいの場所である。しかもこの時期は様々な花が咲いていて目も楽しませてくれる。