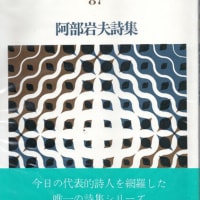現代では、ゆくりなく見えるすべてのことは〈ゆくりなく見えるようにつくられた〉ものにすぎないのであり、それに気づかないふりをするしか、〈ゆくりなく見えるようにつくられたもの〉を楽しむすべはない。そこには驚きも感動もない。映像はたんなる確認行為でしかないのである。
(辺見庸『私とマリオ・ジャコメッリ』p. 77)

アレッサンドラ・マウロ編
『MARIO GIACOMELLI――黒と白の往還の果てに』
(青幻社、2009年)

辺見庸
『私とマリオ・ジャコメッリ――〈生〉と〈死〉のあわいを見つめて』
(日本放送出版協会、2009年)
図書館の書架の間を行きつ戻りつし、読みたい本を探しあぐねていたとき、写真に関する本でもいいかと思いついた。人並みに一眼レフで写真を撮るのだが、最近、もう少しいい写真が撮れないかと考えることもあったからだ。
写真の分類の書架に「辺見庸」の名前を見つけて思わず手にしたのが『私とマリオ・ジャコメッリ』という本である。マリオ・ジャコメッリという人物を全く知らなかったのだが、「生と死のあわいを見つめて」という副題そのものは、辺見庸という作家がずっと主題としていたことに思えて、なんでこのコーナーにあるのかと訝りながら手にしたのだった。この本は写真家ジャコメッリに作家辺見庸が共鳴しえたもろもろが書き記されているらしいので、「ジャコメッリ」で検索して『MARIO GIACOMELLI――黒と白の往還の果てに』という大判の写真集を見つけ、辺見庸本と一緒に借りだした。
まず辺見庸の『私とマリオ・ジャコメッリ』を読み、作家の言葉をたよりに写真集を眺めたのである。私は、写真芸術(ないしは芸術写真)という領野にほとんどなじみがない。だから、この2冊を並べて読み、眺める機会が得られたというのは、私にとってとてもいい偶然、幸運な偶然だった。
まず、辺見庸の次のような言葉を肝に銘じつつ、写真を開く(以下、『私とマリオ・ジャコメッリ』からの引用は『私と……』とページ、『MARIO GIACOMELLI』は単にページのみを記す)。
フォトグラフ(photograph)という外国語に「写真」という訳語をあてたのは、日本人にとって不幸なことであった。写真とはすなわち〈真を写す〉の謂だが、これほど政冶的であり、また罠でもあるような名辞もないだろう。なぜなら、映像(写真)提示されればただちに、「これは現実に存在するものを写したのにちがいない」という思いこみがわれわれに生じるという仕掛けが、写真という名辞と装置のなかにあらかじめ組みこまれているからである。 (『私と……』、p. 18)

《自然についての認識》1977-2000年、マルケの野(p. 51)。

《自然についての認識》1977-2000年、マルケの野(p. 56)。
写真集は、ジャコメッリの風景写真で始まる。《自然についての認識》や《大地の物語》という農地のシリーズと、《わが物語の海》という海浜のシリーズである。前者は耕された農地の畝が幾何学的な印象を与える写真がほとんどで、後者は海水浴場や小さなボートの浮かぶ海岸縁を上空からまっすぐ下に見下ろした写真で、いわゆる風景がというよりは風景を用いた「コンポジション」と称される抽象絵画のような効果を与えている写真群である。
これらの作品には自然そのものと言えるような風景はない。人間によって耕された大地であり、小屋や海水浴客のパラソルが並ぶ砂浜がジャコメッリの自然ということのようだ。言ってしまえば、ジャコメッリは人間が深く関与した自然をどう表現するかに腐心したように見えるのだ。自然といい風景といいながら、ジャコメッリはそこに写し込まれた人間の存在を抽出しようとしているのではないか。たしかに、これらの写真群は、自然が持つ抽象絵画的な美を切り取って見せてはいるが、その美には人間が関わっているということが主題から外せないのではなかろうか、そう思う。
どこが抽象だというのか! 私が愛するジャコメッリのなかには、私がもっとも偉大だと思えるジャコメッリのなかには、悲劇的夢想性は現実の責め苦を礎とし、彼のリアリズムは視覚の威力の申し子なのだ。 (p. 163)
私は「抽象」という言葉を使ったが、フェルディナンド・シャンナは上のように力説している。いくぶん、日本語としての(訳文の)構造が分かりにくいが、ジャコメッリにおける「視覚の威力」に異論をはさむつもりは毛頭ない。シャンナの言う「リアリズム」は目に見えたままを写し取るリアリズムではなく、主題の実相のリアリティの強度について言っている。
辺見庸は「視覚の威力」をジャコメッリの「眼=カメラ」として、現実から主題を抽象するジャコメッリの創作方法について述べている。
かれはカメラにも、ましてそのメカニズムにもさほどの興味を示さない。なぜなら、かれにとってのカメラはかれ自身の眼だからである。その眼=カメラによって、自分の主観に映ずるなにものかのイメージを現実空間からすくいあげて画像として抽象してゆく。ジャコメッリは撮るのでなく、眼で描くのだ。それがジャコメッリの創作方法である。 (『私と……』、p. 100)

《庭師の妻》1956年(p. 76)。

《ロレート》1958年(p. 92)。
辺見庸は、ジャコメッリを「写真家」とカテゴライズすることに異を唱え、「映像作家、映像作品と呼ぶべき」(『私と……』、p. 19) と主張する。実際、ジャコメッリは主題表現のため様々な手法を駆使している。それは、例えば、自分の写真を「フォトショップ」で加工することすら「リアリズム」の棄損とためらってしまうような凡庸な私(たち)の写真のまったく異なった極にある。
「われわれが分析しているイメージはかなりの確率で複合プリント、二つの異なるネガから得られたフォトモンタージュ」(p. 82) とパオロ・モレッロは指摘するが、決してその技法ばかりではない。
たとえばかれは、重ね撮りや意図的な手振れなどの技法はもちろん、映像上にものも貼りつければ、絵筆で絵や模様まで描いた。自分の眼をカメラだと考えていたかれは、自身の眼にとりこんだ、あるいは自身の眼に浮かんだイメージを〈表現〉するためには、なんでも平気でやったのである。古典的な、もしくはナイーブな写真芸術家なら、ジヤコメッリの映像を〈写真〉とはおそらく認めないだろう。 (『私と……』、p. 93)
しかし、私のような「古典的な、もしくはナイーブな」一観者にすぎない者にとっても〈写真〉と名指しうる作品もある。それは、上の《庭師の妻》であり《ロレート》シリーズに含まれる作品などである。
《庭師の妻》はジャコメッリの母親であるというが、使い込まれて先端が光り輝く象徴的な鋤、それと並ぶ農婦の表情、そして手前に置かれた太く力強い右手のそれぞれの存在感が圧倒的なリアリズムとしてある。一方で、この作品はきわめて主情的な表現主義のようにも思える。この写真は、ジャン・フォートリエの初期作品である《管理人の肖像》に描かれた老嬢の前に組まれた手を思い出させる。それは小柄な婦人像に似つかわしくないほどの大きく強調された手であった。
「時間」と「死」がジャコメッリの写真に通底するものだと語るのは、辺見庸ばかりではなく、表現は違っても『MARIO GIACOMELLI』に抄録された評者たちも同様である。母親の手も、古い鋤の先端の輝きと不均等な磨滅の様子、農作業で鍛えられつつも荒れていく手、すべてが凝縮された時間としてピン止めされている。
《ロレート》シリーズはおそらく「ロレートの聖母」で知られる巡礼地での撮影だと思われる。グエルチーノの絵画《ロレートの聖母を礼拝するシエナの聖ベルナルディーノと聖フランチェスコ》では二人の聖人が礼拝しているが、カラヴァッジョの《ロレートの聖母》では貧しい身なりの巡礼の男女が描かれている。ジャコメッリの写真はそれぞれに人生を抱えた巡礼の人々が疲れた体を休めている情景で、いわばカラヴァッジョの「ロレートの聖母」から聖母子像と巡礼者の祈りの姿をあえて外すことで、現代の人生の疲労と苦悩を浮き彫りにするようなリアリズムを獲得している。中央に並んで座っている二人の婦人の眼差しに捕らえられて目が離せないのである。

《ルルド》1957年(p. 89)。

《死がやって来ておまえの目を奪うだろう》1954-1968年、セニガッリアのホスピスでの撮影(p. 101)。

《死がやって来ておまえの目を奪うだろう》1954-1968年、セニガッリアのホスピスでの撮影(pp. 102-3)。
《ロレート》シリーズもそうだが、病や身体的障害の恢復の奇蹟を信じて巡礼する人々を写し取った《ルルド》シリーズや、セニガッリアのホスピス施設を撮影場所とした《死がやって来ておまえの目を奪うだろう》シリーズに(私にとっての)ジャコメッリらしさがよく顕われているように思う。
ルルドもまた巡礼地なのだが、巡礼路の周辺の情報を一切消し去って、奇蹟を信じて集まってくる人々の列のみを写しとって(映しだして)いる。《ルルド》シリーズには病める人の肖像のような写真もあるが、どちらかと言えば、集まった巡礼者の集団の映像に主眼が置かれているように思える。ベッドに横たわる人も含めた巡礼者の大集団が祈りを捧げている光景を写した1枚は端から端までびっしりと人ばかりで、その地の情報は何も与えられていない。主題は「人間」であり、その「生」と「死」である。
《死がやって来ておまえの目を奪うだろう》というシリーズの作品は、どれも私には衝撃的なものだった。私は102歳で死んだ母親を看取り、今は112歳と高齢の妻の母と暮らしている。しかし、肉親や身近な老人を私(たち)が見つめることとジャコメッリのホスピスの住人へ向ける凝視とは大いに異なっているようだ。
もともとジャコメッリの母親がこのホスピスで洗濯婦として働いていて、少年時代から出入りを続けていることでこのシリーズの撮影が可能になったとされている。しかし、「時間」を紡ぐことすら覚束ないほどに「死」が目前にある人びとを対象としてこのような「時間」と「死」をイメージとして形作るのは、決してそのような撮影条件によるのではなく、ジャコメッリの過酷なまでに凝視する眼の力であるに違いない。
死の床にある老女とその場所から立ち去るかのごとく配置された黒ずくめ(または黒い影だけ)の人で構成された1枚は、「ホスピスの生活」の写真のなかでも「もっとも名高いもの」とパウロ・モレッロは評して次のような解説を与えている。
中央下に年老いた女性の顔を、そしてそのまわりをぐるりと取り囲んだほかの女たちの、何人かは座り、ほかはゆっくりと遠ざかってゆく黒い影を見せる。前景の女性は頭をハンカチでおおい、目を蘇り、唇は力なく開かれている。その顔のトーンは蠟のようで、血の気がない。もちろん女性はまだ生きている、が、伝わってくる想念は、最後の息をひきとる瞬間は遠くないだろうというものだ。ジヤコメッリはこの程なき旅立ちの、すでに無形化しつつある、薄れゆく軽さの――そしてすなわち、魂の表現の――想念を、技術的には多重露出によって表している。 (p. 81)
辺見庸は自らの臨死体験を踏まえて、写真家は死にゆく者たちを見ているが、死にゆく者はまたこちらをよく見ているのだと語る。そして、ジャコメッリのこれらの作品群は、ジャコメッリ自身が死にゆく者たちの側から見ているのではないかと言うのである。
「死にゆく人間の意識の側から撮っている」と私が感じたあの一枚は、おそらく、〈見る—見られる〉の相互的関係、あるいはその弁証法にかれが気づいていたことの証ではなかろうか。
かれは被写体であるおばあちゃんの意識の側から撮った。少なくとも、そのように撮ろうとした。そして結果的に、生と死のあわいを、「生に依存した死、死に依存した生」という神秘を埋めこんだ映像をつくりあげたのである。 (『私と……』、pp. 66-7)

《スカンノ》1957年、アブルツッォ州スカンノでの撮影(pp. 146-7)。

《スカンノ》1959年、アブルツッォ州スカンノでの撮影(pp. 148-9)。

《スカンノ》1957年、アブルツッォ州スカンノでの撮影(pp. 146-7)。

《スカンノ》1957年、アブルツッォ州スカンノでの撮影(p. 157)。
辺見庸の評言の中で私が最も感銘を受けたのは、ジャコメッリの創造する世界は「識閾」と呼ばれるべき領野で展開しているというものである。
私はジャコメッリのほとんどの映像に知覚心理学などでいう識閾のような心的領域を見ている。識閾とは、なにかに気づくかどうかの意識の境目であり、人間の意識が生起し、あるいは逆に消失していく境界でもある。そこでは意識は薄く、きれぎれでありともすればすぐにもとぎれそうになっている。そこはまた、はしなくも潜在意識や記憶の驚くべき古層がかいまみえたりもするところであり、映像芸術にとっては淡水と海水がまじわるがゆえにさまざまの魚たちがあつまってくる汽水域のように謎めいた〈意識の秘境〉だ。そんな識閾をだれよりも感じさせるジャコメッリの映像に、私はいやおうなく惹きつけられる。 (『私と……』、p. 30)
ジャコメッリの「潜在意識や記憶の驚くべき古層」は私たちのそれと通底しているだろう。だから、それは、誰にでもある「時間」と「死」を通じて形成された識閾となっていて、スティグレールが語る「象徴」[1] と同じように私たちの共感の根拠となっている(スティグレールの象徴よりももっと意識の深い領野にも思えるが)。
《スカンノ》のシリーズは、古い習慣や風俗を残している小さな村スカンノの人々を写したものである。それぞれに重ね撮りやモンタージュの技法が施されている写真は、明らかに異様な(視覚的に違和のある)映像でありながら、デジャブのような懐かしさも醸成している。辺見庸は、中央の少年だけに焦点があっている一枚を、これは〈異界〉の映像であり、「いまだ知らぬあの世のデジャヴ」を見ているのだと評している。
「スカンノの少年」の映像は、ジヤコメッリによってとらえられた〈あの世〉であり〈これから見る夢〉であり、〈まぼろし〉なのである。 (『私と……』、p. 9)
村の石畳の坂道を上る牛と数人の人はどこか茫洋としていて、振り返った少女の顔だけに焦点があっている一枚には、こんな夢をどこで見たことがあると思わせる効果がある。見知らぬ背景も登場人物もぼんやりとしているが、たった一人の人の顔だけがありありと思い出せるほど鮮明な夢、そんな夢を本当に見たかどうかじつは記憶にはないのだが、よく見る夢のように思えてしまう。これこそが「識閾」の象徴的共有性なのではないか。

《良き大地》1964-1966年、マルケの野 (pp. 176-7)。
辺見庸は、ジャコメッリの作品にはあまりキリスト教の影響を感じないという趣旨のことを述べているが、私は《良き大地》というシリーズ名そのものにキリスト教を感じた。写真集の最初に集められていた写真シリーズの「自然」は耕された農地のことであり、《良き大地》で描かれる世界も農地とそこで働き、暮らす人々を描いている。この大地は、聖書で語られる豊穣の大地、惠みの大地のイメージである。
ジャコメッリ自身は、キリスト教的精神性を写真表現に明示的には持ち込んでいないのはたしかだと思うが、イタリアの地に根付くように続いたキリスト教文化は意識されざるままに「識閾」の中の背景をなしているのではないかと思われる。しかし、辺見庸がジャコメッリの写真に見る「聖性」は、個別的な宗教を越えてすべての人間において同等である「死」を通じて獲得されたものに違いない。
映像から読みとるかぎりにおいて、ジャコメッリの死生観は、そこに立ち会った人間でなければわからないようなおそろしさを秘めていると私は感じる。それは、人間的とか非人間的とかいう問題ではない。そのような、いってみればありきたりのヒューマニズムではない。そのような次元を突きぬけたところにしか、かれは関心をもっていなかったとおもわれる。ジャコメッリが惹かれたのは、死にゆく人間がつかの間放射する〈聖性〉のようなものだったのかもしれない。
いまわの際にある者の聖性。ジャコメッリはたしかに死にゆく者の幾人かを聖人のように撮った。 (『私と……』、pp. 68-9)
誰にでも例外なく訪れる「死」によって生まれる共有性こそが、私たちが芸術作品を通じて共鳴しうる根拠なのかもしれない。そして、じつは私(たち)の貧しさが無意識的に「死」を避けてしまう日常的頽落に基づいているだろうことも確かなことのように思われる。
[1] ベルナール・スティグレール『象徴の貧困』(新評論、2006年)。
街歩きや山登り……徘徊の記録のブログ
山行・水行・書筺(小野寺秀也)
日々のささやかなことのブログ
ヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)
小野寺秀也のホームページ
ブリコラージュ@川内川前叢茅