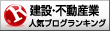これ
初めて飲みましたが美味しいですね。

屋久島の焼酎だそうです。
ここ数日
毎晩飲んでます。
どんな味かって?
まぁ芋焼酎の味です
これでは読んでる人は分かりませんよね
実は私は実際には酒の味は良く分かりません。
でもこの酒が美味しいと言ってる
矛盾してますよね
でも私の中では矛盾はしていません
この酒は美味しいのです
ただし
私が美味しいと思うのは
酒その物ではありません
私はこの焼酎をくれた人の心
これを美味しいと感じてるのです
滅多に手に入らない焼酎だから
そう言って
友人が私に持って来てくれました
だから美味しいのです。
私は酒だけでは無く
料理も味は良く分かりません
高い料理も安い料理も
大差が無い
私の味覚はその程度です。
でもどうやら
これは私だけでは無いようですね
先日ある料理番組で
有名な料理人が言っていましたが
料理は味より見た目
だそうです。
だから
高い料理は器にこだわり
綺麗な盛り付けをする訳です。
女性で言えば
化粧をして高級ブランドの服を着れば
美人に見られる
あれと一緒って訳です。
しかしそうやって考えると
女性は大変ですよね。
歳を取れば
見た目を維持するために
服も化粧品も
ますますお金がかかりますからね。
その点私たち男は
もう見た目はあまり気にする必要もありません
ダサイおやじ
その評価に甘んじてますから
毎日楽に生きています。
料理の話に戻すと
美的感覚が磨かれていれば
見た目の美しさで料理が美味しいと感じる
どうやらこれが高級料理の本質かも知れません
その意味では
美的感覚に乏しい私は
特に高い料理を食べる必要も無い
って事になり
経済的にも楽になります。
ただ
私は見た目には無頓着ですが
人の心
これに対しては大変敏感です。
長くこの仕事をしてきましたので
結構人間の内面が見えるようになっています。
だから
私は今回のお酒のように
それに心が加わると
大変美味しいと思う訳です。
私の友人で
大手の会社をリタイヤした人が言っていました
もうこれからは
食事は美味しい物しか口にしない
と
まぁそれはそれで良い事だと思いますが
私自身は
もうこれからは
本当に心の通じる人たちとの時間
これを大切にする
そう思っています。
そうは言って
仕事柄あまり人の好き嫌いも言っていられませんが
少なくとも
付き合って苦痛を感じる人とは
もう仕事もしなくなりましたね。
先日もある知り合いから土地の売却の話をいただきましたが
忙しいから他に頼むように言いました
良く知ってる人ですが
良く知ってるだけに
トラブルになるのが分かってるからです。
なんせ客が付けば
値段を上げて来る人ですからね
若い頃は無理して付き合いましたが
今はもうそんな気持ちはありません。
This is the shochu
first time I've had this,
but it's delicious.
It's shochu from Yakushima.
I've been drinking it every night for the past few days.
How does it taste?
Well, it tastes like sweet potato shochu.
That all
I'm sure readers won't understand
Actually, I don't really know the taste of alcohol.
But I'm saying this shochu is delicious.
That seems like a contradiction, doesn't it?
But to me, it's not a contradiction.
This alcohol is delicious. However, what I find delicious is not the alcohol itself.
It's the heart of the person who gave me this shochu.
My friend gave me this
saying that
It's a rare shochu, so I bring this to you
. That's why it's delicious. +
I don't know much about alcohol, but I don't know much about food either.
There's not much difference between expensive and cheap food.
That's the extent of my taste.
But it seems I'm not the only one who thinks this.
A famous chef said on a cooking show the other day
that food is more about appearance than taste.
That's why expensive food is carefully prepared with beautiful dishes
For women, it's the same as if they put on makeup and wear high-end brand clothes and are seen as beautiful.
But if you think about it like that, it's tough for women, isn't it?
As they get older, it costs more and more money to maintain our appearance, both in clothes and cosmetics.
In that respect,
we men don't have to worry so much about our appearance anymore.
I accept my appearance is poor and we live comfortably every day.
Going back to the topic of cooking,
if you have a refined aesthetic sense,
it seems that you can appreciate food because of its visual beauty.
This may be the essence of fine cuisine.
In that sense,
I, who lack an aesthetic sense, don't need to eat particularly expensive food,
which makes things easier financially.
However, although I don't care about appearances,
I am very sensitive to people's hearts.
I've been in this job for a long time,
so I've gotten to see the inner workings of people quite well.
That's why I think that when heart is added to it, like with this shochu
it tastes really good.
A friend of mine who retired from a major company said that
from now on, he will only eat delicious food.
I think that's a good thing,
but from now on,
I will cherish the time I spend with people who truly share heart.
but because of my job,
I can't really say what I like or dislike,
but at least I no longer work with people who make me feel pain when I'm with them.
The other day, an acquaintance approached me about selling land,
but I told him to ask someone else because I'm busy.
I know the person well,
I know that it will cause trouble.
After all, he is the kind of people who will raise the prices if we find customers.
When I was younger,
I forced myself to be with them,
but now I don't