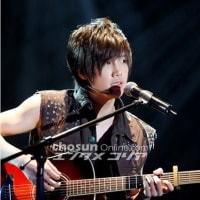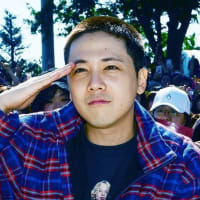原発はなぜ日本にふさわしくないのか 竹田恒泰 小学館
本の紹介をするにあたって、本の著者の背景も伝えなければならないと思うようになりました。
この本の著者は、「日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか」というベストセラーを最近著した、明治天皇の玄孫にあたります。
この本の導入部に、素敵なエピソードがありました。
著者の友人が新潟から、震災直後にトラックをチャーターし、米などの支援物資を積んで被災地に向かったときのエピソードです。
行政に預けるのではなく、自分たちでもっとも困っている避難所に物資を届けようと、とある小学校に着いたとき、「うちの避難所はまだ物資が足りているほうなので、もっと困っているところに運んでほしい」と断られたというのです。これが11ヶ所続き、12ヶ所目に、本当に困窮している避難所にたどり着き、空腹の避難民に炊き出しをすることができたとか。
この友人が新潟に帰りついた後でテレビを見たら、「足りている」と断ったいくつかの避難所が映し出されていて、どこも物資が足りないと報道されていたというのです。足りているという状態は、せいぜい1日ひとり当たりおにぎり1、2個の状態のことだったそうです。それでも、より困っているところがあるはずとボランティアの物資を譲り合ったというのです。
わたしはこのエピソードにぐっと捕まれて、原発反対という著者の本題に引き込まれてしまいました。
読み終えた読後感は、堤未果さんの「ルポ貧困大国アメリカ (岩波新書)」を彷彿させました。
堤さんの本では、高待遇の研究所に勤めることのできた科学者が土壌調査を行っていたら、そこは核実験で放射能汚染された場所だったなどと、アメリカの知られざる暗い部分をあぶりだすような本でしたが、この本も同じです。
日本でも、社会の弱者である失業者やドヤ街に暮すホームレスに、高待遇の仕事を斡旋したようにみせかけて、実は被爆の可能性のある原発の除染作業にあたらせているという実態があるというのです。原発は定期的に検査を行うため、その検査のたびに科学者等が入れるように、弱者が除染作業に駆り出されているとか。使用済みウランの処理方法についてや、日本はウランを輸入していますが、輸出国ではやはり原住民などが発掘しているなど、社会的弱者の犠牲によって支えられている原発の事情が明らかにされています。
著者の意図をおおざっぱにいうと、弱者の犠牲に成り立つ日本の和や美に合わない原発は、日本にふさわしくないので、日本が世界に先立って、原発を廃止していこうというものです。そういう未来もいいかもと考えさせられる本でした。
本の紹介をするにあたって、本の著者の背景も伝えなければならないと思うようになりました。
この本の著者は、「日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか」というベストセラーを最近著した、明治天皇の玄孫にあたります。
この本の導入部に、素敵なエピソードがありました。
著者の友人が新潟から、震災直後にトラックをチャーターし、米などの支援物資を積んで被災地に向かったときのエピソードです。
行政に預けるのではなく、自分たちでもっとも困っている避難所に物資を届けようと、とある小学校に着いたとき、「うちの避難所はまだ物資が足りているほうなので、もっと困っているところに運んでほしい」と断られたというのです。これが11ヶ所続き、12ヶ所目に、本当に困窮している避難所にたどり着き、空腹の避難民に炊き出しをすることができたとか。
この友人が新潟に帰りついた後でテレビを見たら、「足りている」と断ったいくつかの避難所が映し出されていて、どこも物資が足りないと報道されていたというのです。足りているという状態は、せいぜい1日ひとり当たりおにぎり1、2個の状態のことだったそうです。それでも、より困っているところがあるはずとボランティアの物資を譲り合ったというのです。
わたしはこのエピソードにぐっと捕まれて、原発反対という著者の本題に引き込まれてしまいました。
読み終えた読後感は、堤未果さんの「ルポ貧困大国アメリカ (岩波新書)」を彷彿させました。
堤さんの本では、高待遇の研究所に勤めることのできた科学者が土壌調査を行っていたら、そこは核実験で放射能汚染された場所だったなどと、アメリカの知られざる暗い部分をあぶりだすような本でしたが、この本も同じです。
日本でも、社会の弱者である失業者やドヤ街に暮すホームレスに、高待遇の仕事を斡旋したようにみせかけて、実は被爆の可能性のある原発の除染作業にあたらせているという実態があるというのです。原発は定期的に検査を行うため、その検査のたびに科学者等が入れるように、弱者が除染作業に駆り出されているとか。使用済みウランの処理方法についてや、日本はウランを輸入していますが、輸出国ではやはり原住民などが発掘しているなど、社会的弱者の犠牲によって支えられている原発の事情が明らかにされています。
著者の意図をおおざっぱにいうと、弱者の犠牲に成り立つ日本の和や美に合わない原発は、日本にふさわしくないので、日本が世界に先立って、原発を廃止していこうというものです。そういう未来もいいかもと考えさせられる本でした。