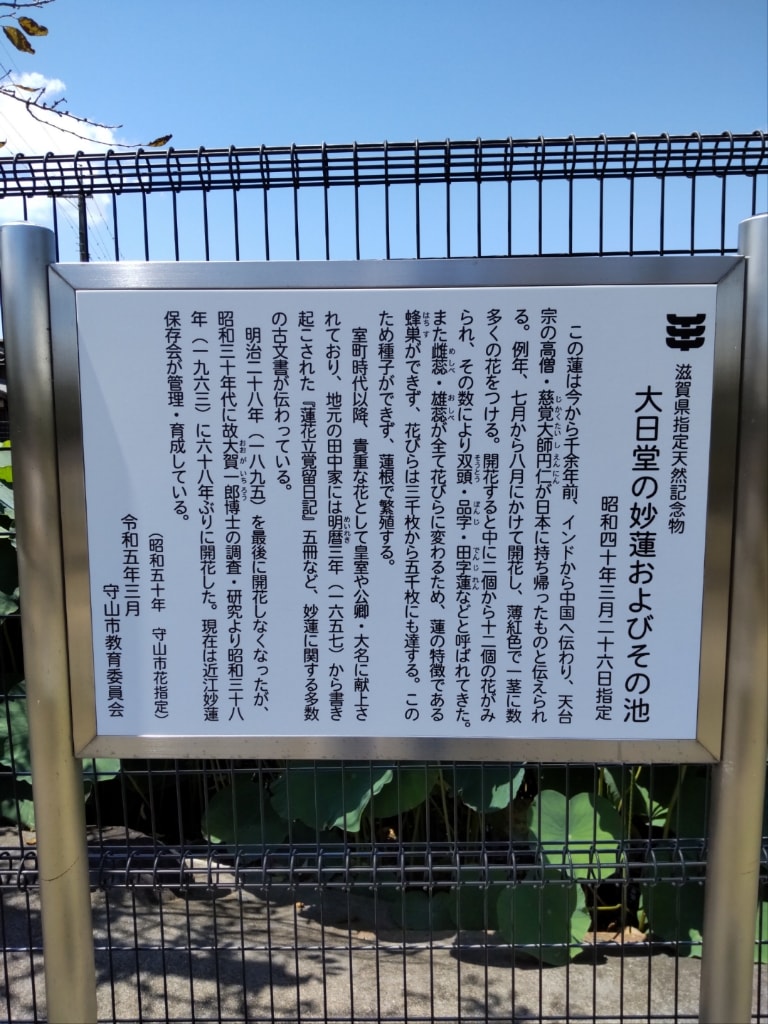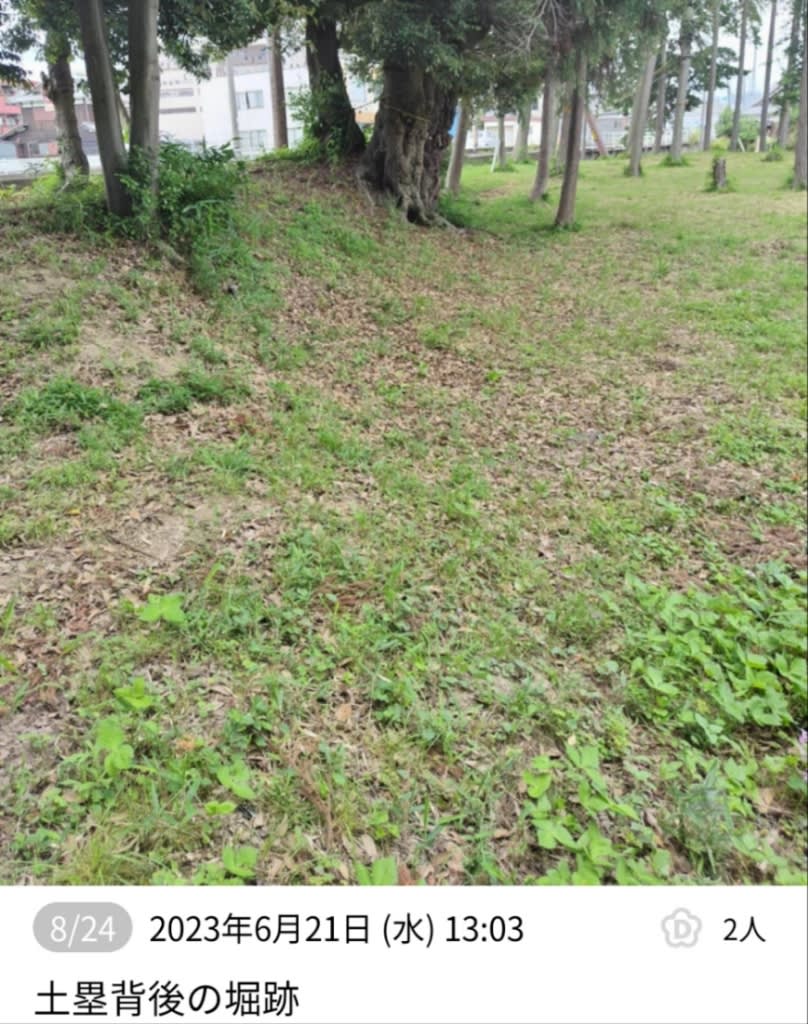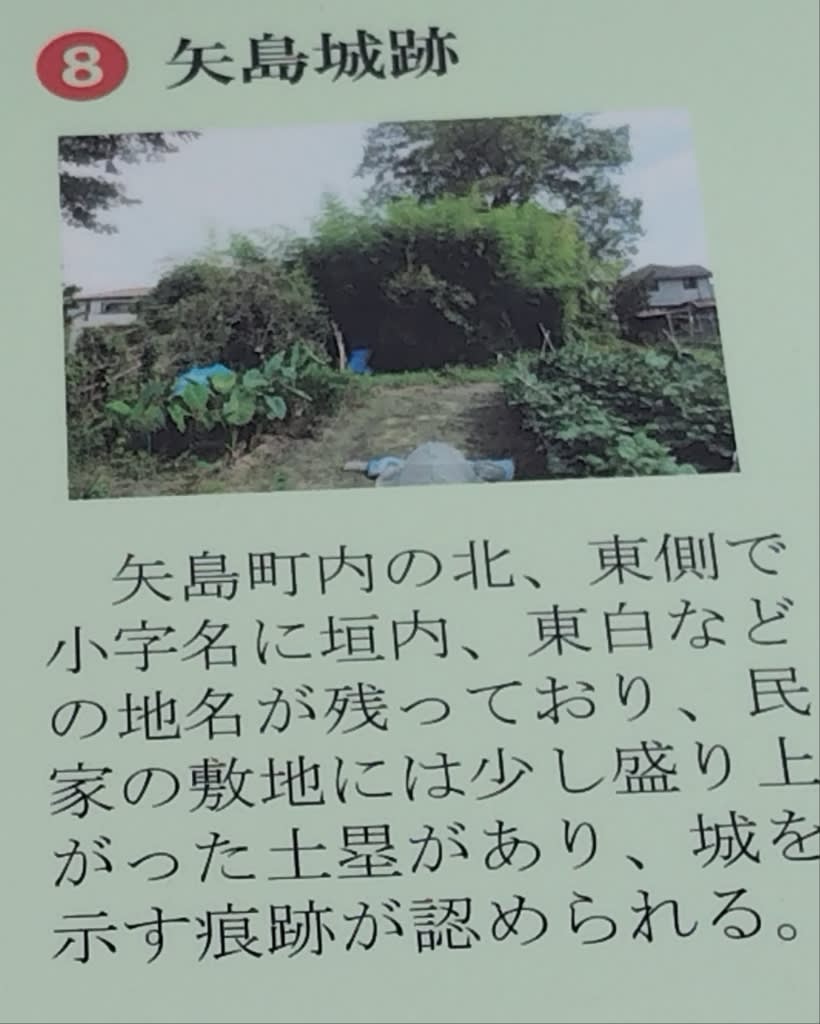地名ちょこっと紹介
【甲良町】滋賀県犬上郡
こうらちょう。
我がひこにゃん市と接していて、犬上川を挟んだ南側の町。
同じ犬上郡ということで親近感あるが、意外にも仲が悪くて市町村合併の話は進まず、車のひこにゃんナンバーも拒否されて破断となりました。
我が市が高圧的な態度をとってるのが気に入らないのかも、ね。
甲良の由来は、犬上川の河原(かわら)→「こうら」に転化した、と言われてます。
小さな町だが、3人の歴史上の英傑を輩出してます。
まずは、「京極道誉」。
足利尊氏を支え佐々木源氏の基盤を築きました。バサラ大名と呼ばれてます。
出雲の戦国大名尼子氏は京極氏の系統で甲良町尼子が本貫の地です。
二人目は「藤堂高虎」
頻繁に主を変えたため日和見大名と呼ばれてるが、築城術に優れていて江戸城を始めとして二条城、大坂城など有名なお城を造ってます。
江戸時代、外様大名は西国や東北などに飛ばされたが、高虎だけは逆に四国から伊賀伊勢へ栄転しました。
外様ながら家康のお気に入りとして信頼された大名でした。
3人目は「甲良豊後守宗廣」
大工の棟梁で高虎との縁で日光東照宮、江戸増上寺などの造営を担当しました。
現在、甲良町役場前に銅像があります。
ちなみに、藤堂高虎の生誕地は藤堂村と呼ばれてたが、江戸時代彦根井伊家2代藩主の直孝が、藤堂家に対して不遜だとして「在士」という村名に変えた。
で、現在も甲良町在士という地名になつてます。
家康は、合戦になった時に一番槍の家柄は伊賀の藤堂家と彦根の井伊家と決めました。
両家お互いに実力を認めてたようですな。
ところで、今回のクイズの選択肢としては甲良町以外に甲西町、甲南町、甲賀町もありました。
3つの町はともに甲賀郡に属したので町名に甲が付きます
なのに、なのに、
平成の合併で、甲西町は湖南市に。
甲南町と甲賀町は甲賀市になり、分裂しました。
同じ甲賀郡(こうかぐん)なのに分裂して
住民は
コウカイしてないかな?
明後日に続く~
□■□■□■□■□■□■□■□■
Φ(*^ひ^*)Φ
夏休みと言えば、NHKラジオ体操。
毎日全国各地から放送されてます。
で、冒頭に必ずその土地の紹介がある。
先日は「福島県のこおりまち」
とアナウンスが。
郡山の間違いじゃないの?
と思ったが、
「伊達家発祥の地」という解説があり、はたと気づいた
「桑折町」のことですよね。
これも難読地名ですな。
数年前、宇和島城に登った時に、桑折門がありました。
伊達家の家臣桑折氏にちなんだ門です。
桑折町に古代の郡衙があった。
郡、こおりと読む。
養蚕が盛んだったので桑折と改名したようです。
寝床でラジオ体操を聞きながら頭の体操をした我が輩でした。
Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ
台風7号、
どうやら我が地方直撃のようです
しかも、お盆に来るとは、
ヤバい!
馬《●▲●》助ヒヒーン♪