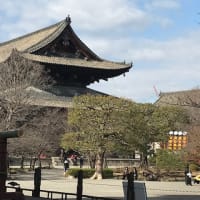かぶき は、かぶく 傾くことを意味した。
歌舞伎は、当て字である。
意味上の対応関係をもつ漢字を使うのが通常である、とされる。
歌舞伎そのものは、ミュージカルを連想して当て字の妙がある。
当て字は、対応する漢字がない場合に、便宜的にある漢字の音や訓を借りて書き記し、さらに和語以外の外来語、外国語の表記に使うことで、慣用的に定まったもの、熟字訓のように、意味関係の対応を見る場合もある。
その字の当て方に、意味読みを充てるかのように工夫を凝らしたしたのが、歌舞伎の外題に見られる。
外題というのも内題に対する呼称で、ともに書誌の用語となるが、その外題を芸題とも言ったりするものに、特殊な読み方となったものがある。
狂言名題
世界大百科事典内の一番目狂言の言及
【一番目】より
>
…歌舞伎用語。一番目狂言の略。武士や公卿等の世界を題材とした時代物の狂言のことをいう。…
【狂言立て】より
…歌舞伎の興行における一日の狂言の並べ方。元禄期(1688‐1704)から寛政(1789‐1801)初年までの,江戸の劇場では,まず儀式的な番立(ばんだち)(三番叟),脇狂言(各座の家の狂言)に続いて,一つの世界に統一された一番目狂言と二番目狂言が続けて上演される。一番目狂言(時代物)は序開(じよびらき),二建目(ふたたてめ),三建目(通説では今日の一番目の序幕にあたるとされているが,絵本番付では二建目から描かれている),四建目,五建目,大詰と上演される。…
ジタル大辞泉の解説
にばんめ‐きょうげん〔‐キヤウゲン〕【二番目狂言】
歌舞伎で、1回の興行の二番目の演目。江戸後期には一番目(時代物)・二番目(世話物)の2演目興行で、のちに間に中幕(なかまく)、最後に大切(おおぎり)が入った。二番目物。
時代物
浄瑠璃・歌舞伎で、江戸時代以前の公卿・僧侶・武家などの社会を題材としたもの。王代(おうだい)物・御家(おいえ)物も含む。一番目物。
世話物
浄瑠璃・歌舞伎で、主として江戸時代の町人社会に取材し、義理・人情・恋愛や種々の葛藤(かっとう)を主題としたもの。歌舞伎では、生世話物(きぜわもの)・散切物(ざんぎりもの)も含む。二番目物。世話。
生世話物
歌舞伎の世話物のうち、写実的傾向の著しい内容・演出によるもの。文化・文政期(1804~1830)以降の江戸歌舞伎で発達。生世話狂言。真世話物。
大辞林 第三版の解説
きぜわもの【生世話物】
歌舞伎の世話物のうち,特に江戸時代の庶民の生活を写実的に描いた脚本,またその演出。怪談物や白浪(しらなみ)物が多い。四世鶴屋(つるや)南北・河竹黙阿弥(もくあみ)らによって完成された。生世話。生世話狂言。真世話物。
ざんぎりもの【散切り物】
歌舞伎世話狂言の一。明治初期,散切り頭に象徴される新時代の社会生活に取材したもの。黙阿弥の「島鵆月白浪(しまちどりつきのしらなみ)」「水天宮利生深川(すいてんぐうめぐみのふかがわ)」などの類。
歌舞伎狂言や浄瑠璃などの題名。元禄(1688~1704)ごろから縁起上、字数を奇数に定め、特殊な読み方をするようになった。
http://www.kabuki-bito.jp/kabuki_column/todaysword/post_160.html
名題と外題 | 歌舞伎美人(かぶきびと)
>
歌舞伎の演目には大変長い題名が付いています。縁起を重んじて奇数で統一し、五文字・七文字と大変長く趣向の凝らされた文字が並んでいますが、これを名題(狂言名題ともいいます)あるいは外題(芸題)と呼びます。
元来は江戸が名題、上方が外題ですが、今日では特にこの区別はないようです。一方別の意味で、俳優のランクを示すことばに「名題」「名題下」という呼称があり、これとの混同を避けて近年では主に外題の方が使われています。
外題には多くの作者が趣向を凝らして来ましたが、特に河竹黙阿弥の作品には『青砥稿花紅彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)=弁天小僧』『天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)=河内山と直侍』『八幡祭小望月賑(はちまんまつりよみやのにぎわい)=縮屋新助』など時代を超えた斬新さを感じさせるものが数多くあります。(K)
歌舞伎は、当て字である。
意味上の対応関係をもつ漢字を使うのが通常である、とされる。
歌舞伎そのものは、ミュージカルを連想して当て字の妙がある。
当て字は、対応する漢字がない場合に、便宜的にある漢字の音や訓を借りて書き記し、さらに和語以外の外来語、外国語の表記に使うことで、慣用的に定まったもの、熟字訓のように、意味関係の対応を見る場合もある。
その字の当て方に、意味読みを充てるかのように工夫を凝らしたしたのが、歌舞伎の外題に見られる。
外題というのも内題に対する呼称で、ともに書誌の用語となるが、その外題を芸題とも言ったりするものに、特殊な読み方となったものがある。
狂言名題
世界大百科事典内の一番目狂言の言及
【一番目】より
>
…歌舞伎用語。一番目狂言の略。武士や公卿等の世界を題材とした時代物の狂言のことをいう。…
【狂言立て】より
…歌舞伎の興行における一日の狂言の並べ方。元禄期(1688‐1704)から寛政(1789‐1801)初年までの,江戸の劇場では,まず儀式的な番立(ばんだち)(三番叟),脇狂言(各座の家の狂言)に続いて,一つの世界に統一された一番目狂言と二番目狂言が続けて上演される。一番目狂言(時代物)は序開(じよびらき),二建目(ふたたてめ),三建目(通説では今日の一番目の序幕にあたるとされているが,絵本番付では二建目から描かれている),四建目,五建目,大詰と上演される。…
ジタル大辞泉の解説
にばんめ‐きょうげん〔‐キヤウゲン〕【二番目狂言】
歌舞伎で、1回の興行の二番目の演目。江戸後期には一番目(時代物)・二番目(世話物)の2演目興行で、のちに間に中幕(なかまく)、最後に大切(おおぎり)が入った。二番目物。
時代物
浄瑠璃・歌舞伎で、江戸時代以前の公卿・僧侶・武家などの社会を題材としたもの。王代(おうだい)物・御家(おいえ)物も含む。一番目物。
世話物
浄瑠璃・歌舞伎で、主として江戸時代の町人社会に取材し、義理・人情・恋愛や種々の葛藤(かっとう)を主題としたもの。歌舞伎では、生世話物(きぜわもの)・散切物(ざんぎりもの)も含む。二番目物。世話。
生世話物
歌舞伎の世話物のうち、写実的傾向の著しい内容・演出によるもの。文化・文政期(1804~1830)以降の江戸歌舞伎で発達。生世話狂言。真世話物。
大辞林 第三版の解説
きぜわもの【生世話物】
歌舞伎の世話物のうち,特に江戸時代の庶民の生活を写実的に描いた脚本,またその演出。怪談物や白浪(しらなみ)物が多い。四世鶴屋(つるや)南北・河竹黙阿弥(もくあみ)らによって完成された。生世話。生世話狂言。真世話物。
ざんぎりもの【散切り物】
歌舞伎世話狂言の一。明治初期,散切り頭に象徴される新時代の社会生活に取材したもの。黙阿弥の「島鵆月白浪(しまちどりつきのしらなみ)」「水天宮利生深川(すいてんぐうめぐみのふかがわ)」などの類。
歌舞伎狂言や浄瑠璃などの題名。元禄(1688~1704)ごろから縁起上、字数を奇数に定め、特殊な読み方をするようになった。
http://www.kabuki-bito.jp/kabuki_column/todaysword/post_160.html
名題と外題 | 歌舞伎美人(かぶきびと)
>
歌舞伎の演目には大変長い題名が付いています。縁起を重んじて奇数で統一し、五文字・七文字と大変長く趣向の凝らされた文字が並んでいますが、これを名題(狂言名題ともいいます)あるいは外題(芸題)と呼びます。
元来は江戸が名題、上方が外題ですが、今日では特にこの区別はないようです。一方別の意味で、俳優のランクを示すことばに「名題」「名題下」という呼称があり、これとの混同を避けて近年では主に外題の方が使われています。
外題には多くの作者が趣向を凝らして来ましたが、特に河竹黙阿弥の作品には『青砥稿花紅彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)=弁天小僧』『天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)=河内山と直侍』『八幡祭小望月賑(はちまんまつりよみやのにぎわい)=縮屋新助』など時代を超えた斬新さを感じさせるものが数多くあります。(K)