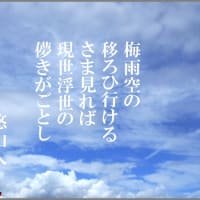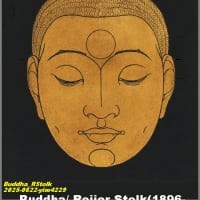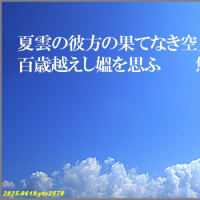2007-0305-yis105
忘れられ涙で濡れた革帯も
切れて縹の帯になったわ 悠山人
○和泉式部集、詠む。
○詞書は、「男に忘られて、装束(さうぞく)などつつみておくり侍りしに、かはの帯にむすびつけて」。
¶装束=古語辞典の見出しは「さうぞく」で、説明に「しゃうぞく」とも、とある。広辞苑では、古くは「さうぞく」とも、と。
¶かはの帯=<革帯。「装束」の際、袍(ほう。[綿入れ])につける帯。黒塗の牛革に玉や石をもってかざる。>
¶たへ、たえ=「たへ」の終止形は「た(堪)ふ」、「たえ」は「た(絶)ゆ」。
¶た(絶)えぬれば=「仲の絶えたことをかける。」(新潮版)
¶はなだ(縹)=依拠本では、「はなだ(藍)」と頭注表記する。<「縹色」の略。薄い藍色。…襲(かさね)の色目の名。表裏とも縹色。> 用例に源氏・絵合から「縹の唐の紙に包みて」(古語辞典) 広辞苑の用例では、催馬楽(さいばら)・石川から「縹の帯」。さらに、新潮版校注には同所(石川)からの歌謡が、こう載る。
石川の 高麗人(こまうど)に 帯は取られて 辛(から)き悔(くい)する
いかなる いかなる帯ぞ
はなだの帯の 仲は絶えたる
源氏・花宴に、和泉と同じ催馬楽の引用があり、渋沢版注釈によると、こうである。
<【扇を取られてからきめを見る】-源氏の詞。『催馬楽』「石川」中の歌詞「帯を取られて辛き悔いする」の文句を「扇を取られて辛き目をみる」と言い換えたもの。『源氏釈』は「石川の 高麗人(こまうど)に 帯を取られて からき悔いする いかなる いかなる帯ぞ 縹(はなだ)の帯の 中はたいれるか かやるか あやるか 中はいれたるか」(催馬楽 石川)を指摘。
【あやしくもさま変へたる高麗人かな】-女房の詞。「高麗人」は『催馬楽』「石川」中の登場人物、それと知って、「帯」でなくて「扇」とは「あやしくも」と答えるが、なぜ「扇」なのか、この女房は事情を知らないので、こう言う。>
『源氏物語』には、ほかにも「縹帯」が重要な鍵となる場面もあるので、付記しておく。
□和105:なきながす なみだにたへで たえぬれば
はなだのおびの ここちこそすれ
□悠105:わすれられ なみだでぬれた かわおびも
きれてはなだの おびになったわ
忘れられ涙で濡れた革帯も
切れて縹の帯になったわ 悠山人
○和泉式部集、詠む。
○詞書は、「男に忘られて、装束(さうぞく)などつつみておくり侍りしに、かはの帯にむすびつけて」。
¶装束=古語辞典の見出しは「さうぞく」で、説明に「しゃうぞく」とも、とある。広辞苑では、古くは「さうぞく」とも、と。
¶かはの帯=<革帯。「装束」の際、袍(ほう。[綿入れ])につける帯。黒塗の牛革に玉や石をもってかざる。>
¶たへ、たえ=「たへ」の終止形は「た(堪)ふ」、「たえ」は「た(絶)ゆ」。
¶た(絶)えぬれば=「仲の絶えたことをかける。」(新潮版)
¶はなだ(縹)=依拠本では、「はなだ(藍)」と頭注表記する。<「縹色」の略。薄い藍色。…襲(かさね)の色目の名。表裏とも縹色。> 用例に源氏・絵合から「縹の唐の紙に包みて」(古語辞典) 広辞苑の用例では、催馬楽(さいばら)・石川から「縹の帯」。さらに、新潮版校注には同所(石川)からの歌謡が、こう載る。
石川の 高麗人(こまうど)に 帯は取られて 辛(から)き悔(くい)する
いかなる いかなる帯ぞ
はなだの帯の 仲は絶えたる
源氏・花宴に、和泉と同じ催馬楽の引用があり、渋沢版注釈によると、こうである。
<【扇を取られてからきめを見る】-源氏の詞。『催馬楽』「石川」中の歌詞「帯を取られて辛き悔いする」の文句を「扇を取られて辛き目をみる」と言い換えたもの。『源氏釈』は「石川の 高麗人(こまうど)に 帯を取られて からき悔いする いかなる いかなる帯ぞ 縹(はなだ)の帯の 中はたいれるか かやるか あやるか 中はいれたるか」(催馬楽 石川)を指摘。
【あやしくもさま変へたる高麗人かな】-女房の詞。「高麗人」は『催馬楽』「石川」中の登場人物、それと知って、「帯」でなくて「扇」とは「あやしくも」と答えるが、なぜ「扇」なのか、この女房は事情を知らないので、こう言う。>
『源氏物語』には、ほかにも「縹帯」が重要な鍵となる場面もあるので、付記しておく。
□和105:なきながす なみだにたへで たえぬれば
はなだのおびの ここちこそすれ
□悠105:わすれられ なみだでぬれた かわおびも
きれてはなだの おびになったわ