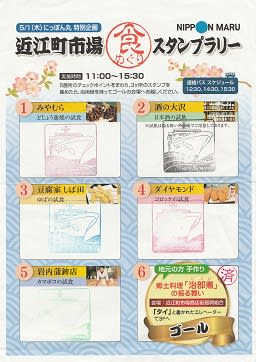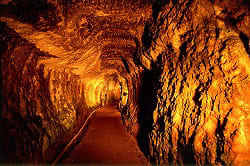5月4日 7:00~

~和食~
若布と豆腐の味噌汁
開きキンキの火取り 卸し大根
岩石玉子
ささがき信田と青菜の煮物
ブロッコリーとハムの酢味噌和え
おから五目炒め
納豆、味付け海苔、香の物
① 白粥 ②特選粥(ザーサイ粥) ③御飯
日本茶
(このほかに、洋風ビュッフェもある)

9:00 青森港入港。

港には観光案内所や名産品の販売所などが並んでいる。
弘前城の桜を観るツアーもあったが、以前行ったことがあり、今回はボランティアガイドさんとの「街歩きツアー」に参加。


青函連絡船だった「八甲田丸」。平成2年に鉄道連絡船ミュージアムとして、資料展示やイベント開催など多目的な場としてご利用されている。
青函連絡船は、1908年(明治41年)に鉄道連絡船として就航した比羅夫丸が青函連絡船歴史の始まり。以来、1988年(昭和63年)まで80年間にわたり、青森港と函館港を結んでいた。
青函連絡船最大の魅力は貨物車両を搭載する「車両甲板」で、鉄道車両が船を通じて海を渡ることは世界的にも大変珍しい事だった。
日本の経済発展に大きく貢献してきた青函連絡船は青森市と函館のシンボルだった。歴代55隻中、23年7ヶ月と現役期間が一番長かった「八甲田丸」を、ほぼ就航当時の状態に係留保存した貴重な施設。
学生時代、ふるさと北海道と東京の行き来には必ず乗ったので、まさに「津軽海峡冬景色」の世界を思い出しながら眺めていた。

「青い海公園」の東端に「明治天皇御渡海記念碑」と書かれた碑と、すぐ側に「海の記念日発祥の地」という石碑が建っている。
1876(明治9)年,明治天皇が1か月半にわたって東北・北海道を巡幸された。随行者には岩倉具視(右大臣)・大久保利通(参議兼内務卿)・大隈重信(参議兼大蔵卿・木戸孝允(内閣顧問官などがおり、総勢200名以上だったという。東京→北関東→東北各県を回り、青森港から灯台巡視船「明治丸」で函館へ。視察後 7月20日に横浜港に戻った。
これを記念して 1930(昭和5)年に「明治天皇御巡幸及御渡海記念碑」が建立され,その周辺は公園になり“聖徳公園”と呼ばれた。1941(昭和16)年に,天皇が横浜に帰着した7月20日が「海の記念日」に制定された。

1990(平成2)年,「御渡海記念碑」の近くに「海の記念日発祥の地」の石碑が建てられ,明治丸の碇のレプリカが飾られた。
1996(平成8)年に“祝日法”が改正されて「海の記念日」は 国民の祝日「海の日」となり,2003(平成15)年に 7月第3月曜日に変更された。

奥州街道は江戸時代五街道の一つで、東京日本橋が起点で終点はさまざまな説がある。江戸時代初期に著された「幕府撰慶長日本図」によると、当時津軽藩の出張機関が置かれていた青森市安方地域が終点とされているという。

善知鳥(うとう)神社は現在の青森市が江戸時代まで、善知鳥村と言われたことから、こう呼ばれている。青森発祥の地。「うとう」は、昔ここに生息していた鳥の名前で、天然記念物。青森では見かけることは少なくなったが、北海道天売島などに多く繁殖している。



善知鳥神社は、志功の少年時代の恰好のあそび場だったという。ここには、何点かの作品が残されている。


(棟方志功記念館HPより)


青森県観光物産館「アスパム」。青森県の観光、物産、郷土芸能などを総合的に紹介する情報発信基地。

ちょうど津軽三味線の演奏時間に間に合い、30分間聴くことができた。やはり生演奏はいい。津軽三味線の名人・高橋竹山のお弟子さんが弾いていた。ちなみに、北島三郎が歌う「風雪流れ旅」のモデルは、高橋竹山だ。

17:00 郷土芸能「ねぶた囃子」に見送られて青森港を出港。
亀山勝子&法男のザ・クラシック笑(ショー)

今夜のメインイベントは、クラシックジャンルを越え、エスプリの技と粋な"音のあやとり"を展開する今まで見たことも聴いたこともない小粋なパフォーマンスショー!
名曲に別の曲をからめ、紡ぎ出すスリリングなドラマ。クラシックか演歌か…直球か変化球か…粋か野暮か…見せます、聴かせます、笑わせます、泣かせます。
この夫婦~何だか妙に面白い…。(船内新聞のプログラムから)
♪早春賦類似メロディーメドレー
♪早春賦1番…知床旅情…春へのあこがれ
♪琵琶湖周航のうた…愛のよろこび…モルダウの流れ…
♪歌のつばさ…北上夜曲…早春賦2番…早春賦3番で仕上げ
☆昭和初期歌謡曲エレジー(全5曲クラシック仕立て)
♪君恋し…ショパンプレリュード風
♪影を慕いて…シューベルトセレナーデ風
♪水色のワルツ…ショパンワルツ風
♪リンゴ追分…ベートーヴェン月光風
♪ここに幸あり…バッハプレリュード風
ざっと、こんな感じでお二人のトークもなかなか面白い。音楽を通じて多彩な社会活動を展開しているお二人のコンサートは、楽しくもあり、「にっぽんの心」を大事にしていこうというメッセージも発信している素晴らしいコンサートだ。お二人とは共通の知人がいることが分かりびっくり!全国どこででも気軽に公演するというので、ぜひ一度聞いてもらいたい。
☆亀さん企画オフィシャルサイト
http://www.kamesan-kikaku.com