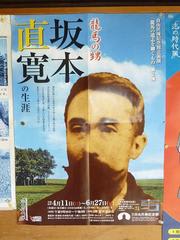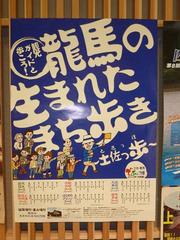小沢氏よ、国民をなめるのも、いい加減にしてほしい。
例の土地購入に関わる4億円の問題について、当初の事情聴取前には、「検察と徹底的に闘う」と凄んでみせたが、今では、「強制捜査権があるプロが2回もシロと判定しているのに、一般の素人がいいとか悪いとかいう仕組みがいいのか」と言い、制度のあり方についても疑問を呈している。検察の調べでは、全くのシロではないのだ。完全な証拠がないというだけ。
4億円もの資金がどこから出たのかについて、最初は「政治資金」と言い、2回目には「銀行融資」と言い、3回目に「個人資金」と変わってきているのだ。このことだけを見ても、ウソをついていることは明白だ。「やましいことは何もない」と胸を張るのなら、どうして、クルクルと話しが変わるのか。状況証拠は限りなくクロに近いのだ。
「国民目線が大事」「国民の生活が第一」などと広言しているのとは裏腹に、都合が悪くなると国民を「素人」呼ばわりする始末だ。だから、国民は小沢氏の説明を信用しないし、ましてや日本のトップリーダーなどにはできないと思っているのだ。
「政治生命をかけて」「命をかけて」と叫んでいるが、「信なくば立たず」という言葉の通り、いくら立派な政策を語っても、信ずることなど出来るはずがない。初めから立候補の資格など、ありはしないのだ。それを、「この難局を乗り越えるには、小沢先生しかいない」と持ち上げている民主党議員には、呆れるばかりだ。
難局、混乱、国益の損失を招いている原因をつくっている民主党政権と、それを牛耳っている小沢氏に、その大きな責任があることを棚に上げておいて、何というレベルの低い言動を繰り返していることか。
日本のトップを決める選挙で、このような事件の説明から始めなければならないとは、何と情けないことか。何と厚かましいことか。こんな疑惑を抱えた政治家が立候補するというのは、どのように弁明しようと、「自己保身」以外の何ものでもない。権力さえ手中にすれば、この疑惑から逃れられると思っているのだろうか。
そして、今また、総理になったら挙党一致の名のもとに、菅氏、鳩山氏を入閣させ、輿石氏も党の要職に起用すると語っている。顔は党内にしか向いていない。3か月前、ともに「政治とカネ」「普天間問題」などで辞任し、引退するとまで言った(例によって、早くも撤回しそうな発言をしているが)鳩山氏を起用するとは、何を考えているのか。国民をなめきっている。こんな政治家を日本のトップにさせては絶対にダメだ。
ほんとうに、民主党でいいのか、ほんとうに小沢総理でいいのか、今こそ、国民も試されている。