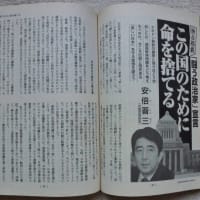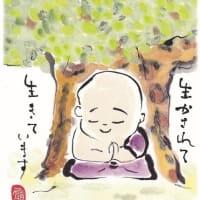先日、北海道小樽市で、2014年7月、女性3人が死亡、1人が重傷を負った飲酒ひき逃げ事件で、32歳の被告に、「危険運転致死傷罪」で、求刑通り懲役22年の判決が下った。当然のことだ。
しかし、この事件において、幾つかの問題も浮き彫りになっている。その一つは、事件当初、検察が「過失致死傷罪」(7年以下の懲役)で起訴したが、被害者家族らが「危険運転致死傷罪」(20年以下の懲役)の適用求める要請書を提出したり、6回にわたって
7万7858人分の署名を提出するなどして、やっと訴因変更の許可を認めたということだ。
悲しみのどん底に突き落とされた被害者家族の皆さんが、ここまでしなければ「危険運転致死傷罪」が適用されないというのは、全く理解できない。
この種の事件で、いつも思うのだが、「事故当時に飲酒の影響で、正常な運転が困難な状態だったということを立証する必要がある」ということ。この論理も全くおかしい。
要は、「死亡」させたことが全てなのだ。小樽の事件でも、弁護側は、事故原因が、「15秒~20秒間スマートフォンを見続けたことによる脇見運転で、過失致死傷罪にとどまる」と主張している。何も酒だけが、危険運転の原因ではないのだ。
事故原因が酒であろうが脇見であろうが、被害者から見れば、何の過失もない者がひき殺されたのであって、関係ないのだ。酒が原因だと罪が重く、その他の原因だと軽くなるというのは、明らかにおかしいことなのだ。「危険運転致死傷罪」の適用要件については、中身を再考すべきだ。
以前、福岡で幼児3人が死亡した飲酒ひき逃げ事件でも、「事件を引き起こすまでは正常に運転できた」という、信じられない論理が展開されて呆れたものだ。
言わずもがなのことだが、自動車事故を引き起こせば、相手の人生をや被害者家族の人生をメチャクチャにしてしまうばかりではなく、自らの人生も放棄することになるのだ。肝に銘じてほしい。