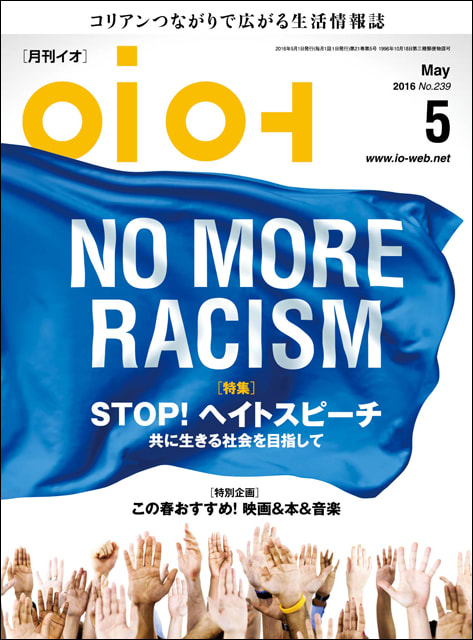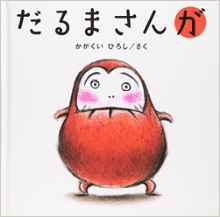先週日曜日、東京青商会主催の「ウリウリコッポンオリフェスティバル2016」に家族で出かけました!
午前10時50分ごろ晴天日和の中、会場に到着してみると、すでにオモニたちがグラウンドの一画で屋台をだしてました!
そこには母校、長野朝鮮初中級学校のオモニ会たちが作ったチョゴリタンブラーが20個限定で売っていたので、迷わず購入。

ひとつひとつ手作りで作られたものは味わい深くておしゃれで可愛いです。
幼馴染の同級生のオンマも屋台でフル稼働、手際よくチジムを焼いていたので思わず購入。お腹を少し満たしてから遊びに回りました。
まず向かったのは、動物ふれあいコーナー。白ヤギ、イヌ、ヒヨコ、ハツカネズミ、カモ、ウサギ、モルモット、アヒル、シチメンチョウ、チャボなど、たくさんの動物たちがおり、抱っこをしたり、餌をあげたりできました。

七面鳥が思ったより大きく、鳥が苦手な私は外で待機。子どもは満面の笑みで抱っこしたり、餌をあげたりを楽しんでいました。
次に遊戯コーナー。色んな遊具やボールプールがあり、子どもたちがたくさん戯れていました。ボールプールは皆のあまりのはしゃぎように、少したじたじ。。。
続いては、参加型ブースへ移動。グルーデコや、パティシエ体験など、様々な体験ができます。
子どもはバルーンアートの教室で、剣をリクエスト。あっという間にかっこいい剣をバルーンで作ってくれました!
私はネイルブースでかわいいネイルをしてもらい、何だか得した気分に。
会場にはコッポン、セサギ、シアリなどのキャラクターもいて、子どもたちの人気者でした。
結局また動物ふれあいコーナーに戻り、子どもはまた動物を抱っこ。14:00の終了までずっとうさぎやモルモットをナデナデしていました。
子どもが産まれてからは毎年ウリウリコッポンオリフェスティバルに行ってますが、動物コーナーは初めての体験!普段ふれあえない動物に気軽に触れることができるのはとても有意義でした!
子どももたくさん楽しめて、オンマアッパも楽しい、そんなフェスティバルでした!
また来年もあれば、ぜひ行きたいと思います。(*^_^*)(愛)
午前10時50分ごろ晴天日和の中、会場に到着してみると、すでにオモニたちがグラウンドの一画で屋台をだしてました!
そこには母校、長野朝鮮初中級学校のオモニ会たちが作ったチョゴリタンブラーが20個限定で売っていたので、迷わず購入。

ひとつひとつ手作りで作られたものは味わい深くておしゃれで可愛いです。
幼馴染の同級生のオンマも屋台でフル稼働、手際よくチジムを焼いていたので思わず購入。お腹を少し満たしてから遊びに回りました。
まず向かったのは、動物ふれあいコーナー。白ヤギ、イヌ、ヒヨコ、ハツカネズミ、カモ、ウサギ、モルモット、アヒル、シチメンチョウ、チャボなど、たくさんの動物たちがおり、抱っこをしたり、餌をあげたりできました。

七面鳥が思ったより大きく、鳥が苦手な私は外で待機。子どもは満面の笑みで抱っこしたり、餌をあげたりを楽しんでいました。
次に遊戯コーナー。色んな遊具やボールプールがあり、子どもたちがたくさん戯れていました。ボールプールは皆のあまりのはしゃぎように、少したじたじ。。。
続いては、参加型ブースへ移動。グルーデコや、パティシエ体験など、様々な体験ができます。
子どもはバルーンアートの教室で、剣をリクエスト。あっという間にかっこいい剣をバルーンで作ってくれました!
私はネイルブースでかわいいネイルをしてもらい、何だか得した気分に。
会場にはコッポン、セサギ、シアリなどのキャラクターもいて、子どもたちの人気者でした。
結局また動物ふれあいコーナーに戻り、子どもはまた動物を抱っこ。14:00の終了までずっとうさぎやモルモットをナデナデしていました。
子どもが産まれてからは毎年ウリウリコッポンオリフェスティバルに行ってますが、動物コーナーは初めての体験!普段ふれあえない動物に気軽に触れることができるのはとても有意義でした!
子どももたくさん楽しめて、オンマアッパも楽しい、そんなフェスティバルでした!
また来年もあれば、ぜひ行きたいと思います。(*^_^*)(愛)