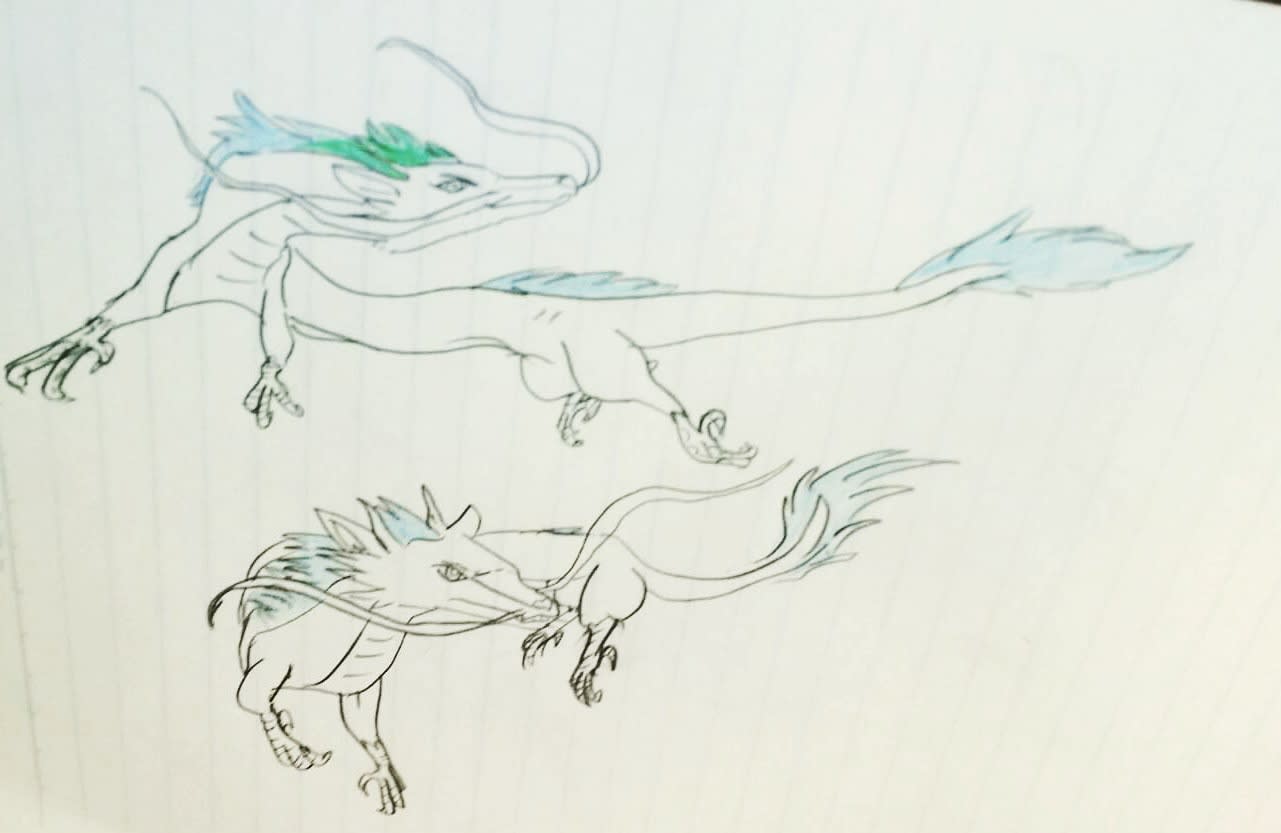先日、祖母が急逝しました。
92歳でした。
高齢なため、頭の片隅にはいつかはという思いもありましたが、
やはりこういったことに直面すると
人の生は死と隣り合わせなのだな、と痛感しました。
私が高校から寄宿舎に入るまでは、祖父母とはずっと一緒に暮らしていたので祖母との思い出はたくさんあります。
困難な時代を生き抜いてきた祖母は、素朴な食材を美味しい食べ物に変身させるのがとても上手でした。
春にはヨモギでヨモギ餅を、
夏には、畑で取れた野菜で漬物を、
秋には、お友達ときのこを採りに行き、それで天ぷらや味噌汁を。
冬には、ストーブの上でお手製の味噌を載せた焼おにぎりを。
そのどれも、祖母にしか作れない味で、本当に美味しかった思い出があります。
祖父のお客様などが訪ねてきても、誰にでも惜しみなく美味しいものを作っては振る舞う、そんな祖母でした。
祖母は日本人ですが、1世である祖父と結婚しました。
7人きょうだいの長女で、当時は家族からも反対されたと聞きますが、
祖父とともに苦しい時代を生き抜いて、立派に生計を立てるようになってからはきょうだいたちをも助け、次第に認められていったそうです。
朝鮮語を話すことはできずとも、子からは「オモニ」、孫たちからは「ハンメ」と呼ばれ、
祖父の歌に合わせてオッケチュムを踊り、お祝いごとにはチョゴリを着て、韓国ドラマを楽しんでみていました。
施設に入ってからも、訪ねていくと「元気か? いっぱい食べるんだよ」と、逆に私たちの心配をしてくれた祖母でした。
祖母を見送りながら、祖母と過ごした日々が思い出されました。
ひとつ私の中で心残りなのは、祖母の若い頃の話をもっとちゃんと聞いて、残しておけばよかったということ。
戦争前後を生き抜いてきた祖母の話しは、きっと後世に残すべき事柄で溢れていただろうに、
祖母の口から少し聞いたことはあるものの、曖昧な記憶しかなく、ちゃんとした形で残すことはできませんでした。
祖母の部屋には、赤ちゃんのころ、母親と撮った写真が飾られています。
年代物の着物に身を包んでいる写真には、その時代の匂いすら感じられます。
在日朝鮮人たちが歩んできた個人史は、その方が何も語らず亡くなってしまえば、もう後に残すことも難しくなります。
個人史にこそ、人々の感情や想い、いまの時代に学ぶべきものがたくさんあると思うのに…。
そういった考えから、来年度からは個人史を語ってもらう「私のオモニ」(仮)というエッセイも新しく始まる予定です。
たくさんの人たちの個人史がイオという雑誌の中で、生き生きと語られれば、と思います。(愛)
92歳でした。
高齢なため、頭の片隅にはいつかはという思いもありましたが、
やはりこういったことに直面すると
人の生は死と隣り合わせなのだな、と痛感しました。
私が高校から寄宿舎に入るまでは、祖父母とはずっと一緒に暮らしていたので祖母との思い出はたくさんあります。
困難な時代を生き抜いてきた祖母は、素朴な食材を美味しい食べ物に変身させるのがとても上手でした。
春にはヨモギでヨモギ餅を、
夏には、畑で取れた野菜で漬物を、
秋には、お友達ときのこを採りに行き、それで天ぷらや味噌汁を。
冬には、ストーブの上でお手製の味噌を載せた焼おにぎりを。
そのどれも、祖母にしか作れない味で、本当に美味しかった思い出があります。
祖父のお客様などが訪ねてきても、誰にでも惜しみなく美味しいものを作っては振る舞う、そんな祖母でした。
祖母は日本人ですが、1世である祖父と結婚しました。
7人きょうだいの長女で、当時は家族からも反対されたと聞きますが、
祖父とともに苦しい時代を生き抜いて、立派に生計を立てるようになってからはきょうだいたちをも助け、次第に認められていったそうです。
朝鮮語を話すことはできずとも、子からは「オモニ」、孫たちからは「ハンメ」と呼ばれ、
祖父の歌に合わせてオッケチュムを踊り、お祝いごとにはチョゴリを着て、韓国ドラマを楽しんでみていました。
施設に入ってからも、訪ねていくと「元気か? いっぱい食べるんだよ」と、逆に私たちの心配をしてくれた祖母でした。
祖母を見送りながら、祖母と過ごした日々が思い出されました。
ひとつ私の中で心残りなのは、祖母の若い頃の話をもっとちゃんと聞いて、残しておけばよかったということ。
戦争前後を生き抜いてきた祖母の話しは、きっと後世に残すべき事柄で溢れていただろうに、
祖母の口から少し聞いたことはあるものの、曖昧な記憶しかなく、ちゃんとした形で残すことはできませんでした。
祖母の部屋には、赤ちゃんのころ、母親と撮った写真が飾られています。
年代物の着物に身を包んでいる写真には、その時代の匂いすら感じられます。
在日朝鮮人たちが歩んできた個人史は、その方が何も語らず亡くなってしまえば、もう後に残すことも難しくなります。
個人史にこそ、人々の感情や想い、いまの時代に学ぶべきものがたくさんあると思うのに…。
そういった考えから、来年度からは個人史を語ってもらう「私のオモニ」(仮)というエッセイも新しく始まる予定です。
たくさんの人たちの個人史がイオという雑誌の中で、生き生きと語られれば、と思います。(愛)