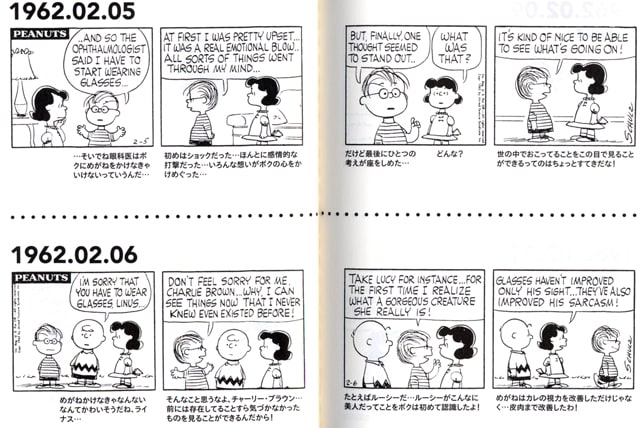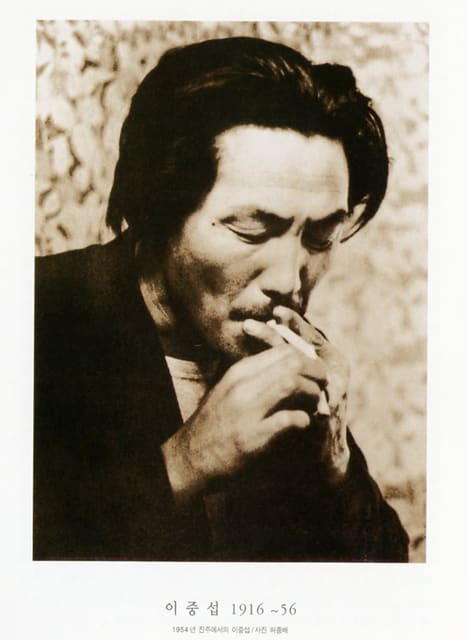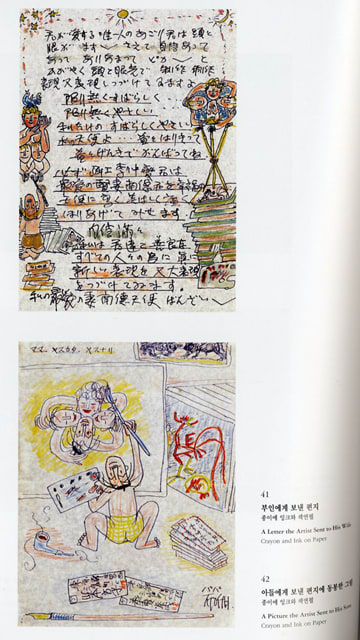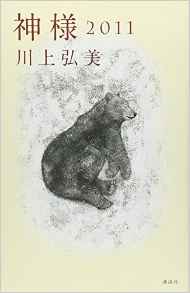5月号の特集は「エンディング虎の巻」。
「人が生きていれば必ず最期は訪れる。
葬儀関連の書籍は数あれど、同胞の場合は日本人との違いもある。
朝鮮半島固有の風習や遺族の思いを知らないまま、葬儀を終えることも多いようだ。
本特集では、近年の葬儀やお墓を取り巻く意識の変化を取材しつつ、
葬儀そのもののあり方を考えてみたい。
身近な人を納得できる形で見送る「エンディング」とは―。」
特集頁は全部で11ページ。
故人を見送る家族たちを取材した「ルポ 同胞葬儀・墓事情」。
葬儀屋、ウリ寺院から見た風景の「増える“小さな葬儀”」。
その他ウリ葬儀を考えるヒントを集めたものを紹介したり、
「私が考える見送り方」を語ってもらったり。
その時になって困らないための準備をまとめた「エンディングを考えるエトセトラ」という頁も掲載。
イオでこうした特集を扱うのは実は初めて。
今回デザインを担当しながら、記者が取材した文章をいち早く読み、
もっと早く取り上げればよかったなと思うほど、色々なことを私自身も知ることができた。
私自身、昨年に祖母が他界した。
身内が亡くなるのは2回目で、その時より大人になったからか、見送りながら本当に思うところが多かった。
1回目は私が高校生の頃、祖父が亡くなった。祖父の葬儀ではウリ寺院のスニム(お坊さん)を呼び、父は白い帽子を被り、私たち女性は白いリボンのピン止めを頭につけて、葬儀をあげた。
昨年の祖母の葬儀の時は、祖母が日本人だったこともあり、日本のお寺のお坊さまを呼んで、葬儀あげた。
でも、出棺の時等はチェサのようにお膳を準備し、クンチョルをあげて送りだすなど、ウリ式と混ざった形になった。
真心がこもっていれば、どんな形でもいいとも思う。
でも、色々な形を知っておいて損はない。
いまの在日同胞のスタンダードな見送り方って?
日本の雑誌には決して掲載されていない、今回の特集、ぜひご一読ください。
イオ2017年5月号は来週月曜日、4月17日発行予定です。(愛)