「あなたは神を信じますか?」と尋ねられたとき、アインシュタインは答えた。
「スピノザの神を信じます」
と。
かっけー。
誰か私にも訊いてくれないか、と思う(笑)。
その時期その時期に、ファンになる哲学者がいた。
それは時にメルロ・ポンティだったり、ヴィトゲンシュタインだったり、デリダだったりフーコーだったりした。
大してテキストを読んだわけではないけれど、それなりにそのテキストに触れては、さっぱり理解できないのになんとなくその周辺に立ち上るパラテキストやメタテキストの匂いをかいくぐって、テキスト本体がその内に孕むブラックホールのような不可視の中心をこわごわ覗くぐらいのことはしていた。
でも、正直な話、その「人」のテキストを好む、ということは、幾分かはそういう種類の「行為」なのではないかしらね。
そして、今はスピノザ。
じゃあそのスピノザ萌えは、いったいいつ頃まで?ってことになるのだろうか。
それは分からない。
しかし、老後の楽しみには十分だという根拠無き確信がある。
今、熊野純彦の『レヴィナス入門』(ちくま新書)をちくま文庫の『レヴィナスコレクション』を脇において読んでいる。
ところどころグッと来る。
しかし、同時に疲れる。
一冊読み終える頃には、鬱々とした気分が本文からこちらに憑依してくるのではないか、と思うほどだ。
文学じゃないのだから、グッとくるとか鬱々とする、とかいう感想を書いてもしょうがないのかもしれないが、私はようやく、哲学をそういう風に享受する仕方を身につけた。
何の役にも立たないけれども、テキストを快楽を持って読むことが可能になったのだ。
それは20代のころからやりたかったことかもしれないのだが、「文学」にはいろいろなものが乗っていて、なかなか単純なそれができなかった。
古典ならそれができるのかもしれない、と思い始めたのは30代も後半になってからだ。
『土佐日記』や『更級日記』、『源氏物語』など、教科書に載っているようなテキストが、どれほど魅力的なものであるのかが分かってきたのは、遅ればせながら高校国語教師をはじめて20年以上も経ってからのことである。
それが40代後半から、哲学的テキストにおいてもようやく現象として立ち上がってきたような気がする。
早熟の天才ならいざしらず、普通の人間がテキストを読むためには、「時」が熟してこなければならないのだ、ということなのだろう。
周辺知識の蓄積と活用が必要だっていうことは、半ば当たっていて、半ばは外れている。
確かに源氏のテキストを生で楽しむためには、それ相応の基礎知識なり多少の訓練は要るだろう。
ただ、年を取るというのはそういう知識の蓄積だけではなく、蓄積された澱のような知識がだんだん「ボケ」てきて、自動的に取捨選択され、ある中高年の一時期にだけ、明晰に枝葉と幹のバランスが、その人間の積み重ねた訓練や知識や知的能力の量に応じて、ごく短い間だけ、世界を過度に明晰に示してくれるということがあるのではないか……
そんな風に私は感じている。
主観的にはこの数年、そういう「時期」に差し掛かってきた。
「分かる時には、そのことが分かるということに外部の標識を必要とせず、しかも自分が分かるということが分かっている」
スピノザがおそらく20代で到達していたであろう、ある意味傲慢でさえあるような純粋な「真理体験」の感触の端緒を、今ようやくかすかにその匂いを嗅ぐ程度のところで味わおうとしているのではないか?
そんな風に思わせてくれる「力」が、今の私にとってのスピノザのテキストには内在していると感じられる。
とりあえず、レヴィナスのテキストと、レヴィナスについてのテキストを読んでいても、そういう感じには駆られない。
スピノザを読んでいると、スピノザだけ読んでいれば十分、という感じがしてくるのだけれど、そのスピノザの破門をイスラエルが撤回しようとしたときにレヴィナスが激烈な反対をしたとか、ライプニッツはスピノザの哲学に大きな興味を抱きつつ、その志向を隠し続けたとか、そういう周辺テキストの「お話」を読むと、どうしてもいろいろ広がっていってしまう。
今手元に積んでいるのは次の三冊。
1『宮廷人と異端者』M・スチュアート(2011年11月書肆心水刊)
2『国家・教会・自由』福岡安都子(2007年12月東京大学出版会刊)
3『2010スピノザ-ナ』(2011年4月学樹書院刊)
スピノザ本も探し出すといろいろあるものです。
1はライプニッツとスピノザを対比しながら、とくにライプニッツの未公開原稿を渉猟しつつ論じた、推理小説のような魅力ある1冊。
読み出したら止められない感じです。ついでに当時のヨーロッパの歴史的な背景など、早わかりの勉強になるし。
2は國分功一郎センセがブログか2chかで絶賛紹介していた(はず)の1冊。学問研究ってこうでなくちゃ、という熱い國分節に惹かれて購入。でも、『スピノザの方法』の言葉に対するこだわり、言語表現への妥協無き迫り方は、テキストを読む喜びに敏感な文学好きには堪えられないですねえ。
この2の本は、実に本格的な論文。
姿勢を正して読まないと理解できないかもしれないので、ちょっと「神棚」に置いてあります)(笑)。
3はスピノザ学会の会報。こういう学会があるんですね、びっくり。そして、中に書いてある論文が読みやすいことといったら!
いや、哲学の学会誌とかいったら、普通こんなリーダビリティは期待できません。哲学的ジャーゴンが満載で、どうにもならないのがあたりまえ。
いや、誤解のないように言っておけば、分かりやすいかどうかは別です。
分かりやすい哲学、なんてない、とも言えるわけで。
ただ、スピノザ研究者の文章は、あきらかに他の哲学者についての研究論文よりも、「空気が通っている」感じがするのですね。
それはやっぱり、スピノザのテキストの、あの「あられもない」明晰さと無関係ではないような気がします。
丁寧でしかもとりつく島がない、というか。
だから、研究者の対象は明晰になりやすい。
つまり、普通だったなら哲学者の文章とか哲学の研究っていうのは何が問題なのかが分かるまでにメチャメチャ大変なわけです。
っていうか、何が問題なのかが分かれば、もうその哲学を半分以上は理解したといえちゃうぐらいなわけで。
ところが、スピノザの場合は、そこがもう分かりやすいというか分かりにくいというか、普通の哲学者のテキストとは根本的に違う「修辞」というか「ルール」と言うか「文体」で書かれているとしか思えないのです。
だから、その研究もまた、その圏域の烈風をまともに受けてしまう、みたいな。
そして、その風の受け方ぐらいは、素人にも見えやすい、みたいなね。
ともあれ、ホッブズ、ライプニッツ、レヴィナス、デカルト、ドゥルーズを横に置きつつ、スピノザについてゆっくり考えるのは、楽しい時間です。
もしかすると、何かの横に置いたとき、スピノザは超輝くように出来ているのかしら?
いや、そういう憑依型、ミラーリング型じゃないなあ。
むしろ、スピノザ以外の哲学者たちが、鏡に映し出されてしまうというか、スピノザの光によってそれ以外の哲学者の何かがあぶり出されてしまう、といった方が実情に近いかもしれない。
そういう訓練は文学の方でちっとはしてきているから、スピノザについて語る研究者の何かがあぶりだされる、その焦げた匂いぐらいは嗅ぎつけやすい、ってことでしょうかね、今まで書いていたことは。
「レンズ」の比喩は使わないでおくけれど(苦笑)。
さて、では「幸せ」の中に戻るとしましょう。
「スピノザの神を信じます」
と。
かっけー。
誰か私にも訊いてくれないか、と思う(笑)。
その時期その時期に、ファンになる哲学者がいた。
それは時にメルロ・ポンティだったり、ヴィトゲンシュタインだったり、デリダだったりフーコーだったりした。
大してテキストを読んだわけではないけれど、それなりにそのテキストに触れては、さっぱり理解できないのになんとなくその周辺に立ち上るパラテキストやメタテキストの匂いをかいくぐって、テキスト本体がその内に孕むブラックホールのような不可視の中心をこわごわ覗くぐらいのことはしていた。
でも、正直な話、その「人」のテキストを好む、ということは、幾分かはそういう種類の「行為」なのではないかしらね。
そして、今はスピノザ。
じゃあそのスピノザ萌えは、いったいいつ頃まで?ってことになるのだろうか。
それは分からない。
しかし、老後の楽しみには十分だという根拠無き確信がある。
今、熊野純彦の『レヴィナス入門』(ちくま新書)をちくま文庫の『レヴィナスコレクション』を脇において読んでいる。
ところどころグッと来る。
しかし、同時に疲れる。
一冊読み終える頃には、鬱々とした気分が本文からこちらに憑依してくるのではないか、と思うほどだ。
文学じゃないのだから、グッとくるとか鬱々とする、とかいう感想を書いてもしょうがないのかもしれないが、私はようやく、哲学をそういう風に享受する仕方を身につけた。
何の役にも立たないけれども、テキストを快楽を持って読むことが可能になったのだ。
それは20代のころからやりたかったことかもしれないのだが、「文学」にはいろいろなものが乗っていて、なかなか単純なそれができなかった。
古典ならそれができるのかもしれない、と思い始めたのは30代も後半になってからだ。
『土佐日記』や『更級日記』、『源氏物語』など、教科書に載っているようなテキストが、どれほど魅力的なものであるのかが分かってきたのは、遅ればせながら高校国語教師をはじめて20年以上も経ってからのことである。
それが40代後半から、哲学的テキストにおいてもようやく現象として立ち上がってきたような気がする。
早熟の天才ならいざしらず、普通の人間がテキストを読むためには、「時」が熟してこなければならないのだ、ということなのだろう。
周辺知識の蓄積と活用が必要だっていうことは、半ば当たっていて、半ばは外れている。
確かに源氏のテキストを生で楽しむためには、それ相応の基礎知識なり多少の訓練は要るだろう。
ただ、年を取るというのはそういう知識の蓄積だけではなく、蓄積された澱のような知識がだんだん「ボケ」てきて、自動的に取捨選択され、ある中高年の一時期にだけ、明晰に枝葉と幹のバランスが、その人間の積み重ねた訓練や知識や知的能力の量に応じて、ごく短い間だけ、世界を過度に明晰に示してくれるということがあるのではないか……
そんな風に私は感じている。
主観的にはこの数年、そういう「時期」に差し掛かってきた。
「分かる時には、そのことが分かるということに外部の標識を必要とせず、しかも自分が分かるということが分かっている」
スピノザがおそらく20代で到達していたであろう、ある意味傲慢でさえあるような純粋な「真理体験」の感触の端緒を、今ようやくかすかにその匂いを嗅ぐ程度のところで味わおうとしているのではないか?
そんな風に思わせてくれる「力」が、今の私にとってのスピノザのテキストには内在していると感じられる。
とりあえず、レヴィナスのテキストと、レヴィナスについてのテキストを読んでいても、そういう感じには駆られない。
スピノザを読んでいると、スピノザだけ読んでいれば十分、という感じがしてくるのだけれど、そのスピノザの破門をイスラエルが撤回しようとしたときにレヴィナスが激烈な反対をしたとか、ライプニッツはスピノザの哲学に大きな興味を抱きつつ、その志向を隠し続けたとか、そういう周辺テキストの「お話」を読むと、どうしてもいろいろ広がっていってしまう。
今手元に積んでいるのは次の三冊。
1『宮廷人と異端者』M・スチュアート(2011年11月書肆心水刊)
2『国家・教会・自由』福岡安都子(2007年12月東京大学出版会刊)
3『2010スピノザ-ナ』(2011年4月学樹書院刊)
スピノザ本も探し出すといろいろあるものです。
1はライプニッツとスピノザを対比しながら、とくにライプニッツの未公開原稿を渉猟しつつ論じた、推理小説のような魅力ある1冊。
読み出したら止められない感じです。ついでに当時のヨーロッパの歴史的な背景など、早わかりの勉強になるし。
2は國分功一郎センセがブログか2chかで絶賛紹介していた(はず)の1冊。学問研究ってこうでなくちゃ、という熱い國分節に惹かれて購入。でも、『スピノザの方法』の言葉に対するこだわり、言語表現への妥協無き迫り方は、テキストを読む喜びに敏感な文学好きには堪えられないですねえ。
この2の本は、実に本格的な論文。
姿勢を正して読まないと理解できないかもしれないので、ちょっと「神棚」に置いてあります)(笑)。
3はスピノザ学会の会報。こういう学会があるんですね、びっくり。そして、中に書いてある論文が読みやすいことといったら!
いや、哲学の学会誌とかいったら、普通こんなリーダビリティは期待できません。哲学的ジャーゴンが満載で、どうにもならないのがあたりまえ。
いや、誤解のないように言っておけば、分かりやすいかどうかは別です。
分かりやすい哲学、なんてない、とも言えるわけで。
ただ、スピノザ研究者の文章は、あきらかに他の哲学者についての研究論文よりも、「空気が通っている」感じがするのですね。
それはやっぱり、スピノザのテキストの、あの「あられもない」明晰さと無関係ではないような気がします。
丁寧でしかもとりつく島がない、というか。
だから、研究者の対象は明晰になりやすい。
つまり、普通だったなら哲学者の文章とか哲学の研究っていうのは何が問題なのかが分かるまでにメチャメチャ大変なわけです。
っていうか、何が問題なのかが分かれば、もうその哲学を半分以上は理解したといえちゃうぐらいなわけで。
ところが、スピノザの場合は、そこがもう分かりやすいというか分かりにくいというか、普通の哲学者のテキストとは根本的に違う「修辞」というか「ルール」と言うか「文体」で書かれているとしか思えないのです。
だから、その研究もまた、その圏域の烈風をまともに受けてしまう、みたいな。
そして、その風の受け方ぐらいは、素人にも見えやすい、みたいなね。
ともあれ、ホッブズ、ライプニッツ、レヴィナス、デカルト、ドゥルーズを横に置きつつ、スピノザについてゆっくり考えるのは、楽しい時間です。
もしかすると、何かの横に置いたとき、スピノザは超輝くように出来ているのかしら?
いや、そういう憑依型、ミラーリング型じゃないなあ。
むしろ、スピノザ以外の哲学者たちが、鏡に映し出されてしまうというか、スピノザの光によってそれ以外の哲学者の何かがあぶり出されてしまう、といった方が実情に近いかもしれない。
そういう訓練は文学の方でちっとはしてきているから、スピノザについて語る研究者の何かがあぶりだされる、その焦げた匂いぐらいは嗅ぎつけやすい、ってことでしょうかね、今まで書いていたことは。
「レンズ」の比喩は使わないでおくけれど(苦笑)。
さて、では「幸せ」の中に戻るとしましょう。












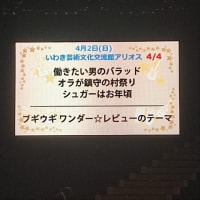
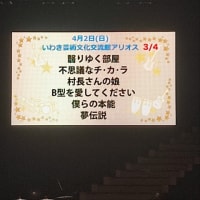
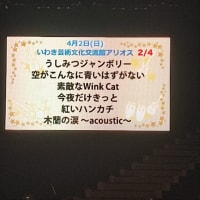
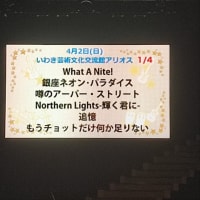




なので、Personal Savior( 個人の救い主=全世界の人間の罪を贖った救世主)であるイエス・キリストの存在を信じるわけがない。ユダヤ教の世界では、イエスはペテン師・魔術師・まがい者。イエスを信じると、ユダヤ社会から弾き飛ばされ、反逆者扱いを受ける。無神論者に対しての扱いは悪くないが、キリスト教徒になれば裏切り者扱いされる。
霊(レイ、the Holy Spirit)である’創造の神’は、人間界に降りてくるために、イエスとなり、肉体を持って、この世に降りて来た。三位一体の神。)しかし、ユダヤ教は創造神だけを信じ、また神は、ユダヤ人以外は雑魚の人種だとみており、ユダヤ人が特別に贔屓され愛されていると真面目に信じている。しかし、今の白人ユダヤ人は聖書のイスラエル人の末裔ではなく、もともとはヨーロッパ人。自称ユダヤ人、なりすましユダヤ人だ。
スピノザもアインシュタインも賢いが、人間であって、神ではないので、所詮、人間的な定義でしか神を理解していない。
そう、創造主を信じるのはたやすいが、ユダヤ教の儀式や慣例は、たとえ心の中だけでも罪(怒り・嫉妬・妬み・ハレンチな想像)を犯しただけで、毎回、動物の生贄を捧げなければいけない。その他、度の過ぎた内容を知ったとたんに、
カッコいいというのが人間的なイルージョンだと気づかされる。