
<校内暴力>カッター見せ、椅子振りかざし キレる小学生
[ 09月23日 01時11分 ]
連日のように教室が騒乱状態に陥り、
男性教諭たちが乗り込んで児童を“鎮圧”する。
児童がカッターナイフで級友の鉛筆を切り刻み、
切れ味をみせびらかす――。
文部科学省の調査で、
小学校の荒れが浮き彫りとなった。
大阪府や神奈川、埼玉県など大都市部で目立って増えている。
小学生はなぜキレやすくなっているのか。
この記事に対しては
いろいろな意見があるんだろうなと想像はつきます。
ワタクシも、お仕事では
こんな修羅場、割と近い雰囲気を経験したことがあります。
保護者はたぶん、「外野」(トラブルにかかわっていない子をあえてこう呼ばせてもらういます)である子どもから
このような話を耳にするだけで、
外野の子ども自身が「普通の出来事」としてとらえている場合、
さほど、きちんとした報告もなされない場合がほとんどだろう。

キレるというのは
どういうことなのか・・・
そんなことから論じていくと大変なことになりますから、やめときます。
でも、学級崩壊のすごさは
割りと身近なところで
おきているんだなあ・・・って言うことくらいは
ココに遊びに来ている人達に知って欲しくて
キーボードに向っています。重かったらごめんなさいね。
危険な行為をする子どもが目立って報道されていますが、
これ以外にも、授業が成立できないほど多動の子や
話の聞けない子が増えたと思います。
同時多発的に多動の児童や衝動的な児童がなにか起し始めていたら
実際あなたは先生だとしたらどう行動しますか??
①まず、一番危ない子を落ち着かせて、周りの子にも注意する。
②「外野」の子に職員室に応援を呼びにいってもらいながら、危険行為を抑える。
③とりあえず、無視して授業を進める。
④その他(おしえてください。)
実際に考えて欲しいなあ・・・と思います。
親としての目線でとらえて見るのと担任としてでは
かなり感情が違ってくるのではないでしょうか?
そして、子育て経験も無い人、
教職経験や子どもとかかわる経験の無い人
子育て真っ最中、
昔子育てした人
すべてに
しっかりと考えてみてもらいたいと思います。
わたしの経験では
こんな状況になるときは
パターンがあります。
A;放任、非行容認保護者と、そういった子どもの複数在籍による問題多発
B;ADHD(注意欠陥多動性障害)など発達障害児童に対する適切な対応不足
と、耐性の低い児童の増加による問題行動の同時多発
Aの場合は地域の特性というか、
保護者がなかなか教育に目を向けにくい職業の場合も多く、
状況が好転することはあまりないです。残念だけど。
Bの場合は、医学的なアプローチ(投薬・カウンセリングなど)でキーマンとなる子を衝動性や多動状態から救ってあげることで
かなり状況がよくなります。
社会的に問題視されているのは、Bの中にある、「耐性の無い子の増加」でしょう。
この耐性の無い子をいかに育てていくかで
状況ががらりと変わってきます。
でも、
こんな中で、どうやって担任一人で
対応しきれるでしょうか?
日本テレビでかなりの視聴率を稼いだ番組「女王の教室」
と言うドラマがありました。
わたしなんぞは怖くて、あまりしっかり見れませんでしたが
ウチの商品たちは
かなりはまって見ていました。
ガツンと引っ張ってくれる大人を求めてるのかも・・・
きららさんのお話されている、
「食育」も大変重要。
野菜の食べられない子はやはり、短気な気がします。
たくさんの料理の味を知らない子は
甘いお菓子やスナック菓子などわかりやすい食べ物に逃げます。
「地域で子育て」すると言う観点もみのがせません。
あいさつ運動なんておこがましいことはしなくてもいい。
ただ、公園で子どもが遊ぶ姿を
たまに見たり、一緒に参戦してみたりするだけでも
子どもはほっとするみたいです。
また、「学校教育に親が積極参加」をもっとしてほしいものです。
自分の子どもの様子は
参観日ではわかりません。
・教室のドアは開けておく、
・いつでもお母さん方が来れる様な雰囲気を作る
・そして、問題を起してしまう子に対して、(その親に対して)の
偏見や差別が極力なくなる様に(二次障害につながるため)配慮する。
これくらいのことはできるかな・・・。
ちなみに、わたしも
この仕事で、なんどか殴られたり、かみつかれたり、失踪した子を
捜索したりしましたが、
妊婦になったら、
おさまりました。
それぞれが抱えている問題も
新たな命の前には色があせてくるのかもしれません。
大切なものを素直に大切に思える気持ちを
肯定してあげるようなかかわりをしてあげたいものです。
人任せにしないで、それぞれ大人ががもっと自分ごととして
この件にかかわってほしいなあ。
そんなかかわりを求めてる
子どもの怒りなんじゃないかしら・・・と思ってしまいました。
[ 09月23日 01時11分 ]
連日のように教室が騒乱状態に陥り、
男性教諭たちが乗り込んで児童を“鎮圧”する。
児童がカッターナイフで級友の鉛筆を切り刻み、
切れ味をみせびらかす――。
文部科学省の調査で、
小学校の荒れが浮き彫りとなった。
大阪府や神奈川、埼玉県など大都市部で目立って増えている。
小学生はなぜキレやすくなっているのか。
この記事に対しては
いろいろな意見があるんだろうなと想像はつきます。

ワタクシも、お仕事では
こんな修羅場、割と近い雰囲気を経験したことがあります。
保護者はたぶん、「外野」(トラブルにかかわっていない子をあえてこう呼ばせてもらういます)である子どもから
このような話を耳にするだけで、
外野の子ども自身が「普通の出来事」としてとらえている場合、
さほど、きちんとした報告もなされない場合がほとんどだろう。

キレるというのは
どういうことなのか・・・
そんなことから論じていくと大変なことになりますから、やめときます。
でも、学級崩壊のすごさは
割りと身近なところで
おきているんだなあ・・・って言うことくらいは
ココに遊びに来ている人達に知って欲しくて
キーボードに向っています。重かったらごめんなさいね。
危険な行為をする子どもが目立って報道されていますが、
これ以外にも、授業が成立できないほど多動の子や
話の聞けない子が増えたと思います。
同時多発的に多動の児童や衝動的な児童がなにか起し始めていたら
実際あなたは先生だとしたらどう行動しますか??
①まず、一番危ない子を落ち着かせて、周りの子にも注意する。
②「外野」の子に職員室に応援を呼びにいってもらいながら、危険行為を抑える。
③とりあえず、無視して授業を進める。
④その他(おしえてください。)
実際に考えて欲しいなあ・・・と思います。
親としての目線でとらえて見るのと担任としてでは
かなり感情が違ってくるのではないでしょうか?
そして、子育て経験も無い人、
教職経験や子どもとかかわる経験の無い人
子育て真っ最中、
昔子育てした人
すべてに
しっかりと考えてみてもらいたいと思います。
わたしの経験では
こんな状況になるときは
パターンがあります。
A;放任、非行容認保護者と、そういった子どもの複数在籍による問題多発
B;ADHD(注意欠陥多動性障害)など発達障害児童に対する適切な対応不足
と、耐性の低い児童の増加による問題行動の同時多発
Aの場合は地域の特性というか、
保護者がなかなか教育に目を向けにくい職業の場合も多く、
状況が好転することはあまりないです。残念だけど。
Bの場合は、医学的なアプローチ(投薬・カウンセリングなど)でキーマンとなる子を衝動性や多動状態から救ってあげることで
かなり状況がよくなります。
社会的に問題視されているのは、Bの中にある、「耐性の無い子の増加」でしょう。
この耐性の無い子をいかに育てていくかで
状況ががらりと変わってきます。
でも、
こんな中で、どうやって担任一人で
対応しきれるでしょうか?
日本テレビでかなりの視聴率を稼いだ番組「女王の教室」
と言うドラマがありました。
わたしなんぞは怖くて、あまりしっかり見れませんでしたが
ウチの商品たちは
かなりはまって見ていました。
ガツンと引っ張ってくれる大人を求めてるのかも・・・
きららさんのお話されている、
「食育」も大変重要。
野菜の食べられない子はやはり、短気な気がします。
たくさんの料理の味を知らない子は
甘いお菓子やスナック菓子などわかりやすい食べ物に逃げます。
「地域で子育て」すると言う観点もみのがせません。
あいさつ運動なんておこがましいことはしなくてもいい。
ただ、公園で子どもが遊ぶ姿を
たまに見たり、一緒に参戦してみたりするだけでも
子どもはほっとするみたいです。
また、「学校教育に親が積極参加」をもっとしてほしいものです。
自分の子どもの様子は
参観日ではわかりません。
・教室のドアは開けておく、
・いつでもお母さん方が来れる様な雰囲気を作る
・そして、問題を起してしまう子に対して、(その親に対して)の
偏見や差別が極力なくなる様に(二次障害につながるため)配慮する。
これくらいのことはできるかな・・・。
ちなみに、わたしも
この仕事で、なんどか殴られたり、かみつかれたり、失踪した子を
捜索したりしましたが、
妊婦になったら、
おさまりました。
それぞれが抱えている問題も
新たな命の前には色があせてくるのかもしれません。
大切なものを素直に大切に思える気持ちを
肯定してあげるようなかかわりをしてあげたいものです。
人任せにしないで、それぞれ大人ががもっと自分ごととして
この件にかかわってほしいなあ。
そんなかかわりを求めてる
子どもの怒りなんじゃないかしら・・・と思ってしまいました。










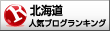















市民祭の開催日なのですが、飛んできたもので怪我をするのはいやなので、
今日は(今日もか)室内でおとなしくしております。
で、朝から考え込んじゃったわいな。
うーむ
軽く憤って書き始めたら
こんなに長くなってしまいました。ま、自分のブログだからいいだろう。
それぞれの責任を全うしていったら、
こんな大きな問題にはならないよ。
子どもがいてもいなくても、
どこかで責任がある問題だと思うんだよなあ・・・。
ま、目先のことでいっぱいいっぱいだから、
自分も人のことは言えない。自戒も込めて・・・
あまりに重かったので、
軽く次回はエセグルメブログに挑戦しました。どうぞ!!
保護者同士の連携って、やっぱり大切ですよね。
うちの怪獣は、はしゃぎすぎでトラブルをおこすタイプです。
それで一学期は何回か担任に話をしに行ったし
相手のお母さんの所にも話をしにいきました。
このとき、保護者同士のコミュニケーションがちゃんと取れていれば
大きなトラブルには発展せずに、子ども自身の力で解決するのを、待つことができる
ということを、実感しました。
あと私自身、できる限り子供に声をかけるように
心がけております。
それは、自分が育児をしていくうえで
周りの皆さんの手助けが欲しいと
切実に思っていた時期があるからです。
見知らぬ土地で、頼れる人間は自分だけ
という状況で育児をしなければならなかった
つらい時期があったので
いまは、赤ちゃん連れの人や、一人で遊んでいる小学生など見かけると
声をかけずにはいられません。
子供もわりと素直に、私の声かけに返事をしてくれるし
悪さをしている子でも、聞いていないようで
ちゃんと私の注意をきいてます。
声かけはあなたたちはちゃんと見守られているよ!というアピールです。
親だけではなく、みんなに大事にされているという安心感を持って、
成長することできたら、キレたりすることも
少ないんじゃないかなぁ・・・と思うわけです。
ちなみに、親に向かって「バカ」と
暴言を吐く子に対し
その子の親の前でもかまわずに叱りつけました。
ものすごくびっくりされましたが、
親同士の仲が険悪になったりせず
うちの子の時にも本気で叱ってねと、
協力体制ができあがりました。
だからうちのも含め、近所の子達は色んなママから
アドバイスされて育っています。
一人でなんとかしなくちゃと思っていた時期があったけど
今は、一人でなんとかしようなんて思っちゃダメだーと思います。
一人でがんばっちゃう親、
放任する地域
これがダブルできちゃうと
マズイんでないか~い
ま、長かった?!
この国の未来を背負う多くの怪獣たちに
もっと意識を持っていってくれればなあ・・・みぽりん・・・
怪獣ブログ初の
思いテーマにコメントありがとうございます。
http://blog.goo.ne.jp/eririnn-sshika-1999/d/20050810
1年生怪獣も元気なんだろうねえ・・・台風でも・・・。
就学前の子どもたち向けに、子育て団体の情報交換をしたり、コンサート、遊びの会などするらしい。要は、一人きりの子育てにならないよう、小さい子供の親が参加できる場を作ろうと言うことですね。去年参加してないから詳しくは知らないんだけど。
私なぞ友達に声をかけられて、気軽に行ったのですが、そこにきているのは自主保育連合の代表だったり、区の委託を受けて子育てサポート活動をしている団体の代表だったり、と、たぶんこのあたりの子育てに関わっているそうそうたるメンバーでありました。
こういうお母さんたちは、本当にすごいです。
いろんなアイディアを持っていて、ほかの人をさりげなくサポートするのね。
すごいなあ、と思うことが多い。
で、その打ち合わせで、防犯についてのなかで出た話。
私が、子どもに声かけをしたらいいんじゃないのか、と言ったら、今はむずかしくなっているとのこと。
なぜかというとですね、親が子どもに「知らない人に声をかけられてもついて行っちゃいけません」ということを、散々教えているので、小学生くらいになると、普通のお母さんに声かけられても、あえて無視するそうだ。
「あんた誰?」という不審な目で見られることが多いとか。
確かに、連れ去り未遂とか多発してるんだよね。
私の身近でも、怪獣兄の同級生のお兄ちゃんが車の中に連れ込まれそうになって、警察に保護された。そんなことを聞くくらい、多い。
正直言って、私も子供を一人で公園にやる気になれない。実家のあたりだったら平気なんだけど。
なんかねえ、都会に近いと、何か個人の力じゃどうにもならないカベがあるらしい。
さびしいことだよね。
確かに三重にいたときは、子どもたちももっと話しかけてきてたなあ、と思った。
私も、子供に話しかけるときは自然に三重弁になる。その方が話しやすい。
注意するのも、方言っていいのよ。きつくなくて。
「だめ」じゃなくて、「そんなんしたら、あかんにー」
やわらかくて、いいよね。
北海道だったら「だめっしょやー」かな。
こっちで、そんな言葉使ったら、変なおばさんだと思われる…
でもね、都会(というほどじゃないけど)は都会なりに、がんばっているお母さんたちもいて、ちょっとほっとしたりするのでありました。
私の住んでるマンションも、地方出身者が多いので、みんなで助け合いながら、子育てしています。
10月はハロウィンをするので、今からみんなどんな仮装しようか、どんな装飾しようかおとなもわくわくしています。
(大人も仮装するよ!)
学校については、また別に書くね。
まとまらなくて、長い上に話題をひっぱりすまぬ…。
4択の件、僕ならその他。おもいっきり怒って、一旦静かにさせるかな。その後、じっくり皆で話し合い、その後時間を作って一人ずつ全員と話し合います。結局、全ての親とも話さないといけないような気もするけど、話しても分からんのやろうね。親がしっかりしてたら起こる問題ちゃうんやから・・・
三つ子の魂百までやねんよなぁ。乳幼児期に大切なもんを親や変わりの大人から受けられんかった子は人としての基礎部分が・・・。哀しいね。
えりりん、いっぱいやり切れん時とかあるけど、僕等大人はあきらめないで頑張って生きましょうね。
いつかきっと・・・
夢見て祈って生きて行こう
その手、みんなやるんだわ。
(それで、声つぶしてるヤツがここに・・・。)
ソレが奴らの思うツボ・・・
大人が興奮するほどテンション上がるのよねえ・・・
その手は1度は効くが
2度目はないのだ・・・。厳しい~(泣)現実。
一人一人と話し合う時間が欲しい。本当に。
それが一番大事だと思う。
即効性はないけれど、
じわじわと効いてくるはず。
いかんせん時間が無いのだよ。最近の学校は・・・。
でも、あらためて勇気をもらったわ。
ありがとう。
ナイフの経験もあるし、椅子も投げられたえりりんより。
おいらはもう少し大きな子供、中高生ですかね・・とは割と接する機会があります。学校の先生が主催してイベントしたり、軽音の定期演奏会とかやったりするんやけど、たまにすっごい孤立してるのがおる。
例えば必須のドリンク料金が、払えなくて帰ろうとした子(男ね。)がいた。すっごい暗い目しててね。 ちょっと可愛そうになって、上まで追いかけて、あとで先生に伝えとくから大丈夫って言って、通してあげたけど、中に入っても1人でいる。先生ステージ付近でイェ~イ!とかやってるねんけど、やってる場合ちゃうどー!と。
けどね、おいらはその一部分しか見てないんだよね。普段その先生が、どういうふうにその生徒と接しているかは、わからない。なので何も言えない。
個人的には、おいらは孤立が気になる。 おいら小学校の最初の頃、ちょっと学校キライやって、結構暗かった。(休んではないよ。) けどその頃ってねー、学校の先生もガキ大将みたいなのも、照れるから話したくない初恋の田島ちなみさんも(くどい!笑)土足で俺の心の中に入って来るもんで、孤立しようにも出来ないんだよね。 一番俺をいじめてる奴が、土曜の昼俺ん家で昼飯食ってたりさ。
今の子供たちは、昔よりも孤立しやすい状況にあるんじゃなかろうか。孤立なんて出来ない状況を、作ってあげたらいいんじゃなかろうか。ゲームとかあるしね、今。閉じこもりやすいよね。先生も怒りにくい時代やし、大変やね。 ちょっと脱線したか。ごめん。(^^;
追伸・・・おいらにもし家族が出来て、北海道に住む事があったら、子供はえりりんスクールに入れるよ。 で、テンションだけ合わさないように教える。笑
学校でも
地域でも
家庭でも、
居場所がある子って
やっぱり生き生きしてて、
元気だ!!
でも、メタりんの言うように、
どこにも居場所がなかったら
そりゃ、アピールもしたくなるわな。
心の安定なんぞあるわけないし・・・。
でもさ、
どこかに居場所があれだけでもシアワセだって思う。
家庭がグジャグジャでも、学校ではしっかりとしたポジションがある子もいるし、
学校ではぜんぜん話せない子も、
近所の子とは元気に遊べる。
どこでもうまくいかないけれど、
家にはあったかい母ちゃんと父ちゃんがいる。
また、学校も家も近所ともうまくいかないけれど、習い事だとかスポーツで力を発揮するヤツもいる。
それでも十分なのよ。
メタりんはちゃんと責任はたしてるよね。
子育ては三つ子の魂百までも・・・なんていうけれど、やり直しきくよ。親がその気になればね。
一番不幸なのは
関心を装う無関心な人たちの中で育つ子どもだな。
「うちの子じゃないからいいわー」じゃ、
日本はどうなっちゃうか心配さね。
今日、4歳の姪の運動会に行って来たんだけど、父兄の皆さんが自分の子供しか観ていない事に驚いた。それもビデオカメラを通してだよ。私達の子供の頃なら父母だけで無く近所のおばちゃん達からも応援の声や罵声が飛んできたものである。寂しくなったものだ。