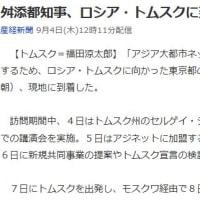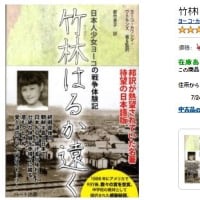<声>・・・そう音楽の天使はこう私に約束させたのだった。
「お前の私のもとで音楽の修練に励みたいという決意は本物のようだ。だが、至高の歌声・・・・例えばカーロッタのような俗なものでなく、人間の心に美そのものに触れたような霊感を与える歌声を手に入れるためには犠牲が必要だ」
犠牲・・・そう何かを得る為には、ましてや美というものを自分の喉に宿すためにはなにか代償が必要なのは理解できた。
「分かります、天使様。よく分かります。どうぞ、おっしゃってください・・・。何をお望みなのですか?」
私は跪き、頭を垂れ震えながら恐る恐る訊ねた。
天使様のようにとまではいかなくても、一瞬でも美そのものになれるなら少々命が短くなっても構わないくらいだった。
「音楽の天使に仕えるには清らかでなくてはならない。分るかね?」
「はい。・・はい、分ります」
もちろんそうに違いない。清い魂だからこそ神は美しいものを体現する資格をお与えになるような気がする。それにブルターニュの村祭りを回りながら音楽の偉大さは決して金銭と交換できるようなものではない、音楽を奏でる事が神を祝福しているのだと言って父はお礼のお金すら受け取らない事が多かった。
「だからオペラ座の軽薄な子ねずみ達のようにパトロンを求める事に躍起になったりせずに私とのレッスンを大切にして欲しい。つまりパトロンを持たず、結婚もしないと約束するのだ。これが条件だ、クリスティーヌ・ダーエ」
なんと簡単な条件だろうか!私はほっと胸を撫でた。もともとくだらない女の競争・・・どんな爵位や人脈、財力を持つパトロンを持てたかという一種の女の虚栄心の小競り合いにはうんざりしていた。
何よりも<声>とのレッスンは未知の世界を切り開いていくような輝きに満ちていた。彼は私の声帯の欠点を直してくれ、今まで知らなかった様々な知識を与えて下さったのだった。
それにさみしさを埋めてくれた<声>にいなくなられるのは絶対に耐えられなかった。喜んで彼の音楽の修道女になろう、そうあのサンヴァンサン・ド・ポール教会の敬虔な修道女のように。
私は二つ返事で約束をした。
即ち純潔を捧げると!
そう約束させた時の自分の感情を上手く表現出来ない。
父親を亡くし悲しみにくれる少女の姿は私の胸にも突き刺さった。普段どおりにしているようで心は死んでいるのがはっきり分るのだった。たった一つの拠り所を失った絶望に今まさに沈もうとするを救いたくて歌いかけてしまった。
もともと才能に恵まれていた彼女を我が音楽の殿堂の中心に添えてみたいと思ったのは無理からぬ事だった。
醜い私と違って歌手として、栄光という王冠を頂くのも夢ではあるまい。いや、そうさせて見せる。
自分が受けるべき輝きを他人に分けてやろうなどとは生まれて初めて思うことだった。
それほど愛おしくなってしまったのだろうか?
まさか、この私が誰かを愛するなどと・・・!!
人が恐れずにはいられない醜い容貌と全身腐肉のような身体では彼女と直接会うこともかなわない。
直接生身の男、化け物として会ったところで何の益もない。
ましてやこの醜い身体であのような白く無垢な身体に触れることなど想像もできなかった。
それに自分の欲望以上に決して見られたくなかった。
私が生涯味わう事のない悦びを彼女からも取り上げよう。
お前は肉の悦びなど永遠に知らなくていいのだ!
火刑のような欲望がそれでなくなるわけではなかったが、彼女の純潔で炎を慰めるのだ。
あとがき・・・
音楽の天使はクリスティーヌに結婚を禁じていました。まぁ、いつも通りの原作の設定ですが。
先日削除しましたが、「肉体的にも癒されているエリックも描きたい~」と書きました。で、あれこれリラックスして・・・する設定を考えてみたのですが結構難しいですね。(記事で書いたダロガというのは腐女子の妄想。好きですが・・・)
まず第一に「醜い姿も見られたくない」、そして第一相手がいない。もしかしたら娼婦なら・・・とも思いますがそれは物理的な行為なので論外。
なかなか難しい条件があるのですが、こういう設定が「結婚してはならぬ」という屈折した要求になったのかもしれません。
でも初心なクリスティーヌなのであまり苦しみにはならないかもしれません。
サンヴァンサン・ド・ポール愛徳修道女会礼拝堂教会というのは原作中に登場する「あれこれ指示するエリックに愛徳修道女会のシスターのように従っていた」というようなラウル視点の描写から。
「お前の私のもとで音楽の修練に励みたいという決意は本物のようだ。だが、至高の歌声・・・・例えばカーロッタのような俗なものでなく、人間の心に美そのものに触れたような霊感を与える歌声を手に入れるためには犠牲が必要だ」
犠牲・・・そう何かを得る為には、ましてや美というものを自分の喉に宿すためにはなにか代償が必要なのは理解できた。
「分かります、天使様。よく分かります。どうぞ、おっしゃってください・・・。何をお望みなのですか?」
私は跪き、頭を垂れ震えながら恐る恐る訊ねた。
天使様のようにとまではいかなくても、一瞬でも美そのものになれるなら少々命が短くなっても構わないくらいだった。
「音楽の天使に仕えるには清らかでなくてはならない。分るかね?」
「はい。・・はい、分ります」
もちろんそうに違いない。清い魂だからこそ神は美しいものを体現する資格をお与えになるような気がする。それにブルターニュの村祭りを回りながら音楽の偉大さは決して金銭と交換できるようなものではない、音楽を奏でる事が神を祝福しているのだと言って父はお礼のお金すら受け取らない事が多かった。
「だからオペラ座の軽薄な子ねずみ達のようにパトロンを求める事に躍起になったりせずに私とのレッスンを大切にして欲しい。つまりパトロンを持たず、結婚もしないと約束するのだ。これが条件だ、クリスティーヌ・ダーエ」
なんと簡単な条件だろうか!私はほっと胸を撫でた。もともとくだらない女の競争・・・どんな爵位や人脈、財力を持つパトロンを持てたかという一種の女の虚栄心の小競り合いにはうんざりしていた。
何よりも<声>とのレッスンは未知の世界を切り開いていくような輝きに満ちていた。彼は私の声帯の欠点を直してくれ、今まで知らなかった様々な知識を与えて下さったのだった。
それにさみしさを埋めてくれた<声>にいなくなられるのは絶対に耐えられなかった。喜んで彼の音楽の修道女になろう、そうあのサンヴァンサン・ド・ポール教会の敬虔な修道女のように。
私は二つ返事で約束をした。
即ち純潔を捧げると!
そう約束させた時の自分の感情を上手く表現出来ない。
父親を亡くし悲しみにくれる少女の姿は私の胸にも突き刺さった。普段どおりにしているようで心は死んでいるのがはっきり分るのだった。たった一つの拠り所を失った絶望に今まさに沈もうとするを救いたくて歌いかけてしまった。
もともと才能に恵まれていた彼女を我が音楽の殿堂の中心に添えてみたいと思ったのは無理からぬ事だった。
醜い私と違って歌手として、栄光という王冠を頂くのも夢ではあるまい。いや、そうさせて見せる。
自分が受けるべき輝きを他人に分けてやろうなどとは生まれて初めて思うことだった。
それほど愛おしくなってしまったのだろうか?
まさか、この私が誰かを愛するなどと・・・!!
人が恐れずにはいられない醜い容貌と全身腐肉のような身体では彼女と直接会うこともかなわない。
直接生身の男、化け物として会ったところで何の益もない。
ましてやこの醜い身体であのような白く無垢な身体に触れることなど想像もできなかった。
それに自分の欲望以上に決して見られたくなかった。
私が生涯味わう事のない悦びを彼女からも取り上げよう。
お前は肉の悦びなど永遠に知らなくていいのだ!
火刑のような欲望がそれでなくなるわけではなかったが、彼女の純潔で炎を慰めるのだ。
あとがき・・・
音楽の天使はクリスティーヌに結婚を禁じていました。まぁ、いつも通りの原作の設定ですが。
先日削除しましたが、「肉体的にも癒されているエリックも描きたい~」と書きました。で、あれこれリラックスして・・・する設定を考えてみたのですが結構難しいですね。(記事で書いたダロガというのは腐女子の妄想。好きですが・・・)
まず第一に「醜い姿も見られたくない」、そして第一相手がいない。もしかしたら娼婦なら・・・とも思いますがそれは物理的な行為なので論外。
なかなか難しい条件があるのですが、こういう設定が「結婚してはならぬ」という屈折した要求になったのかもしれません。
でも初心なクリスティーヌなのであまり苦しみにはならないかもしれません。
サンヴァンサン・ド・ポール愛徳修道女会礼拝堂教会というのは原作中に登場する「あれこれ指示するエリックに愛徳修道女会のシスターのように従っていた」というようなラウル視点の描写から。