一昨年から(前の会社でパワハラ&会社のルールのイタズラで俺を救急車送りにしたお局さんが作っていたので、良いモノは自分も出来る様にしてしまえって考えて・・・男同士だったら角材で殴っているわ・・・現場の人とか派遣さんとか弱い者イジメばっかりしてからに、弱い者が弱い者を叩くとか、本当に世の中おかしくなっている)
始めた味噌作り、
↓
昨年はバタバタしていて仕込めなかったので、今年はキチンとやろうと思った。
今年も閉鎖前の築地に行った時に場外のいつも豆を買う店で、
「味噌に使う豆を下さい、去年だか一昨年もここで買ったんだけれど・・・」って言ったら、
「あ、それは『鶴の子』だよ、あと2週間したら入荷するから、その時又来てよ!!」って言われ
↓
2週間後行ってみた訳なんだけれど、当然売る方は業者取引では無い自分の顔は忘れているワケで(←、ま、それは立場が逆だったら自分もそうだから良いんだけれどね・・・)
↓
「今年、記録的大不作で~11月になったら又来てよ!!」って言われ、
でも・・・、
・もう2週間待ったんだし、又、来て入荷していなかったらな~っていうのと、
・自分が『鶴の子』という銘柄の大豆でしか味噌を作れないようになる事が怖かった事。
(レシピがあるのが調理で、レシピが無くても作れるのが料理って昔板前さん達と話していたし、どっちの方がが大事ってこともなく調理も料理も両方大事なのだけれど、その材料が無いから出来ないってなんかカッチョワルイ気がして)
・『鶴の子』と『他の豆』との違いを把握しておく事も大事な事なのではないか?って
なんとな~くぼんやりメリット・デメリットが頭の中に浮かんできて、
↓
今、入荷しているもので味噌に向いているものを教えて頂いた。
↓
で、宮城県の奨励品種でもあるシロメ大豆というもので、後日、調べると・・・

・宮城県は北海度に継いで大豆の栽培面積が第二位。
・加熱後にエグミが抑えられ、甘味が強い。
・大豆の目(ヘソ)が白いからシロメと言われ、黒目と違い色が目立たないので豆腐や味噌・煮豆・豆菓子等、加工用品に向いている。
・タンパク質と糖分が豊富らしい。
・国産大豆の中でもワンランク上。
な~んだ、これも良い豆なんじゃない!!
(確かに煮上がったモノを1個食べたら甘かった・・・)
ということで日を決めて、洗ってから→水に浸し

18時間以上置く。
※前回はどうしても外せない急な用事が入ってしまったので2日間漬けてしまったが、
本当は前回と同じ作り方の方が比較がし易いけれど、それは正式ではないので18時間~20時間だけ漬けてふやかしてみた。

新しい水で炊く。

その間に麹と塩を混ぜ、塩キリをつくっておく。
(ビニール袋に穴が・・・ショック!!、なんだこのポリ袋・・・なんか今回ヤバいぞ・・・???)
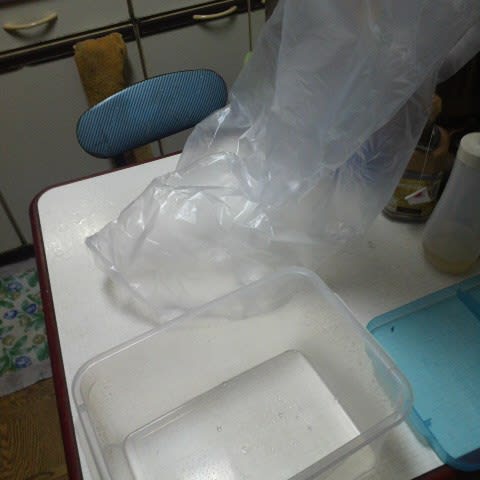
最初は強火で後は中火~弱火だが、

あまり火力が低くてもアクと共に皮が出てこない。

このぐらいは必要なのかなぁ・・・?

アク取りも大きい網すくいよりも

前から使っていた方が取れる。

今回は2日漬けていないから、柔軟に本来3時間煮る所を4時間にしてみた。
(5時間煮る人も居るから・・・でも、3時間の時点で豆が潰せたから3時間で良かったかも、もくは3時間半)
↓
今回は鍋に付いたカスが固まりこびり付く前に先に洗ってしまう。

これは正解だった。
1回詰めたんだかれど、なんか前回より硬い気がするので・・・
(ま、今回2日間漬けていないから、これが正式なんだろうけれど・・・)
取っておいた煮汁と塩で種水を作る事にした。

(『種水』を入れると粘度を軟らかく出来るがカビ易いんだよな~)
↓
今回も使わない予定だったので冷めていたから1度沸かして、塩を入れる。
調べると、
・煮汁500mlで→塩60g
・煮汁300mlで→塩40g
が多かったのでその塩梅で。
(煮汁300mlだったから40gの塩にした)

熱々だと麹が死んでしまうので、冷煎して少しだけ冷ます。

もう1回容器に入れた味噌をほじくり出して、種水をレンゲでちょっとづつ入れて粘度を調整・・・ヤバイ、殺菌どころじゃねーな。

ふと気付くと、透明なケースの横から見ると空気穴が何箇所か見える。
(やはり前回より余裕が出て、前に気付かなかった事に気付く様になる)
こういうところからカビてしまいそうなので

よく押した。
(種水を入れたので押して動かせるぐらいの粘度はある、前回は少し呼吸させる事を意識したが、今回は種水を使ったのでなるべくカビさせ無い事を意識させてみた、保存料や添加物を使っていないので多少はどんな味噌もカビで破棄する分はあるものだが)

なんとなく、昔、店で毎日糠みそを作っていた時の事を思い出して、
(やはりアレも1度沸かした塩水を入れるから・・・)
↓
糠みそもやっぱり、味噌なんだなぁって改めて感じた。
(出勤してから、よく俺、朝・夕営業前に毎日糠みその手入れをしていたよな~、体力があったんだなぁ・・・鷹の爪で皮膚はかぶれたが・・・)
前回の要領で
↓
ラップ
↓
ワサビ
↓
皿

↓
1Fの暗い所に持っていって、ビニール(←このポリ袋・・・冒頭の破れていたものと同じポリ袋だが大丈夫か?)で包んで、鉄アレイをビニールで包んだ重しを乗せて

あまりキツク縛ると発酵菌が呼吸を出来ないかな?と思って、やや軽く縛って

とりあえず「作成年月日」を貼り付けて寝かす。
今回はどうなるかな・・・
(ミスが多過ぎた・・・)
あと最初に上手くいき過ぎると、課題が見付からないから、
↓
次、ここをこうしようとか改善点・問題点・気を付けるポイントが解らない。
↓
だから課題が見付かった方が後々の為になるし、
「課題が見付からない事の方が怖い事なんだよ」って後輩達に教えてきた。
どんな業種も職種も、常に向上心みたいなものを持たないと活きていけない世の中だと思うので(=特に料理はそうかもしれない)。
事務に特化している人が苦手なのはそういう事なんだと思う。
(自分も事務モードの時は絶対に料理をしないし、勘や感性が鈍っているから=事務モードの時は料理の丁度良い塩梅をキチっとやり過ぎてしまい、味が強くなる傾向があるから)
『今回は』
・前回、記録しそびれた部分を確認出来たし、
・課題が、随分見付かったと思う。
・皆が使っている『種水』の使い方も解ったし。
・ただ2日漬けて(暑さで腐らない限り)、水分を豆の分子・原子レベルに浸み込ますワザはアリな気がする。
・最初のポリ袋が穴が空いていたのかなんなのか解らんが塩がもれていたので、その分をなんとなく足して(←床に散らばった塩の分量なんて解らんわ)、
↓
殺菌の為に上に塩を多めに蒔いた。
(前回が私の事だから薄味に作った為に、少し塩気が弱くて味噌汁にした時に大量に使わざるえなかったのもあって、もしかしたら薄かったかなぁ~?というのもあったので、まあ馴染めば塩気も多少はやわらぐが)
↓
ただ、今回、塩気が濃かったら、塩分は強いのにコクが少ないという事にもなりかねない。
4時間煮て、旨味も外に出ているし。
こればかりは回数を重ねて出来てみないと解らないものなぁ。
(気候・温度・湿度の問題もあるのかもしれないし)
忘れないように後から『追加』
しまう時に縁に付いたカスや塩は焼酎で殺菌をしたクッキングペーパーで拭いておくと良い。

次に作る時の為に。
因みに『鶴の子』についても調べてみた。
(現段階で、より比較出来る部分を可視化出来るかな?って・・・後でどの辺が良くなかったか?も明確に目で振り返れるし)
↓
・国産最高品種大豆(→どうりで高いワケか)
・大粒(→どうりで出来上がりの量が違う訳だ、前回2日ふやかしたというのもあるが)
・モチモチした食感
・「ユウヅル」、「早生つるの子」、「甘露」、「白鶴の子」、「つるの子」というブランド名でいくつか流通をしている。
・自然な甘さ。
・皮が切れ易い(→それで煮た時に皮が浮いてき易いのね)
↓
調べたら、別に味噌に皮が入ってはいけないって事も無いようだが、発酵しても皮は分解されないので、アクと共に多く皮をすくい取った方が滑らからしい。
(今回取るには取ったが、4時間と煮過ぎたからか皮が破れて紛れ込んでいる量が多いと思う)
↑
メーカーさんは全部の皮を剥いてから、蒸したりしているようだ。
蒸した方が煮るより旨味が残るらしい。
(やっぱり煮過ぎてはいけないのか!!)
3ヵ月後(ぐらい)に、天地返しを行った。
(やんないとダメなんだろうな~、これ・・・)
特にカビみたいなのは見当たらなかったが、タッパの縁に白いモノが、塩とか大豆のカスだと思うんだけれど。

不思議と味噌作りは、アクシデントが起きても動じず、次の動きを考えられる事が多い。
(やはり日本人のDNAだからだろうか?)
一応、消毒するアルコール(焼酎)をクッキングペーパーに浸み込ませて拭き取る。

作り作り始めの初めの最初からしておけば良かったな

天地を反した後、消毒した拳で縁まで含め中までグググっと押し込んで空気を抜くが、
手早くやって雑菌をなるべく付けないように。

ラップを殺菌して

ひっくり返して

又、元の様に新しいワサビを置いて、封と重しをして又3ヶ月~6ヶ月ぐらい寝かす。
(3ヶ月ぐらいしたら食べられるようになるらしいが、前回は冬の終わり頃に作って、夏を越えさせたのかな?)
・夏を越えさせて更に長期熟成させるか?
・痛み易い夏前に熟成を切り上げるか!!?
やはり最初は見よう見真似で出来てしまうが、それ以降の方が疑問が出てくるものだな。
始めた味噌作り、
↓
昨年はバタバタしていて仕込めなかったので、今年はキチンとやろうと思った。
今年も閉鎖前の築地に行った時に場外のいつも豆を買う店で、
「味噌に使う豆を下さい、去年だか一昨年もここで買ったんだけれど・・・」って言ったら、
「あ、それは『鶴の子』だよ、あと2週間したら入荷するから、その時又来てよ!!」って言われ
↓
2週間後行ってみた訳なんだけれど、当然売る方は業者取引では無い自分の顔は忘れているワケで(←、ま、それは立場が逆だったら自分もそうだから良いんだけれどね・・・)
↓
「今年、記録的大不作で~11月になったら又来てよ!!」って言われ、
でも・・・、
・もう2週間待ったんだし、又、来て入荷していなかったらな~っていうのと、
・自分が『鶴の子』という銘柄の大豆でしか味噌を作れないようになる事が怖かった事。
(レシピがあるのが調理で、レシピが無くても作れるのが料理って昔板前さん達と話していたし、どっちの方がが大事ってこともなく調理も料理も両方大事なのだけれど、その材料が無いから出来ないってなんかカッチョワルイ気がして)
・『鶴の子』と『他の豆』との違いを把握しておく事も大事な事なのではないか?って
なんとな~くぼんやりメリット・デメリットが頭の中に浮かんできて、
↓
今、入荷しているもので味噌に向いているものを教えて頂いた。
↓
で、宮城県の奨励品種でもあるシロメ大豆というもので、後日、調べると・・・

・宮城県は北海度に継いで大豆の栽培面積が第二位。
・加熱後にエグミが抑えられ、甘味が強い。
・大豆の目(ヘソ)が白いからシロメと言われ、黒目と違い色が目立たないので豆腐や味噌・煮豆・豆菓子等、加工用品に向いている。
・タンパク質と糖分が豊富らしい。
・国産大豆の中でもワンランク上。
な~んだ、これも良い豆なんじゃない!!
(確かに煮上がったモノを1個食べたら甘かった・・・)
ということで日を決めて、洗ってから→水に浸し

18時間以上置く。
※前回はどうしても外せない急な用事が入ってしまったので2日間漬けてしまったが、
本当は前回と同じ作り方の方が比較がし易いけれど、それは正式ではないので18時間~20時間だけ漬けてふやかしてみた。

新しい水で炊く。

その間に麹と塩を混ぜ、塩キリをつくっておく。
(ビニール袋に穴が・・・ショック!!、なんだこのポリ袋・・・なんか今回ヤバいぞ・・・???)
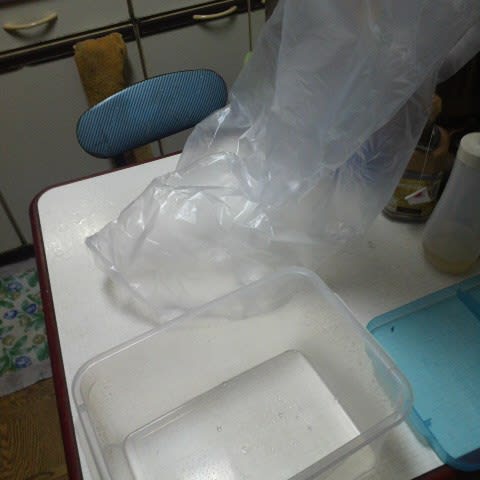
最初は強火で後は中火~弱火だが、

あまり火力が低くてもアクと共に皮が出てこない。

このぐらいは必要なのかなぁ・・・?

アク取りも大きい網すくいよりも

前から使っていた方が取れる。

今回は2日漬けていないから、柔軟に本来3時間煮る所を4時間にしてみた。
(5時間煮る人も居るから・・・でも、3時間の時点で豆が潰せたから3時間で良かったかも、もくは3時間半)
↓
今回は鍋に付いたカスが固まりこびり付く前に先に洗ってしまう。

これは正解だった。
1回詰めたんだかれど、なんか前回より硬い気がするので・・・
(ま、今回2日間漬けていないから、これが正式なんだろうけれど・・・)
取っておいた煮汁と塩で種水を作る事にした。

(『種水』を入れると粘度を軟らかく出来るがカビ易いんだよな~)
↓
今回も使わない予定だったので冷めていたから1度沸かして、塩を入れる。
調べると、
・煮汁500mlで→塩60g
・煮汁300mlで→塩40g
が多かったのでその塩梅で。
(煮汁300mlだったから40gの塩にした)

熱々だと麹が死んでしまうので、冷煎して少しだけ冷ます。

もう1回容器に入れた味噌をほじくり出して、種水をレンゲでちょっとづつ入れて粘度を調整・・・ヤバイ、殺菌どころじゃねーな。

ふと気付くと、透明なケースの横から見ると空気穴が何箇所か見える。
(やはり前回より余裕が出て、前に気付かなかった事に気付く様になる)
こういうところからカビてしまいそうなので

よく押した。
(種水を入れたので押して動かせるぐらいの粘度はある、前回は少し呼吸させる事を意識したが、今回は種水を使ったのでなるべくカビさせ無い事を意識させてみた、保存料や添加物を使っていないので多少はどんな味噌もカビで破棄する分はあるものだが)

なんとなく、昔、店で毎日糠みそを作っていた時の事を思い出して、
(やはりアレも1度沸かした塩水を入れるから・・・)
↓
糠みそもやっぱり、味噌なんだなぁって改めて感じた。
(出勤してから、よく俺、朝・夕営業前に毎日糠みその手入れをしていたよな~、体力があったんだなぁ・・・鷹の爪で皮膚はかぶれたが・・・)
前回の要領で
↓
ラップ
↓
ワサビ
↓
皿

↓
1Fの暗い所に持っていって、ビニール(←このポリ袋・・・冒頭の破れていたものと同じポリ袋だが大丈夫か?)で包んで、鉄アレイをビニールで包んだ重しを乗せて

あまりキツク縛ると発酵菌が呼吸を出来ないかな?と思って、やや軽く縛って

とりあえず「作成年月日」を貼り付けて寝かす。
今回はどうなるかな・・・
(ミスが多過ぎた・・・)
あと最初に上手くいき過ぎると、課題が見付からないから、
↓
次、ここをこうしようとか改善点・問題点・気を付けるポイントが解らない。
↓
だから課題が見付かった方が後々の為になるし、
「課題が見付からない事の方が怖い事なんだよ」って後輩達に教えてきた。
どんな業種も職種も、常に向上心みたいなものを持たないと活きていけない世の中だと思うので(=特に料理はそうかもしれない)。
事務に特化している人が苦手なのはそういう事なんだと思う。
(自分も事務モードの時は絶対に料理をしないし、勘や感性が鈍っているから=事務モードの時は料理の丁度良い塩梅をキチっとやり過ぎてしまい、味が強くなる傾向があるから)
『今回は』
・前回、記録しそびれた部分を確認出来たし、
・課題が、随分見付かったと思う。
・皆が使っている『種水』の使い方も解ったし。
・ただ2日漬けて(暑さで腐らない限り)、水分を豆の分子・原子レベルに浸み込ますワザはアリな気がする。
・最初のポリ袋が穴が空いていたのかなんなのか解らんが塩がもれていたので、その分をなんとなく足して(←床に散らばった塩の分量なんて解らんわ)、
↓
殺菌の為に上に塩を多めに蒔いた。
(前回が私の事だから薄味に作った為に、少し塩気が弱くて味噌汁にした時に大量に使わざるえなかったのもあって、もしかしたら薄かったかなぁ~?というのもあったので、まあ馴染めば塩気も多少はやわらぐが)
↓
ただ、今回、塩気が濃かったら、塩分は強いのにコクが少ないという事にもなりかねない。
4時間煮て、旨味も外に出ているし。
こればかりは回数を重ねて出来てみないと解らないものなぁ。
(気候・温度・湿度の問題もあるのかもしれないし)
忘れないように後から『追加』
しまう時に縁に付いたカスや塩は焼酎で殺菌をしたクッキングペーパーで拭いておくと良い。

次に作る時の為に。
因みに『鶴の子』についても調べてみた。
(現段階で、より比較出来る部分を可視化出来るかな?って・・・後でどの辺が良くなかったか?も明確に目で振り返れるし)
↓
・国産最高品種大豆(→どうりで高いワケか)
・大粒(→どうりで出来上がりの量が違う訳だ、前回2日ふやかしたというのもあるが)
・モチモチした食感
・「ユウヅル」、「早生つるの子」、「甘露」、「白鶴の子」、「つるの子」というブランド名でいくつか流通をしている。
・自然な甘さ。
・皮が切れ易い(→それで煮た時に皮が浮いてき易いのね)
↓
調べたら、別に味噌に皮が入ってはいけないって事も無いようだが、発酵しても皮は分解されないので、アクと共に多く皮をすくい取った方が滑らからしい。
(今回取るには取ったが、4時間と煮過ぎたからか皮が破れて紛れ込んでいる量が多いと思う)
↑
メーカーさんは全部の皮を剥いてから、蒸したりしているようだ。
蒸した方が煮るより旨味が残るらしい。
(やっぱり煮過ぎてはいけないのか!!)
3ヵ月後(ぐらい)に、天地返しを行った。
(やんないとダメなんだろうな~、これ・・・)
特にカビみたいなのは見当たらなかったが、タッパの縁に白いモノが、塩とか大豆のカスだと思うんだけれど。

不思議と味噌作りは、アクシデントが起きても動じず、次の動きを考えられる事が多い。
(やはり日本人のDNAだからだろうか?)
一応、消毒するアルコール(焼酎)をクッキングペーパーに浸み込ませて拭き取る。

作り作り始めの初めの最初からしておけば良かったな

天地を反した後、消毒した拳で縁まで含め中までグググっと押し込んで空気を抜くが、
手早くやって雑菌をなるべく付けないように。

ラップを殺菌して

ひっくり返して

又、元の様に新しいワサビを置いて、封と重しをして又3ヶ月~6ヶ月ぐらい寝かす。
(3ヶ月ぐらいしたら食べられるようになるらしいが、前回は冬の終わり頃に作って、夏を越えさせたのかな?)
・夏を越えさせて更に長期熟成させるか?
・痛み易い夏前に熟成を切り上げるか!!?
やはり最初は見よう見真似で出来てしまうが、それ以降の方が疑問が出てくるものだな。























