神代文字

(jindai12.jpg)

(jindai10.jpg)

(jindai11.jpg)
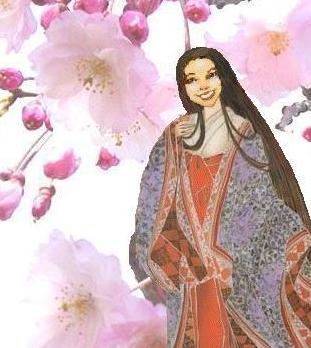
(himiko93.jpg)

(himiko22b.gif)
デンマンさん。。。 どういうわけで神代文字を取り上げたのでござ〜ますかァ?

(kato3.gif)
ネットサーフィンしていたら次の動画に出くわしたのですよ。。。

(jindai-moji5.jpg)
■『動画を観る』

確かに、神代文字というのはネットでは時々話題になっていますわ。。。先日、デンマンさんがしばしば取り上げている反日作家の伊藤浩士先生のブログを覗いてみたら次のような記事を見かけましたわ。。。
文字

(jindai30.jpg)
古事記の伝承では、応神天皇の時代に百済から王仁(わに)という学者が日本に論語と千字文をもたらしたとなっていて、王仁こそが日本の文字の始まりだとされています。応神天皇も王仁も存在が怪しくはっきりしないのですが、王仁を音読みにすれば、オウジンですから、同一人物で、応神天皇が百済人で日本に文字の文明をもたらした可能性もあります。
仏教も暦も文字も百済経由で日本にやって来ており、百済人がもたらしたとされており、古代豪族の多くも渡来人系であるとされていますから、大和朝廷は、文明を持たない原住民の上に、発達した文明を持った百済人が権力構造を構築したものと考えられます。神武天皇が高天原からやって来たのは嘘で、応神天皇=王仁が百済からやって来たのが歴史的事実でしょう。
そうなると邪馬台国のころに文字があったのかどうかですが、文字があれば保存する必要がありますから、竹簡とか粘土板に書くことになりますが、そういうものが邪馬台国に比定される遺跡から見つかっていないことを考えると、倭国には文字がなく、使者が魏の皇帝に出した上奏文は帯方郡の役人に代筆してもらっていたのでしょう。蛮夷を連れて行けば帯方郡の手柄になりますから代筆くらいはやります。
応神天皇は存在が怪しいのですが、朝廷では近世に至るまで応神天皇を天皇家の祖としており、応神天皇である八幡神、神仏混交で八幡大菩薩とも呼ばれますが、それを崇敬していましたから、開祖が文明である文字を持って来たとの伝承であれば、話の辻褄としては合います。
本居宣長は漢字が伝わるまでは日本には文字は無かったと言っています、平田篤胤が日本には独自の文字があったとしたいので神代文字を捏造しました。捏造するにしても、他の国に類のない文字を創作する智慧はなくて、韓国のハングルをパクって、神代文字を捏造しました、昔からパクリと捏造は日本の愛国者の得意技だったのです。
奈良時代以前の日本語の発音は母音が8つありました、ところが神代文字の母音は5つなので、後世の捏造であることは明らかです。捏造と分かっているので長い間無視されてきましたが、日本社会で極右勢力が台頭すると、漢字の渡来以前に神代文字が使われていたと主張する人が増えて来ています。
残っていない事実を指摘されると砂に書いていたから消えたのだと主張するバカ(詭弁・妄言・虚言・暴言の櫻井証)がいるかと思えば、参政党のアドバイザーになっている小名木善行などは、神代文字が先にあってそれが中国へ行って漢字になったという、正気の沙汰とは思えない議論をやっていて、神代文字に関しては全日本バカ決定戦の様相を呈して来ています。
コメント

1.
奈良時代のように、今でも日本語に母音が8つあればもう少し日本人も外国語の習得が容易になったかも知れませんね。文法が難しくて、発音が簡単という点では日本語はフィリピン🇵🇭語(タガログ語)に似ていると思います。
日本語が外国の言語に影響を与えたとするなら、系統関係が認められるはずなのですが、日本語は孤立した言語であるとされていて、その日本語が外国語に影響を与えているはずがなく、日本信者阿呆ホシュ達はその点でもご都合主義ですね。
ブラジル🇧🇷の人で日本は教育が素晴らしいから経済大国になった、サッカーの強さをあげても良いから、日本の教育制度をこちらに欲しいですねと言った人がいたのですが、外国人なので日本の実情が分からないので仕方ない面はありますが、今の日本は全く上手くいっておらず、教育もいじめや体罰や不登校、学級崩壊などの問題が噴出していることを知らないのでしょうね。
そうした人には、日本人が理屈や道理で動かない人間で、そういう部分を真似したら駄目ですよと教えてあげないと駄目ですね。隣の芝生は青く見えると言いますが、日本よりブラジルの方が余程将来性があると言っておいた方が良いと思います。
sl715046(反日マニア)2023-12-28 07:18:05

2. Re:無題
>sl715046(反日マニア)さん
日本はユーラシア大陸の文化の終着点なので、そこの文化が入って来て土着のものと入り混じって成立しています、日本から言語や技術などが大陸に向かって発信されることはあり得ません。言語にしても外来の文字など習得しましたが、日本語が外国語に影響を与えることはありません。
日本信者阿呆ホシュ達は、世界の文化や言語は日本発祥であり、日本のものが外国に伝わって外国の文化や言語が成立したとしています。神代文字が漢字のもとなどという飛んでもない妄想も語られている状態です。
日本の教育が素晴らしくてその原点は教育勅語であるから、レーガンやサッチャーが自国へ教育勅語を持って帰って使っているというデマがありましたが、ブラジルの話も似たようなものでしょう。
どこの国でも問題を抱えておりそれは自力で解決するしかなく、他所の国の真似をしてよくなるものではないこれは当たり前のことです、日本は特に良くないのにその真似をするなどあり得ないことだと思います。
itou-hirosi1999(伊藤浩士)2023-12-28 20:43:49
『第27回 文字』より
2023-12-28 07:00:00
(反日作家・伊藤浩士のブログ)

これは伊藤浩士・反日作家が2013年の12月に書いた記事ではありませんかァ〜。。。

そうですわ。。。神代文字で検索したら出てきたのでござ〜ますわァ。。。
僕もこの記事を読みましたよ。。。「(神代文字が)残っていない事実を指摘されると砂に書いていたから消えたのだと主張するバカ(詭弁・妄言・虚言・暴言の櫻井証)」が居ましたというのが印象的でした。。。
デンマンさんは神代文字を認めているのですか?
神代文字が大昔にあって日本語の文字の源流だという人がけっこう居るのだけれど僕は信じていません。。。
神代文字

(jindai11.jpg)
神代文字は、漢字伝来以前の日本に存在したと主張されてきた、固有の文字のことである。
国語学的に見て完全に否定されている。
通説において、日本には漢字以前に書記体系は存在せず、日本独自の文字である仮名文字が出現するのは9世紀から10世紀のことである。
「上古の日本に何らかの文字体系があった」とする説は、すでに鎌倉期から卜部兼方などが提唱していたが、神代文字に関する議論が特に盛んになったのは近世のことである。
この時代、多くの神代文字が「発見」され、平田篤胤ら神道家によって盛んにその実在が主張されるようになったが、こうした文字の存在を疑う声は、当時からすでに大きかった。
近代に入ると、神道系新宗教によって、盛んに神代文字により書かれた古史古伝の存在が喧伝され、こうした文書は政官界にすら強い影響を与えることがあった。
また、国学者のあいだでも神代文字を信じる者がいた。
これゆえ、当時の国語学者はその存在を黙殺することができず、これを繰り返し否定する必要があった。
山田孝雄による神代文字否定論をもって、神代文字の真偽が学術的に鑑みられることはなくなった。
山田以来、神代文字の存否を論じるような研究は途絶えたが、神代文字という概念は近世・近代の思想潮流を大いに反映するものであり、思想史の観点から研究が続けられている。
漢字の伝来と仮名の発生
日本列島(倭)に漢字を記した事物が伝来したのはおよそ1世紀のことであると考えられており、漢委奴国王印や、新代の銅銭である貨泉などが出土している。
日本列島に文字文化が浸透したのがいつであるかについては不明瞭であるが、5世紀には稲荷山古墳出土鉄剣、江田船山古墳出土鉄刀、隅田八幡神社人物画像鏡などにみられるよう、日本語の地名・人名が漢字を用いて記されるようになる。
6世紀から7世紀にかけては中国大陸の行政機構が取り入れられるようになり、官人を中心に漢字の識字層が増えていった。
とはいえ、太安万侶が和銅5年(712年)編纂の『古事記』序文において、「已に訓に因りて述ぶれば、詞は心に逮らず。全く音を以ちて連ぬれば、事の趣更に長し」と嘆くよう、日本語に用いる書記体系として、漢字は扱いやすいものではなかった。
そこで、これを補うための表音文字であるところの仮名が成立していった。
片仮名の起源となったのは漢文訓読にあたって用いられた省画された漢字であり、日本においては伝神護景雲2年(767年)書写の『大方広仏華厳経巻第四十一』などに角筆による書き込みが確認されている。
また、漢字の草体をさらに崩す形で成立した平仮名については、藤原良相邸跡(9世紀)から出土した墨書土器などに初期の例を確認することができるほか、貞観9年(867年)の『讃岐国司解有年申文』などにも用いられている。
こうした仮名文字が、漢字とは異なる文字体系として認識されはじめたのは9世紀末から10世紀前半のことであると考えられている。
たとえば寛平9年(897年)の宇多天皇宸翰である『周易抄』では、訓注用仮名として万葉仮名の草体に基づくもの、傍訓用仮名として省画体本位の片仮名が使い分けられている。
10世紀には万葉仮名は使われなくなり、平仮名のみで書かれた文献、片仮名のみで書かれた文献も多く現れるようになった。
史書によれば、上古の日本において文字は用いられていなかった。
大同2年(807年)に斎部広成が著した『古語拾遺』には、「蓋し聞く、上古の世未だ文字有らず、貴賎老少、口々に相伝え、前言往行は存して忘れず。書契以来、古を談ずるを好まず」とある。
『古事記』によれば、応神天皇15年に百済王の遣いとして遣わされた王仁(和邇吉師)が、『論語』十巻と『千字文』一巻を付して貢進したとされるが、『千字文』の成立はそれより時代の下る梁代に周興嗣によっておこなわれたものであり、史実性は詳らかではない。
とはいえ、伝統的には「応神期をもって日本に文字が伝来した」とする見解が多く、大江匡房『筥埼宮記』、一条兼良『日本紀纂疏』などが同説をとっている。
歴史
上古の日本に独自の文字体系が存在したという説がとなえられるようになったのは、鎌倉期のことであり、卜部兼方の『釈日本紀』(鎌倉末期)には、以下のような記述がある。
又問う。仮名字、誰人作なす所か。
答う。師説に、大蔵省の御書の中に肥人の字六七枚許有り。先帝御書所に其字を写さしめ給う。皆仮名を用いる。或は其字未だ明ならず。或は乃の、川つ等の字明かに之見ゆ。若し彼を以て始と為すべきか。先師の説に云う。漢字我が朝に伝え来ることは応神天皇の御宇なり。和字に於いては其の起り神代に在るべきか。亀卜の術は、神代より起れり。
所謂る此の紀一書の説に、陰陽二神姪児ひるこち生あれます。天神あめのかみ太占を以て之を卜うらない、乃ち時日を卜定して之を降したまう。文字無しは、豈に卜を成すべけんや。作者、事の濫觴、神代には在るべき者は、幽玄にして測り難し。伊呂波は弘法大師所作の由申し伝うるか。此れは昔より伝来の和字を伊呂波に作成せらるの起りなり。
—卜部兼方、『釈日本紀』
同書には、「師説」によれば、「先帝」が大蔵省の御書所に「肥人の字」なる文字を写させたとある。
この文字には「乃」や「川」にみえるものがあったといい、兼方はこれを典拠として、弘法大師が仮名をつくったというのは誤りであり、上古にはすでに仮名があったと考えるべきであると論じた。
また、彼は、そうでなければ当時太占のような占いができたはずがないと述べている。
しかし、山田がいうように、亀卜と漢字の関係が緊密であったことが事実であったとしても、太占がそうであるとする根拠はない。
山田孝雄のように、ここでいう「師」とは矢田部公望のことであり、「先帝」は醍醐天皇を指すという論がある一方で、新村出は、公望の著作にそのような主張は存在しないとして、兼方あるいはその師の説であるという以上のことは言えないと論じている。
さらに、忌部正通が正平22年・貞治6年(1367年)に執筆したとされる『神代巻口訣』は、より具体的に神代文字の存在に触れている。
いわく「神代文字は象形なり。応神天皇の御宇、異域の典経始めて来朝す。推古天皇の朝に至って、聖徳太子漢字を以て和字に附す」とある。
同説は、上古の日本においては「象形文字」が用いられていたものの、聖徳太子による国史(国記・天皇記)編纂にあたって廃されたというものである。
さらに、卜部兼倶(吉田兼倶)が応仁・文明期に執筆した『日本書紀神代抄』には以下のようにあり、上古の日本には博士(声明の旋律をあらわす符号のこと)に類似した文字があったと述べている。
一方で、山田は兼倶は明らかに平安中期に生まれた五音博士(五声をあらわす博士)を下敷きにして同文字について論じていること、卜部家の祖先にあたり、上古の文字にも興味を持っていたはずの兼方がこの文字に対して一切触れていないことなどから、卜部家伝来の神代文字が存在したという説については疑問視している。
いろは四十七字は弘法大師之を作す。カタカナは吉備大臣之を作す。あいうえおの五十字は神代より之有る。神代の文字は一万五千三百六十字あるぞ。はかせと云が神代の字なり。伊弉諾伊弉冉天浮橋の上に立て曰く、底下豈に国無からんやと。廼すなわち天之瓊矛以て指下して之を探かきさぐりしかば、是に滄溟あおうなばらを獲き。其後万物を生す時にうらをしたぞ。卜うらは陰陽の源五行の変より起るぞ。
其処から文字は出来るぞ。紙墨にあらわすばかり、文字ではないぞ。森羅万象は天地自然易なり。伏義空中に向かいて一画を下すは自然の文字なり。陰陽は元来一なり。散りて万物と為る処にて文字の数も多なるぞ。一念の心は多念はない。万物の転を被り、万念を作すほどに、文字も万物につれて、繁多になるぞ。亀を焦す時に、五にわりて配五行ぞ。変する時に一万余りを為すぞ。文字も万物の変に依て、五万三千余を為すなり。
—卜部兼倶、『日本書紀神代抄』
また、兼倶の子である清原宣賢が大永年中に記した『神代抄』には「神代の文字は秘事にして流布せぬ。一万五千三百六十字あり。其字形声明のはかせに似たり」とある。
宣賢の玄孫にあたる清原国賢も、慶長4年(1599年)の『日本紀神代巻奥書』において神代文字の存在に触れている。
延宝期に「発見」された『先代旧事本紀大成経』は『先代旧事本紀』の底本をうたった。
同書は長野采女により偽作され、黒滝潮音によって刊行された偽書であるが、同書には、アマテラスが発した47字からオオナムジとアメノヤゴコロが神代文字をつくったとする記述があり、後世に大きな影響を与えた。
とはいえ、山田が論じるようにそもそも当時の日本語は47音ではなく、三ツ松誠は、「かかる神代文字は、いずれも『大成経』の影響を受けた偽作だということになる」とまとめる。
垂加神道家の神代文字
中世においても上古の日本に独自の文字が存在したという見解は存在したものの、実際にこうした神代文字が「発見」されるに至ったのは近世のことである。
享保9年(1724年)に垂加神道家である跡部良顕が著した『和字伝来考』は、当世においては、儒学ばかりを学び神道について無知であるゆえに「我国を文字なき夷国と覚たる者」が多いことを嘆き、師の渋川春海が紹介する「十二支の神代文字」について触れる。
良顕は、これが神代文字であることは、春海だけでなくその師である山崎闇斎も認めるところであると論じる。
同文字は実際に春海『瓊矛拾遺』にもあらわれるものの、「神代文字と謂うべき者か」とその書きぶりは抑制的なものであり、かつその典拠が『琉球神道記』に記述のある、琉球の十二支記号であることは、平田篤胤なども指摘するところである(琉球古字)。
山田は、良顕がこの事実に気づいていなかったと批判する一方、原田実は阿比留文字などにもみられるよう、琉球や朝鮮といった日本の「辺境」に神代文字の痕跡が残っているとする考えは一般にあったものと論じている。
神代文字に対する懐疑論
近世において神代文字の実在について論じた学者としては新井白石が早く、「奉答本郷平先生問目」において以下のように述べている。
平田篤胤は『神字日文伝』において「近き世の人に、神代に文字ありと論(い)えるは、新井君美ぬしぞ始なりける」と論じているが、白石の口ぶりは断定的なものではない。
白石は同文をそえて佐久間洞巖に書簡を送っており、熱田神宮や出雲大社に伝わるという竹簡を見ない限りには神代文字の真贋は論じられないと述べている。
東方文字其の来る尚し。蓋し太古以降歴世其の体を変じ、列国其の制を異として、考詳の由無し。俗に聞く神代文字、美嘗て其の聞くを得るは凡そ五つ。或いは其の字読むべからざる者有り、或いは科斗書に如く者有り、或いは鳥篆に如く者有り、古体の変蓋し此の如し。
天武の世更に新字を造ること四十四巻、其の体梵書の如し。又肥人書有り、薩人書有りて、肥人書一二字即ち今なお通用する者有り。古きは列国各其の字あり、亦た以て証有り。卜部家所伝一万五千三百七十九字乃ち是れ亀を灼くの兆は猶ほ卦の爻有るがごとし。
—新井白石、奉答本郷平先生問目
近世においてはじめて神代文字を全く否定する論考を出したのは貝原益軒であり、『和事始点例説』には「今巫覡の家に上古の和字と称し符に書は遵生八牋 不求人等に載たる中華道士の符章に書く偽字なるを知らで上古の和字と思へるは固陋の至なり」とある。
また、『自娯集(じごしゅう)』においては『古語拾遺』や『筥埼宮記』などを引用し、上古の文字の存在を否定している。
太宰春台も『倭読要領』において「吾国に文字なき事は、先賢の説明白なり……巫祝の徒(ともがら)往往吾國に文字ありしことをいうは皆孟浪の談なり」と、端的に神代文字の存在を否定する。
彼ら漢学者のみならず、多くの国学者も神代文字に際しては冷淡であった。
契沖は『和字正濫鈔』において「此国に神も人も文字を作り給はぬは漢土にならひて然るべき故あるなるべし」と述べるほか、本居宣長は『古事記伝』において「今神代の文字などいう物あるは、後世人の偽作(いつわり)にて、いうにたらず」、賀茂真淵は『語意考』において「此れの日出ずる国は、五十連の音のまにまに言(こと)を成して萬ずのことを口から言い伝える国なる」と論じている。
竹内文書

(takeuchi-bunsho.jpg)
『竹内文書』は神道系新興宗教である皇祖皇太神宮天津教が「神宝」として伝えていた文書・文献の総称である。
教祖の竹内巨麿いわく、皇祖皇太神宮は人類発祥以来の歴史を誇る古社であったが、彼が明治33年(1900年)に茨城県多賀郡磯原町で同宗教を「再興」するまでは廃絶していた。
同書には多数の神代文字が収録されており、阿比留文字・阿比留草文字・豊国文字といった既存のものからオリジナルのものまで、五十音図のかたちに整えられたものだけでも38種類の文字体系が記載される。
竹内らは名士に対しても積極的にロビー活動をおこない、昭和3年(1928年)3月29日には公爵・一条実孝、海軍大将・有馬良橘などを磯原に呼び寄せ、「神代文字神霊宝巻」なる文献を拝観させた。
この2ヶ月後には陸軍大将の本郷房太郎が同文献を拝観し、「日本に文字の起源ありとは、実に得がたき文化の発祥地といわねばならぬ」と感激したという。
竹内文書の信奉者としては、ほかに小磯国昭が存在した。
小磯は竹内文書をはじめとする古史古伝を政官会や軍部に広める活動をしていた中里義美と懇意であり、昭和15年(1940年)には中里が代表を務める神之日本社主催の「神日本思想強調の夕べ」なる会合で、以下のような内容の講演をおこなっている。

(kuniaki_koiso.jpg)
海外諸国の至るところに発見される奇妙不思議なる彫刻の文字が我国の神代文字に合すれば、これまた簡単に読破されるというではないか。
故に吾等は断じて現実の科学証左に捉われることなく、報本反始の古き昔に還って、揺ぎなき万代の根柢を為す神代史実の究明こそは、刻下焦眉の急であると断ぜずには居られない。
—小磯國昭、「神日本思想強調の夕べ」講演
とはいえ、大本同様、天津教も取り締まりの対象となっていた。
昭和11年(1936年)には特高警察が、竹内および信者のひとりである吉田兼吉を不敬罪・文書偽造行使罪・詐欺罪で検挙した(第二次天津教事件)。
同年6月、狩野亨吉は『思想』誌上に「天津教古文書の批判」を発表した。
狩野は以前にも『竹内文書』の鑑定をおこなったが「人心を刺激する恐れ」から言葉をぼかした批判をするにとどまった。
しかし、軍部に同文書を鵜呑みにする者がいるという事情を知り、その社会的影響にあらためて鑑定に乗り出したという。
狩野は同文書の「神代文字之巻」を換字式暗号の要領で解読し、「年」「即位」「勧請」「水門」といった漢語が散見されること、古代の文献においては「幼童の数え歌にさえ古い呼方を伝えている」数詞がすべて漢音であることなどを批判している。
狩野は同事件において検察側の証人として出廷したほか、橋本進吉も竹内文書における神代文字の「原文」が「訳文」と対応関係にないこと、神代文字なるものは近世の偽作にすぎないことなどを証言した。
昭和19年(1944年)12月1日に竹内は無罪判決をくだされるも、同事件により竹内が不敬罪の公判に付せられたことは大きく、教団組織自体は解体を余儀なくされた。
こうした状況下の昭和16年(1941年)、中里は近衛内閣に「神代文字実在確認ノ建白書」を提出することを考え、連署をもとめるべく、朝鮮総督をつとめていた小磯を訪ねた。
これに対し、小磯は「独自に神代文字の研究機関設置の件を建白したいから」という理由で断り、翌年再び中里が訪朝した際には独自の「神代文化研究機関」の創立草案を示し、「その人選と組織編成」を中里に依頼したという。
小磯は組閣の2ヶ月前にあたる昭和19年(1944年)においても、『日本におけるキリストの遺跡を探る』なるドキュメント映画の撮影に、当時の大卒初任給の27倍にあたる2306円を拠出するなど、熱心に竹内文書を信奉したが、結論として当時の時勢にあたって小磯は無力であり、太平洋戦争敗戦の年である昭和20年(1945年)4月、小磯内閣は「何もできないままに総辞職」した。
近現代における神代文字論
明治維新後も神代文字に関する論争は続いた。明治4年(1871年)には藤原政興が『神代字源考』を上梓したほか、矢野玄道は明治8年(1875年)に篤胤『開題記』の反駁に反駁するという体裁をとり『懲狂人』を著した(刊行は明治22年・1889年)。
こうした関係から、当時の国語学者は神代文字を単に荒唐無稽なものとして黙殺することができず、繰り返し神代文字の存在を否定する必要があった。
明治36年(1903年)に金沢庄三郎は『日本文法論』を上梓し、
「1. 神代文字は表音文字であり、象形文字の段階を踏まずにそうした高等な文字があらわれるのは不自然であること」
「2. 『文』に代表されるように、和語の文字に関する語には漢語由来のものが多く、神代文字の実在を仮定するなら不自然であること」
「3. 神代文字は朝鮮の諺文に酷似すること」をもって神代文字を否定した。
平井昌夫によれば、これをもって神代文字非実在論が国語学における定説となり、以来国語学者で神代文字実在論をとなえるものはいなくなったという。
ほかに、吉沢義則による昭和21年(1946年)の『国語史概説』においては、
「1. 『仮名本末』に記されるよう、いわゆる神代文字は偽作であること」
「2. 表語文字に先んじて表音文字があらわれることは考え難いこと」
「3. 仮にそのような文字が存在したのなら、わざわざ異なる言語系統に由来する漢字を輸入する必然性がないこと」
「4. 神代文字は上代特殊仮名遣を反映していないこと」を根拠に神代文字が否定されている。
フランスの日本学者であるレオン・ド・ロニは1882年に“Questions d’archéologie japonaise: communications faites à l’Académie des inscriptions et belles-lettres“を発表し、阿比留文字はハングルを起源とする日本の古代文字であり、その源流はデーヴァナーガリー文字に辿ることができると論じた。
1883年、ロニは東洋語学校のテキストとして『古事記』を翻訳したが、原文の訓読にあたって阿比留文字を用いた。
ロニは藤原政興による『神字古事記』を所蔵しており、平藤喜久子はおそらくこれが原本となったのであろうと論じている。
これに応じて、バジル・ホール・チェンバレンは、同年に“On two questions of Japanese Archaeology”を発表した。
同論文において、チェンバレンは神代文字は「熱狂的な神道復興主義者」たる篤胤の創作にすぎず、古代日本に文字があったとする証拠よりも、なかったとする証拠のほうが強力であることを論じた。
チェンバレンは明治19年(1886年)に日本語でも「神字有無論」を発表し、神代文字の存在を否定した。
チェンバレンは神代文字を否定する論拠として
「1. 神代文字が、表意文字ではなく直に表音文字からはじまるのは奇妙であること」
「2. 神代文字があったのならば、漢文訓読にあたってヲコト点のような記号を用いるのは不自然であること」
「3. 『文(ふみ)』『簡(かみ)』のように、書に関する国語はなべて漢語由来であること」
「4. 神代文字が存在したのならば漢字を借用する必要性は薄いこと」
「5. 日本に表音文字を発明するほどの文化があったのならば、後世に中国文化を輸入しているのは不自然であること」
「6. 古書に神代文字の存在に言及するものはないこと」
「7. 神代文字の語順とされる『ひふみよ』という言葉は当時の史料にみられないこと」を挙げている。
出典: 「神代文字」
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

デンマンさんが神代文字はなかったという根拠はなんでござ〜ますか?

あのねぇ〜、イギリス人のチェンバレンさんが明治19年(1886年)に「神字有無論」を発表し、神代文字の存在を否定したのですよ。。。外国人が客観的に資料などを調べて研究した結果なので日本人が主観的に、どうこう言うよりも説得力があるのですよ。。。
つまり、チェンバレンさんの見解を支持するのですか?
そうです。。。

(1850年10月18日 - 1935年2月15日)
バジル・ホール・チェンバレン(Basil Hall Chamberlain)は、イギリスの日本研究家。東京帝国大学文学部名誉教師。
明治時代の38年間(1873年-1911年)日本に滞在した。
アーネスト・サトウやウィリアム・ジョージ・アストン(William George Aston)とともに、19世紀後半から20世紀初頭の最も有名な日本研究家の一人。
彼は俳句を英訳した最初の人物の一人であり、日本についての事典"Things Japanese"(『日本事物誌』)や『口語日本語ハンドブック』などといった著作、『君が代』や『古事記』などの英訳、アイヌや琉球の研究で知られる。「王堂」と号して、署名には「チャンブレン」と書いた。
「1. 神代文字が、表意文字ではなく直に表音文字からはじまるのは奇妙であること」
「2. 神代文字があったのならば、漢文訓読にあたってヲコト点のような記号を用いるのは不自然であること」
「3. 『文(ふみ)』『簡(かみ)』のように、書に関する国語はなべて漢語由来であること」
「4. 神代文字が存在したのならば漢字を借用する必要性は薄いこと」
「5. 日本に表音文字を発明するほどの文化があったのならば、後世に中国文化を輸入しているのは不自然であること」
「6. 古書に神代文字の存在に言及するものはないこと」
「7. 神代文字の語順とされる『ひふみよ』という言葉は当時の史料にみられないこと」

漢字が伝わる前に神代文字はなかったというチェンバレンさんの上の理由は しごくもっともなのですよ。。。特に、神代文字が存在したのならば漢字を借用する必要性はなかったはずです。。。卑弥子さんも、そう思いませんか?

確かに、そう言われれば、ごもっとなことでござ〜ますわァ〜。。。日本語を書く文字としては使いづらい漢字よりも、もし神代文字が漢字伝来の前にあったのならば、日本人に馴染(なじ)んでいる神代文字があるのだから、それを用いて『古事記』が書かれたはずですわァ〜。。。
僕も、マジでそう思うのですよ。。。

(laugh16.gif)

(june902.jpg)















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます